« 2012年12月 | メイン | 2013年02月 »
2013年01月27日
債券利回り
あれほど…世間を騒がした欧州危機も峠を越え、ユーロ圏の市中銀行は中央銀行へ1371億6千ユーロ(16.7兆円)の資金を、2年前倒しで返済されると言います。嘘を申告していたギリシャの国債利回り推移は、ジャンク債顔負けの宝物銘柄でしたね。あの時にイタリア国債への投資を進言した野村の元社員は、自分の意見が通らずに辞めることになりましたが彼は正しかったのですね。野村はリスクを取る余裕もなくチャンスを逸しました。振り返れば、結果論は誰にでも言えますが、自分自身がその環境下で決断を迫られると、どう対処するのでしょう。この投資に失敗すれば、あとがない状況であれば、どうしても冒険は出来なくなります。つまり投資で成功する秘訣は、「一か八かの状況に追い込まれないこと」ですね。常に余裕を持たねば正しい判断はできないという事です。国債投資でも簡単に資金を増やせる訳です。(上はギリシャ、下はイタリア)
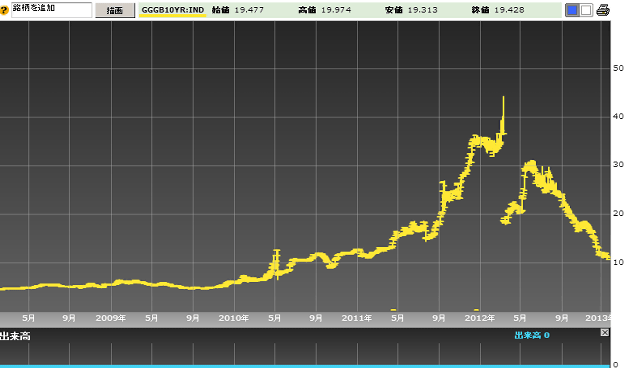
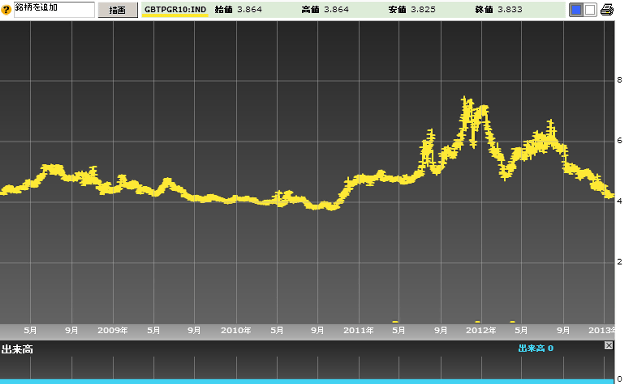
ギリシャは当事者であり、なかなか投資は出来なかったでしょうが、イタリアは問題ないと早くから考えていました。通常、株式投資でも二番手銘柄が成功する確率は大きく減ります。ギリシャ国債の最高利回りは44%ほどですね。それが10%近くに下がっているという事は4倍以上になったわけです。二番手のイタリアは7%を超えたところで世間はワイワイと騒いだのです。現在は4%台ですから1.25倍程度ですね。それにしてもギリシャ国債は仕手株なんてものじゃないですね。債権価格推移でみれば120円台から、いきなり20円台に急落し、そうしてまた4倍にもなるのは大儲けのチャンスだったとも言えます。クーポン・レートによりますが、5%のものが44%の最終利回りなら、債券価格は13円になり、それが10%に戻ると69円になりますからね。7%なら18円が81円です。つまり瞬間に売られた44%の利回りと言うのはすごい数字です。
ここで余談ですが、仮にアベノミクスが失敗した場合、2%の国債がどのように価格変化するか考えてみました。3%への金利上昇は91円程度で予想の範囲ですが、5%まで金利が上昇すると76円になり、7%まで金利が上昇すると債券価格は64円になります。つまり35%程度の損失を抱えるわけですね。これがアベノミクスの失敗系の現実ですね。自分で債券価格を計算してみると良いですね。僕が計算した表を掲げておきます。黄色が5%クーポンの場合、緑が7%の場合、ピンクが2%の場合で、上の数字は利回りの数字で左が年数です。赤字が債券価格の変化ですね。
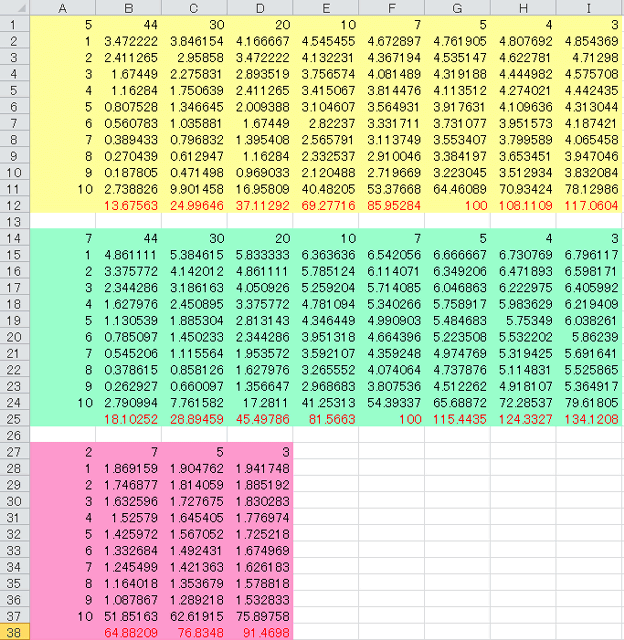
この二つのグラフは、なかなか興味深い現象で、この値動きから僕らは多くの事を学ぶことが出来ます。自分自身が、どの程度、リスクを許容できるかと言うのは、大きな問題です。中には生活費を賭けて冒険している人も居るでしょうし、生涯資金を確保したうえで余裕資金を投資している人も居るでしょう。投資している人の年齢によっても、どの程度のリスクを背負えるかも変わります。若者は仮に失敗しても人生をやり直す事が出来ますが、老人が失敗すれば、再びチャレンジするチャンスは、かなり減ります。人それぞれによりリスクの感覚は大きく違いますね。証券マンの現役時代によくこの事を考えました。このお客様には大型株しか薦められないとか…。しかしカタルの性根は博打好きで、どうしても流動性より、値動きを重視する傾向が強いのですね。同じ銀行株でもリスクウェートは大きく違います。
通常、デフレ環境では1番手しか相場になりません。更に相場の持続期間も長く続きません。市場に参加者が増えると、リスクの許容度が上がり始めますね。それは皆が儲かっているから冒険を出来るようになるからです。昨年の11月は株価位置も低く、リスクウェートはそう高くありません。しかし現在の株価位置は高く、かなりリスクウェートは上がっています。加えて首つり足の連発は、かなり強弱感が対立していることを示唆していますね。通常は投資残高を減らし、様子見する株価位置です。ただカタルは何度も述べていますがハイリスク投資を信条としており、もっとも効率のいい投資を探す傾向にあります。だから2倍、3倍に資金が膨らむわけですが…。その反面、リスクウェートは非常に高いのですね。今、このリスクウェートを更に高めるべきか? 今は悩んでいます。
多くの皆さんは安全で儲かる銘柄を探すのでしょうが、そんなものはありません。大きく儲かる可能性があるものはリスクが高く、株価の変動率が高いのですね。だから失敗したらお金は物凄く減ります。その代り、成功すれば何倍にもなっていきます。でも安全を求めれば、こんなに株価が上昇しても、せいぜい2割、3割の世界なのでしょう。比較的、安全と考えられている国債などの債券投資でも、こんなに価格変動が起こるものなのです。日本国債などゴミ屑みたいなもの、アベノミクスが失敗するリスクも当然あるでしょう。もしそうなれば、7%どころの金利上昇で済まないかもしれませんね。過度に金融政策への依存度が高まると、アベノミクスのリスクが巷で騒がれるようになります。今は、全く心配はありません。しかしリフレ政策とは「もろ刃の剣」なのですね。リフレ政策下では、株式は安全資産です。ましてや3%もの配当利回りに推移する株価水準ですからね。
投稿者 kataru : 15:44
2013年01月20日
連想
アルジェリアのプラント武装事件は終了したようですが、多くの犠牲者を出したと言います。この事件の引き金はマリ政府の要請を受けたフランス軍の空爆攻勢によるものだと言われています。マリにはリビアの残党が多くの武器などを持ち込み戦っていると言います。カダフィー大佐率いるリビア政府を叩いたのはNATOです。今のシリアの混乱も反政府組織を支援する欧米寄りの影の力が働いていると言います。シリアは北朝鮮以上に厄介な独裁政治なのでしょうか? イランの核開発、北朝鮮の動きを一方的に批判している欧米は、嘗て自分達が行った核実験などの優位性を誇示しており、世界での発言権を確保しています。米国は生物兵器などの開発を根拠に、イラクに侵略戦争を起こし支配しました。その為に爆弾テロは多発しています。アフガニスタンも強引にアルカイダの組織を武力でつぶしたのでテロが起こっているとも言えます。結局、報道されている欧米よりの考え方は本当に正しいのでしょうか? 中東のアルジャジーラは良く犯行声明を放送していますが、この度、米国のテレビ局を買収しました。これで報道の流れは、少しは変化するでしょうか?
株価を考えるうえで、このような背景を探ることは非常に重要です。何しろ、経営者自身が詐欺師のような連中もいますし、会計法も知れば知るほど隠されたマジックが存在します。作為的に決算数字を作ることが出来ます。勿論、グローバル化の進展で国際会計基準が整備され、包括利益と言う考え方の導入も始まっています。しかし市場の動きをみるとこの包括利益を根拠にして相場に発展した銘柄は、まだ存在しませんから一般的な認知は進んでいないものと思われます。結局、正義とか法律とかの解釈は一般的な認知なのでしょうね。どれが正しいというものは、ないのかも知れません。日本のデフレ社会による低迷は起こるべきして発生した当然の帰結です。日本は過去に置いて高成長するために様々なマジックを使ってきました。そのマジックのツケを払ってきたわけですね。
米国はそのマジックを巧みに使い国民を誘導し価値観を変化させています。アメリカン・ドリームなどのマジックは、国民の幸福度に繋がるのかどうか…マイケル・ジャクソンやホイットニー・ヒューストンなどは幸せだったのでしょうか? 物質的な豊かさを手に入れた事が幸せなのでしょうか? 長いデフレ社会において、この辺りの感覚に目覚めた日本人は多いですね。先日、紹介した東大名誉教授の月尾嘉雄さんの考え方も、その点を指摘していました。ブータンの国王が来日した折も話題になりましたね。幸福度と言う話が…。最近、ミャンマーが話題になっていますが…先日、僕は中国の「侵略外交」と述べていますが、歌手のリンリンさんがマンダレーの死と言う曲を謳っており話題になっているそうです。
WSJより背景を説明すると、『リンリンさんによると、過去10年の間に大勢の中国商人がマンダレーに押し寄せ、地元の企業を買い漁ったり、住民を市外に追い出したりしたという。この「マンダレーの死」という曲を歌う彼の姿はファンの1人によって撮影され、インターネット上に公開された。それ以来、数十万人がその動画を見た。「どの公演でも、必ずこの曲がリクエストされる」と語るリンリンさん。中国文化や勤勉な多くの中国人は尊敬するが、彼らとの取引では得られるものより奪われるもののほうが多いと不満を口にした。リンリンさんが歌に込めた厳しいメッセージやその反響の大きさは、経済や軍事、政治の面で大国化した中国に対する反感がミャンマーを初めとするアジア近隣諸国で高まっていることを示す1例だ。中国による天然資源の採取や同国製廉価品の輸入といった商業的問題から、領有権をめぐる対立や同国初となる空母の配備などの地政学上の問題まで、懸念材料は多岐にわたる』
市場原理主義が人々を豊かにすると考えてきましたが、節度のある行動が気品に繋がり尊敬を集めるのでしょう。日本の経済援助のやり方も、大きく変わり始めています。ただ物を与える一度限りの施しより、自立できる循環型の社会構築が必要なのでしょう。以前、紹介したことがある住友化学のアフリカでの蚊帳の製造などは、良い取り組みの一つですね。労働の場を提供してマラリアなどの疫病を防ぎます。企業経営方針もそうですが、政策も有効な仕組みもあります。再生エネルギー買取法が自民党政権下でも継続される見通しとの事で良かったと思っています。エネルギー価格は上がり企業の競争力は奪われますが、日本はエネルギー問題をもっと真剣に考えた方が良いですね。それに太陽光の変換効率の改善余地は大きく技術革新を先駆できるかもしれません。シャープは昨年末に従来の2倍近い変換効率の製品を開発したとか…それでも37%と言う数字だそうです。更にわが国周辺には100年分の天然ガスに匹敵するメタンハイドレートが眠っていると言われています。コストが合うのか分かりませんが、掘削技術の進化でシェール革命がおこる米国の事例もありますからね。
今日も話が大きく飛んでいますが、昨日の続きでもあります。市場で物色される銘柄の背後には、必ず相場に発展する潜在力があるのですね。その潜在成長率が高い企業の株価が未来利益の存在に繋がり、未知の魅力に惹かれ人々の心を動かします。昨日の銘柄選別の続きですが、目先の利益を優先する相場から未来利益を優先する相場に変化を見せるのですね。相場の物色対象はだんだん広がっていきます。先駆した人気株から出遅れ物色に…更に潜在力を評価する相場へと…。信用力の創造はPER100倍の夢まで容認するようになるのですね。ソニーが大きく水準訂正しているのは、行き過ぎたデフレ社会の読みを払拭している相場ですね。PBRの存在が背景にある訳です。だから米国本社の売却で利益が出る構造が改めて認識されたのですね。しかし現実はパナソニックと違い、まやかしの域を出ませんが…。三菱UFJが純資産価格の1倍割れの現実はどう考えてもおかしいのです。赤字企業のソニーさえ修正され始めていますからね。
このような数々の矛盾が更生されてから、初めて、ようやく経済成長のまともな話に移れるのでしょう。故に先駆した銘柄のスピード調整はありますが、全体相場のボリュームアップの相場は続くのでしょう。
投稿者 kataru : 11:56
2013年01月14日
信用創造と乗数効果
先日、何気なくNHKを見ていたら、大正デモクラシーと大本教「出口なお」などの解説をしていました。大正デモクラシーって? 教科書で普通選挙権運動などを推進した吉野作造などの名前は知っていましたが…何にも時代背景も知らずにいましたから、インターネットで調べ始めました。まだ途中ですが…。何やら、時代背景が似ている様な気もしたので参考になるかな?と考え調べ始めた訳です。やはり歴史は面白いですね。此方のサイトは…時代背景を分かりやすく語っているようです。このサイトの捉え方は参考になるでしょう。
さてこれから、日本はどう進むのか?と言うのは、難しいですね。
民主党政権下では、鳩山さんは急ぎ過ぎましたね。僕は日米同盟の見直しを含め、憲法改正など日本の根本的なあり方を再構築する必要性を感じています。中途半端な自衛隊の形を徴兵制度まで含め考え直すべきでしょう。一方、このまま日米同盟を堅持しながら、グロバリゼーションを推し進めるやり方も考えられますね。既に国家と言う存在感が希薄な時代になりつつあります。楽天のやり方は強引ですが、どの企業でもTOEICの800点は標準化しそうです。電子機器の発展により言葉の障壁も、まもなく、なくなるでしょう。TPPなどのあり方をみると国際化の流れは時間の問題ですね。金融危機は欧州問題に発展しユーロの価値は守られたように、何れ通貨も統一されるのでしょう。
僕には理解できませんが、高度な計算が要求される医薬品や新素材の開発など「京」などのスーパー・コンピュータの汎用化により、更に開発スピードが速まるのでしょう。昨日のリカードの「比較優位論」から、国際分業が効率化社会を形成している話は面白かったでしょう。石器の手斧からマウスの比較論は、実に有益な視点でした。マット・リドリーの「アイディアがセックスするとき」と言う考え方は、今の時代の象徴です。
日本が置かれた今の状況は、バブル崩壊後の再生期であり、日本は1989年、しかし米国は2006年、2007年です。サブプライムローンからリーマンショックの過程は金融工学の行き過ぎだったのですね。株価もそうですが時代を推し進める為に、先ず、大きな期待感が先行することがあります。相場は理想買いと現実買いに区別されるように、最初は夢を買うのですね。丁度、今、始まっている金融相場は、夢の理想買いの相場です。やがて理想買いは終わり、現実の利益を待つようになります。だから相場は中間反落を経過するのです。利益が出る前の調整ですね。私は、金融工学の発達によるBIRCsの発展は、その成果だと考えています。東西冷戦崩壊から市場経済の浸透は、グロバリゼーションには欠かす事が出来ない作業だったのでしょう。歴史的な現象は人類の進歩に何れも意味があるのでしょう。互いに関わりを受けているのです。見えない糸により結ばれているのですね。NYで羽ばたきした蝶が、やがて日本に台風をもたらすというカオス理論の世界の話です。皆、必要なパーツなのでしょう。
相場を観察し次の展開を予想する。今回の相場のスタートは8月でした。おそらくこの頃から、日銀はマネタリーベースの調整の反省が、芽生え始めたのでしょう。株価は正直ですね。3月中旬には下げ波動に入っています。この動きを見て、日銀は再びマネタリーベースを増やす必要性を感じていたのでしょうね。事実、日銀は7月に追加緩和策を実施し始めており、9月、10月と追加緩和を実施しています。このような行動を見て、かたるは10月末から、久しぶりに強気に変化し始めました。その為に11月に入りマネタリーベースの話を増やして、レポートを掲載しています。一般の認識はアベノミックスの成果ですが…。衆議院の解散を決めたのは11月14日ですからね。野村証券の株価をよく見れば分かります。
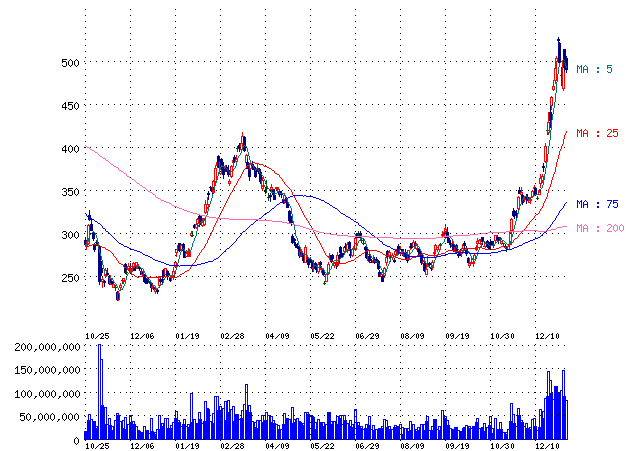
実は、今日は「信用創造」の話を補完しようと考えています。信用創造の真意はお金の動きを活発化させる事です。その結果、土地や株などの資産価格が上昇します。この現象は「鶏と卵」の関係にあります。どちらが先と言う訳ではありません。しかし株価だけが上昇を続ける事でもないのです。株価の維持には、裏付けが必要なのですね。誰もが納得する価値観の共有化ですね。加藤あきらなどが、何故、潰されたか? 価値のない株価を創り上げ、自由の範疇を超えたからですね。故に加藤銘柄の担保価値が失われ、自壊しました。それでは価値のある株価とは何か? 株価を裏付ける資産価格や未来の利益を作る能力ですね。解散価値などはPBRと言う指標で、未来の利益はPERと言う指標で一般化されています。更に配当利回りも、預金金利との差で、歴然と存在しますね。定期預金金利が1%以下なのに…何故、裁定現象が起きないのでしょう。不思議ですね。益利回りの考え方はここにあります。本来、お金は金利の高い商品へ流れます。ところが現実の日本株は、この正常な価値観が働かない異常な現象下にあります。
本来、経営者は利益率が10%も確保されるなら、お金を借りてでも事業の拡大をめざし利潤を追求する筈です。ところが現状は、お金があっても先行き不安から行動を手控え、現金保有率が高まったままの状況です。わが国のバブル期の不良債権処理は2003年に終了しましたね。その後、自己資本の補強をしている最中で、その作業も既に10年が経過します。いい加減に本来の機能を発揮しても不思議ではありませんね。その現象がソフトバンクのスプリント買収資金への融資ですね。まだ米国から許可が得られませんが、イー・アクセスなどへの出資比率の見直しなど環境を整備しています。兆円単位の融資復活は、象徴的な現象の一つでしょう。M&A資金は非常にリスキーな案件です。しかもリスキーにも拘らず、リターンである金利は安い筈ですね。このような案件の融資が実行されるという事は、我が国の金融界はバブルや金融危機の後遺症から完全に立ち直っている証でしょう。
兆円単位の海外投資などが背景にあり、円安に傾いているとも言えます。何もアベノミックスの成果ではなく、時代が好転する時期に来ている訳です。あとは時代の方向性をコントロールするだけです。今のところ新政権の方向性は正しいのでしょう。株価など見ても市場の反応は良好ですね。単に株を上がることは、誰にでも出来ます。ある程度の資金を有していれば…誰にでも可能ですね。しかしその株価を支える根拠の業績が見えないと株価はやはり下がります。ベンチャリの失敗は、夢を支える支援がなかったですね。成長期はあのような企業に資金融資するのが、正常な金融機能の状態ですね。無借金企業で夢のある投資をし、お金が回り始めていたのに…。銀行などの支援は得られませんでした。2003年から2006年は、まだ不良債権処理が終わったばかりで、銀行にユトリがなかったのでしょう。今度はソフトバンクへの金融行動を見ると…時機は到来しているようです。
ここまで書いても、まだ皆さんには見えないでしょうね。
野村証券の株価は色んな意味を秘めています。現状は明らかに高過ぎますね。つまり株価を支える合理的な背景が乏しいので、500円近い株価の評価は難しいのです。しかも邦銀の配当利回りの修正も、まだ完了されていません。三菱UFJでは1%程度までは許容範囲でしょう。みずほでは2%程度かな? つまり邦銀の株価は、まだまだ安いのでしょう。なにしろ、危険な投資へ、融資を出来るほど内容が改善されているにも拘らず、市場の評価は低いままですね。このような株価修正が、今後も継続されるのでしょう。先駆した銘柄から、全体へ広がる展開が始まるのでしょう。全体水準の底上げ運動ですね。シャープの休みやアイフルの休みは、その現象の一つでしょう。故に、カタルは出直りは速過ぎると述べています。決して株価が高くて、下げると言っているわけではなく、休みが必要だと人気銘柄は述べています。マツダの変化はまだ見えませんが、おそらく同様でしょう。為替の修正も、そろそろ一服しても不思議ではありません。少なくとも、邦銀の株価修正が終了するまでは、先駆した株は、休みが必要な時期に来ていると考えています。信用創造の話は、邦銀の株価修正の意味を秘めています。
別に株価を上げることが信用創造につながるとの意味ではなく、経済が回復する過程で、マネタリーベース、つまりハイパワード・マネーの適正な乗数効果が生まれる事をカタルは述べているのですね。貨幣乗数効果、つまり日銀が供給したお金が、市場に還流し動く様子ですね。この動く様子を表したのが貨幣乗数なのです。1月5日の株式教室でこの話を掲載しています。問題にしているのは「M2」の前年度比の伸びと共に掲載されている乗数倍率の話しです。経済が活性化すると、この乗数倍率が膨らんできます。いくら電子マネーが普及しても、今の停滞する数字は異常ですね。90年代の貨幣乗数は10倍以上あったのです。本来はM2より、M3などのマネーストックの数字を用いるべきですが、歴史的な検証が出来ずに仕方なしにM2を用いています。
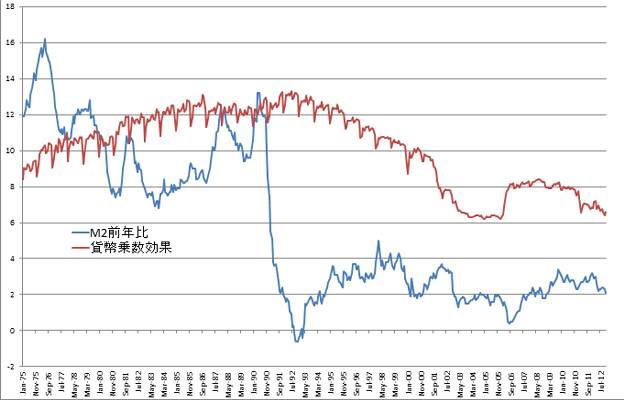
信用創造の結果、株価が上昇し、地価が上がりなどの資産効果が出てきます。その結果、企業はようやく安心して、設備投資などに動くのですね。鶏と卵の関係なので、一概に言えませんが、カタルの指摘する信用創造とは、究極的に貨幣の乗数効果が高まった姿を目指しています。しかし12倍を超えるようなバブル期の現象は、やはり行き過ぎなのでしょう。日銀はこの指標を、もっと大切に扱うべきでしょうね。2006年の過剰な引き締めは、今日の日銀批判に繋がっていますね。もしあのまま緩和を続けておけば、米国発の金融危機にも早めに対応が出来たのでしょう。まぁ、結果論ですが、2006年には8倍を超えはじめたのに…、折角の自律的回復の芽を潰しましたからね。
株価を上げる作為的な信用創造は意味がありません。必ず株価が上がるのには、背景があるのです。その背景を大切に育てる事が出来るかどうかの施策が、結果として信用創造を促進させることに繋がります。成長シナリオを復活させるためには様々な仕掛けが必要で、法人減税を餌に給与水準に引き上げや設備投資など用いるのは一つのアイディアですね。このような奇抜なアイディアは長続きしませんが、一時的な効果はあります。小さな灯がやがて大きな炎に繋がるかどうかの瀬戸際にあるのが、株価を見ると良く分かります。
投稿者 kataru : 13:48
2013年01月13日
豊かさとは…?
昨日は株式教室で「株の売り場」のテクニカル面の解説を少ししました。まぁ、さわり程度の感触ですが…すべてを理解してもらおうとも思っていませんし、僕のキャリアを理解するのは、所詮は無理なのです。だって僕はこれまで30年から学生時代も含めれば40年くらいの歳月を、株価の動きを読むために捧げてきたようなものですから…。もし自分の人生の中で、正しく基礎を伝授してくれる人がいたなら、僕が経験してきた様々な失敗を犯さずに時間が節約できたことでしょう。でも残念ながら小さな証券会社では教育制度も限られますし、先輩の経験則の伝授は限られた範囲でしか伝わりません。学校の教科書のように整理されていれば効率的で良いのですが…なかなか株の世界は奥が深く難しいのです。経済学だけでは理解出来ませんし、数学や言語能力…など様々な基礎知識がないと成功できない仕組みになっています。
今日は考え方の論理のなかで先日、NHKの番組を見ていたら、これは素晴らしいヒントだな…と感じたのでご紹介しておきます。その番組の様相はこちらです。どうぞ…。僕も原稿を書く為にもう一度、聴いたのですが最後の方が切れている様で…? 最終部分は此方から、補完しました。マット•リドレーって、分かりやすく現代社会を解説していますね。
このプレゼンと言うか、授業の中で僕が何度か解説しているリカードの比較優位論の話が登場していますね。この授業は分業化により進化するスピードが速くなっていると述べていますが、人類の進化は近年、非常に早くなっています。携帯電話を見れば分かります。先日、「京」の話をしました。コンピュータが発達し、今まで考えられなかった生産方式などが生まれる事でしょう。どんどん進化は早くなりますよ。もう直ぐ、ロボットが人間社会に共存しますからね。日本はこの分野の研究開発に、もっと傾斜すべきでしょう。自動車産業やファナックなどの工作機械部門は世界トップで、膨大な需要は世界中に存在し、少子化と言うキーワードを強みに生かせますからね。製造ラインではファナックの他にも安川など、沢山の産業の基盤が存在しています。先日、グーグルが自走式の自動車開発をしており世界トップ水準だと述べました。勿論、トヨタも取り組んでいますよ。しかし要は、やはり頭脳部分ですね。カーナビの進化に期待しています。ツガミは汎用品開発で中国の成長により、一時、人気になりましたが、所詮はファナックに敵いません。まぁ段々、話がそれますから、この辺にしないと…。
既に先程紹介したビデオを見ているとすれば、皆さんはそろそろ限界に近い筈ですから、簡潔に話を進めなければなりません。産業革命が始まった英国では、国民一人あたりのGDP、所得を倍増するのに150年の歳月がかかったと言います。ところが米国では倍増するのに僅か30年だったとか…。更に近年、中国やインドでは、その「何分の一」かの時間で達成したと言います。アベノミックスもそうですが、今の日本はこの成長力を加速させようとしています。故に株価も上がっているのですが…。
昨日の1月12日の日経夕刊には、東大名誉教授の月尾嘉雄さんが「豊かさのV字回復」と題してのレポートが掲載されています。私の話を理解するためには読んでみて頂きたいものです。この記事には、挫折者のヒントも隠されています。「経済のV字回復」から「社会のV字回復」を述べられています。豊かさとは、一人あたりのGDPを増やす事が、本当に幸せなのかという問いですね。豊かさとは何か?と言う命題です。
昨日は新潟に帰る為に久しぶりに東京駅に行きました。ついにあの古くなった鉄鋼ビルも解体されていましたね。更に昔、僕が通っていた和光証券が入っていたビルも解体されていました。きっとビルを新しく建てるのでしょう。東京駅は昔の駅舎を残し現代風に変えましたが、日本ではまだまだ使えるビルを、古くなると壊して新しくしますね。古くなった配管や空調などを取り換え半永久的に使える芸術的な価値を有する建物は残せないのでしょうか? アントニ・ガウディのような…。更に現代ではロンドンのシティー周辺の街並みは味がありますね。ラグビーボールのような建物やロイズの建物など…。
何故か、自民党が目指しているアベノミックスは、方向性が少し違うように感じているのは僕だけの現象でしょうか?
投稿者 kataru : 13:12
2013年01月06日
資産効果の話し
読者から総資産経営の意味を問われたので…簡単に解説します。経済は拡大モデルが基本になっています。わが国は1985年のプラザ合意以降、政策ミスを連発したために構造調整に戸惑いました。そうして1989年の東西冷戦の崩壊から、鄧小平の開放改革政策に代表されるようにBRICsの影響で空洞化の調整に苦しんでいます。日本モデルを模倣するBRICsの価格優位性に技術革新が追い付かずに勝てなかったのですね。ガラパゴス化と言われて久しい時間が経過しています。
昨年からの株式の値上がりは、その需給バランスを大きく変えるための期待感で株式が上がっています。その需給バランスの基本がインフレ率の調整なのです。何故、わが国の構造改革が長引いているかと言えば、日本独特の風習や文化にあります。江戸時代の鎖国制度の環境に良く似ていますね。TPPの問題で大きく揉めるのも知識不足と間違った報道です。よく考えれば分かりますが…何故か、日本人はあまり考えません。これも画一化教育の弊害でしょう。故に一刻も早く教育問題に取り組まねばなりません。記憶力より独創的なアイディアを生む付加価値教育を優先させねばなりません。
さて今日の主題は総資産経営で大手金融業の総資産が大きいのは当たり前で、カタルの指摘がおかしいかどうかの話です。日本の銀行は、企業などもそうですが…基本的に総資産経営です。カタルの指摘する総資産経営とは規模の拡大を求めることを示します。日立は代表的な企業ですが近年は方向転換を始めています。日本は過去において基本的に儲けが少なくても売り上げを増やすことに重点を置いてきました。理由はインフレ率が高かった影響もあります。しかし世界の基準は違います。ROEと言う投下資本に対する利益率で企業の優劣を競い合っているのです。産業障壁を引き下げて利益率の低い産業の門戸を開放しなくてはなりません。TPPなどで問題になっている一部の弱小産業の保護は別の問題ですね。どの国でも農業への補助金は存在します。CAS冷凍技術などの開発もあり様々なアイディアが効率的社会で生まれるようになっていますから、日本の農水産業も捨てたものではないと思いますが…なかなか活用する人が居ませんね。まぁ、その話は兎も角…。
何故、金融緩和によって金融業の株が上がるかと言う基本的な概念が皆さんには不足している様なので…基本的に総資産規模の大きな金融業は利ザヤで稼いでいます。今の住宅金利や貸出金利は預金金利との鞘で計算されて決まっています。この計算の前提がデフレ型になっているのですね。この前提で利益が生まれるように金利などが設定されています。下のグラフを少し説明しますが、オレンジの線が基本的な調達金利、または資産の調達価格だと考えてください。青色は実際に日本が行ってきた政策の動きを示しています。aの線はプラザ合意から東西冷戦の崩壊までで、bは資産価格を引き下げた1990年代初めの現象です。年収の5倍で家を買うために住宅価格を無理やり引き下げた動きです。そうして構造改革を渋った90年代の自民党政権の失政がcで、現在はgの位置にあります。まぁ、株価のイメージ図だと考えていいのですね。基本的に株価はインフレ率に連動して動きます。本来の経済は緑色の1のように右肩上がりの環境下で、正常な経済活動が出来るようになっています。この傾きを大きくすればaのような失敗をするわけですね。基本的な傾きはGDPの成長率の1%~2%程度上が望ましいのです。しかし我が国は2の桃色のような状態を長く続けてきました。その為に本来、適正な基準から大きく乖離しています。オレンジと青のギャップはかなり開いていますね。つまり普通の政策を実行するだけでこのギャップが埋まります。これが基本認識です。
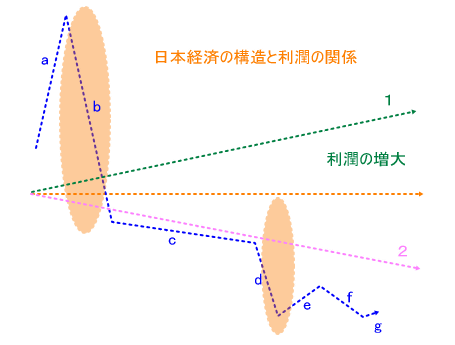
銀行は多くの人からお金を集め運用しています。みずほのケースでは総資産165兆円の内およそ預金は79兆円、譲渡性預金は12兆円など…でお金を集めて運用しています。これまではデフレ化だったので投資した株式が値下がりしたり、企業に貸し出したお金が不良債権になったりする確率が高かったのですね。その為に毎年のように償却損を計上しています。今の利益モデルはこのようなデフレ化でも利益が出るように構造調整されており金利などが決められています。ところが経済全体のインフレ率が上がると、投資した株式や貸出先の経営が上手く行き償却損が減りますから運用益が想定より増えます。預金を全額株式投資していたと考えると、この考え方はより良く理解できるでしょう。実際は違いますよ。自己資本規制比率などがありそんな事は出来ませんし、日本国債を下がると思っても勝手に売ることもできません。色んな制約があります。それでも期待インフレ率1%を2%にすると政府が公約するという事は大きな事で、インフレにするのは実は簡単なことなんです。本気になれば…の話ですが。
どうも消費税の引き上げも決まり、自民党が大勝したので日銀は正論を主張できない環境下にありますね。この部分を市場は大きく評価しているのでしょう。さて大手銀行の話に戻しますが、運用が大手銀行などの金融機関の仕事なのですね。僕がいくら努力しても単純平均株価が下げ続ける環境下では、買いで儲けるのは至難の業、僕にはその能力がありませんでした。しかし多少、インフレになるなら取り分のパイが大きく増えますから、そのおこぼれを授かる確率は大きく上がります。同じことが金融界全体で起こります。1%の利潤の増大は165兆円なら1兆65百億円ですね。預金金利も上がりますが、これは計算されており直ぐに反映されません。しかし貸出金利などは市場金利に連動して直ぐに反映されます。勿論、国債価格の値下がりなどもありますから、インフレが全部利益に繋がる訳ではありませんが、大手銀行はデュレーション(期間投資利回り)が考慮され運用されていますから、長期国債の割合を減らし短期債に傾斜していますから、大きな損失にならないでしょう。勿論、債券先物を利用したヘッジもあるでしょう。因みにみずほの国債投資は34兆円ほどです。平均して何年なのか詳しく調べてないから分かりません。大手銀行はリスクの大きな国債を減らし、リスクが減る貸し出しを増やしますから利潤が増大する環境下になりますね。
しかし製造業は地方の工場や工作機械、在庫などが主だった投資先ですから総資産効果は薄いですね。仮に工事期間が2年程度のデベロッパーなら、地価が値上がりし金利分などの経費が浮くかもしれません。故に長谷工などのマンション業者の利益も増えてきますから株価は騰がる筈ですね。貸出金利と預金金利の引上げの時間差が利潤に繋がり予期せぬ利益を生んできますね。川崎汽船は保有している株価が上がったために一旦は償却した損失を戻し利益で計上するとか…。ようするにインフレ率が上がるという事は、このような予期せぬ利益を至る所で生み、活動的な社会構成になるのです。だから本来は「緑の線」を経済環境に戻さねばなりません。生命保険会社の収益構造を考えてもインフレ型社会の良さが分かります。年金生活者や公務員から、若者に所得移転が行われる正しい社会構造への転換が始まるのでしょう。やがてうつ病患者は少なくなり、夢を抱ける社会構造に変わり、皆が行動的になりますから、昨日示した貨幣乗数効果も引き上がります。問題は日銀や政府が80年代の貨幣乗数効果が生まれるまで緩和するかどうかの姿勢ですね。
投稿者 kataru : 11:34
2013年01月03日
信用創造
新しい年を迎え3回目のレポートですが、年が変わってすぐに新しいアイディアが生まれるわけでもなく、相変わらず迷っていますね。11月14日以降の株価上昇率は高く、いつ一服しても不思議ではないし…同時に歴史的な転換点を迎えている可能性も高く、初期波動が非常に強くなるケースもあるからです。通常の上げ相場なら常識的にそろそろ一服します。しかし今回は本格的な株価上昇に向けての環境が整っています。何しろ「美しい日本」と述べた首相が「危機突破内閣」との認識です。あの時と同じ条件下なのですが、世情の見方が180度、変わっていますね。世論もようやく株屋のイメージと重なってきたように感じています。
年末の株価上昇率は非常に速く、多くの人が乗り遅れていることを考えると、これから株価上昇が始まると考えても不思議ではありません。事実、日経平均株価のチャートを見れば確かにここ5月間は陽線が続き、11月、12月は上昇率が高くなっています。この動きは近年では2009年の3月から8月までの6気月連続上昇に続くものです。最近、記憶に残っている本格的な上昇は2003年の動きですが、あの時は5月から8月まで一気の上昇でした。
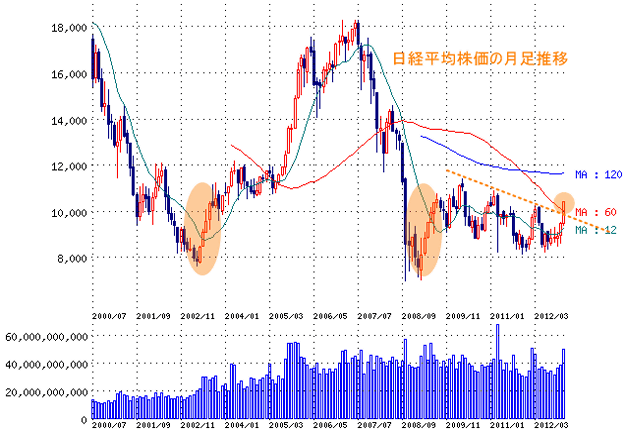
「みずほ」は5月が68円から69円、6月は71円から94円、7月は96円から108円、8月は110円から145円、そうして9月が145円から250円に一気に株価は爆発しましたね。その後も株価は上昇し翌年の4月の560円を付けて月末は522円で株価上昇は一服するわけです。つまり68円の株が522円までで、およそ7倍です。(当時は1株10万円が現在の100円、つまり株数1株が1000株に増えています。)今回はその株式発行済み総株数は当時より2.26倍に増えており、当然、本格的な金融相場に発展しても上昇率は大きく鈍ると思われます。しかし本格的な金融相場を検証するには、このみずほの動きは参考になります。
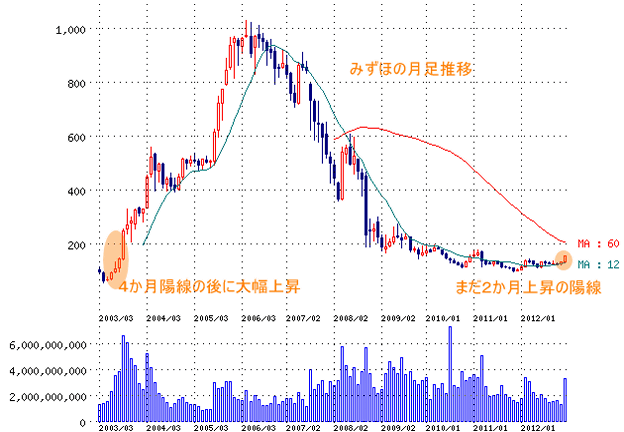
現在のみずほの配当利回りは3.8%です。通常、長期金利と同じ程度になるのが普通です。つまり1%前後まで配当利回りが落ちるとすれば、株価は3倍以上になっても不思議ではありません。大手都市銀行はこれまで資産デフレの逆資産効果を受けていました。しかし今度はマネタリベースの増加に物価目標が加わり資産効果が生まれると考えるのが普通ですね。昨年、つまり今期の決算数字には持ち合い株式の減損会計もありましたが、今度は、その様な逆資産効果がなくなると考えていいわけです。みずほの総資産は165兆円もあります。仮に1%から2%の資産増加効果が生まれるなら、1兆6千億から3兆円の利益効果が生まれます。大手銀行の総資産規模が如何に大きいか?リストをご覧下さい。製造業の比でありませんね。
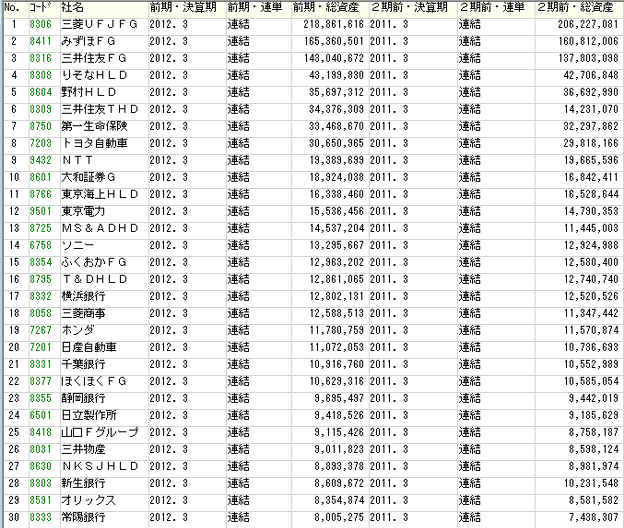
資産効果とはどんなものか?
米国では住宅ローンの担保に入っている家の価値が上がると融資枠が増え、その融資枠が消費に向かいましたね。返済が出来なければ家を売って返済できます。今の日本は田舎の家では価格はありますが、需要がなく売れません。税務署は物納を渋りますね。このような状況は異常です。信用創造機能が全く失われています。この問題点は大きな経済的な損失です。背景には長引く不良債権処理により土地担保金融の機能が失われたためですね。北海道の原野まで価格を付けて、売買できる状況はどうかとも考えますが、人間が生活できる環境である道路や電気、水道がある所であれば、地価の最低保証を付けても良いと思います。インフラ整備が出来ているなら、通常は坪単価1万円程度が妥当な最低ラインでしょう。問題はこの辺りまで信用創造が回復するかどうか? ここが一つの目安になります。2006年においては、株や都心の土地は値上がりしましたが、ここで日銀はバブルの反省に傾きました。まだ銀行の土地担保の信用創造が生まれる前に引き締め政策に変わった所に、金融危機の勃発でしたね。今回は2006年と同じ失敗の轍を踏まないようにして欲しいものです。
果たして今回の動きが本格的な信用創造まで、繋がることができるのかどうか?この辺りが相場の分岐点でもあるのでしょう。
投稿者 kataru : 13:00
2013年01月02日
配当利回り
マネタリーベースは非常に重要で、株価に大きな影響を与えると考えている訳です。
昨年10月末からの様々な検証作業を通じ、その大切さを見てきました。基本的に人間の希望を支えるために、常にパイは拡大しなくてはなりません。取り分の領域が減れば当然成功確率は減り、少数の勝者だけになります。全体のパイが大きくなっていれば、他人比較との偏差値評価では横ばいかも知れませんが、人間は希望を持ち続けることができるでしょう。ある程度の自己満足がなければ意欲も失われますからね。昨年末の動きは希望を感じる動き、その動きが昨日のグラフから感じられると思います。実はエクセルの対数目盛だとマイナスが出ないのですね。そこでもう一度、作り直しました。下のグラフは、株価は対数目盛を利用し、マネタリーベースの前年比は、そのままの数字を用いました。やはり2006年からの調整は異常ですね。バブルの発生の悪夢が、日銀の政策担当者に甦ったのでしょう。故に過剰な引き締めに繋がったのでしょう。加えてこの時期に金融危機が起こる訳で、まるでジェットコースターに乗っている様な異常な政策運営ですね。過去の検証では適度な伸びが必要なのです。経済成長を望むならマネタリーベースも前年比で5%以上の増加が必要なのでしょう。高い成長なら10%近く、お金を供給せねばなりません。現在はかなり疲弊していますから、末端まで潤いが届くまで供給の拡大を続けるべきでしょう。
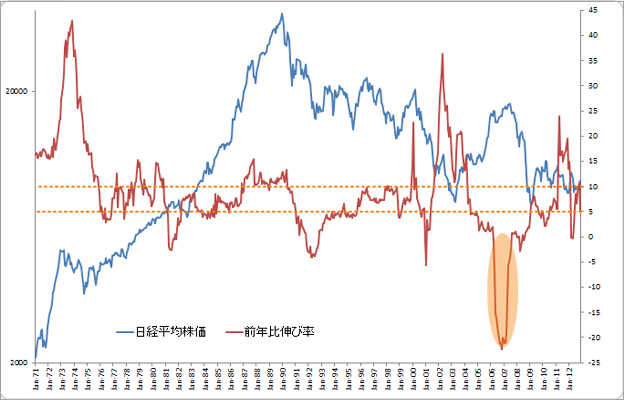
現状では円安への株価の相関係数は非常に高いですが、基本は為替の水準ではなくベースマネーの推移なのではないかと考えています。僕たちが失敗した2006年の減らし方は尋常の減らし方ではありませんね。明らかにバブルの反省が背景にあったのでしょう。しかし日銀には地価推移の詳しいデータがある筈です。もっと資産価格に配慮した政策を実行すべきでしょう。土地がお荷物になるような資産劣化は、完全に信用創造機能を破壊していますね。これでは総資産の大きな我が国の多くの企業は、毎年償却損を強いられ、折角の付加価値が幻に消えていますね。信用創造がいかに大切か、もっと学ぶべきでしょう。デフレ傾向が続く以上、住宅投資をしている人間は何時までも浮かばれません。住宅ローンの重さは家計(消費)の圧迫に繋がっていますね。企業も個人も同じことです。今回の緩和政策が持続的な成長に繋がるかどうかは、単に地価動向に掛かっていると思っても不思議ではなく、株価の行方と共に地価動向も注意深く観察しなくてはなりません。
バブル期のPER50倍とか100倍とか言う株式持ち合いを支えにした過剰な信用創造は完全に解消されています。地価も収益還元法価格まで…所謂、配当利回りと同じ基準まで地価も下げています。既に資産価格の構造改革は完全に終了していますね。日本のGDPを支え、輸入額と輸出額を改善させ多少の蓄えを得る政策は重要です。過剰に原発懸念を抱くべきではないでしょう。これまで創り上げた社会基盤をどう生かすか? 既に多くの条件は整っており、総合的にプロデュースする能力が問われていますね。縦割り社会の弊害を言われて久しいのです。マサチューセッツ工科大の伊藤さんの様な存在は非常に重要ですね。人と人を結びつける能力が問われます。折角、インターネットが発達しており、この機能を使わぬ方はないでしょう。
参考までに配当利回り3%以上、時価総額1000億円以上と標準偏差10以上の株のスクリーニングを実行しました。やはり「みずほ」は載っていますね。シグマが高いという事は値動きが激しい事を示しており、同時にリスクも増しているという意味です。この基準では僅か12銘柄ですが、シグマの基準を外すと57銘柄が挙がります。3%以上の配当利回りの銘柄は798銘柄ありました。

投稿者 kataru : 11:12
2013年01月01日
新春を迎え…
あけましておめでとうございます。
今朝の東京は風もなく晴天の小春日和です。これから久しぶりにかみさんと二人で深川の七福神めぐりをしてきます。今日は先ほど作りましたグラフを見て2013年を感じて頂ければ幸いです。金融の力に頼る「効果と怖さ」を、我々は既に学んでいます。今の日本は金融力を全く否定していると思います。資産価格を上昇させる信用創造は、人々の生活に潤いを与えるものと信じています。世界は金融デリバティブの過剰な金融拡大の反省にありますが、日本は1989年以来、バブル経済の反省をしてきました。最近の研究によれば、2000年代に入ってからの過剰な反省は、金融機能の破壊に繋がり、わが国の実力を過小評価させる動きになっています。
その結果となった経済力の停滞は、中国、韓国などの領土問題にも発展しています。日米同盟を支える源泉は経済力です。米国は明らかに迷っていますね。岐路に立つ日本経済を救うのは適度な信用創造でしょう。既にPERやPBRなど代表的な指標から見ても、かなり構造改革は進んでいます。少なくとも私は、配当利回りで評価される株の世界を経験するのは、今回が初めてですね。みずほの株価は157円で配当は6円ですから、手数料や税金などを考慮しないと3.8%の利回りになります。あくまでも正論の筋を通し、今年、一年を楽しんで終わりたいと願っています。その第一歩が今日と言う2013年1月1日です。
新しい年を迎え、互いに頑張りましょうね。
(下記のグラフは日経平均株価とマネタリベースの残高、そうして前年度比増減のグラフです。何れも対数目盛を採用しました。詳しく知りたい方は12月16日のコラムで紹介しましたように日銀のホームページに飛んで自分で調べてください。)
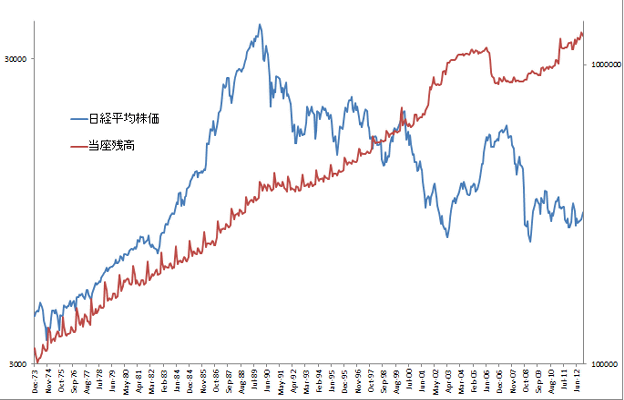

投稿者 kataru : 11:33