« 2012年11月 | メイン | 2013年01月 »
2012年12月31日
大晦日
呆れるモラルハザードですね。日経新聞を読んで唖然としました。だから日本村と揶揄される訳です。民間企業がイカサマをするのなら分かりますが、国がやれば倫理観が歪み、どんどん犯罪へのハードルが低くなります。警察官が殺人を犯すのは当たり前の光景になるかもしれませんね。ただ自民党政権の必死さは同時に伝わりますね。背景に中小企業資金円滑法などの処理も控えており、シャープやパナソニックを救おうとする意図も同時にあるのでしょう。勿論、自民党特有の集金システムが背後は働くのは、当然の昔ながらの手法です。製造業支援とはお題目ですが、今は非常時でないから許されるかもしれません。「美しい日本」などと言うお題目を唱えた前政権より、「危機突破」内閣と参議院選を控え危機感が伝わり、このスタイルはありなのかもしれません。
年末を迎え、最後まで苦しんで浮かぶアイディアとの戦いを繰り返しています。ようやく、形になるのかどうか? 糸口が見つかると良いのですが…先程まで検証作業をしていました。年明けは難しい選択になりますね。10月末から抱いた期待感は淡くなってきています。ドキドキ感より最近は戸惑いを感じ始めてきましたね。あと2週間程度だとは思いますが…その後の展開が見えない以上、空売りを考えるのも筋かも知れません。どうかな?ただ同時にこの株高でも全く影響がないグループも存在し、その路線へ流れが変わるのかどうか?
こんなことが分かるなら、こんな生活はしてない訳です。
武富士に拘ったあの現象が、ようやく…こんな形で市場に出るとは…。しかし行き過ぎた形は必ず修正が出て来るのが、市場と言うものなのでしょう。さてお昼からはのんびりとテレビでも見るかな? でもなかなか面白いものがなく…昨日はバイオハザードを見ていました。最近お気に入りは当初は嫌いだったのですが、AXNの「MADMEN」ですね。シリーズ3の後半から見始めたのですが…今度のシリーズ4も興味があります。でも久しぶりにのんびりしたお正月を送っています。そうだ…これから年賀状を作るんだった。最後までお読みいただき有難うございます。みなさん、よいお年をお過ごしください。
投稿者 kataru : 12:27
2012年12月30日
円安と株価
謎が深まり理解不能な現象が生まれています。
先日、2005年からの日経平均株価と為替の相関関係を調べ相関係数が0.89と極めて高い数字だと述べました。確かに近年は為替が円安になると日経平均株価が上がっていたのです。しかしどうも僕にはこの現象はおかしいのでは…と思うのですね。通常、通貨高になればその国に投資して利益を得られますが、通貨安になれば投資しても為替分が相殺され投資額は減る訳ですね。だって、もし自分が米国人なら日経平均株価は上がっても為替が円安になればその分が損をしますね。1$=79円が1$=87円になれば、ドルで生活する人はおよそ1割も目減りしますね。
そこで時代を遡り長いデータでも検証してみました。バブル期以前(1989年)の相関関係は、円高が株高に繋がっていました。1971年から1989年末までは、実に-0.84で完全に今と違い逆相関関係にあります。つまり円高になると株は上がっていたわけです。理屈的にもこの方向性が正しい筈です。円が買われる環境なら日本株に投資しても株式投資効果と為替効果で二重の効果が生まれ投資は最適になります。1971年から2012年末まで調べると-0.57と逆相関の関係ですね。つまり円安≒株高ではなく、株安なのですね。ただここ10年間は円安が株高に結びついています。この理由はどうしてなのでしょう。日本の構造的な問題なのでしょうかね?
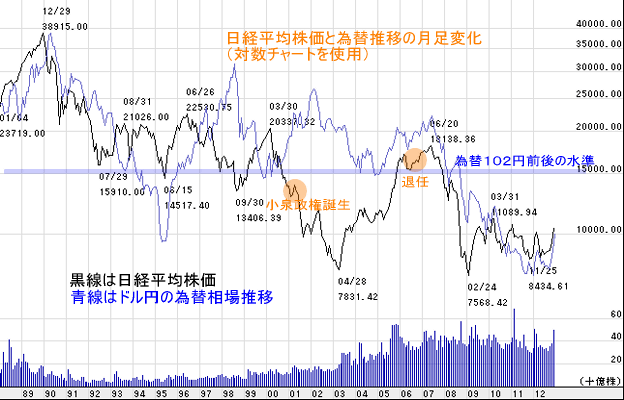
90年代とそれ以降の日本では空洞化の調整が行き過ぎていたのでしょうか?どうもこの解釈が正しいような気がしますね。僕には小泉・竹中改革のUFJ事件は行き過ぎていたように感じます。小泉政権の誕生は2001年4月です。その弊害が現在の貸し渋りに繋がっているのでしょう。あの強引な不良債権認定を行った金融庁の態度が、現在の日本の金融機能を駄目にしたのですね。やはり山一倒産辺りで留めるべきだったのでしょうね。その陰で異常な不良債権処理が行われ、外資系のファンドは、当時、ボロ儲けしました。僕の友達が大儲けして、世の中に出たのもこの時期です。何しろ金融庁は、兎に角、不良債権を減らせの一点張りで、妥当な地価より1/10の価格で処理を迫られた物件もかなりありましたね。いきなり10倍ですよ。この表現はオーバーですが、買い手が不在の所に、大量の不良債権処理の為の投げ売りが、金融庁の指導で実行されたのですね。この時期に土地転がしをすれば、確実に数十倍程度の資産形成ができました。その為にみずほが58300円に、つまり58円台に急落します。
何故なら、双日(日商岩井)は多少のいかさまをして生き延びていますね。鐘紡などまで広げたスキームは、やはり失敗だったように思いますね。しかしこの反動もあり、一度、大きく回復したのですが、体力がない為に世界的な金融危機で再び沈んだのでしょう。この世界危機は、金融機関の自己資本比率規制強化に繋がり、我が国の総資産経営は痛手を受けます。その為に自己資本を、みずほは2.26倍、三井住友は2.43倍、野村は1.95倍、三菱UFJは1.41倍(2.16倍)、三菱はUFJとの合併が2005年の10月でやはり1.41倍と見るべきだと思います。…とそれぞれ発行株式総数が増えています。賢いのは、この点でもやはり三菱ですね。
ここでドル換算の日経平均株価と円換算の日経平均の10年間の推移を比べてみます。下の通りです。上記の長期の日経平均株価と合わせてみると…今回の株価波動は2007年2月の高値まで伸びても不思議ではありません。もし本格的な構造改革を迎えることが出来るなら…(国の借金が減り始める正常な状態が作れるなら)、1996年6月の22750円も視野に入るのでしょう。そうして最高値38957円の奪回ですね。先ずはリフレ政策による資産価格の上昇への期待感だけで、2010年4月の11408円をクリアするのでしょう。この辺りが当面の目途ではないかと推測しています。
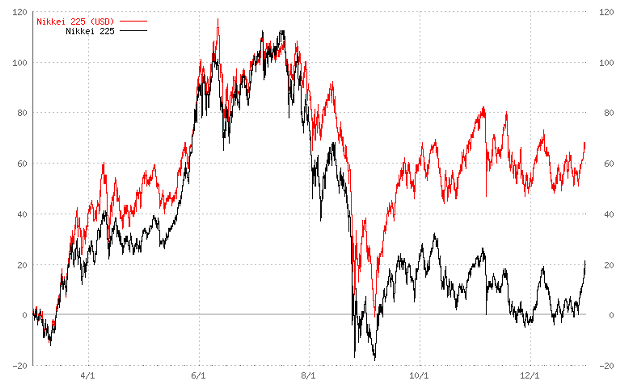
おそらく行き過ぎた空洞化の是正も始まり、国内回帰する産業も出てきても不思議ではありませんね。何しろ日本は世界最高水準のビジネス環境です。中国は第二の経済規模ですが、知的財産権の侵害など…環境は整備されていません。為替の水準は100円前後を目指すのでしょうね。纏まりのないレポートが続きますが今回の検証を通じて、少し背景の知識が補われてきたようです。昨日のレポートもそうですが、株価が上がるには必ず背景がありますね。その背景を理解して銘柄を選択することは大変重要です。
投稿者 kataru : 15:42
2012年12月24日
見えない糸の連鎖
今から考えるのは、とっても早すぎるし予感のようなものですが…、国民の総意が自公民の数を決めた訳で、文句を言うつもりもありませんが、僕は当初、自民中心の連立内閣を想定していましたが、小選挙区制度の弊害からか大きくぶれたようです。その結果、日本は僕が望んでいた政策が、形は違いますが、似たようなものが実行されそうです。
僕はお金を掛けなくても日銀がメザニン・ローン形式でリスクを共有し、復興ファンドを創設すれば良いと述べました。GDPの10%程度の50兆円規模の投資で、未来都市のモデル都市建設にしようと述べました。メザニンなら50兆の2割の投資で総額が集まります。同じ10兆円の投資ですが、これなら金融レバレッジが掛かり、総額で10兆円が50兆円に膨らみ、日銀は1%の利回りではなく3%~5%程度の収益を得られます。更に何より眠っている他の資金が40兆円も動き出しますね。そうすれば政府自ら国債を発行しなくても民間主導で未来都市が実現可能になると考えました。
政府の役割は特例区の税制優遇などを実行するだけですね。そうすれば未来都市への移住権はかなり高額で販売でき、世界中からセレブが集まり効率的な社会が建設されると述べたことがあります。日銀は日本国債を買うより効率的な資金運用が出来て、日本の未来に役立つと信じています。しかし結果は僅か10兆円程度の景気予算で中途半端な需要、嘗て失敗した自民党の大盤振る舞いの無駄な公共事業投資の域にあるような様相です。まだ実態が分かりませんから何とも言えませんが…。日銀は更に10兆円の増額を決め、7月、9月、12月と合計31兆円ですかね。実態は安倍さんが選挙期間に失言した日銀引き受けに繋がっています。これで100兆円を超え、GDPの20%部分が日銀保有になりますね。
仮に泥沼からの脱出に失敗すると日銀への負担が益々大きくなり、結果はより悲惨なものに繋がります。いよいよ悪魔のシナリオが同時に始まる訳ですね。問題は米国でも同じです。米国も同様の実験を行っています。ドルの信認が維持されるなら失敗ありませんが、微妙な展開ですね。不思議なことに「財政の崖」を前に、米国国債の格下げの話は聞きません。以前より状況は悪化しているのに、何故か、格付け機関は沈黙しています。
日産のマーチが生産移転され、歴史的な事象として何度かカタルは登場させています。理由は空洞化の需要不足を埋める行為で、理に適っているグローバル化の一環です。このバランスが日本の構造改革に繋がっているのですね。少し解説が必要な部分ですが…この事象は非常に重要なのです。あれから2年、いや3年かな?震災の影響もあり貿易赤字が膨らみ、ようやく、ここにきて円安傾向に変化しています。この時期に注目しているのが、アップルの米国本土での生産活動の再開の話ですね。丁度、日産マーチの生産移転と逆の関係にあります。米国はドル安政策を続け、ようやく構造改革のバランスが整ったのかも知れませんね。アップルだけでは判断が付きませんが、このニュースは価値のある現象です。
どうしても話題にしなければならないのは、三菱商事の本社移転の話です。金属資源だけとは言え、三菱の重要なウエートを占める機関が海外移転すると言います。売り上げ規模から考えれば、わずかとはいえ本社機能そのものを移転させるのですから驚きですね。シンガポールの法人税率は17%程度と言われています。
まだ糸口を列挙しているだけで、自分自身も繋がりが見えていませんが、いずれも重要なパーツですね。明らかに今までと違う新たな現象がスタートしています。投資心理は微妙な問題で、心の動きは非常にデリケートな話です。今回ばかりは、焦りに繋がり爆発するかもしれません。僕は今回、始まった現象を見て、多少違和感を抱いていました。「Jトラスト」は異常な最高裁の判決から生まれた現象です。故に一旦、会社を潰し、過去を清算させて利益だけと言うか、権利を行使するために生まれた会社ですね。武富士などの過去の清算をダミーに委ね権利を得た訳です。こんなことをしなくても武富士は残っていたのですが、あの判決で歪められた道徳観の市場原理が生んだ株価なのですね。少し難しいかもしれません。抽象的な表現だから…、同じことが存続会社で次々に起こっていました。アコムからアイフル、オリコと続きましたね。そうしてマツダが野村の営業力で公募価格を上回っています。背景はLNGの輸入から貿易赤字で円安にぶれたからですね。
一方、今年はシャープからパナソニック、ソニーが人員整理を強行させています。政策支援を生かせないほど弱体化した時代遅れの体制だったのでしょう。共通しているのは国内需要に頼ったテレビ販売で、グローバル化の対応に失敗した証です。日銀が述べている需給ギャップの話ですね。構造改革の象徴的な現象と捉えられ、このリストラを切っ掛けに円安に為替は転換しています。シャープは兎も角、パナソニックは驚きですね。一つの時代が終了した象徴的な現象に見えます。時間をかけ構造改革してきた結果、パナソニックも耐えられなかったことは…日本全滅を示唆していますね。
おそらく頭のいい政策官僚は、自分達の限界を悟ったのでしょう。故に市場原理に従った政策に転換し始めたのかもしれません。この時間的な背景はこれまで優位だった年金生活者や公務員にも改革を迫るものになります。デフレからインフレの意味するところは、世代間格差の是正でしょう。若者は20万の給料から5万円も支払っています。それも限界になり、とうとう日銀券の劣化により清算を開始する時期が来たのでしょう。先進国全てに共通していますね。最近、スピードが速くなっていますね。
先日、僕はビデオをDVDにおとしてもらいました。今はBDの時代ですが、記憶容量は格段に伸び、技術革新は続いています。HDももう直ぐ半導体のチップに変わるかもしれませんね。村田やTDKの技術革新はすごい技術ですね。何故、メーカーが時代に遅れたのか? 技術的には世界トップなのに…パナソニックやソニーはサムソンなどに敗れましたね。おそらくマネジメントの違いかと思います。教育ですね。日本は戦後ロボット生産教育に徹底しました。その為に政治家も寝ぼけた連中が多いですね。マニュアルがまさにそうです。若者の雇用に当たって外食産業を始め、何処もマニュアル営業です。この弊害の転換点が来ているのでしょう。個人情報保護法案など、はやく廃案にすればいいのです。個人の利益を守るんじゃなくて、行動を阻害する弊害の方が大きいですね。個人の裁量権がドンドン奪われていますね。ここにも日本村社会の良さが消え、市場経済との「ダブル・バインド」が存在します。日本村社会の良さは裁量権にあります。人間は本来、考える動物なのですね。目先の不都合があれば、問題を克服するために工夫するものですね。それを縛っているのがマニュアルですよ。画一化教育の弊害が随所にあり、はやく教育制度を変えないと日本民族の滅亡になります。まぁ、歴史は面白く、だからグローバル化に新天地を求め多くの優秀な連中は日本から離れています。三菱の動きはその一端なのでしょう。
話しが飛び飛び、皆さんにはよく理解されてない部分もあるでしょう。僕自身が迷っており探っている段階だからでしょう。相場論からすれば、ここ1週間かな?調整期になってから金融株が上がってきた印象です。僕の読みが鋭くなっているのか?それとも…見えてないのか?僕には金融株の上昇スピードが遅すぎる展開に見え、相場観のずれが生じているのではないかとも考えています。昨日のマネタリーベースと日経平均株価のチャートを見ると未だに底値圏で蠢いて(うごめいて)います。壮大な相場がスタートしている可能性は非常に高くなっていますね。ただ言えることは恐ろしいことが起こるかもしれないという予感も同時に存在します。何かまた怒られそうですね。哲学的すぎると…。まぁ僕自身が見えてないから、こんなレポートにも繋がるのでしょう。取りとめのない空想に発展したレポートでしたね。
投稿者 kataru : 14:20
2012年12月23日
読者からのメール
最近は思いついたアイディアの検証が上手く進まずに途方に暮れていました。昨日はテレビで映画三昧、一日中、ゴロゴロしていた次第です。久しぶりに海外ドラマなども数多く見ました。シャッターアイランドからモスキート・コーストなど…FOXのキャッスルなどもお気に入りですね。ドクターハウスも久しぶりに見ました。僕はauの光を利用していますがネット以外の機能を使ったのは久しぶりですね。とうとうガイシの浄水器も壊れて汚くなったので新品に変えることにしました。これまでは一番高い物でしたが、今度は一番安い物に切り替えます。カートリッジの価格が2万円近いので新品に切り替えても大きな出費増とは言えません。実は先輩のご厚意で臨時収入があり壊れ始めた生活用品を変えることが出来ます。情けない限りですね。2年前は何とか食えるかな?と、自分の力を過信して、新しい投資方法に挑んだのですが…ディーリングの実験をやるうちに震災などがあり失敗でしたからね。再び挑戦し始めている所ですが…どうなるか。
最近は昔の読者からもメールを頂くようになりました。その方から情報を頂き、この話は僕が思っている事とも共通しており、紹介しておきたいと思います。2006年、僕がマネタリーベースの推移を気付かずに、買いオンリーで挑み失敗し、挫折した経過の裏舞台ですね。福井さんが引き締めを実施するわけです。確かにリーマンに代表される金融危機の影響で日本経済も後退したのですが、主要因はやはり日銀ではないかとも思ってもいます。少し遅れていましたが、最近は本筋の金融株にも買いが見られはじめ、本格的な上昇相場への助走が始まったようです。2006年の落ち込みの背景を描いた内容が此方のサイトにありますから、良かったらご覧ください。安倍さんは余り頭が良いとは思いませんが、意外に財務官僚の応援もあり上手く事が運ぶかもしれません。
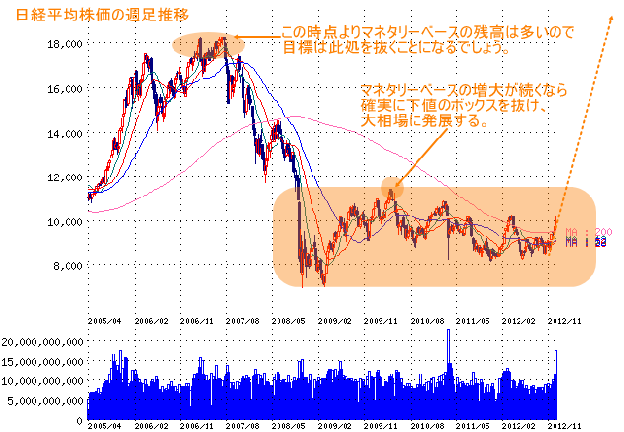
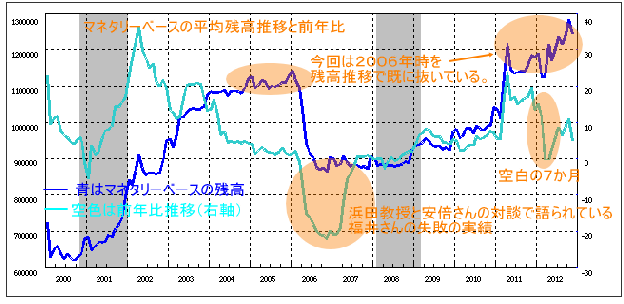
昨日も少し掲げましたが…目先はスピード違反気味ですが、全体を眺めれば、まだまだ序盤なのですね。助走に過ぎないことが良く分かります。今回も3月には、一度、拡大を止めていますからね。白川さんはやはり日銀マンです。空白の7か月が生じるわけですが、消費税の引き上げが話題になると、準備を始めるわけですね。この法案には経済成長の付帯条件がありますからね。その為にここにきて慌てて日銀は10兆円の連発から今回も再び増額です。およそ30兆円を増やすのです。GDP比で7%規模なので、マズマズ効くのでしょう。この姿を見て為替も反応をしています。外人筋は基本的に結果主義で政策が動くなら買い続けるのでしょう。日銀の発表から実際に効果が出るまで半年近くの時間差があります。その点を留意されてください。
皆さんもこのコラムを読み、カタルが掲げるマネタリーベースと株価のレポートを何度も読み返し、自分自身で調べてみれば、カタルの考えを納得されるはずです。このようなバックボーンがあれば、お金など簡単に作れますね。問題はタイミングです。そのタイミングを掴むための検証作業は続く訳です。今朝は布団の中で気付いた試みの検証をこれからします。果たしてどんな結果になるか? 有益なデータが得られると良いのですが…
投稿者 kataru : 11:42
2012年12月16日
検索してみよう!
自己資本比率規制が金融の力の源であるリスク許容度を奪い、流動性の罠が生まれました。つまりお金が動かなくなる現象ですね。一般的にリスクに対する考え方は、時間により増幅されます。つまり投資する時間が長ければリスクは増大するわけです。この危険を避ける為にネット・トレードは短期売買に集中しました。この売買手法は、日ばかりを主眼にするもので、銘柄の善し悪しは関係ありません。今日はどんな動きをするか?…と言う短期の主眼によるもので、人気が集中し出すと、最初にその流れを掴まえ、最初に乗った人が勝ちで、他は負け組の世界ですね。一日で勝ち組と負け組が決まります。故にその日限りの動きが主流になります。翌日には若干、前日のムードを引き継ぐケースは多いですが、基本的に、新しい一日が始まった瞬間から、別の銘柄との観点で相場が動きますね。
一方、カタルの投資はオーソドックの投資を心掛けています。基本的に中長期に上昇する銘柄を選定しようと努めています。その為に投資した会社の利益が増えるかどうか?時代を読む工夫が必要になります。最近のデータから米国経済の回復が可能性は高いのですね。ただし目先的に「財政の崖」と言う財政支出の削減と減税の終了。つまり増税効果が消費支出を減らし経済の需要を減らすので、景気が落ち込むというシナリオですね。この為にFRBは追加の金融緩和QE3を実施し、更に最近はツイストオペの終了で長期債の買い入れが減るのでそれを補い、さらに失業率のターゲット目標6.5%を加えていますね。この政策は、つまり資金需要のバランスを加減し株などの資産インフレにより、消費の下落を防ぐ効果を生んでいます。通常、米国株は下げるのですね。ところがFRBは資産価格の下落が消費に影響を与えることを知っているから、下げないように予防的な処置を講じるようになっています。
今までの常識では結果が生まれてから、その結果を受け対策を実施するというものから、予測に基づいて行動するようになっていますね。この時間差に日米間の政策方針の違いがみられます。日本は常に後講釈と言うか…結果を踏まえて国民の声から行動を嫌々起こす。と言う側面が多かったのですね。だから先日の白川さんの反応に繋がっています。日銀は欧米の中央銀行より率先して金融緩和を実施していると反論をしている訳です。結果が全ての世界で自分は一所懸命に勉強したが受験に失敗したと言い訳をしている訳ですね。しかし米国は結果が全て…失業率が上がると批判を受けます。だから今度は失業率を目標値に据えて改善するとバーナンキは主張しています。
ここで日銀の検索サイトに飛んでマネタリーベース残高と前年比増減を調べてみましょう。自分で探すのは手間がかかりますが、一度覚えれば必要な時に自分で確認できます。その様子を示しますね。順を追って選択しグラフの作成まで日銀のサイト上で作れるようになっていますから、視覚的に様子が分かりますから、皆さんの相場観の参照になるでしょう。作業が終了したら、10月の26日の「今日の市況」から株式教室、コラムを通じて、この辺りの考え方を解説し直しています。今回の株高の背景を、マネタリーベースから説明していますから参考にして下さいね。僕は自分で調べて、自分なりに考えて書いているから、僕は頭に入っていますが、皆さんはその作業をしていませんから、僕の認識より株高の背景に対する考え方が、希薄だろうと考えますから、改めてこの認識を植え付けておきたかったのです。
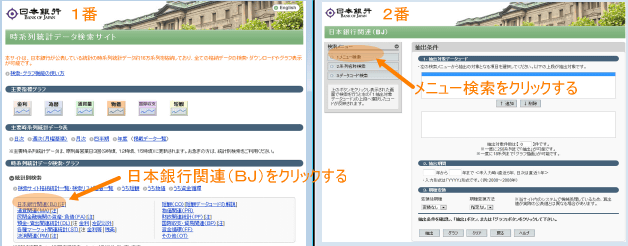
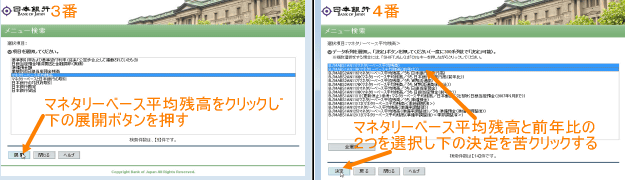
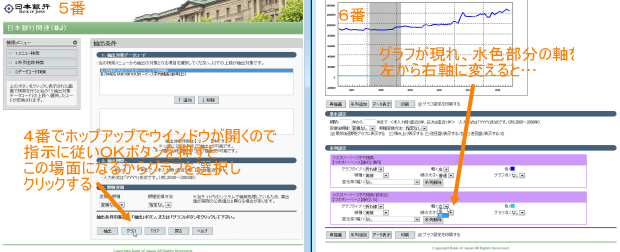
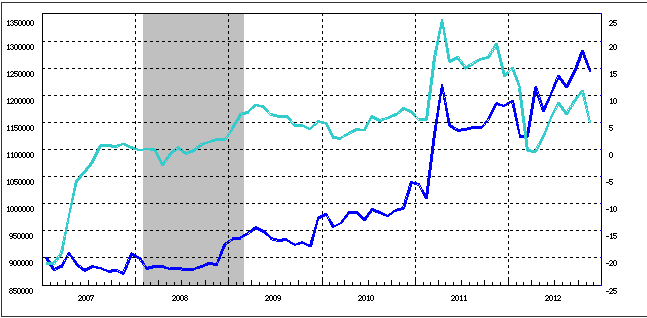
しかし…残念ながら僕の理想とする相場展開と、実際の…この2か月ほどの相場展開は若干イメージが異なっていますね。この誤謬が気になっているのです。実は昨日の原稿は書いている途中で、その引っかかりが気になり、また空想の旅に出て疲れてしまったのですね。どうもシックリこないのです。違和感が生まれた時は注意を要します。おそらく相場に参加している投資家もその事を潜在的に意識している筈です。毎年繰り返される新春相場への期待値で相場が下がるとも思いませんが、昨日の無制限と認識していたのに、15兆円の貸し出しと判明した言葉の違いなど含め、何か違和感を覚え始めていますね。このような時は、通常は確かめ作業が市場で起こる筈です。つまり相場は弱ければ下がりますし、強ければ物色に変化が生まれます。
昨日、解散が決まった11月14日からの上昇率の検証をしました。これまで二度、大相場への相場のスタートを経験していますが、どうも記憶はあいまいですが、少しイメージが違うのですね。潜在的な金融相場と…。このギャップが気になって仕方がないのですね。早くも来春に予定される日銀総裁の椅子に焦点が当たっています。武藤さんや竹中さんが有力候補となっていましたね。まぁ、3代続く失敗を繰り返したプロパーからの起用はないでしょう。つまりだれが日銀総裁になるにしろ、更にアクセルが踏まれることは確実です。加えて何処かの時点で、円安の弊害が指摘される時期が来るかもしれません。100円を超えれば、企業の合理化努力では吸収できませんね。90円を超えた段階で青色吐息でしょう。特にパンなどの小麦メーカーやガソリン価格など…影響が在るのでしょう。
マネタリーベースの増大は続くものと思われ、相場が下落するシナリオは考え辛く、やはり物色の方向性が変わる可能性があるのでしょうか?しかし…見えませんね。今週は総選挙の結果を受け、自民党政権の先走りをするのでしょう。故に三井住友建設などが有力視されますが、金融株が飛ぶような場面があると、直ぐに一服の展開を迎える可能性もありますね。ただ銀行セクターが上がると途端に市場マインドが大きく変わります。ボリュームが一段とアップしますからね。そこで調整波動を迎え仕手系の個別物色か?と言う読みが今の選択肢ですね。今日は16日ですから、来月の半ばまで強含むと読むのが一般的かも知れません。
時間とリスクの関係を考慮しながら、新しい相場展開を読むことになるのでしょう。さぁ、これから選挙にでも行ってくるか…皆さんも、ぜひ投票を!
投稿者 kataru : 13:36
2012年12月09日
桜田門外の変
昨日、テレビで「桜田門外の変」が放映されていました。それにしても…面白いものですね。人間の欲望と言うのは…限りがありません。水戸藩士の立場から描いた幕末模様のドラマですが…関鉄之助が舞台の主人公を務めており、その背景を調べてみたくなったのです。彼の存在は明治維新の一翼を担っていた可能性がありますね。何も坂本竜馬など…有名な人間だけが時代を創っていったわけでなく、井伊直弼から安倍正弘などの人間が当時の時代を創り上げる背景の一部に溶け込んでいます。どうしても株式市場の裏に隠された見えない糸を考えて行くと時代の背景を探ることは必要になります。
相場を作るのはいくつかの重要な要素があります。その重回帰分析のなかで複数の説明変数が株価を左右するので、その背景を探る訳ですね。相場を作るのは時代の流れを読むことです。先日、いくつかの今後のパターンが考えられるとしてマネタリーベースの増加の観点から、もっとも影響を受ける金融株の中から、三菱UFJ、みずほ、野村証券を掲げ、自民党の財政政策の公共事業投資から、三井住友建設や大手建設株を選択、更に産業革命に匹敵する情報革命のIT分野からグリーやDENAを選択していました。もし方向性がもっと絞れれば…仮に中央道の崩落事故が事前に分かっており、「予防保全」と言うキーワードがもっとクローズアップされ、残る確率が高いなら三井住友建設だけを選び資金を集中投資すればよかったのですね。
ここで相関関係から効率的なポートフォリオの配分が影響します。皆さんにはシャープ・レシオなどと言う考え方まで理解しておく必要はないでしょうが…カタル投資はリスク・ウェートが高いですからね。気を付けねばなりません。
つまり関鉄之助の立場だけで物事を判断できません。暗殺された側室の子、井伊直弼は父の死後、三の丸尾末町の屋敷に移り、17歳から32歳までの15年間を300俵の捨扶持の部屋住みとして過ごしたのだそうです。ここでのチャカポン(茶・歌・鼓)時代の遊び生活が、その後の出世に影響し大老職まで繋がるのでしょうが、その陰には、勝海舟やジョン万次郎などを登用した阿部正弘の存在が深く関与しているようです。歴史は面白いですね。ジョン万次郎と三菱の創設者、岩崎弥太郎は、この当時から関係を築いているようです。丁度、今の時代のように…インターネットが発達してアラブの春から時代変化は、ペリーの来航の時代背景に良く似ています。
人のつながりが、歴史を築いています。考え方の違いや選択の違いにより、人間関係の相関図が生まれ、思想の違いが仲間関係を築きます。関東連合や山口組などの組織から、桜田門の人脈まで…色んな考え方が交差し、社会構成が創られますね。市場原理主義者に日本村社会論理など…どれが良いという選択肢は決められませんね。関鉄之助は1858年に越前、鳥取、長州に遊説に行っています。そうして実行隊長として1860年3月に井伊直弼を襲撃し暗殺します。その後、2年程度、逃亡生活をして時期を待ちますが、1862年6月に斬首されています。大政の奉還は1867年10月ですね。僅か5年程度の違いですね。
新しい世の中を見る為に奔走し、夢の実現が見られない人生があります。彼らの奔走が薩摩藩を動かしているとも言えますね。意見はそれぞれ違うのでしょうが…単なる恨みなどが桜田門外の変に繋がったわけではないでしょう。時代背景を考えれば、幕府と米国の不平等条約の締結が、大きく影響を与えています。今の世も日米同盟に関わり、地位協定の壁が沖縄県民の心情を大きく揺さぶっており、鳩山さんの退任に繋がりました。歴史の流れ、株式の…相場の流れは、時代背景に大きく影響され、人々の心を動かし相場模様が演じられていきます。
投稿者 kataru : 12:24
2012年12月02日
為替と株価の連動性
昨日の続きは又にしますが…基本的に一般的な認識と言うのは、怪しい幻想のようなものだという可能性があります。円安だと何故、日本株が上がるのか?
日本は加工貿易国家で、GDPに与える輸出の寄与率が大きいから、円安になると企業利益が大きくなり、株価も上がるというのが一般的な認識です。円安になれば価格競争力が上がるというものですね。しかし…自動車業界にとっては、確かに有利です。しかし考えてみれば分かりますが、円高が進み既に大衆車などは、日産だけでなくトヨタも生産移管をしており、そんなに円安が有利かどうかわかりませんね。むしろ国家として見れば、食料品やエネルギーなどの購入代金の方が大きく、総体的に考えると円高の方が有利なのかもしれません。それなら何故、為替と株価の連動性が高いのでしょう。ここでベータ値と言う考え方が有効になります。果たして円安は株高に連動しているのでしょうか? 今日はこの連動性を見る為に、日経平均株価と為替の関係を見てみようと考えています。
さて検証の結果、近年は多少、円安になると株価が連動している傾向もありますが、それほど強く表れているかどうか…。マイナスの時期もありますからね。必ず連動しているとは言えません。1998年頃は、むしろマイナス連動率も高くなっています。近年は多少円安になると株価が上がる傾向があると言う程度でしょう。(黒の線はベータ値の近似値で移動平均線のようなものです。)
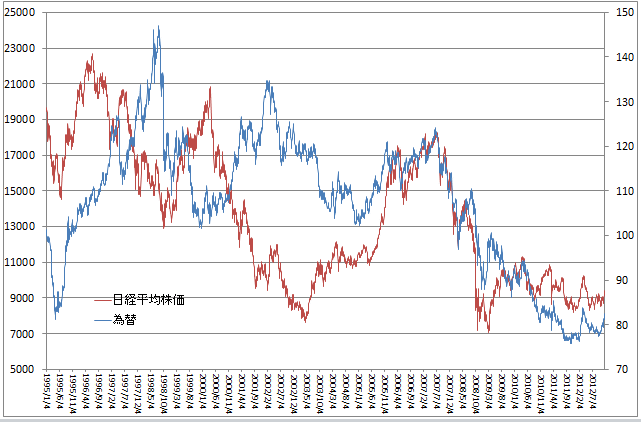
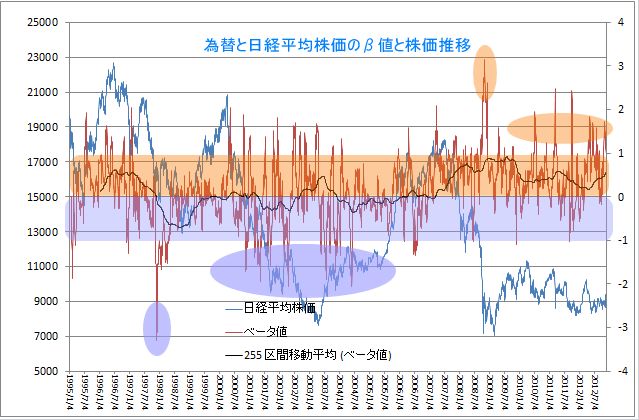
投稿者 kataru : 19:10