« 2012年10月 | メイン | 2012年12月 »
2012年11月25日
投資のタイミング
今年も間もなく終わりそうですね。1989年のバブル相場はやはり異常だったのでしょうかね? 僕が証券界に入社した頃の日本株は8000円で、NYダウは一ケタ違う800ドルだったのですね。それがいつの間にか逆転しています。NYは10倍になったのに…日本は横這いですね。30年以上の空白か。一つの理由は非効率な資金配分です。この所、マネタリーべースと株価から「信用創造」の話をしていますが、日本は東西冷戦下において、土地担保金融の仕組みを構築して総資産経営を実施してきました。具体的に総資産経営とは規模の拡大を示します。売り上げさえ伸ばせば、利益率はどうでも良かったのですね。この経営が成り立った背景は規模の拡大により資産が増え、その資産が従来は膨らんできたので、多少、経営の失敗があった時は、その資産を売却して穴埋めに使う見せかけの経営を長らく実施してきました。この事を総称してカタルは売り上げ重視の経営を総資産経営と述べています。この中には見えない援助も含めます。よく日本は恩を売るという事をしますね。NECは今回、ルネサスにその恩を売りました。本来は必要のないお金ですよ。しかし日本村社会の参加料のようなものですね。この連帯意識も総資産経営の中には含まれています。
故に、我が国の邦銀は経営に必要ない土地を買い、店舗を拡大させ、株式の持ち合いをして成長してきましたね。しかし土地担保融資が減ったら…収益の源泉を失いました。純粋に事業融資を見て来ませんでしたね。だから担保はあるかとか、保証人はどうだとか…を気にしていたのです。自分達が融資に対し事業が伸びるか?とか、この融資により経営が成り立つか?…とか、そのような判断は二の次だったのです。土地担保による信用創造が失われた時代、本物の事業経営者の時代になり、右往左往しているわけです。
先程、テレビで野田総理が、多くの人は土地や株を持ってないから上がってもインフレになるだけと、安倍さんを批判していましたが…彼は財務省論理の代弁者ですからね。でもわかっていませんね。やはり馬鹿政治家と言うか…みんな政治家のレベルは、あの程度なのでしょう。安倍さんもそうだし…真剣に考えた事が無いのですね。土地や株が上がると信用創造が生まれ、ユトリが生まれますね。そうすると人間の行動は大胆になり消費は伸びるし、投資が起こるのですね。だから常に信用創造の重要性を経済では考えないと駄目なのですね。米国はCDSと言うものを保証して信用創造を膨らまし、実体金融を上回る規模まで膨らましたのですね。架空金融の拡大ですよ。金融危機はこの膨らみ過ぎた部分、実体金融と乖離した部分の調整をしたわけですね。乖離した株が下がる原理と同じですね。財務官僚は信用創造の力をよく理解せねばなりません。
更に今日の日経新聞の2面に米国と日本のROEの比較が載っていますが、今述べた総資産経営の実態が映し出されており、今後は固定資本形成による成長ではなく消費による成長、つまり本当の経営の良し悪しにより、付加価値の高い経営が望まれる勝負の時代になります。日本株のPBRが割安なのは付加価値を生まない資産を多く持ちすぎています。東電を見れば分かります。保養所、健康保険組合による診療所、運動グランドから講演設備など…兎に角、無駄な資産を多く抱えています。多くの大企業はそうですね。日立などは代表的な事例です。しかしグローバル基準では、如何に付加価値を高めるか?つまりROEを高めるかと言う効率的な資金配分を求められますね。IAS(国際会計基準)により、ものさしが同じになります。日本の企業も米国の企業も同じ土俵にあがり勝負です。売り上げに対し、如何にコストを掛けずに儲けるか…どれだけ付加価値を生むかの戦いです。この付加価値は人々の心を揺さぶることですね。芸術であり、音楽であり、要するに人々を魅了させるものですね。原価を掛けずに…高い付加価値を生む戦いなのです。
ゲームはある意味で一つの芸術なのです。嫌う大人は大勢いますが…。ゲーム業界のROEは高いですよ。ROEは付加価値を測る物差しで、世界はその競争をしています。故に一人あたりのGDPが、常に競われる訳です。円安になれば日本の一人あたりのGDPはどんどん減りますね。その失われる分、頑張って効率的な資金配分を実施しないとなりませんね。余った予算を年度末に無駄に使う硬直化した仕組みを変えねばなりません。
自民党政権は、コリゴリだと言うのはヤン場ダムや諫早の代表事例があるからです。森政権下のIT投資ならある程度は、意味は分かります。民主党政権下で修正を試みましたが、前原さんの失敗は人間の感情を無視したものだったからですね。今の原発の後処理と同じですね。フクシマの問題は、早く、一度全ての土地を国が買い上げるべきなのですね。そうすれば、被災者は諦めが付き、新しい生活への踏ん切りも付くのです。再開発して戻りたい人は、後で優先的に住めるようにすればよかったのですね。何故、そのような政治決断ができないのでしょう。小者ですね。東電などと言う一民間企業を悪者に仕立て上げ、逃げるのは小者がすることです。兆円単位になれば、国家責任です。その為の法律なのに…トホホ。
一方、日経一面の素材価格の下落の話は、中国の非効率な固定資本形成の拡大による弊害ですね。この点では日本の資産配分の方が、嘗ての大蔵省の方が上のような気がします。構造改革に失敗した後半は、日本も間違いましたが…。中国の場合はスピードを速めた為に色んな弊害が生まれているようですね。ただ一時的なバランス修正でしょう。詳しく見てないので、いつごろ解消されるか分かりませんが、日経新聞が取り上げて一般化させると言うことは終盤が近いのでしょう。商船三井の芦田さんも、ここの落とし穴に嵌りましたね。2006年からの成長は、米国の「影の銀行システムの発展」により成り立ったBIRCsの成長だったのですね。嘗ての造船ブームと同じで、新興国全部が日本化したと思い、投資を削るべきでしたね。まぁ、今の淘汰で最新船に保有船が入れ替わり、将来は良いでしょうが…、この世界景気の回復がいつになるか…各国は財政赤字に苦しんでいるから、大ブームが巻き起こるかどうか難しいですね。幸い、日本はアジア圏ですから、中国は減速しても、アセアンなどの成長国を抱えますから物流は伸びますからね。来年になると船舶も回復の兆しが見えるかもしれません。ただ、かなりの過剰投資だったから…。川崎汽船に投資した小手川君(あだ名はJFさんだったかな?)も、財務指標の罠に嵌ったんですね。オリックスに投資した時には、流石に一流の領域だな…と感心していましたが、川崎汽船は難しいかな? でも時間が解決します。彼の判断は間違ってないので時間の問題だけでしょう。
企業経営者も難しいのですね。設備投資を何処の国でするか? まさか原発事故が起こるとは考えていませんし…日中関係がこれほど悪化するとも考えていませんね。ソフトバンクの孫さんの決断に僕は賛同できますよ。このタイミングで日本の円を借りてドルに投資するわけで、仮に1ドル80円のものが120円になれば…スプリントの株価が上がらなくても5割の儲けですね。全ての点でグローバル戦略に乗っているタイミングだと思っています。だからソフトバンクの株価が上がっている背景も、その点を加味している可能性があります。
シャープの片山さんは何を見誤ったのでしょう。亀山は兎も角、堺への投資は冒険でしたね。でもソニーと同じで優れたDENAを持っているから、アップルなどから支持されて存命していますが…あまり調べてないのでコメントはできませんね。ソニーの出井さんも有機ELなどに拘ったために薄型への後手を踏み、折角の映画やゲームのソフト資産が生きていませんね。勿体ない話です。経営者の投資のタイミングは難しいのです。下は大手不動産のキャッシュフローを追ったものです。何れ、この意味を語りますが、先ずは皆さんがこの表を見て、この意味を考えてみてください。今日は時間がないからね。この辺で…
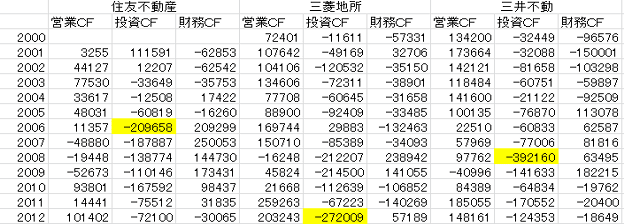
投稿者 kataru : 12:31
2012年11月23日
影の銀行システム
見えない糸からの推測は、所詮は仮説にすぎないわけで、実際にその方向性に向かうか分かりません。昨日の「選択のパラドックス」は、最初に大和証券のCMで用いられていたと記憶していますが、人間は選択肢が増えると買い物をしなくなるそうで…選択肢はせいぜい3~5程度なのでしょう。選択肢が15も20もあると一見すると便利のようですが、かえって選択に悩み、購買意欲が低下すると言うものですね。ホンダのN-ONEは大丈夫でしょうか? さて、田中さんが取り上げておられる「影の銀行システム」と言う記述に関心を惹かれたので、一般化してないので少し解説してみます。僕のページでは何度か「金融デリバティブの発展」として解説してあります。要するに「信用創造」ですね。
経済が発展するためにはお金が必要です。景気が良くなるとか…悪くなるとか…この違いは丁度、電子レンジのようなものですね。電子レンジの構造は食物にある水分子をマイクロ波により振動させて摩擦熱で温めるわけですね。基本的に景気が良くなるというのも同じことで経済の中には人間が沢山いるわけで、その人間を動かせばいいのですね。一所懸命にマラソンをさせても効果は薄く、経済上ではお金を使わないと駄目ですから…お金が盛んに動けばいいのですね。例えば何年も株価が低迷すると、人々の人気は離散し、投資行動が停滞します。カタルがよく引き合いに出す、市場全体のリスクですね。指数による上下で株価が上がっても多くの人は魅せられないのです。ところがJトラストのように29円の株価が2600円にもなれば約90倍ですから…僕が投資しても上手く行けば…と考え投資する気持ちが動くようになりますね。買い物も同じ原理ですね。人々の欲望を刺激して行動を促進させます。人間が動くという事はお金が動きますからね。
さて信用創造とは…行動する為に危険が伴うと皆が躊躇(ちゅうちょ)します。「二の足を踏む」と言う心理にさせては駄目なのですね。株価が急騰すると…あぁ、買っておけばよかったと後悔の気持ちが湧きますね。このような心理を与え、更に誰かが最初に冒険の気持ちで思い切って買って儲かると…これが自信に繋がりこの人は、さらに投資額を増やし投資を続けます。この連鎖の輪が必要ですね。投資に対する信頼感を与えることは非常に重要です。一時、日本はITブームが起こり、小手川君のような存在の若者が誕生します。要すると…それに続こうと、我も我も投資ブームに火が付きますが…若者の懐は浅く、直ぐにITブームは下火になりました。ただ若者は、何故、失敗したか考え、再びチャレンジしますね。ここが若者の特権です。人生に時間があるから何度もチャレンジします。しかし年金生活者などは生活手段がないから、一度、失敗するとチャレンジをしなくなります。2001年からの市場原理導入により外人投資家が2003年に復権し、今度は小泉政権の後を任されたはずの市場原理主義者、安倍政権の樹立が、外人投資家に安心感を与えている可能性が高いですね。特に「日銀に国債引き受け」と誤解を招くような、インフレターゲット論を唱える信者なら、日本は市場経済化の道を再び歩む…んじゃないか?と外人投資家が考えても不思議ではありません。ここに信用創造が生まれる原点があります。
日本の高度成長の原点は土地担保融資と言う信用創造の仕組みでした。ところがバブルの絶頂期にこの仕組みを米国の指摘により放棄してきました。宮澤総理が失敗したと嘆いたマジックですね。人間はおろかな動物ですよ。でも何かの「心の糧」は絶対に必要ですね。先日、孫さんのビデオを見て頂きましたが…彼の心の糧の原点は、彼のおばあちゃんにありますね。あの貧しい時代の経験が「心の糧」になり、人間の行動力を生み出しています。経済も同じですね。信用創造の定着、信用創造の仕組みが確立されないと景気は不安定でなかなか新しいシステムに移行できません。今は移行期ですね。EUの問題もそうですし、この「影の銀行システム」も同じです。
この影の銀行システムは実際の銀行取引ではなく、架空の信用創造なのですね。CDSと言う、もし融資先が倒産したら、その取引の損失を補うと言う架空の信用創造の仕組みを示します。AIGが破たんしたのは、このCDSを補償できなくなったからなのです。何故、このような仕組みが発展したかと言えば、オプションの原理がブラック・ショールズにより確立されたからですね。金融工学、所謂、確率論の数学の分野ですが、緻密にコンピュータを使った計算された仕組みですね。金融取引の保険ですね。生命保険や疾病保険などは有名ですが、金融取引の保険が開発され、この取引額が大きく膨らんだのですね。しかし、いろんなところが推測で影の銀行システムの取引額を発表していますが、(下のグラフはNY連銀のもの)相対売買の店頭取引なので実態が分かりません。故に総枠として自己資本比率のタガを嵌めれば、ある程度は規制が出来ると始まっているのが「バーゼル3」と言う仕組みですね。
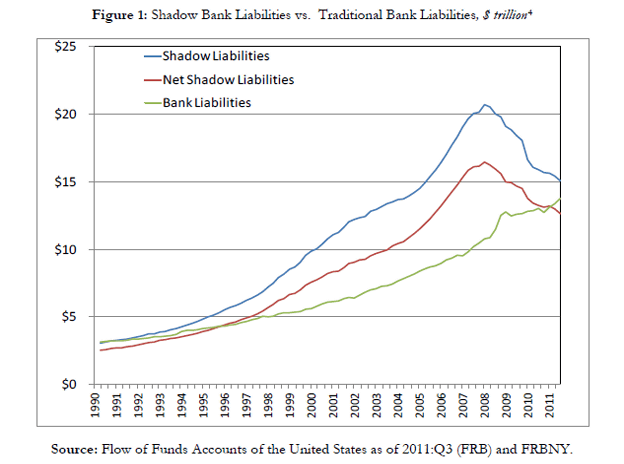
前回の金融危機は、この影の銀行システムが実体をあまりに遊離して乖離したので、その調整として弱体しているリーマンが生贄に捧げられました。市場原理らしい、弱肉強食の仕組みですね。市場経済の仕組み上、必ず、行き過ぎは修正されます。FRBがQE3と言う金融拡大をしているという事は…この「影の銀行システム」(CDSなどを利用した金融デリバティブの仕組み)が拡大していることを示します。だから実体景気は悪いのに、米国の株価は実体景気に大きく先行して回復しています。原油価格もなかなか下落しませんでした。
何故、新興国が急速に発展できたのか? 通常は資金が動きませんよ。ところが安い保険料で投資額が保全されているという錯覚をしていたのですね。信用創造です。金融デリバティブの発展により影の銀行システムが確立され、皆がその仕組みを容認して取引をするようになり、リスクの高い筈の金融取引が実現されるようになりました。その為にBRICsが急速に発展したのですね。何もこの仕組みが悪いのではないですよ。「影の銀行システム」と言うネーミングの響きは悪いですが、この仕組みのおかげでソフトバンクによるボーダフォンの買収は実現され、日本は情報社会の最先端を走っていますね。ソフトバンクがスプリントを買収し、今度はグローバルに船出しますね。この買収を支えるのは劣化している欧米の銀行を乗り越えた邦銀の力なのですね。確かに中小企業円滑法の整理はありますが、それ以上に欧米の銀行が沈んでいるのに…今度は邦銀が活躍できるチャンスになっていますね。どうも…日銀の新手の無制限貸し出しが、寄与し始めている可能性は非常に高いですね。相場をみていると…何か、そのように感じますね。
投稿者 kataru : 12:05
2012年11月18日
分水嶺
維新と太陽が一緒になりました。しかし…まだインパクトは少ないですね。結局、第3極の政権を実現させるには、石原さんと小沢さんの様な水と油の関係のような人間関係にある人達が、大義の下に集まらねばなりません。今のままでは、そよ風程度の影響かな? 今の日本の体制を破るには、もっと強い暴風が必要なのでしょう。株屋としては安倍さんの考え方に大賛成ですが、彼は政治家一族の出ですからね。世襲制ですから育ちの点で、今の荒波を乗り越えられるかどうか? むしろ橋下さんの様な育ちの方が可能性はあります。坂本竜馬の家計は貧しかったという話ですが…この先入観は、どうも大河ドラマの影響かな?
今日の日経には金融緩和が述べられていますが…あの程度の記事はどうも愚作ですね。一つだけ気になったのは、慶応の池尾和人の発言ですね。「構造改革は、辛抱強く成し遂げなければならない」という記述です。わが国の成長を支えたのは加工貿易システムです。安い原材料に付加価値を付けて、加工して輸出する加工貿易が日本の成長を促進させてきました。この富を糧にして輸出によりGDPを引き上げましたが、貿易摩擦を生みプラザ合意でこの魔法の杖が使えなくなったのですね。プラザ合意頃から、前川レポートの内需拡大が問題にされましたが、GDPの構成比をみると依然として消費の比率は米国より低いですね。彼のレポートの骨子は内需拡大と市場開放、金融自由化です。TPPは未だに実現していませんね。1985年からの課題が、まだ揉めています。でも同時に、この金融の自由化により、今の「失われた時代」を生んだとの批判もあります。「馬鹿とハサミは使いよう」と言います。
現況を見ると、パナソニックやソニーなどの超一流企業まで、構造改革の手が伸びています。1992年末のパイオニアの指名解雇から始まった構造改革は弱小企業をなぎ倒し、ようやく日本の本家にたどり着いたのでしょう。ここで慶応の池尾さんの発言が生きてきます。「時間をかけて構造改革するしか道はない。」彼の他の意見を、読んだことはありませんが、この文面から察するにマネタリスト的な考え方をする人ではありませんね。おそらく現在の金融緩和に否定的なのでしょう。何故、頭のいいはずの官僚組織が機能しないのか? 僕には長らくの謎だったのです。彼等はきっと、この構造変化の道を採用したのでしょう。日本村社会は劇的な構造変化に耐えられるような構造でないと判断したのでしょう。故に今の失われた状況が生まれています。
しかし米国は別の道を模索しましたね。ロックアウト解雇を選択し失業率が高まりました。しかし果敢な金融緩和によりドル安を背景にして、製造業も同時に支援しています。日本と違う戦略ですね。一方、日本は中小企業円滑法の採用など…所謂、延命策を永遠と続けています。市場は安倍政権の誕生を読み、僕の目には五分五分の感覚です。昨日はチャート面から少し補足しましたが…何故、三菱UFJは新安値を付けているのに三井住友やみずほは2003年の安値を下回らないのでしょう。株式持ち合いの影響なのでしょうかね? それとも、もう少し時間が掛かるのでしょうか?
三菱はどちらかと言えば、純血主義ですね。合併して大きくなっていますが、内部の話を聞くと東京銀行もUFJ出身者は余程実力がないと、三菱との人間においてハンディがあるのでしょう。しかし僕の知り合いの事例を見れば、この噂される排他的な人事も、本当かな?と疑いたくなります。何故なら、正論を押し通す仕組みを維持しているように見えます。僕の友達は1年分の年収を補償され、移籍させられました。証券界の常識では1カ月分程度、更に余分に考えても、せいぜい3か月でしょう。それを1年分払ったのです。つまり…非常に紳士的な会社ですよ。岩崎弥太郎が創った三菱は、UFJの吸収過程を見れば、我が国の根幹をなすグループですね。この会社の動向が、日本の政策の中枢と繋がっていると思われます。東大法学部の人脈は、日本の根底を成していますからね。
安倍さんは残念ながら、この人脈の筋から離れています。別に学歴で物事をみようとは思いませんが…ハッキリ言って親の七光りの血族人脈で、今の地位を得た人ですね。だから今の難局を乗り切れるとは…到底、考えられません。今の時代は孫正義のような貧しい時代がないと…孫さんが成功された時に、涙を流し講演されていました。その映像が此方です。
以前も紹介したことがありますが…何度、聞いても感動を貰いますね。僕は野田さんも嫌いじゃないですね。あの16日の日を語った国会答弁はなかなか、どうして…、彼の発言も感動を与えてくれます。おそらく手腕は兎も角、彼も誠実な人なのでしょう。でも残念ながら、安倍さんにも、石破さんにもそのような感覚は、今の所、抱きませんね。むしろどうせ駄目なら橋下さんを選択したいと思っていますが…、野田さんも捨てがたいな。と考えますね。何しろ、いくら財務省論理優先の政策とは言え、党を割ってまで実現させた行動力は捨てがたいものがあります。つまり僕の選択はまだ決めていませんが…株屋としては安倍さんですが、野田さんか、橋下さん、どちらかの選択になるでしょう。
マネタリーベースから見れば、いつ起こっても不思議ではない株価上昇も、まだ分かりません。このまま上がるかもしれません。その確率は五分五分程度でしょう。日銀の無尽蔵の貸し出し支援は、どのような広がりを持つかですね。この政策はホームランになる可能性も秘めています。奇しくもパナソニックもソニーもリストラですからね。とうとう日本を代表する一流企業まで、構造改革の手は伸びてきました。この需給バランスの改善は、日中の貿易額推移からも垣間見られます。株価面も、GDPの構成比からも、全てのデータが構造改革の終盤を告げています。いずれにしても…長かった「失われた時代」が終わりを告げる時が来ましたね。あとはタイミングなのですね。国民の選択と見えない糸のタイミングがどう変化して行くのか?
年金資金なら、現物株投資なら…全体に間違いがない株価水準なのです。しかし時間が見えないのですね。目一杯張るとすればレバレッジをかけます。そうすれば時間や変動幅が問題になります。この微妙な揺れ具合が、成功か失敗かを分ける成否の分水嶺です。だから走り出してからでも良いのですね。上手に行動しようとか、うまく立ち回ろうとか…思わなくても、余っている資金なら株を買って待てばいいし、半分だけ投資してあとは時代を確認する方法もあります。いろんな選択肢はありますね。僕は残念ながら、ユトリがないから一発に賭けるしかありませんが…そのタイミングに迷いがある以上、なかなか行動に移せないが、同時に時間も限られています。だから運命論が僕の心を縛っています。時代の流れに身を任せるしか最後は仕方がありません。孫さんが成功できたのは…あの苦しい時代がバネになり、努力もされて、しかも時代が味方をしたのですね。同じように努力して挑む人は大勢いますが…あとは運、天命を待つしかありません。長く投資をしていると運を感じることは良くあります。果たして僕にその機会は回ってくるでしょうか?
ユーチューブの孫さんの講演を、こうして聴ける時代です。インターネットは素晴らしいですね。やはり革命ですよ。産業革命以上の飛躍期なのでしょうね。ただ時代の渦の中にいる僕らには、その事を客観的に判断できないのでしょうね。この渦の中で、もがき苦しみ努力して早く高みに登り、少し休みたいですね。さて最近は三角関数に興味を覚え、あるアイディアの検証をしてみようかとも考えています。僕のエクセルには色んなデータが集まり始めていますからね。もう少し数学やコンピュータのプログラム知識があれば…な。これから少しずつ勉強するしかないな。
投稿者 kataru : 12:14
2012年11月11日
紅葉と性の喜び
誰もが見れるインターネットの閲覧を、著作権の名のもとにタガをはめる行為は、如何なものでしょう。例えば、日経新聞の転写をしようとするとコピー&ペーストが使えません。つまり、著作権があるから勝手にコピーはするな! この記事には著作権がある。との表明なのでしょうね。それならばインターネット等を利用しないで、公開しなければいいと思います。あくまでインターネットでの公開なら、誰もが自由に使っても良いのではないかと思っています。誰かが、勝手にユーチューブに楽曲を投稿したとします。この場合は悪質なケースに辺り、それを二次利用するのは問題があるでしょうが…。そもそも新聞の記事などに著作権などあるのでしょうかね? 新聞は事実を伝える報道で客観的な事実は公のニュースですね。もしこの論方が通るなら、事件を取材するドラマにも著作権がある筈で、メディアは勝手に報道できないことになりますね。当事者の利用許可が必要になります。自分達は公に報道する義務があるから、勝手に事件を面白おかしく報道しても良いと言う勝手な論理は如何なものでしょう。悪質な取材競争は一般庶民の生活の権利も侵していますね。芸能界はそれを商売にしているから報道しても許されるという論理も拡大解釈になりますね。
ただ事件でなく論文なども新聞に書かれていますが、新聞はインターネットと同じで公器ですからね。やはり一旦発売された以上、みんなが利用しても良いのではないかな? この著作権の話ですが…図書館は購入した本を無料で貸し出していますが、図書館は一回あたりの貸し出しで、いくらか著作権料を作者に払っているのでしょうか? おそらく払っていませんね。何故、図書館は許されるのでしょう。レンタルソフトも同じ範疇ですね。映画などのDVDを二次利用していますね。更に、この著作権には時間の概念がないのでしょうか? 古い作品は無料となっていますが…。発売後1年、2年も経ったCDが当初2000円なら、1年後は1000円、2年後は500円、3年後以降は200円と言う形の時間概念を導入するのが正しい値付けではないでしょうか? 本も一緒ですね。もっと合理的な価格形成が出来ないものなのでしょうか?
一方、株価はいつも市場価格により上下しています。野菜の価格形成と一緒ですね。基本的に需給バランスで動いていますが…その背景には色んな仕組みが働いています。一般的には業績が良くなると株価が上がりますね。そうしてカタルは、この数週間のテーマとしてマネタリーベースと株価の関係を、推論を交えて解説してきました。この何回かの特集はカタルの考えであって正解ではないかもしれませんし、異論もあるでしょう。市場には様々な意見があって良いと思っています。市場経済においては正解などないのでしょう。常に周りを取り巻く環境は変化し、時代と共に市場参加者も変わり、考え方が変わっていきます。
昔は配当利回りだけで株価を捉えていた時代が長く、時価発行増資もなかったのですね。全て額面発行で、株主割当増資が多かったのですが、日本楽器(ヤマハ)が1968年に最初に時価発行増資を実施し、それから現在の形態が一般化しましたね。現在は制度上の不備も多く増資の手続きに時間が掛かり、その為にシャープのような問題も起こりますね。シャープの増資引き受けが、制度上の問題だったのかどうか…僕にはわかりませんが、その可能性はあります。行政の仕組みは時間の概念がありませんからね。
日本の場合は、野村証券が株式持ち合い活動を推進したと言います。日本村社会構造ですね。つまり株主の権利を形骸化させる行動でした。この為にバブル期は異常なPERの水準にまで株価が上昇し、その価格を説明するためにQレシオなどの概念が導入されましたね。この背景は日本村組織が収益を無視した、総資産経営に向かった、規模の拡大を追い求めた時代の弊害です。その為に邦銀は自己資本比率規制問題で発生しており、日本の失った時代を長引かせる要因にもなっています。少し分かり辛いでしょうか?
日本は高度成長するために、その基礎が必要になったのです。その為に土地を利用したのですね。土地に複数の価値を持たせ…路線価とか、固定資産税評価額とか、基準地価とか、公示価格とか…いろんな価格が存在していました。この背景には実際の取引価格が基準になるのですが、少ない取引の売り手と買い手の相対売買で価格が決まり、そもそも時価評価が難しいと言う問題があります。しかし要する土地担保融資を認めてきた信用創造の仕組みに問題が在ったのですが…この仕組みのおかげで高度成長が出来たことも事実です。
要するに地価を利用した信用創造は妥協の産物ですね。
この信用創造を実現させたのは日銀であり、長く土地担保融資を認めてきました。大蔵省もね。昔は日銀の権限は非常に強かったですね。窓口指導は絶対的な権限を有していました。しかし現在は日銀の権限は、以前ほど強くないですね。その代りに金融庁が台頭しています。本来は大蔵省が関与することが筋違いなのでしょう。金融機関は日銀が管理する事項なのでしょう。ところが日銀は失態を何度も犯したので、大蔵省の力が強くなって行き、今では財務省の傘下になったような印象もあります。独立性なども良く問題にされますね。それはこれまでの実績がないから、仕方がありません。でも日銀だけのせいではありません。
「生活大国づくり」を作成した宮澤政権下では、地価を下げる為にバブルの絶頂期に、その作業に取り掛かっています。今日の日経新聞には、先日、僕がマネタリーベースと株価で解説した時期の模様が、13面に掲載されていますね。僕は金融面に焦点を充て東京協和信用や安全信用組合を掲げましたが、日経新聞では分かりやすく、桃源社が落札した蒲田の土地価格が657億円で、建設費込みで1000億円のビルが、銀行に398億円で自己競落され、その後、最終的に区が173億円で落札した模様が描かれていますね。1000億が173億円ですよ。この下落分の大半を金融機関が負担したのですね。だから膨大な不良債権が発生し、その結果、金融機能が失われ、長い失われた時代の低迷に繋がっています。
しかし、この記事も間違いに気づいていませんね。確かに米国の地価合計を上回る日本の地価創造は間違っていたのですが…その事を修正する時期も問題です。しかも、そもそも信用創造の間違いの存在を、そのまま認めておいてもよかったのです。その間違いを米国から指摘され、その論調を開くと、直ぐにこの信用創造の仕組みを間違いと認め、正論を展開する間違いを、この記事は気付いていませんね。レポートを書いた人は、この意味を理解していますか? 宮澤喜一や尾崎護、小川是などのエリート集団は、米国の戦略に踊ったのですね。
だってお金などは、所詮、紙くずですよ。皆が信じるから、紙くずが価値を有するのですね。その価値を守る為に、財政赤字の問題などが欧州で問題になっています。しかし日本にしか存在しない土地の価格が、米国と比較して割高でも良かったのです。なにも土地の価格が日米で、同じ評価でなくても良いのですね。確かに市場原理主義において、収益還元法によって、その存在価格は論理的な価値に収斂する筈ですが…それを直ぐに改めなくても良いのですよ。今、日本の財政問題が話題にされ、他国と比較してGDP比で問題を問われていますが…確かに正論ですが、直ぐに慌てて修正しなくても良いのですね。お金は充分に回っているのですから…。為替を見れば分かりますね。円を持っているのは、日本人だけですから…米国はこの仕組みを上手く使っていますね。ドルの信用創造を世界に認めさせています。少し難しいかな?
僕らは何を基準に行動するか? このような問いかけをしているようですね。最後は生きる意味とか、信条のようなアイデンティティーの問題になりますね。
付加価値の最高峰は人々を驚かせる、感動を与えるものですね。絵画であり音楽であり人間が感じる五感を揺さぶる価値が最高の付加価値です。GDPの成長はそれを競うゲームなのですよ。だからハードではなくソフトが無限の価値を秘めているのです。何故、グリーがこの評価なのでしょう。多くの人が時間を費やしていますね。人々を魅了しているから人間は時間を費やすのでしょう。
性もそうですね。これは本能を刺激して商売に結びつけていますが、ラブストリーなどが映画や小説のテーマになるのは、人々を魅了するからですね。セックスはその演出に過ぎませんね。最初は射精する快楽を求め行動しますが…次第に女性に対し多くの付加価値を求めるようになります。夫婦が互いに成長しその変化を楽しむとか…人間的な成長の刺激を求めるのが互いの関係とも言えますね。だから互いに成長してないと、生活に変化が生まれずにパートナーの存在価値が薄れていきます。セックス以上にベットでの会話などは大きな意味を持ちますね。もちろん、男にとって普段、日常見せない仕草を見せるベットでの女性の表情などは魅力的なものです。その変化が日常のそれと比較し深ければ、深いほど欲望を掻き立てられますね。東大を出たバリバリの女性のエリート上司だが…彼女の夜の乱れた姿を想像することが…エロスに繋がります。丁度、紅葉と同じで寒暖差が激しいほど綺麗なのですね。
すこし話はそれてきましたが…小説を書く訳ではないですからね。話を戻しましょう。今日は何をテーマにしたのでしょう。そうです。著作権の話しから株価の話をする為にCAPMモデルまで話を持って行こうと画策したのですが…いつしか路線から外れました。面倒くさいから書き直すのは止めて、いきなり、結論を…飛躍していますが、市場リスクと個別株リスクの産物で株価は決められており、現在は市場が非常に低迷しているために個別株の優位が反映されにくい状況だと認識されています。故にマネタリーベースと株価のレポートを書いたことに繋がっていますね。だって個別株の優位性をいくら説いても、それ以上に市場全体が沈んでいるから、ものさしが歪んでいますからね。
先ほどの話に戻りますよ。日経記者が書いたピーク時の日本の地価がGDPの5倍で、その時にGDPの2倍の米国の国土が4つも買えると言う論理を持ち出し、故に日本の土地が高いから下げなくてはならない。と言う論法を米国が持ち出し日本の政策官僚はもっともだと納得して、その甘言の乗ったのですね。その結果が「失われた時代」ですよ。ところがこの政策の結果、収益還元法などで下げ止まる筈の地価も、配当利回りで下げ止まる筈の株価も、まだ下げ続けているから不思議ですね。市場全体のリスクの影響が強すぎて、個別株の優位性など論じても仕方ないから、2年前に株屋を辞めたのです。しかし最近の研究では、そろそろ、この修正が起こりそうですね。いつまでも無尽蔵の紙くずの信用創造が、実体価値と遊離して広がり続ける訳がありませんね。必ず、大きな修正が起こりますね。肝心のCAPMモデルの話しもせずに…いきなり結論に急ぎましたが、日経新聞さんのこの「経済紙を歩く」と言う正論は、実社会に於いて正しい選択だったのでしょうかね? 物事にはいろんな見方があるのですね
投稿者 kataru : 14:21
2012年11月04日
ベースマネーと株価3
池上彰さんのニュースの裏解説が人気になりましたが…カタルのIRNETはその小型版で株式市場を取り巻く環境にスポットを充てています。例えば今朝の日経新聞で新築のビルが好調だという記事が一面に踊っていましたが…あの背景は震災の影響が在りますね。水面下では既に話題になっているのでしょうが…東京都は間もなく耐震規制を発動するのでしょう。そうすると古いオフィスビルは改築をしなくてはなりません。だからリートは危ないのです。もともとリートの組み入れビルは、採算は合うが古く、価値が薄いビルが母体になっています。だから耐震性で問題があるビルがゴロゴロと組み入れられていると想像できますね。当然、これから修繕費が嵩みますから利回りが落ちるでしょうね。つまりリートは投資価値が薄いという事です。調べてないので分かりませんが、間違いなく耐震基準に問題があるビルが多いのでしょう。果たして、今日の日経新聞の一面だけでそこまで考えを発展させた人は何人いるでしょう。池上さんの解説はこのような形なのですね。この発想や展開力を生かすには、日々の積み重ねが必要です。誰にでもすぐに連想できるというものではありませんね。彼は毎週、数冊の本を読むのだそうですが…1年に300冊程度は目を通し、熟読するのは1週間に2冊程度なのでしょう。その努力がその発想の源になりますね。
実はカタルが現役の頃、駒形重吉さんのマンションに良く遊びに行きました。いつも常務や社長などのカバン持ちですが…彼の発想や物事の考え方に驚かされていました。彼は大光相互銀行を興したのですが…田中角栄と仲のいい友達でした。新潟県は米どころで昔から中央経済界と結びつきがありましたね。ある日、田中直紀が選挙のあいさつに来てお金の話が出たので、駒形さんは佐川急便の親父さんの所に挨拶に行けと言ったそうです。駒形さんがそう言う以上、裏で工作をしなくてはなりませんから、駒形さんは佐川の親父さんに掛け合って、10億円用意するように頼んだんだそうですが…。挨拶に行った田中直紀は、お金の話を佐川さんの前でできなかったのですね。折角、駒形さんが裏で頭を下げ、頼むと言ったのです。直紀が佐川の親父さんの所から帰った直後、駒形さんの所に佐川の親父さんから電話があり、「直紀は金の話ししなかったから、出さなかったよ。」と連絡があったとか…もう駒形さんはカンカンに怒っていました。折角、自分がおぜん立てをして直紀を挨拶に行かせたのに…って具合ですね。裏話ですが…、この話が元にあり、先日、防衛大臣に任命された時に、この人事は駄目だな…と感じたのですね。案の定、国会で失言をして退任しましたが…。ずいぶん昔の話ですよ。僕が現役のカバン持ちですからね。田中直紀さんも若かったのです。でもこのような実体験などの裏付けが、発想の輪になり構想が広がる訳です。
昨日の東京都の地価動向をみれば、不良債権が膨大なことが分かります。加えて問題なのが三重野さんや宮沢さんの後処理の過ちですね。この過ちの為に晩年、宮沢さんは後悔されていました。かれは自分が行った失政の後始末の為に、晩年になって大蔵大臣を引き受けたと話していましたね。キャリア組トップの優秀な宮沢喜一さえ間違うのですね。経済は難しい。何故か? 人間心理であり、国家間の策略が影響するからです。みんなわからないのです。だからカタルは考えられる仮説をいくつか用意し、その検証作業を続け、いつも相場観を修正します。まだ、このバブル当時の後処理が付いていませんね。りそな銀行が代表例ですし、日債銀の後継のあおぞら銀行もそうです。この現実は明らかにおかしいでしょう。20年以上前のバブルの爪痕のツケをまだ払い続けているのです。だから大相場がやってくると言う根拠に繋がっています。20年の鬱憤の蓄積が相場になるのですね。その新しい胎動が聴こえませんか? 何故、私がマネタリーベースと株価の特集を組んでいるか?よく背景を考えてください。
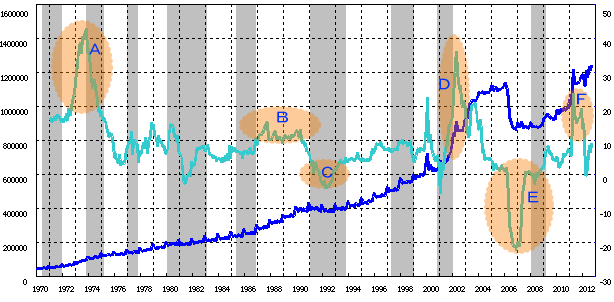
さて今日は90年代に入り、バブル崩壊後の「C」の部分の検証をしましょうか…。
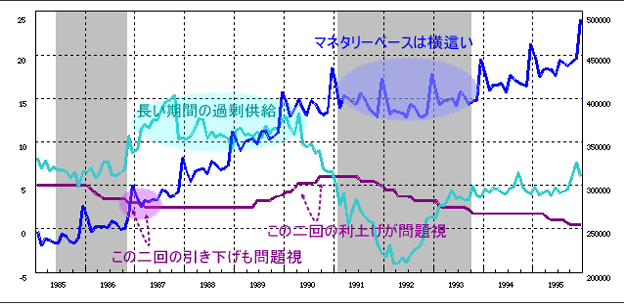
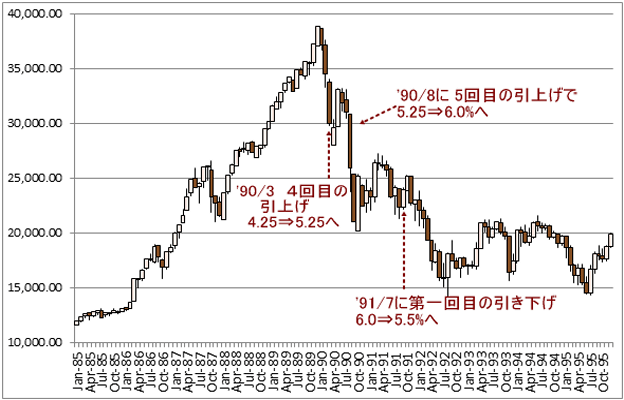
特に問題にされるのが第5回目の引上げですね。当時の株価は大暴落の最中ですね。その中で三重野さんは株や土地が下がっても実体経済に影響はないと述べて利上げを実行したのですね。彼は澄田さん時代には日銀副総裁をしていたのです。バブルの主因を造っていたわけですね。1986年10月や1987年2月の引き下げは、過剰供給の原因になったのです。2年2か月に及ぶ長い期間の低金利を続けた失政の責任も三重野さんにはある筈ですね。たぶん、慌てたのでしょうね。資産インフレの原因になった過剰貸し付けの実態を誰かに指摘され…自分達の過ちに気付いたのでしょう。既に1987年から1988年には限度を超えていたのですね。事実、1987年に多くの金融株は天井を付けています。そうして1988年からの株価上昇は先物からの「ねつ造」ですね。作為的に作られた株価操作であり演出です。このような市場の動きを無視していたために、手痛い報いをあとで受けることになります。
余談ですが、三重野さんが重要な副総裁のポストについていた時代背景は、ゴルバチョフがペレストロイカを実行し始めた頃で、これが1986年4月ですね。この年に発生したチェルノブイリ原発事故を切っ掛けにして、情報公開(グラスノスチ)が始まります。情報公開は非常に重要なキーワードになっていますね。そうして1989年のベルリンの壁崩壊に繋がる訳ですから…。情報公開は外部からの監視の力が働くのですね。検察の捜査方法が問題化され、尋問の可視化の話が進んでいますが…情報公開は非常に有効なのです。効率化社会において、隠匿は悪なのですよ。だから日本村論理が崩壊し、市場原理主義が栄えているのです。公正な競争を守る為に…。もし澄田さんにしても三重野さんにしてもこのような時代背景の認識があれば…、このような間違った政策は実行してない筈ですね。近年、ケイジアンからマネタリストの時代になったのも市場原理の動きを観察することが政策の決め手になっています。だから財務省の計画経済を元にした予算編成は古い考え方とも言えます。
日本村論理が崩れ「流動性の罠」の状態に陥るのが1995年後半から1997年代の時代なのでしょうね。この罠を一旦、抜け出すのが皮肉にも2001年9月11日のテロが切っ掛けの金融緩和ですが、その後の動きは金融規制に翻弄されるのです。自己資本比率規制の問題ですね。時代の検証はさらに進みますが、これまで見てきて分かったことは、マネタリーベースの残高は前年比で常に5%以上の伸びを保ち、場合によれば大きく増やしながら市場を監視するという事なのでしょう。日本はフロー重視の考え方が主流ですが、世界は違いますね。為替動向をみれば分かりますが、ストックの重要性が分かりますね。三重野さんは株や土地が下がっても経済に影響はないと暴言を吐きましたが間違いです。
米国の事例もホームエクイティーローンを通じて、住宅価格の値上がり分を消費に充ててきたのですよ。この事実の逆を日本は今やっているわけです。毎年稼ぐフローの可処分所得を資産価格の値下がり損に充てているのです。年金問題等は良い事例です。だからなかなか可処分所得が増えずに景気が悪いのですね。この異常な状態が、間もなく大きく転換します。僕らはもう直ぐ大金持ちになりますね。
これは基本です。つりの浮きのような感覚ですね。沈めば浮くのです。大きく沈めば沈むほど反発も大きいと考えられますね。奇しくも日銀はバブル期の反省が過ぎて、2006年に過剰引締めを実施して失敗しました。あの時代まで日本の実力はあるのでしょう。つまりこの7年間は行き過ぎた沈みの現象でしょうね。この概念はカタルの強気論の背景でもあります。ただ歴史を検証すると…大統領が変わりますからね。中国も、もう直ぐ共産党大会が行われ主導者が変わります。ゴルバチョフの事例を見ても分かるように大きく変化する可能性がありますね。日本もそうだし…条件は整っていますが…いずれにしても、もう直ぐ始まりでしょうね。
投稿者 kataru : 13:20