今日の市況(2012年)(2012年09月03日)
かたる:自分でもなかなか行動に移せないのですが…人間が決断をする為にはいくつかの行動を促すパーツが必要になります。例えば日本村論理の理解の為に、先日、かたるは山本周五郎の「樅の木は残った」を引き合いに出して日本の現状を解説しました。しかし多くの人はこの小説を読んだことはないでしょう。文庫本で3冊の上中下の3部作で新潮社から発売されています。アマゾンで中古の文庫本を注文しても良いでしょう。NHKでは大河ドラマとして放送していたようですが…。あのコラムを読んで、実際に小説を読む行動を起こした人は何人いるのでしょう。「恥辱に耐える」原田甲斐と表現しましたが、正しいかどうかは人の感じ方です。何故、かたるが心惹かれたかと言えば、今の低迷相場に相対するには忍耐力が必要で、小説の舞台に環境が似ているからですね。時が来なければ…行動はなかなか起こせないのです。
一昨日だったかな? 防災の日でNHKでは人間の危機対応の話をしていました。その中で人間の行動パターンの分析があり、火災報知器が鳴った程度では人間は避難をせずに、他の要素が重なった時に、人間は行動を起こすというのです。火災報知器が鳴り、煙のにおいがするとか…。火災報知器が鳴り、誰かが火事だと叫んだとか…の時に、初めて人間は行動すると言うのですね。先日、カタルの住んでいるマンションで火災報知機が鳴りました。最新式の設備らしく避難誘導を指示する声がします。カタルはボタンを押し報知器の声を切ったのですが、実際の行動はしませんでした。マンションですから大丈夫だと…判断したのですね。しかし数分後に消防車が来たので、初めてマンションのドアを開けて表を見ましたね。二つの事例が重なったためです。しかし結局、装置の誤作動だったようです。
人間の行動パターンは偶然の事象が重ならないと行動には移らないようですね。株価が上がるパターンも企業業績の向上と、他の夢が必要になります。大きな相場になるのは偶然の社会環境が重なることが必要になりますね。人気が人気を呼ぶのは、一つだけの事象では駄目なのですね。ましてやデフレ社会で資産価格が下落する時代です。基本は名実成長率にあると言っても良いでしょう。GDPデフレーターなるものが存在する現状では、全体が沈むので逆風下での行動は慎まなくてはなりません。カタルはこの基本姿勢に逆らって生きてきたために失敗をしたのです。しかし…今日の日経新聞には、この現象に変化が生じると述べてありました。先日の政府見通しの追加版が掲載されていましたね。さてここまで書いて、皆さんはピンときましたか?
おそらく、ここまでカタルが書いたことで、あの記事だな…と感じられた方は、もう一人前でしょう。今日の日経新聞でカタルが興味を持って読んだのは一面のLEDの話し、先日からカタルはイノベーションと需要の話をしている続きですね。この一面の記事と資生堂の中国市場の動き、シェールガスの話し、そうして景気指標の需給ギャップの話ですね。この需給ギャップの話は非常に面白かったですね。小竹さんが述べている背景を調べてみようかという気になりました。本文を引用すると…「こうした需給ギャップとインフレ率(消費者物価ベース)の関係(いわゆるフィリップス曲線)を期待インフレ率も勘案して推計すると、3四半期程度のラグを伴って、需給ギャップの縮小とともにインフレ率は高まり、また、期待インフレ率の水準によってフィリップス曲線が上下にシフトする関係が描ける。すなわち、需給ギャップが改善すればインフレ率は当然高まるが、同じ需給ギャップ水準であっても、期待インフレ率が1%から2%になれば、0.4%程度高いインフレ率の経路に経済が移行することが示唆される」となっています。
難しいことは良いのですが…次のグラフを見て頂ければ、株価が上がった時期と期待インフレ率が高まった時期が一致するのが一目瞭然です。今回の白書は非常に重要な示唆をいくつか与えてくれます。一度、じっくり読まれるのも良いでしょう。白書は此方です。
インターネット社会は素晴らしいですね。アラブの春が起こるのも、時代のスピードが速まるのも実感できます。昔はわざわざ白書を買い求めたのですね。しかし今は無料で、しかも自宅で簡単に読むことが出来ます。官僚は統計分析が仕事ですから、白書は一流ですよ。この白書を政治家が生かせないことが問題なのですね。最近の官僚も下積みが短いのか…政策誘導への行動がないのか分かりませんが…二流になりましたね。折角、時代分析が出来ているのに応用力が足りません。教育制度の問題でしょう。もう少し期待インフレ率の解析をしなければなりませんが、今日は漠然と期待インフレ率が高まれば株価が高くなるという事だけを留めておけば充分でしょう。
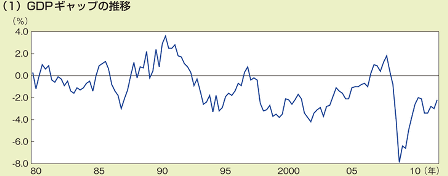
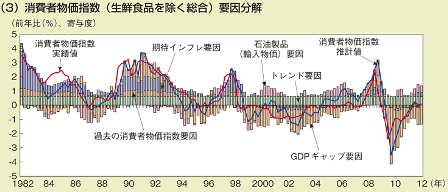
 「今日の市況」は人気ブログランキングに参加しています。
株式会社「ケンミレ株式情報」さんのチャートへ
「今日の市況」は人気ブログランキングに参加しています。
株式会社「ケンミレ株式情報」さんのチャートへ投稿者 kataru : 2012年09月03日 11:00

