« 2013年10月 | メイン | 2013年12月 »
2013年11月30日
自動車生産を考える
今日は先日、疑問に感じた自動車生産の資料を集め考えてみました。日経新聞をはじめとする大手8社の発表数字を何処から持ってきたのでしょう。おそらく独自に各社が発表している数字を合わせたものではないかと思うのですが、カタルがデータを集めてきたJAMA「一般社団法人、日本自動車工業会」の数字を元に原稿を書こうかと考えています。新聞数字との違いは、たぶんJAMA(日本自動車工業会)のデータは、小さな会社も含めてある全体の数字なのでしょう。
何故、こんな事を考えてみようと思ったかと言うと、「アーク」の狙いは正しかったかもしれないからですね。昨年11月に異次元緩和の期待から円安が起り、カタルは、当初、空洞化した生産が、国内回帰するのでは…と考えた経緯があります。しかしながら、なかなか戻らない国内生産をみて、アークをカタル銘柄から外したわけです。アークはホンダ系を中心とする金型メーカーですからね。別にアークなどはどうでも良いのですが…「時間の壁」を考える重要性を認識しているのです。この材料を元に、例えば007の村田のWiFiモジュールの動向を推察するヒントになるんじゃないか…とも考えている訳です。時代の流れは分かるのですが、実際の業績に寄与するタイミングを判断するのは、なかなか難しいのです。
例えば、建設の売り上げ計上は、何処で計上するのか?と言う会計法の問題があります。工事の進捗状態に合わせ、随時、計上して行くのか? それとも工事が終了した時点の完工基準で売り上げ計上するのかどうか? さらに工事代金を回収した時に、売り上げ計上するのか? 色んなケースがあり、一般的には進捗状態に合わせ計上されていきますが、実際に工事が完成し、引き渡しの段階になって、相手が倒産し未入金などと言うケースもあり得ますからね。大きな金額の場合は、契約に合わせ3割とか半分とか、途中で一時入金する場合もあるのでしょが…、この辺りは恣意的で難しいのです。同じように製品開発をして展示会を催し、そこから商談に発展し、更に個別対応の為に共同開発して、製品を納めるとか…。例えばWiFIモジュールの場合、ある程度、製品完成メーカーに合わせた仕様変更があるかもしれないし…、実際に売り上げ計上されるのは、何時なのか?
要するに、この辺りの疑問は、007以外でも発生している訳です。実際に日揮のケースは1年も相場になるのに待たされました。環境が改善しているのに…、どの時点で売上変化が生まれるのか? この辺りの考え方は株式投資にとって非常に重要なのです。だからこの円安環境から自動車業界の生産を海外から戻し、国内回帰しているなら、新たな政策発動から1年が経過しており、この程度のタイムラグが普通なのか? この辺りの考え方が色んなケースでも参考になると考え、自動車生産のデータを集め、自分なりに資料を作っているのです。基本的にカタルは、日経新聞の恣意的な報道に何度も騙されているので、報道内容を鵜呑みにせずに、自分で裏付け捜査をしている訳ですね。そうしていたら10月の生産台数が日経新聞は82万5137台となっていましたが、JAMAの発表数字は87万1434台と違っていました。この辺りは小さなメーカーも団体に所属しているからJAMAの資料を基に考える方が良いのでしょう。アークのケースを個別に調べるとしたら、ホンダの生産高を追うとか…投資家、それぞれが自分で調べてみればいいのです。
ただこのような作業は無駄に終わることも良くあります。推論はあくまでも想像で、現実ではないからですね。ここで2011年のデータがあるので、概略を掴んでおかねばなりません。中国の自動車販売は1851万台、米国は1304万台、日本は421万台でブラジルが363万台、ドイツが351万台となっています。世界では72225万台の車が販売されています。一方、自動車生産は2011年の中国では1842万台なので、ほぼ100%です。米国は866万台で66%なので輸入超過です。日本は840万台の生産なので約200%なので輸出が多いのですね。ドイツの生産は615万台で175%ですね。韓国は日本より輸出比率が高く、国内販売は158万台ですが、生産は456万台で290%なのです。
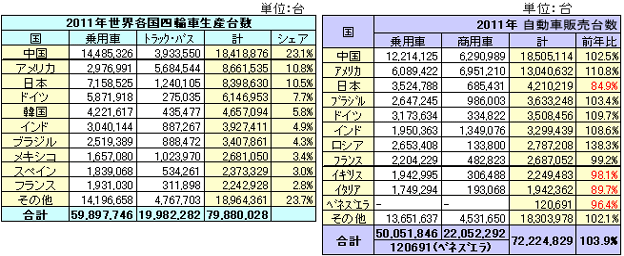
さて問題の国内自働車生産拡大のニュースは、今日の日経新聞にも自動車と建設作業員は人材不足の様相との記事が掲載されていました。建設各社は好調なのですが、資材高や人件費高だから利益が伸びていませんでしたね。だから大成建設の株価はオリンピックの発表から横ばい推移を続けています。建設全般に同じです。内需は好調なのですよ。来年も消費税の減速分を埋める為に、補正予算が組まれ基本的に建設需要は増大しています。だから時間をかければ大成建設も上がりますね。単なる時間調整です。この所、カーテンのサンゲツなどもTV・CMが見られるようになってきました。広告宣伝を打てると言うことは本業も好調なのでしょう。このように住宅関連資材提供会社も好調の様子です。このような要因の合わせ、カタルは日銀の政策失敗も念頭に置き、EU経済の回復やグローバル展開を鑑み、LIXILや日本板硝子なども参考銘柄に掲げているも面白い見方だと思っています。トヨタの期間工増大が見出しに踊っていましたが、本当に自動車の生産拡大が続いているのでしょうか?
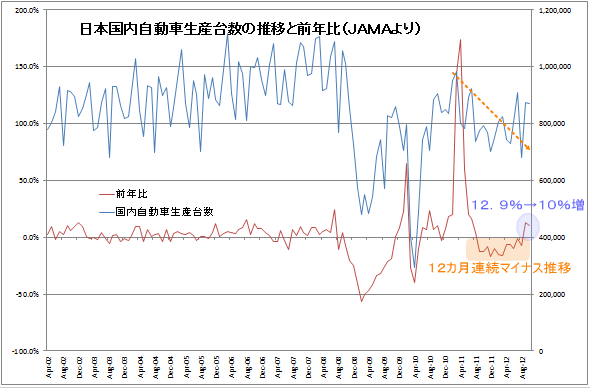
上のグラフで見る限り円安効果による明確な生産活動回帰の動きは見られません。むしろエコカー減税特需による在庫調整が終了し、通常の生産活動に戻っていると言う印象ですね。さらに消費税の引き上げによる駆け込み需要を見込んだ、在庫積み上げ投資が増えているのかもしれません。在庫投資は見込み生産ですから、実需とは少し意味合いが違います。ただ円安推移からの時間のタイムラグから、9月の12.9%増から10月は10%増となっている可能性がないと一概に否定していいものかどうか…。データから様々な推測は成り立ちどれが正解なのか見えにくいのです。
ただ102円台の為替推移が、白井さんの講演会を切っ掛けにしていると言うのは興味深い現象です。つまり日銀が市場の期待通り、緩和拡大の行動に出るなら、確実に信用創造の流れは生まれるという事です。世界の投機資金は日本の不動産に流れ込み、ケネディクスが狙い通りスター株に育つのでしょう。…が、しかし、黒田さんが何もしなかったら、グローバル銘柄の選択の方が正しいのかもしれません。ソフトバンクにファーストリテイリングが高く推移している現状は、GDPデフレターを改善できないと言う見方も示唆しているのかもしれませんね。あまりに物価ばかり強調しすぎている解説は、何か違和感を覚える次第です。
おそらく自動車経営者は、在庫投資と為替水準を両睨みしての行動なのでしょう。故に今後、数カ月は前年比でプラス圏の生産回復になるのでしょうが、タイの世情動向もあり、国内の生産回帰なのかどうか…。やはり、このデータだけでは読み切れませんでした。どれも可能性は存在しますね。国内回帰のアークの選択も、日本の失政が続きLIXILや板ガラスなどのグローバル展開企業と言う選択も、正しい政策が実行され、国内の信用創造が膨らみケネディクスが物色され、投資活動が活発になる本当のGDPの成長もあり得ます。最近はベンチャー企業に対する投資熱も、ナスダックの上昇からも窺えるように上がっており、時代の要請による技術革新の007も有力候補になっています。全体の相場環境は良く、少なくとも節分辺りまで、経験則では、株は上昇を続けるのでしょう。しかし指数ばかり追うと消費税の引き上げ後の失速も考えられ、しっぺ返しを食らう可能性も来年になると考えねばならないかもしれません。まぁ、今日の考察は中途半端ですが、何か参考になったでしょうか?
2013年11月23日
割安株のリスト
今日のテーマはNISAが来年から導入されると、現物株投資が一般化する可能性があります。割安の銘柄を買ってほったらかして置けば、何れ、定期預金より良い投資になると言う非常に保守的な観点からの銘柄選択ですね。そのリストを提示して置きます。
3つのリストは同じリストですが、配当利回り、ROE、そうして資産価格の上昇から低PBRと言うそれぞれ狙いを変えた選択により順位が違います。配当利回りは説明が必要ないですね。基本的に経営効率はROEで判断されます。投下資本を利用してどれだけ利益を上げたかという視点ですね。PBRはケネディクスと同じで、これまではデフレ環境で資産を持っているより現金の方が有利でしたが、今度は持っている資産の活用が問われる可能性があります。そこで割安に放置されている資産価格の上昇が期待されますから、純資産が株価に比べ割安の銘柄を上位にリストアップしました。このリストは保守的な観点から時価総額の大きなものが選択されています。3000億円を下限にして選択されています。
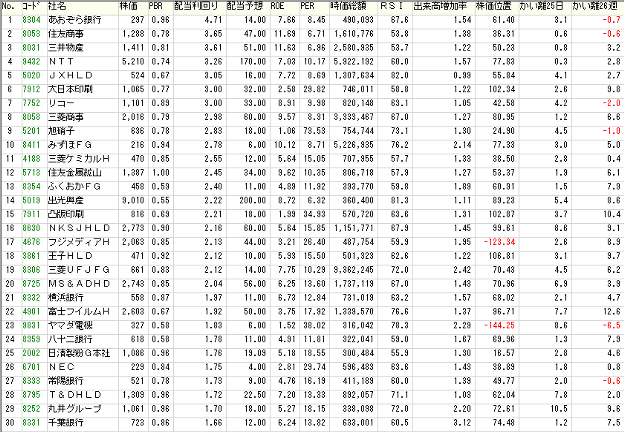
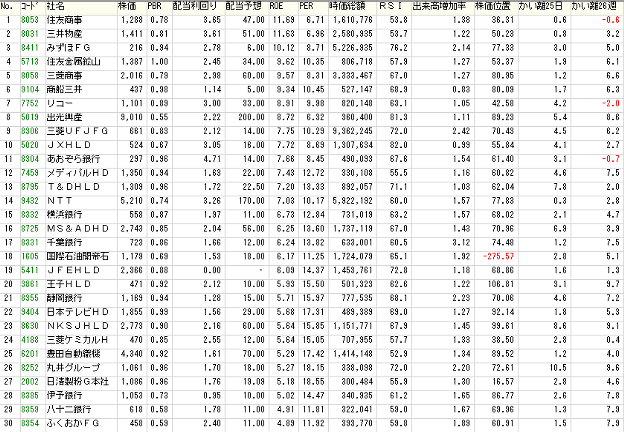
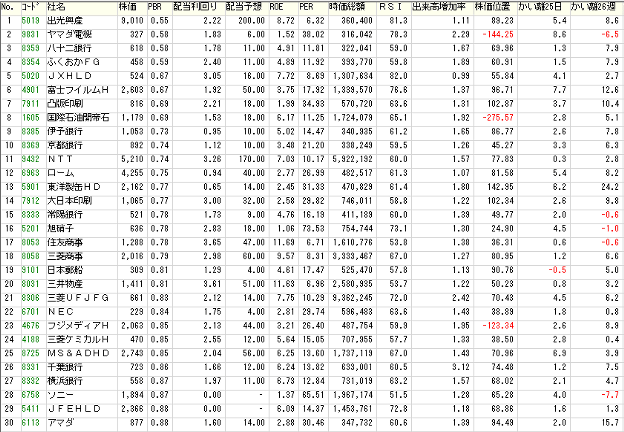
今日は最近の日経平均上昇の謎と言うか…、これからの展望を研究していたのでアップが遅れました。本当はその原稿を書く予定だったのですが…途中で、勉強するのが嫌になり挫折し、簡単な原稿を選んだ次第です。明日、再挑戦できればいいのですが…どうかな?
2013年11月16日
ヤクザで始まりヤクザで終わる
今週の相場は一部のヘッジ・ファンドが決算対策の準備の為にとった行動に、日本の個人投資家が追随したのでしょう。丁度、調整が完了していることもありタイミングもよく、パンチがきいた印象の展開になりました。もともと日本株の投資環境は、海外に比べ非常に恵まれた状態にあります。理由は、長い失政の為に、相場の需給バランスが完全に枯れきっている状態なのですね。
長い間、日本は銀行と一般企業などの株式持合い関係を維持してきました。この現象はいったん解消されたにもかかわらず、2005年頃だと思いますがフジテレビ株を巡り、ライブドアが米国金融の力を借りて、フジテレビの買収に動いた事件を切っ掛けにして、終わったはずの株式保ち合いの動きが再熱します。米国金融の力を恐れた能力がない新日鉄のサラリーマン社長が保身の為に、再び、銀行との株式の持ち合いを始めたのですね。しかし米国の金融危機が起こり、銀行の資本増強と言うグローバル環境により、再開されたこの動きは直ぐに解消されました。此処にも日本村論理の崩壊が見られます。原発事故で東電が叩かれている構図も、日本村社会の崩壊の一環です。
つまり日本に残った既得権勢力の象徴である55年体制が次々に崩れ、グローバル化している現象が広がっているのです。TPPで先日はJAの萬歳章会長が経団連の米倉さんと握手をしていましたね。この光景も似た背景があります。既得権勢力は、確実に力を失いつつあるわけで、日本が長い間、構造改革を実施してきた成果は、時間が解決している訳です。1989年から続いた日本株の調整は、基本的に転換点を迎えているのでしょう。ソフトバンクのスプリント買収、ファーストリテイリングのグローバル化など…数え上げればキリがありませんね。要するに、日本株は放っておいても、株は自然と上がるタイミングに来ている訳です。カタルが需給バランスは、完全に枯れきっていると言う表現を用いているのは、こういう日本の社会環境が背景にあるのです。
未だに、みずほの反社会的融資を問題にする構造はありますよ。金融庁の既得権勢力ですね。偽装表示もメディアの既得権勢力の力でしょう。基本的に彼らは巧妙に自分達の組織の温存を狙い、事件を利用しているのです。メディアの誘導は世論の誘導であり、自分達の保身に利用するのですね。しかしそんな内部構造は、だんだんグローバル競争の真の市場経済の動きに押されていきます。これが時代の流れですね。TPPへのJAの戦いも、何れは押されるから、経団連の米倉さんとJAの萬歳さんが犬猿の中なのに同席し、メディアに画像に乗ったのです。この辺りの背景を理解しないと、今回の株高の真の姿が見えないのでしょう。メディアは外人のヘッジ・ファンドの先物からの買いにより、株価が上昇したと誤報とも言える解説をしていますが、実態は日本の投資家であり、個人のネットトレイダーが日経レバレッジのETFを買い進んでいるから、今週は大幅高したのでしょう。その背景は、多くの株が調整を完了しており、新しい波動入りの状態になっていたのですね。カタルは先週から今週にかけ、三菱UFJの解説などを増やしています。200日線上に株価が位置しており、何かが起こると…述べていましたね。
多くの株価が、一旦、株価位置が上がると、下がらないようになっています。代表事例は邦銀株です。みずほはほとんど下げずに時間調整をしてきました。007もそうですね。ボックスが確実に切り上げています。カタルは三菱UFJの妥当価格を算出しています。14日の「今日の市況」で、最低株価の800円台は回復するだろうと述べています。理論上は、1300円前後が市場経済としての妥当株価だとも述べています。つまりそこまで日本株の水準訂正が続くのでしょう。日本の社会環境がグローバル環境に変化しているから、株の需給バランス調整が済んだのですね。それが200日移動平均線のタッチするのを観て、多くの株が反発した真髄なのでしょう。外人のヘッジ・ファンドが関与しましたが、単に切っ掛けに過ぎません。基本はイールド・スプレッドなどの論理的な株の割安感を支えている構図が底流にあるのでしょう。
さて今週の株高の背景を語りました。外人買いも要因にありますが、本当は日本人個人の日経レバレッジ・ファンドの買いが、全体相場を持ち上げたのですね。本来なら、先物からの買いなので、需給バランスは不安定で、一般的には日経新聞の一面解説にあるように、短期資金が中心なので、急ピッチに上げる株高を警戒すると言う解説は、頷けるように思いますが、本当は、この解説は違うのでしょう。カタルは株式持ち合いの関係やJAの萬歳さんの話を、何故、ここで持ち出したか?この背景を考えれば、新しい波動がスタートしたとみるのが妥当でしょう。事実、アベノミクスの始動からの相場展開を考えると、今回の株高は本物の相場展開だという事が分かると思います。偽物と思われる相場の株価もなかなか下がりませんね。東電を始め、3Dに、オリンピックなど…。たいして業績の上積みが見込めないのに…株価は維持されています。ガンホーなどは代表事例でしょう。どうもガンホーは底入れの動きに入っているみたいですね。スーパーセルを親会社のソフトバンクと共同で買収し、今度は、本社をフィンランドに移転する検討をしていると報道されています。この動きは新しい動きですよ。ただ直ぐに株価は反応しないと思います。何故ならパズドラの一時的な利益の見極めが必要だからです。このような展開がなければ…極端な事例ですが、KLabのような展開に株価はなっていたはずです。
7月の人気株の「リプロセル」などの動きを見れば、カタルが野村主導の新規上場株の人気株の「エナリス」の相場を批判する構図が理解されると思います。一時的な人気は冷めるのですね。株価をある程度上げることは、お金さえあれば誰にでも出来ます。しかし上がった株価を維持し、更なる上積みを期待できる株は、なかなかありません。熊谷組を既に相場は終わっているでしょう。しかしケネディクスは上がった株価を肯定し、更にその上の株価を約束する構造が、背景にあります。今は数字に合いませんから、強弱感が対立し仕手戦になりますね。しかしカタルはサマラリーを期待した500円割れ以降、何度も新高値をチャレンジし、年末年始に4ケタになると豪語していました。それは高くなった株価を、さらに上げる要素が背景にあるからですね。その源が、1兆2000億円に上る受託資産の管理の権利です。この不動産を右から左に所有者を移転させるだけで、皆がハッピーになる時代環境にあるのですね。1989年から失われ続けた地価の下落と言う膨大な貯金が…ようやく生きる環境下にあるのですね。一般の景気循環の話ではないですよ。明治政府が生まれて蓄えられた時からの含み利益を飛ばしたのが…このデフレ環境の「失われた時代」なのですね。如何に膨大な貯金かが、分かるでしょう。その回収に入る相場なのですね。だから4ケタは単なる通過点で、4000円も可能性があるし、政策次第では1万円の声がかかるかもしれません。
時代背景を知り、相場観は組み立てられています。
007は産業革命以来のユビキタス社会と言う技術革新です。ケネディクスは長い失われた時代のツケを回収する相場です。ちんけな相場とスケールが違いますね。現状の株価が2倍になっても論理的に株価が合う銘柄なのですね。ようやくケネディクスクラスの銘柄が活躍できる相場環境になってきました。何しろ野村証券が、金曜日に人気NO1になったのです。大きく大和証券に離された株価ですが、社長が足りないからですね。氏家以降、野村は多くの人材を失いました。やくざ絡みの不祥事を一掃しようとした為に、清貧思想の蔓延が始まった為ですね。バブル崩壊当初、野村は東急電鉄株の取引を巡り、やくざ問題で叩かれました。やくざ相手に商売を出来る実力派を排除したのですね。しかし本当に仕事が出来るやつは、やくざ相手でも商売にするのです。みずほの2億円程度の問題と規模が全然、違う話です。確かに、あの「にぎり」はやり過ぎで、汚い損失補てんでしたが…、今の実力派を排除する清貧思想も行き過ぎでしょう。今のみずほなどの反社会的勢力の総額は、僅か2億円、悪いことは悪いのですが、テレビでワイワイと拘る問題でもありません。如何に清貧思想が蔓延し、この動きが終局に来ているかを、知る社会現象です。長い「失われた時代」のデフレ環境は、野村のやくざに始まり、みずほのやくざで終演でしょう。
2013年11月09日
連想ゲーム
米国の雇用統計を、毎回、市場は気にしていますが…日本株市場にそんなに大きな影響が在るのかどうか…。むしろ中国の第18期中央委員会第3回全会(3中全会)の行方の方が気になるのですが、何故か、報道は少ないですね。中国の現状はいま、成長鈍化や急速な高齢化、膨れ上がる地方政府の債務に加え、環境汚染や腐敗、農村部の土地接収などの問題に対する国民の怒りの高まりに直面しています。成長が加速している間は、社会の不満を抑え込めますが、最近はテロが起り、難しい局面のようにも感じます。中国の姿勢を観ていると情報管理と言うものの大切さが、分かるような気がします。
日本の偽装表示関連の報道ぶりを見ると、メディアの異常な採り上げ方が分かります。昔から感じていたことですが、何故か、日本のメディアは、一つの流れを、どの局も一斉に報道します。その報道の仕方も、ほぼ同じ流れですね。全てが画一化の流れの中にあります。日本人の意識改革の原点は、やはり教育でしょう。時間が掛かりますが、早くから手を付けないと、人材は育ちませんからね。どうも中学生や高校生の多感な時代が、大切な時期なのでしょう。感受性が一番高い年頃です。どう教育をするか…。生活するだけで手一杯だった株屋時代、子供の教育に時間を割くゆとりがなく、悲しい現実が思い出されるばかりです。
世の中には、様々な考え方があり、価値観も人により様々に異なります。ブランド品を欲しがる人も居れば、食に拘る人も居ます。何をテーマにして生きるか? 自分探し…などとフラフラした時間を過ごすのも、人生の大切な時間かも知れません。カタルの友達のブツブツは成功組なのかどうか…。一応、豪華な自宅に、旧軽井沢に別荘などを持ち、50代後半で現役を引退、現在は自分で百姓をやり、晴耕雨読の毎日を送っています。彼は大学時代、8年だったか、10年だったか…留年をして、フラフラと海外旅行をして過ごしていましたね。あの時間を与えてくれた親父に感謝していました。一般的に見れば、彼の人生は成功組かも知れません。
ただ米国の本物の投資家には、遠く及びません。
みんな現役時代はジム・ロジャーズのような生活スタイルに憧れて頑張る訳ですが…成功組に入るのは難しいですね。カタルの場合もチャンスはあったのです。上京した頃、日本株に拘らず、米国のマイクロソフトを買うチャンスがあったのですね。あの頃、カタルはアスキーに魅了されていました。もしマイクロソフト株を買っていれば、今頃は、別次元で暮らしていた事でしょう。
そのジム・ロジャーズの言葉ですが、「全ての主要な中央銀行、全ての主要国の政府が自国通貨の価値を積極的に下げている。これは有史以降初めてのことだ。日本は無制限に紙幣を印刷すると言った。するとバーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、「われわれは年間1兆ドルを投入することができる」と言った。欧州は「必要なことは何でもする」という。世界は流動性であふれ返っており、それを享受している人々は楽しい時を過ごしている。でもそれは完全に人工的なもので、ひどい終わり方をするのは目に見えている。」と語っていますね。同時に農業生産者の高齢化も指摘しています。日本は異常な現象です。農地の企業取得が今回も見送られています。おそらく農業は成長産業になるのでしょう。今なら、まだまだチャンスですね。混乱する過渡期にあり、新しい時代を築ける分野でしょう。
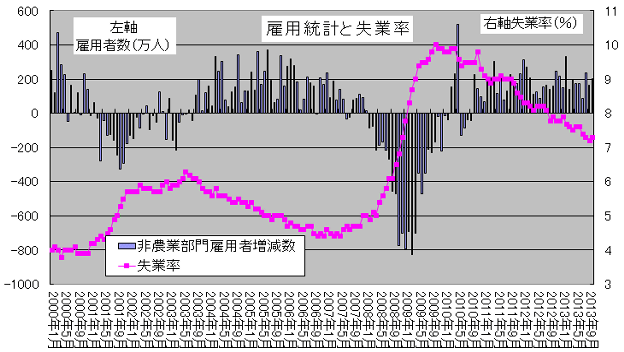
改善する雇用統計、しかしこのグラフを見れば…痛みを抱えたままの姿が分かります。正常な水準まで回復するのは、かなり難しい課題だと言うのが分かります。何故なら、ITバブルが崩壊した後の失業率のピークは6.3%だったのですね。そこから改善しています。しかし時間軸を5年程に限ると、現状は、かなり改善しているように見えるから不思議なものです。金融危機後の回復は続いていますからね。前の悪い時期のピークが分からないからです。失業率10%からの回復ですからね。しかし回復しているとは言え、7.3%程度では、以前のピークより、まだまだ悪化したままなのですね。
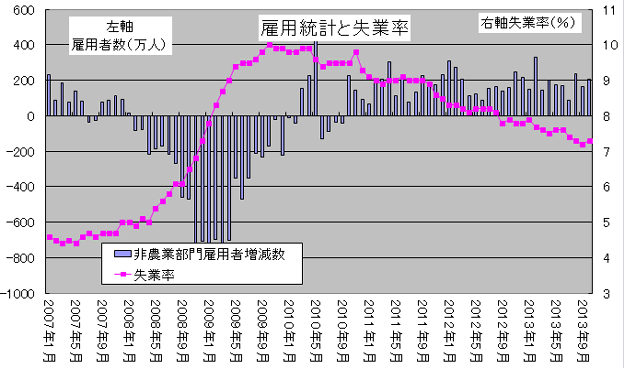
世界の中央銀行が、これほどの緩和政策を採用しているのに…、何処に富は偏っているのでしょう。先日、ドバイやアブダビの物価水準をテレビで観る機会がありました。日本人の感覚からして、非常に割高な水準でした。外人ファンドの多くはキャッシュ比率が高いままなのだそうです。いったい何を警戒しているのでしょう。今日は意味のないゴタクを並べていますが…このような想像は相場を考えるうえで重要です。基本的な世界経済の背景を探る連想ゲームは、次のステップの手掛かりになるからです。日本の市場は3つの需給不安のトンネルを、間もなく抜けるのでしょう。年末年始の株高に向け、その前のステップに過ぎません。今決算数字は大きなサプライズはなく、大体、予想の範囲だったようです。
来週はケネディクスと007が、2Qの決算発表を迎えますが、現状の株価は大きな期待感もなく、株価は横這いのままですからね。どんな数字が出ても株価の波動を大きく変えることはないのでしょう。基本的に回復途上にあり、株価が下がれば買い場になるのでしょう。ケネディクスは利益剰余金のマイナス分を、資本準備金を振り替えてゼロにして復配するかどうか…。それとも何処かで特別利益を計上して解消するのかどうか…。どうやって処理するのでしょう。会計上はこの辺りが焦点になるのでしょう。
カタルの選択は基本的に経済環境を念頭に置いており、その流れの中で銘柄を選別しています。だからグリーのような基本環境が変わると失敗することがありますね。現状のグリーは、需給バランス面から注目されます。空売りの買戻しは続き、通常は株高方向に向かうのでしょう。金曜日に高かったのは、その動きの一環ですね。しかしグリーの需給面での整理は済みましたが、新しいステップはなかなか見えません。DeNAの方が株価は下げましたが、背景はまともなのでしょう。本日の日経新聞一面の「非課税の私的年金の創設」、4面の「第二のビッグバン」などの記事は「信用創造」を補う政策の一環です。ケネディクスの潜在的な株価価値を押し上げています。同時に11面のWiFiに絡むメールアドレスの入力要求に困惑の記事は007の価値を高めている関連記事でもあります。この辺りの感覚が皆さんに伝わるかどうか…。
株式投資は、いくつかの関連現象から将来予測するのです。決算を観ても分かるように自動車関連は好調を続けています。しかし株価は業績の高水準を競うものではなく「変化率」を競うのですね。変化率の観点では前年比で比較しますから、高水準に戻った業績位置が今度は比較対象になり、変化率の観点では落ちますから、たとえ増益になっても、株価は横這いと読むのが普通でしょう。むしろ決算が期待通りに動かない方が、良くなった時のインパクトが大きく将来性を感じるわけです。だから株価変動率が一番高いのは、赤字から黒字への転換点であり、復配などの時点に株価の変動率が高くなるのです。この辺りの感覚は素人には分かりにくいのでしょう。プロは通常、赤字から黒字に転換する業績の激変株に狙いを定めます。今日はフラフラと…くだらない御託を並べました。このような一見、無駄に感じる連想ゲームは新しいヒントを生む源になります。
カタルが感じる感覚が正しいとは限りませんが、何かヒントになれば幸いです。
2013年11月02日
実質金利はマイナスへ
この原稿は金曜日に書かれています。尚、3連休は出かける為に、日曜日のコラムはお休み、月曜日は早めに帰宅すれば書くかもしれませんが、お約束は出来ません。ご了承ください。
昨年の印象が強い為か…。例年、気にされる11月の決算対策のアノマリーを忘れていたような気がします。12月は外人ファンドが決算を迎え、決算対策が行われます。どうしても11月半ばまで弱含みに推移するのは致し方ないのかもしれません。ポジション調整です。先週、一部のヘッジファンドが「アベノミクスの失望論」を展開しましたが、多くの賛同は得られずに、この見方は、一旦、後退したのかもしれません。ただ春先の期待感は長期金利動向などにみられるように大きく後退していますし、為替も最近では100円を超えることは難しくなっているようです。カタルはどちらかと言えば円高論者ですから…為替水準はあまり問題にしませんが、長期金利の動きは、いくら日銀の買い入れ規模が大きいとはいえ…やはり気になります。
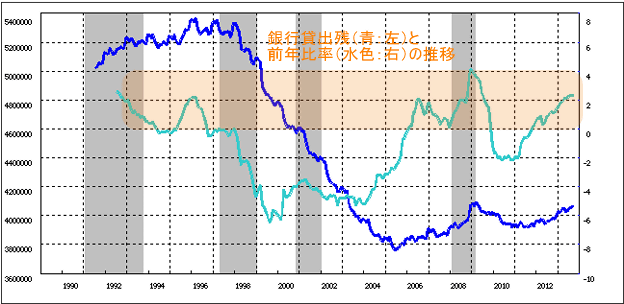
このグラフは、銀行貸出残の推移と前年比率の動きを示したものです。
通常、経済活動が活発になれば、売り上げが伸び、利益が膨らみます。つまり全体のパイが大きく膨らんでいくのが正しい成長の過程です。付加価値の合計であるGDPも増え、今、さかんに問題になっている賃金も増えるのですね。だから資産と共に、借り入れも増えます。全体のパイが増えるのが正しい経済成長です。経済が加速すれば、するほど、借り入れは増えることになります。借り入れコスト(長期金利の利回りは0.6%+0.3%程度)からインフレ率〈消費者物価の達成目標2%〉をひいた実質金利が、マイナス圏に現状はなる筈で通常は投資活動が盛んになり、経済全体のパイを後押しします。日経新聞、火曜日朝刊17面の「一目均衡表」の意味は、その事を言っています。カタルが信用創造(ケネディクス)の重要性を何度も説いているのは、そのためです。
日本は長い間、日本村社会の構造改革を実施してきました。
その為に日本独自価格が崩壊し、内外価格差の是正が行われ、企業は海外生産を増やし、国内生産を実施する企業は減り、空洞化しました。ユニクロが世間に登場した当時を思い出してください。驚く価格設定だったのです。日本の衣料品価格に日本村社会価格が通用していたからユニクロ・プライスに驚いたのです。プラザ合意以降、日本村を支えていた終身雇用や年功序列という、日本村論理が市場原理にさらされたのです。これが「失われた時代」の構造調整です。
他にも色んな事があるのですよ。株式持ち合いなども、その論理の一環の仕組みです。東西冷戦の終焉は、米国の保護がなくなり、プラザ合意と言う円高を切っ掛けに、日本にグローバル化を突き付けたのです。ようやくTPPまで来ました。コメなどの関税を撤廃すれば、日本はようやくグローバルな土俵に立ったと言えるのでしょう。未だにむかしの日本を懐かしむ声が多く聞かれますが…グローバル化は情報の共有に始まり、避けられない壁なのです。国際会計法など…みんな一元化の流れにあります。金融機関の自己資本比率規制も、その流れですね。この構造改革が終了したのが1998年から2003年の年でしょう。折角、浮上したのに…既得権力者の逆襲や米国の金融危機などがあり、再び日本は沈み、アベノミクスで再浮上しているのが、今の時間の流れです。ざっとこれまでを振り返りました。
さてここに来て、一部のヘッジファンドが主張する「アベノミクスの失望」は良く分かります。みずほ銀行の反社会勢力への融資問題が、総額で2億円程度なのに…大きな社会問題のように報道される実態は、どう考えても失われた時代の清貧思想の流れにあります。折角、黒田さんの異次元緩和で、ここまでお膳立てして来たのに…揺り戻しの動きにも見えますね。法人税改革などは時代の流れです。逆らっても地球上で生きているならルールに従わざる得ないのです。サムソンが代表するように、国際競争に勝利できるかどうか…なのですね。パナソニックが買収した三洋電機の白物家電を、中国のハイアールが買収する流れは、日本が構築した仕組みの陳腐化を証明しています。TSMCの躍進に追随できなかったNECなど…事例を掲げれば限りがありません。日本村論理の基礎社会資本整備自体が陳腐化しているのですね。震災後の原発処理を観ても分かります。電力料金は上がり、企業の生産活動の選択肢は、日本という地理的な選択をしたくても難しくなっています。金融庁は厳格な減損会計を迫り、銀行独自の許容度を奪っているのです。不良債権問題を巡る金融庁との意見対立からUFJは争いに負け、消滅させられた事実は、心理的な悲劇ですね。
その現象が先ほど見て頂いた銀行貸し出しに現れているのです。
ようやく前年度比で顔を出した2006年2月には早くもライブドア事件が起こりますね。折角浮上したのに…、再びベースマネーを大きく絞る日銀など、日本の中枢機構は明らかに狂っています。その結果が自殺者の増産と、ブラック企業の誕生ですね。若者の実に25%近くが、自分の会社はブラック企業だと感じているのだそうです。サービス残業などは良い方でしょう。ギリギリの政権交代が、民主党政権の誕生に繋がったのですが…本来の役目を忘れ、内部崩壊し、再び自民党政権の誕生でアベノミクスが実行されていますがヘッジファンドの杞憂かどうか…。日経平均株価が長い間、三角保ち合いを演じている理由を、政策の中枢を担う人たちは理解しているのかどうか…。ここに来て「アベノミクスの失望」が生まれる根拠は、みずほのやくざ融資問題にも象徴されているように感じるのは、果たしてカタルの考え過ぎかどうか…。
ただニトリの米国進出、ソフトバンクのスプリント買収、最近ではドンドン企業がグローバル化戦略を打ち出しています。ピジョンは代表的な成功事例ですね。こんな中で、日産自動車が通期企業業績を減額修正しました。この理由は新興国、ブラジル、インド、ロシアの新モデルに関する、一時的な現象と説明されているようですが、早くにグローバル戦略を打ち出していた日産だけに、時代の流れの象徴でもあります。おそらくタイなどへの生産移転が完了していたために、他社程の為替メリットを受けられずに、FRBの金融政策変更の影響を受けたのでしょう。本来なら伸び続ける中国が補うのでしょうが、日中間の問題が響いています。日産は他社に先駆けグローバル展開をしています。自動車セクターの株式をお持ちの方は注意を要する内容です。
さて、このような現象を見ると、今こそ、日本の信用創造をはじめとする政策の重要性が、分かると言うものです。日産自動車の決算内容をもう少し吟味する必要性を感じますが、既に日付が変わり疲れて来たし…又にしましょう。やはりアベノミクスの成功には信用創造企業の復活が欠かせませんね。市場がこの重要性に気付くのは何時なのでしょう。決算発表が行われ大きな驚きはないでしょう。株式相場は来年をにらんだ動きを続けます。年末年始は1年を通じ、一番、期待感が溢れるはずですが…今年の条件はいくつかの懸念材料が越年します。迷走するFRB、あのバーナンキの市場への警告は何を意味したのでしょう。米国の財政問題からの一連の展開は、情報収集活動を含め、米国の力の低下を示していますね。オバマ政権は難しい時期を上手く乗り切りましたが、米国の信頼性を裏切ったのは大きな汚点でしょう。日本ではやはりなかなか引火しない設備投資と消費税引き上げでしょう。
ただ日本は復興需要から社会資本設備の更新需要、オリンピックなど…待ったなしの需要を多く抱えており、上手くスマート・シティーへの転換できるかどうか、本来なら準天頂衛星のみちびきの4機体制の実現を、前倒しで実施しなくてはなりません。このような新しい社会資本整備を早めに実施して、ベンチャー企業が誕生する社会環境を整える必要性があります。それを…いくつかの選択ミスが余り重なると、失われた時代を延長させることになりますね。今は非常に大切な時期なのです。それでは時間です。また来週。