« 揺れる心理 | 最新の記事 | 株価波動の考え方 »
デフレ脱却と長期金利(2013年07月27日)
どうも相場は、当初から予定していた路線(シナリオ)との見方が、正しいのかもしれません。5月23日の下落を受け1か月程度の調整で上昇し、参議院選を目途に二番天井を形成し、再び下値調べに動くと言うシナリオが当初の読みでした。カタルはこの戻り相場でケネディクスを選択しましたが、効率は今ひとつでした。…と言うより、安値を上手く捉えられなかったのです。安値からは約2倍ですからね。007も同じですね。基本的にケネディクスは初期第一波動が大きかったので、その反動を消化するほど需要が強くなかったようです。だから高値を更新できなかったのでしょう。それと業績の推移でしょうね。この辺りの見方は難しいですね。逆に今回は初期波動がそれほど強くない銘柄が、今回は5月の高値を超えています。もう一つは裏付けのある常識的な銘柄ですね。ただそのような銘柄も勢いよく新高値を更新するものではありません。
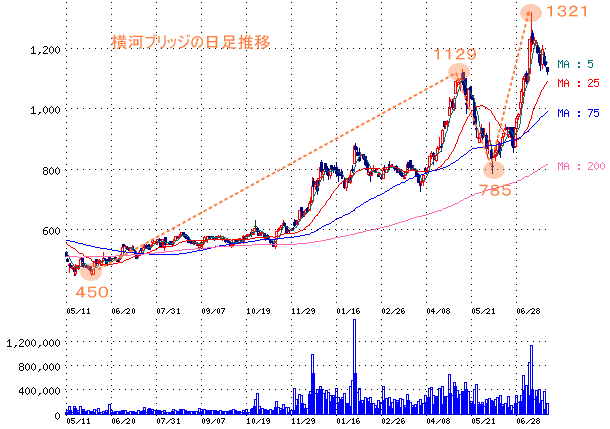
これら4月の高値を超えたものは、例えば横河ブリッジは6月から5月の上昇率は、450円から5月13日の1129円ですから2.5倍ですね。そうして富士重工のスタートは、昨年の8月の545円で今年5月23日の2765円なので5.1倍です。その後、横河ブリッジは6月7日の安値785円で30%の下落率で7月11日に1321円を付けて5月の高値を抜いています。5月の高値より17%の上昇率ですね。富士重工は5月23日に山を付けて6月7日に1950円を付け29%の下落率です。それから7月19日2882円を付けて二番天井を取りました。今の所は5月の高値より4.2%の上昇ですね。一般的な銘柄は昔からある「3割乱高下に立ち向かえ」との諺どおりになっています。しかも下落の期間は1か月未満ですね。通常はこんなものです。日柄と変動率に注目して下さい。
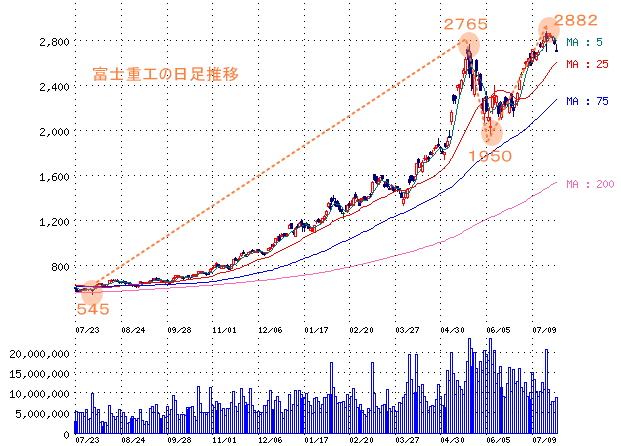
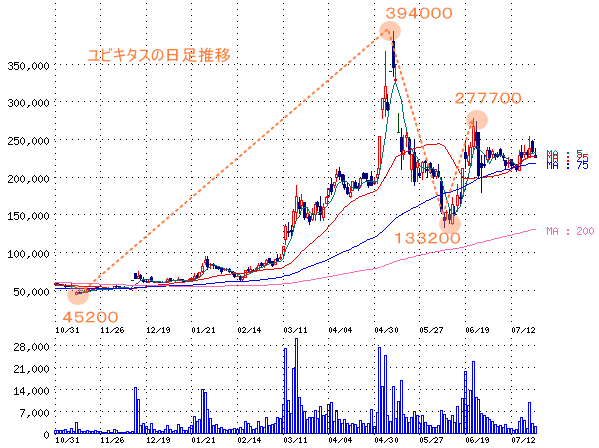
現在力を入れているカタル銘柄の007は昨年11月12日の45200円から上昇を開始し、5月13日に394000円を付け調整に入りました。8.71倍ですね。業績の裏付けがない為に6月7日に133200円です。この下落率は66%と大きかったですね。業績の裏付けが見えない為に落ち込んだのでしょう。しかし直ぐに立ち直り6月24日に戻り高値277700円を付け、現在は横這いですね。残念ながら未だに5月の高値を抜けていません。
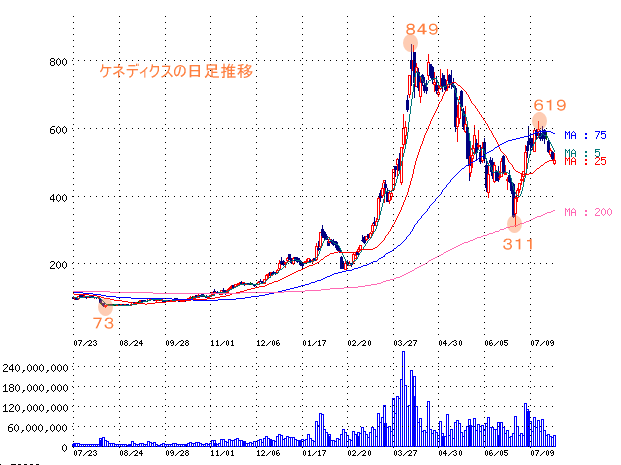
同じく力を入れているケネディクスは昨年8月15日の73円がスタートだと思います。そこから今年4月9日の849円でしたね。実に11.63倍です。そこから下げ6月27日の311円が下値で戻り相場に入りました。これまでのところは7月16日の619円です。この銘柄もどちらかと言えば、赤字ではないですが利益幅は小さく裏付けが見えない為に落ち込みが強く下落率が大きく311円まで下げています。63%の下落率ですね。
今、カタル銘柄と一般株の銘柄の事例を比較し、相場の推移を見ました。夢は大きく相場を育てますが調整には脆いのですね。その為に調整の下落率が大きくなります。折角の二番天井のチャンスを、今回は綺麗に生かせずに。前の高値の更新を今の所は成し遂げていません。おそらく初期波動が強く、その反動でしょう。更には業績の推移でしょうね。しかし初期波動が大きな銘柄ほど、大相場に繋がることは過去の経験則から学んでいます。007もケネディクスも利益の最大化をまだ実現していませんが、横河も富士重工も過去の利益推移の中では、マズマズの回復と過去最高利益を掲げています。利益が最大で高値を更新する銘柄と、利益が見えない、または小さな段階で、相場が始まる銘柄と…相場の若さや大きさの立ち位置は違いますね。企業業績は3年から5年と伸び続けるのが普通です。相場の初期波動の形成は裏付けがあるから…夢が背景にあるから、初期の相場の上昇率が高くなるのです。やがて利益を上げながら…更に株価は上昇するのが普通でしょう。
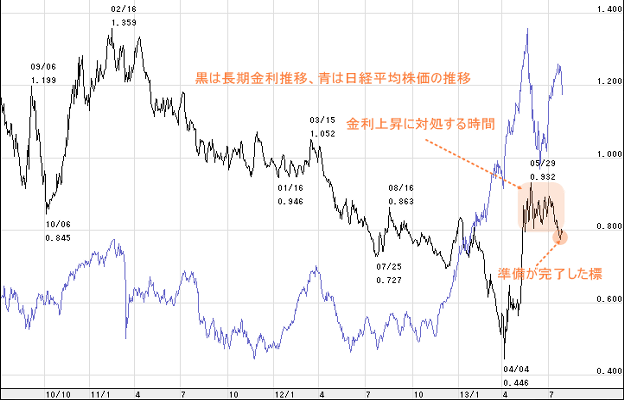
二番天井の意味を話し始めたら、長くなってしまいました。実は本論をこれから述べようと考えています。今週は参議院選の結果を受け、本来なら政策期待の銘柄が買われるべきなのに…、多くの銘柄は、僅かな売りを消化できずに沈みました。需給バランスを見ると外人投資家は買っておるようですが、国内勢の売りが続いています。失われた時代にどっぷりと漬かっている印象です。まぁ、無理もありませんね。当初はアベノミクスの異次元緩和でスタートを切ったのですが、その路線が続くかと思われたのに…。「逐次から適切」…と、折角、のぼった梯子を外され、途端に常識的な方向性に変化しましたからね。現状は、何やら不退転の決意も霞んでいます。ここで長期金利の動向を見て下さい。下のグラフは黒が長期金利の推移で、青は日経平均株価の動きです。最近の長期金利動向は0.8%のボックスを下に抜けています。つまりデフレからの脱却準備が完了しましたね。一番、恐いシナリオは長期金利の対処が出来ない急騰です。これでは何のためのデフレからの脱却なのか、分かりませんね。
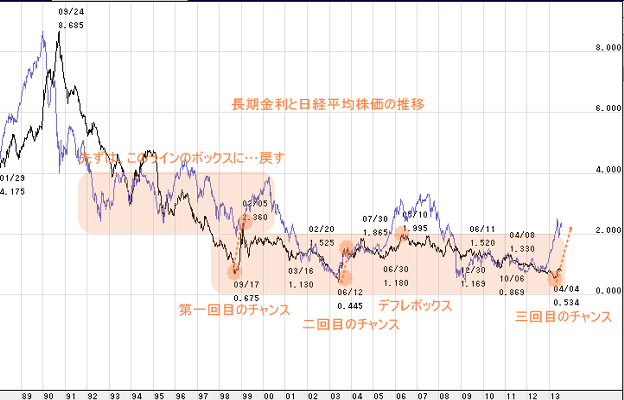
金利水準を見る限り、そろそろ第二段のステップに歩み出しても良いようにも感じます。次は1%ラインを目指すべきなのでしょう。時間軸を大きく引き伸ばすと分かりますが…1998年が日本の不良債権処理の分岐点なのでしょう。ダヴィンチに、何故か拘っているように感じるかもしれませんが、わが国の不動産の理論価格が定着した時期が1998年なのです。その時にダヴィンチの金子さんは、理屈が合う不動産価格だから、自分で商売を始めたのですね。つまり不動産は、収益還元法と言う論理的な適正価格まで下がったわけです。お金を借りて不動産を買い、ビルを建てて、貸し出しても理屈に合う利鞘が生まれた地価なのですね。この事は長期金利のボックスからも分かります。1998年9月0.675%まで金利が下がり、翌年に2.36%まで上昇し、その後、このボックスを一度も抜けていませんね。
希望が見える成長率を実現させるという事は、金利水準がこの下値のボックスを抜ける事を意味するのです。アベノミクスの成功は国内成長率を高め、適正な状態に戻すことが主眼になります。最初の10年はバブルの清算ですが、後の10年以上もの揉み合いは、政策不信による空洞化との戦いでしたね。ほら…1998年は、急激に金利は2.36%まで急騰しましたね。同じように2003年の6月は0.445から1.5%ラインまで一気に上昇し、その後、時間をかけて2006年5月の1.995%まで上昇しました。今回は3日目の挑戦です。時間軸を引き延ばすと、分かりやすいでしょう。孫さんが未来のビジョンを考える時に300年後の未来から30年後の未来ビジョンを検討している姿に似ています。迷ったら、時間軸を変えて相場の意味を考えるのです。
何故、カタルが0.8%~1%のボックスに拘っているか…その意味がだんだん理解されてくるでしょう。デフレ脱却とは…90年代の株価水準に戻ることを示唆しているのです。つまり1998年の後に付けたITバブル期の株価20833円を抜くことが、最初の第一歩なのでしょう。早急に株価が15000円と20000円のボックス(1990年代の動き)に先ずは戻し、そのステップを完了させ、ようやく次の成長期が段階的に見えてくるのでしょう。今回の金利上昇期にボックスを形成した後に、長期金利が0.8%を一旦は割り、大手都市銀行は次の準備が整ったのだから、新しい流れが、そう長い時間ではなく、近い将来、見えても不思議ではないようにも感じます。