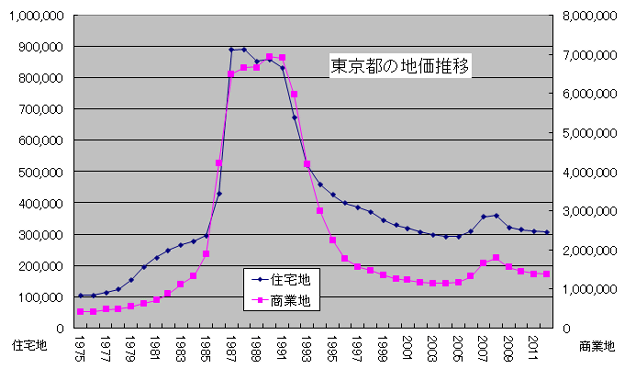« 今年を振り返り… | 最新の記事 | 売り場の見分け方 »
総資産効果の検証(2013年01月05日)
どうも株価や歴史を検証して行くと、三重野日銀総裁や速水総裁、福井総裁の失敗が日本経済に大きな影響を与えています。まぁ、何も金融政策だけの失敗ではありませんが…竹下内閣から宮沢内閣、更には森政権辺りもミスの連発が続いたのでしょう。丁度この時期に株価は大きく下がり、バブルの発生から破壊やITバブルが勃発する前後に政策ミスが起こっているようです。
基本的に1989年や2000年に失敗し、更に折角、浮上した回復の芽を2006年に潰すわけですね。二つの点でそのことが分かります。一つは市場に出回っているお金を急激に絞ることをしたのが三重野総裁ですね。マネーサプライの前年度比の伸び率の変化で異常な三重野さんの行動が説明できます。それ以降、信用創造機能が全く失われています。データを観察すると、見えてくるのはマネーサプライが回復し、貨幣乗数効果がある程度上がるまで資産インフレを容認すべきなのでしょう。そうして実際に庶民が浮かれるようになってきたら、徐々にお金の量を絞ればいいのですね。ところが貧乏人なのか…歴代の日銀総裁は僅かに変化の兆候が出て来ると、過去のバブルの影に怯えて、途端に引き締め政策に走るようです。速水、福井と連続で同じ失政を犯しています。白川さんも昨年3月にお金を絞っている所を見ると…その傾向がありますね。このツケは綺麗に払わねばならないでしょう。
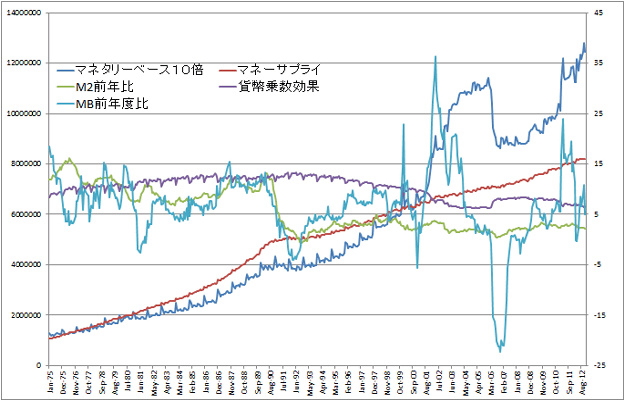
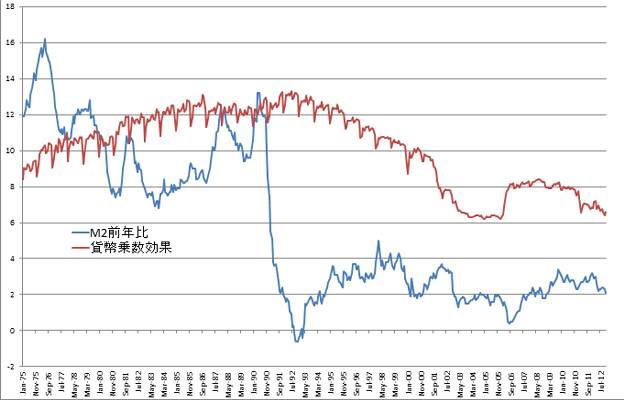
大発会はアイフルやオリコが大人気になっていますが、この背景はカタルが失敗した最高裁の今井判事への判決への怨念ですね。武富士のかたき討ちですね。異常な現象の修正はこのように必ず起きます。一つのグラフに集約しようと押し込み過ぎて見難いかもしれませんが、このグラフは様々な事を語っています。やはり今起きている現象は、やがて資産インフレに繋がると思います。長年掛けて調整を続けてきた構造改革の行き過ぎた面が修正される相場が始まったのでしょう。資産価格も2006年の頂点が一つの目安になるのでしょう。
だってどう考えても働かずに遊んでいる人間が優先される社会構造は異常ですからね。年金額を減らすわけにいきませんから、間違いなくインフレによる調整が進むのでしょう。それも資産効果を利用することを考えるようになるでしょう。中国の成長もそうですが固定資本形成のGDP比率を上げることは資産価格の上昇に繋がり、見えない付加価値を発生させ、その余力が消費活動を押し上げ、最終的に再び一人あたりのGDPを押し上げる相乗効果を発生させます。だから総資産効果が高い株式の値上がりが、優先される相場展開になると考えています。
ところが理論武装されていない多くの人は目先に値上がりしか見えてない訳ですね。故に野村証券が、あっという間に2倍になった背景も分からずにいるわけです。株価が上がったので恐くて株を買えないのですね。何故、私が期間の長いチャートやデータを多用しているのか? 今日だって1975年からの数字を持ってきて説明しています。歴史観が働くのですね。1993年に細川内閣が誕生し55年体制が崩壊し、混迷を深めてきました。体制転換から20年が経過し、そろそろ脱皮してもおかしくありません。
バブル当時は、個人のレベルで坪単価1億円以上のビルを買っていたのですね。僕の嘗てのお客さんは地方の土地を郵便局に売り、その代金で代替地を東京駅の前に買いました。小さなビルを二つ買ったのです。数十億円ぐらいなのでしょう。当時、土地を売って土地を買うと税金が安かったのです。アドバイザーは長谷川慶太郎でした。しかし馬鹿な行動でしたね。あのお客様もバブル期に日本国債を買うのが一番でした。そうして、その利息で生活すべきでしたね。月300万円程度の家賃を払いながら豪華なマンションに住むのが理想的でしたね。
今度は長いデフレが終焉を迎え、インフレの時代に向かうと思うのが常識的な発想です。しかし今の政策は正しい選択かどうかわかりません。コントロールできれば、このやり方は良いのですが…どうでしょう。2014年4月から消費税を引き上げる為に間違いなく政策官僚は動いているようです。今日はこの前提で話を進めます。年初から掲げているように、資産効果が出て来ると考えられますから、総資産の大きな会社の株が上がると確信しています。理由はマネタリーベースの増大がこれから実行されるからです。日銀は9月、10月、12月と連続で緩和策を実施しています。この効果は6か月程度遅れて現れてきます。何処でマネーサプライの前年度比が伸びて、乗数効果まで変化が現れるか分かりませんが、少なくとも当面は株価が下がることを考えないで済みそうですね。
2006年のピーク時が当面の目安だと述べましたが、総資産の大きな順に株価を検証して行きたいと思います。先ずは総資産218兆円の三菱UFJですが2006年の高値は1950円です。その後、増資により1.449倍に増えましたから1345円が目標株価になりますね。総資産165兆円のみずほの当時の高値は1030円で、株数の増加は2.269倍ですから453円です。総資産143兆円の三井住友は13900円が高値で株数は1.90倍に増えたので、7315円ですね。現在の株価はそれぞれ484円、163円、3225円ですから上昇余力は2.77倍、2.77倍、2.26倍になることになります。野村は2870円で、その後増資で1.953倍ですから1469円になり現在の株価は524円ですから2.80倍ですね。
もっと目標株価は高いかと考えていましたので、少し意外でした。何れも3倍弱で妥当なのでしょうか? まぁ、これで当面の目標株価が決まったわけです。計算してみて現実を知る結果かな…僕のイメージはもっと強いものを想定してレポートを書き始めたのですが…現実は厳しいものですね。100兆円規模の資産効果は大きなものがある筈で、2006年の時より強くなる筈ですね。何故なら、それ以降も資産デフレが進んでおり、ギャップが広がっているからです。ここで地価動向を調べてみましょう。あらら…こちらも駄目でしたね。既に地価の面では収益還元法の論理価格で動いているようです。なかなか狙い通りのデータが得られません。今日のレポートの狙いは失敗でしたね。本当はカタルの総資産価格からの株価推論はもっと高いのでは…と考え、レポートを作成してきたのです。少なくとも5倍程度の数字を期待していたのですが3倍とは…現実は厳しいな。