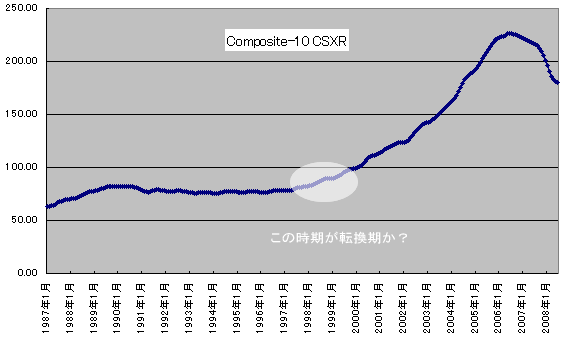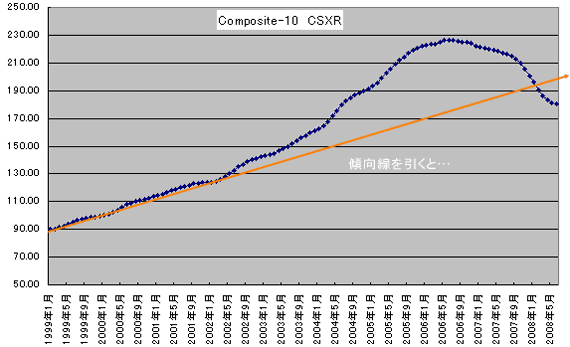米国金融の混乱(2008年09月20日)
米国金融が混乱しています。しかし市場主義を標榜する米国ですから当初から心配はしていません。政権交代が迫るなかで前ゴールマンサックス証券CEOのポールソン財務長官はよくやっているのでしょう。日本との違いは処理のスピードの違いですね。今日は揺れる金融問題の根幹である仕組みを考えて見ましょう。
世界の銀行はBIS規制に縛られています。総資産に対する自己資本規制があり8%が最低ラインになっています。わが国の三菱UFJ銀行はおよそ11.2%を維持しています。今回の混乱は資産に占める証券価値が下落した為に、米国では時価会計が厳格になっているので損失が確定しなくても持っている資産の減損会計が求められます。シティーバンクの総資産はおよそ2兆1千億ドルです。サブプライム関連証券だけに留まらず、全ての不動産融資に対する証券が大幅に下落し、その損失処理の為に自己資本が毀損し増資を実施したのですね。
尚且つそれでは健全の目安と言われるBIS規制が維持できないために総資産の圧縮を余儀なくされます。この総資産の圧縮が始まると実体経済に悪影響を与えます。しかしどの金融機関もリスクを抱える余裕がないために買い手が見つからず、傷付いた資産を処分できずに抱えています。その為に、元である不動産価格が下がると、更なる損失の計上を余儀なくされる負の連鎖が今回の問題です。日本ではこの為にデフレ状態が一般化しGDPデフレーターが発生したままなのです。閉塞感の根元は活動意欲が鈍っている為なのですが…まぁ、日本の話は置いておいて…。故に不動産価格の問題は重要で、更に今回の処理は抜本的に不動産の値下がりから金融機関の連鎖の悪夢を解消させる道筋なのですね。RTC(整理信託公社)の設立は大きな意義があります。株式が上がるのも道理でしょう。
これまでの金融機関は損失の元を抱える中で貸し出しを伸ばすことはリスクを抱えることになります。だから貸し渋りがおき経済活動が低迷していくのです。勿論、収益を上げるためには貸し出しを伸ばさなくてはならないのですが、リスクのない貸し出しなどないのです。自己保全の為に金融機関が保身に走れば経済は萎縮する一方ですね。株屋としては既に第二幕に目が行くのですね。この話は明日のビスタニュースの原稿に書く予定です。私はGSEへの公的資金投入がこのタイミングで実施されることも予期していませんでしたが、メリル、シティーの決算がターニングポイントになるとの予想の元で行動していました。今後、いろいろ言われるでしょうが、今回の処理が迅速に実行されれば予想の中でもっとも早いタイミングの相場回復になるでしょう。残念ながら、日本株は外資系投資家に依存していますからね。
下のグラフはS&P提供のケース・シラーの全米10都市の住宅価格指数の推移です。
米国政府の妥当な処置だと言う理由が分かりますね。やはり市場経済の国は良いね。