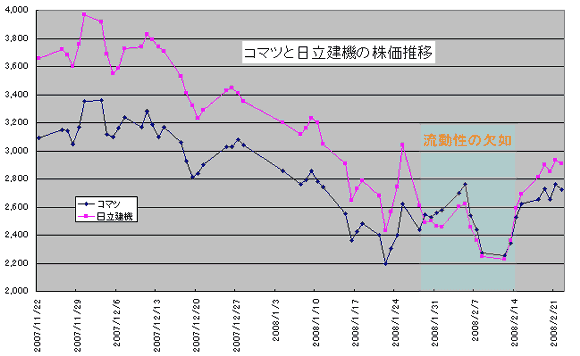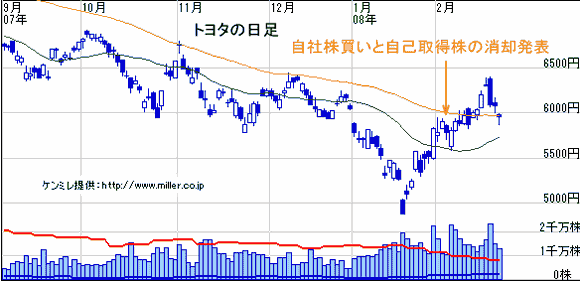流動性の回復(2008年02月23日)
今日は先日の追加レポートです。
先々週、「デッカプリング(非連動)とリカップリング(再連動)」と言うテーマでレポートを書きました。その追加ですね。あの時の予測は正しかったようです。流動性の欠如から、市場は極端に保守的になり様々な現象が生じました。普通は考えられない株価水準まで多くの会社の株式が売られました。サブプライム問題だけでは説明が付かないのです。市場原理を問う相場だと言う認識が、マスコミにも理解されてないようです。私が正しいかどうかわかりませんが、依然、異常事態が続いているな…と考えています。
ビスタニュースの原稿に割安株リストを載せましたが、1100銘柄を越える会社が一株辺りの純資産以下なのです。しかも営業黒字で配当利回りが1%以上もあるのです。通常は黒字なら利益が蓄積されますから、毎年、自己資産は増えます。故に株価がそれ以下にはならない筈です。新日鐵をはじめとする大企業が株式の持ちあいを再開し、コーポレートガバナンスが欠如している現れでしょう。日本の病魔である官僚社会主義が深く根付き、市場が悲鳴をあげている様子でしょう。単純平均株価をみればわかります。現在は335円ですが、この水準は1977年の水準です。つまり日本の躍動感は後退しているのでしょう。GDPに対する政府支出は増え続け誰もその事を話題にしていません。マスコミもグルなのでしょうね。結局、情報コントロールが上手いのでしょう。インターネットの発展により誰でも真実が分かるようになりました。自分で総務省のデータをエクセルに落とし、グラフ化すれば簡単に分かります。GDPが成長しないのに、政府系支出が膨らむのです。

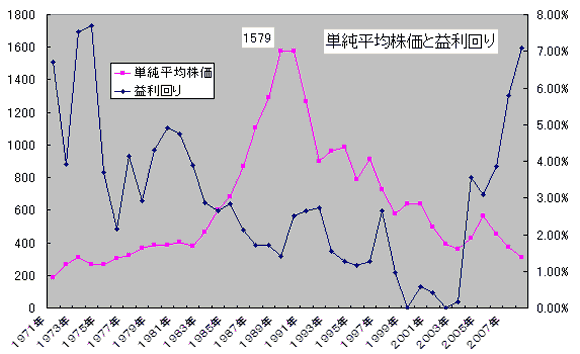
このような環境下でサブプライム問題の終焉を迎え、収拾過程に移行している姿が現在の状態なのでしょう。奇妙なのは景気が悪化するのに資源価格が高騰している事実です。投機資金が入っていると言えばそれまででしょうが、理屈からして不可解です。考えられるのは…ここからはビスタニュースの原稿にさせて頂き、兎も角、まともな市場経済感覚をしている企業の株が上がるのはやはり市場原理ですね。そうして先日掲げた、日立建機とコマツの株価レースを見れば分かるように、市場は健全化の道を歩んでいるわけです。やはりケチですがトヨタはトヨタらしいスタイルで自己防衛を謀っています。ブルドックのような後出しジャンケンを許す社会の仕組みが歪んでいるのですね。このような環境下で自社株が異様に安くなっているのに対策を練らないのは経営者として失格でしょう。
掲げたグラフの解説をしなくてはなりませんかね? 説明をしなくても分かりますよね。