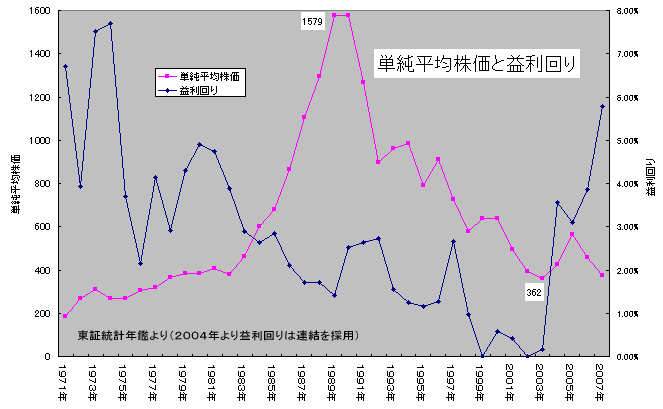« システマチックリスク | 最新の記事 | かたるの失敗 »
胎動(2008年01月19日)
株価は合理的に出来ているのでしょうが、時々、反乱を起こします。市場参加者の心理が傾くのですね。不安が不安を呼び、恐怖に変わりパニックになる。恐慌心理と言うやつです。通常は途中で冷静な心を取り戻す時間が必要になるのですが、その考え直す時間が追いつかない場合があります。現在の市場心理はそのような現象が重なっていますね。東証一部上場企業1731社のうち775社がPBR1倍以下の有配企業なのです。44.7%も占めているのです。信じられない感覚です。これらの企業を買い取り解散したら、どのくらいの金額が残るのでしょうか? PBR1倍を割る企業は存続価値があるのでしょうか?これらの企業は株主を無視した経営をしていると言っても過言ではないでしょうね。コーポレートガバナンス(企業統治)と言う言葉が生まれ、かなりの時間が経ちましたが、日本には村意識が強く残っているのでしょうね。
株がいくら割安だと言っても正常な経済状態でなければ意味のない話です。国民一人ひとりが、現在置かれた日本の状況を考える必要があるのでしょう。1969年にヤマハが国内で初めて時価発行増資を実現しました。それまでは額面発行が主だったのです。そうして今年は初めての三角合併が実現しましたね。シティーバンクが日興証券を株式交換で傘下に納めました。歴史的な出来事でしょう。今回の株安により、既にグローバル時代が幕明けた印象を強く感じます。私は最近単純平均株価の意味を考え続けています。2003年に株価は底を付け上げましたが実際の可処分所得は増えずに国税局の平均給与所得は下がり続けていました。日銀をはじめとする政策当局はこの意味を理解していたのでしょうか?まぁ賃金(雇用)は景気の遅行指数ですが…
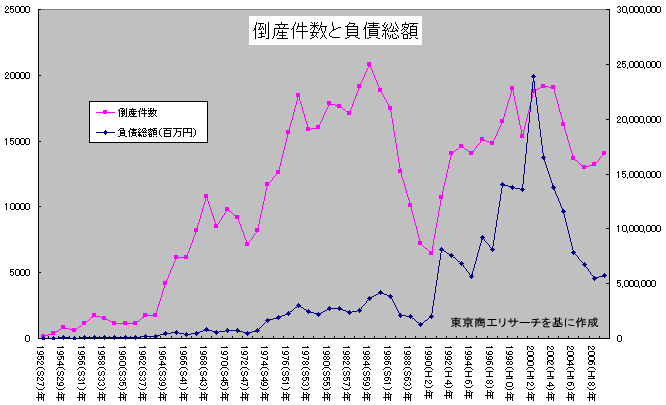
昨年の企業倒産件数は14091件で2年連続の増加、金額では4年ぶりに4.1%増え5兆7279億円となりました。この統計は日経平均株価ではなく単純平均に連動しています。街角景気と呼ばれる国内景気指標もそうですね。グローバル化を推し進める大企業と日本が舞台の中小企業の景況感はかなり違うのでしょう。私が名目GDPと実質GDPの話を持ち出す例と似ています。一人あたりのGDPは世界比較をすれば、どんどん劣化しているイメージですね。昨日のテレビでは燃料費の高騰により漁が困難になっている漁師の話が話題になっていました。農林水産省が税金をばら撒き救済するというのです。わが国の農業政策の失敗を顧みずに、同じような愚作を演じているように感じました。国民が政府を頼る姿勢がダメなのでしょうね。
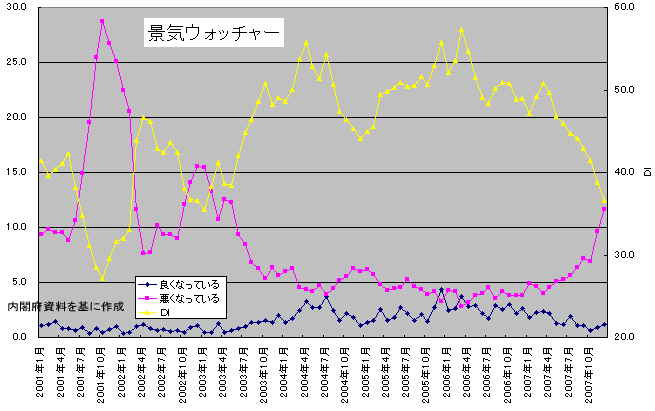
「合成の誤謬」と言葉が、政策不況に繋がっているように感じます。確かに姉歯の偽装建築が建設基準改正法に繋がり、法案は正しい選択なのでしょうが、明らかに準備不足を露呈しています。サラ金規制もおせっかいだな。と私は感じますが、ものを考えない国民レベルから見れば必要な政策なのかもしれません。(金融が縮小しますから実体経済は更に縮小します。)金融商品取引法も同じでしょう。田沼政権から松平政権に移った江戸時代と現代は同じような時代なのでしょう。中国の成長を支えているのは「文化大革命の圧制」の反動なのでしょう。そのような歴史的な観点から日本株を見ると「失われた時代」は新たな飛躍の時代の種なのでしょうね。そうしてBRICsの成長により、一時的なカンフル剤効果がサブプライム問題から消えつつあるのが、今の日本の姿なのでしょう。ここで再び気付くのでしょう。日本は新しい構造改革をスタートさせねばならないと感じるのでしょうね。産みの苦しみは、何年か続くのが道理です。底入れチャートを、現在、研究していますが、底練りも必要なのですね。同じ現象のように、現在の日本経済がダブります。
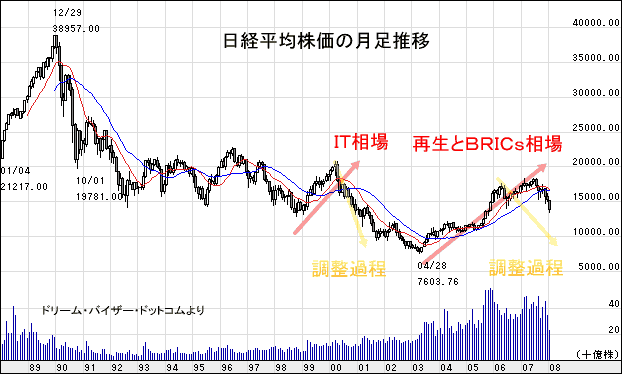
単純平均を見て、益利回りを見ると、夜明けは来ているが、なかなか新しい陽が昇らない感じでしょうかね。しかし今年は2003年に続き、3度目の正直と言うやつで、復活の年になるのでしょう。1998年、2003年、そうして奇妙にも同じ5年ごとに訪れている2008年の回復元年。今度こそ、長い期間の上昇波動が始まるのでしょうね。明るさを感じる年初の相場に、私は見えるのです。(みんなはこれから暗くなると言いますが…)今年、始まる長期上昇波動は、最低でも2012年ごろまで続くのでしょう。そうして38915円の日経平均株価と、1579円の単純平均株価を抜く相場に繋がると考えている僕は、やはり考えが飛躍しすぎで馬鹿なんでしょうね。こんな事を今から言う奴は誰もいませんから…。でもカラ元気と思われるかもしれませんが、失われた時代の流れから、IT相場、そうして再生相場、BRICs相場をみて、そう感じているのです。単純平均株価は、その謎解きの素晴らしい切っ掛けになりました。何故か株価は下がり追証に苦しんでいますが、奇妙に明るさを感じるのです。