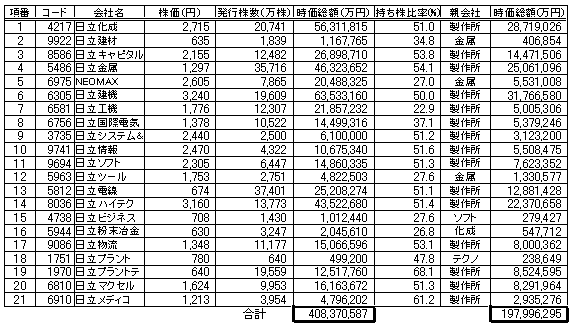« 株価急落を受けて… | 最新の記事 | 物色の流れ »
M&A(2007年03月24日)
最近の新聞記事を読むと、外資系ファンドが増配要求している記事をよく目にするようになりました。先日の東京鋼鐵のケースでは経営者側と、いちごファンド側とでプロキシーファイト(委任状闘争)が起こり、経営側が敗退しています。日本は新時代を迎えたものですね。その様子を下のグラフから確認が出来ます。金融機関の持ち株比率が、株式の持ち合いにより一時46%まで高まりましたが、今では26.3%まで減っています。近年では外国人投資家の持ち株が増えて24.1%まで高まっています。
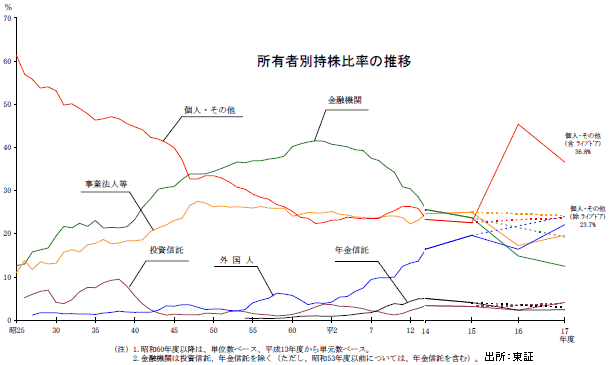
このような状況下で最近の様子を拾い出すと…中部電力、ノーリツ、シンニッタンを始め、電力卸売会社のJパワーに対しても英系の「ザ・チルドレンズ・インベストメント・マスター・ファンド」(TCI)が増配要求をしています。ところが経済産業省の北畑隆生事務次官は15日の記者会見で「外国のファンドには電力会社の公益性を理解してもらうべきだ」と語ったとか報道されています。奇妙な構図ですね。何故、民営化して株式上場をしたのでしょうか?その民間会社に役人が口出しする。しかし電力の安定供給は当たり前の話で、増配要求がくるほど儲かっているなら許認可価格なので料金の引き下げをすべきではないかと言う議論もあるわけです。
サッポロビールはスティールパートナーズがTOBを考えているとか…面白くなってきましたね。その一方でエルピーダの坂本社長は「私より経営能力が高い人が居るなら、経営をいつでも変わる」といっていますね。昔、ソニーの盛田さんも、そう言う発言をしたとか…フジテレビのように経営権に拘る会社がある一方で、正当なグローバル経営をする経営者も居るのです。
5月には三角合併が解禁され、これから大株主と経営側が対立する構図が増えます。買収に対する防衛策を採用する会社が株主総会で信認を得ようとしていますが、株主としては現経営者より有能な経営者が居るなら、経営を変わっても株式価値を高めてもらいたいわけで、果たしてTBSのような目論見は通用するのでしょうか? 仮に買収防衛策を支持し経営側に立てば、その株主の株主から、株主代表訴訟を起こされるかもしれません。
例えばTBSの場合は、三井物産などは会社側の立場なのでしょうが、物産の株主から見れば、TBS株は物産の投資の一手段であって楽天側についても株主価値が高まれば良いわけですからね。確かにM&Aは、三角合併のスケジュールなどを考えると、相場の流れの一環を担いそうですが、投資の本質姿勢からは外れていますね。TOBをかける側から見れば、その会社に欠点があるから買うわけで、経営が変われば会社価値が上がる可能性があるから…つまり有効に経営資源を使ってないから、経営権を狙われるわけですね。
投資の本来の目的はその会社を育て、会社の成長と共に株主も儲かるというのが理屈ですから…会社が狙われていると言う短期目的で、株式投資をするのは筋が違うような気がします。しかし株式投資には色んな見方があるのでしょう。例えば最近の人気になっている日立です。その買いの根拠を下の表は示していますが…この意味が皆さんに分かりますか? 答えは明日、ビスタニュースで解説する事にしましょう。