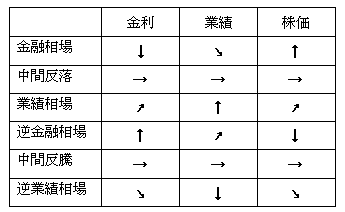« 今年を振り返り… | 最新の記事 | ソフトバンクとトレンドライン »
景気と政策(2007年01月06日)
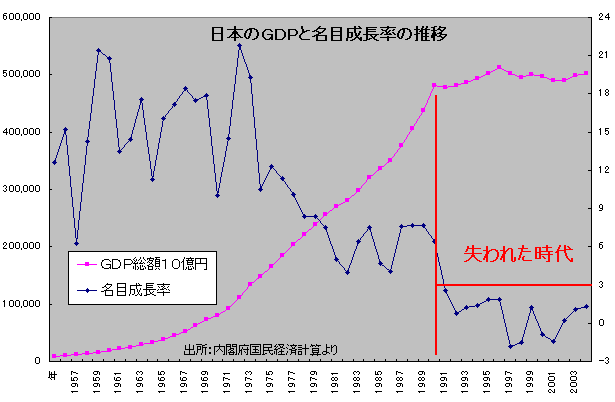
上のグラフを見ると分かるように、わが国のGDP成長率は完全に止まっているのです。この間のアメリカの平均GDP成長率は実質で3.2%(95~05年)なのです。日本は何故、このような体たらく道しか歩めなかったのでしょうか? この間に金融政策や財政政策を実施しているのに…、アメリカのような先進国でさえ3.2%ですよ。中国などは9.2%(95~04年)平均で2005年は10.2%の二桁成長です。情けない姿です。イギリスだって2.9%(95~04年)の成長なのに…トホホ。
構造改革の問題なのですね。道路特別財源の一般財源化さえ実現できないのです。この額は2007年度の余剰分が、実に7000億円だそうです。この7000億円が掘っては埋める無駄な人員の作業代に消えていく。こんな予算の使い方をしていれば、世界競争に負けるのは当たり前。折角の道路族の切り崩しも小泉内閣でも出来ずに、安倍政権では逆にやり込められる始末です。一体、マスメディアは真実を報道しているのでしょうか?
年末にかけ日本株は新日鉄のディーリングなどで盛り上がってきましたが、果たしてこのまま上がるのでしょうか? 経済財政政策の内閣府特命担当大臣の太田弘子さんは1月にも中間報告を上げるそうですが…成長力のある政策に踏み切れるのでしょうか? 伊藤忠の丹羽さんも諮問会議のメンバーですが、どうなるのでしょうね。実はこのような財政政策の行方は非常に重要なのです。
景気の行方に左右するのは金融政策だけでなく、財政政策は非常に需要です。一般的に財政政策は公共事業投資のような裁量的な財政政策を示しますが、租税の仕組みは富の流れを変えますし、規制緩和などの仕組みが景気に大きく影響するのですね。わが国の行政は事前型の指導方式から、事後型の取り締まり罰則方式に大きく変わりました。だからMOF担などの民間ポストもなくなっているのでしょう。
例えばサラ金規制です。一般的にはあまり景気に関係ないように見えますが、大きいですね。インターネット業界の広告の1/3ぐらいはサラ金関連だったとかで…一連の規制強化の為に広告を自粛したので、ネット関連の広告価格が暴落したとか言われています。更にパチンコ屋などの産業も不振になっていると言う話を聞きます。
このような規制は正常化への道なのでしょうが、景気へは一時的な落ち込み要因になりますね。昨年の資金供給残高は日銀のゼロ金利解除などの影響もあり13.3%減の96兆982億円だそうです。経済が拡大するなら、ありえない話しですね。勿論、電子マネーの普及などの影響もあるのでしょうが…このような話は難しいですか?
実は株の仕組みを知る上で、このような景気刺激策の話は非常に重要なのです。景気の波には様々な波動があり、企業の製品在庫の過不足から来るといわれる「キチンの波」(40ヶ月)、そうして設備投資の増減による「ジュグラーの波」(7~10年)。液晶や半導体の償却年数は、先頃の税制改正で5年の全額償却に改定されましたね。短くなる傾向にあります。そうして建物の建て替えなどで生じる「クズネッツの波」(20年)丸の内の再開発や日本橋の再開発などは一例でしょう。そうして注目される技術革新による「コンドラチェフの波」(50年)などの景気波動により物色される銘柄が変わるのですね。古くは産業革命、今はインターネットの普及期ですね。
これらの景気波動の波に時代背景をあわせ、銘柄を選別するわけです。今回と次回は再び景気循環と銘柄物色のおさらいをしようと思っています。かたるの本にも載っていますし、金利と株価の関係は非常に重要ですね。政府は景気の浮き沈みにより、財政政策と金融政策のバランスを考えて、景気を安定的な成長路線に載せるのが使命なのですね。一番上のグラフのように「失われた時代」などと不名誉な名前を付けられないように、政策官僚は努力すべきなのです。
本来なら、このような事態を生じさせた政策の担当官僚や当事者(政治家や日銀総裁)は首ですよね。民間企業なら業績を悪化させたのですから確実に首になります。ところが退職金をもらい天下って更に暴利を貪っているのが、官僚社会主義者達の食えないところです。はぁ、悲しいかな。夕張化は益々近づいている。それでは、次回は景気と株価のグラフなどを用いて解説しましょうね。一応、表だけを掲示しておきますね。思い出しました?