« 金利裁定 | 最新の記事 | 株価(流れ)の決まり方 »
金儲けは社会貢献(2006年12月16日)
基本的な株の考え方
株式投資は切っ掛けの多くはお金を儲ける為です。将来必要とされる産業の資金を投資すると、その産業が非常に伸び、その会社が繁栄し株主も儲かります。これは普通の株式投資の考え方ですね。
このようなお金を儲けるという事は、効率的な社会作りの一翼を担っているとも考えられます。日本の教育は間違っていますね。株式投資で儲けたお金を不労所得と呼び蔑むのです。リカードの「比較生産費説」と言う考え方があります。自由な貿易環境において、生産性の高い産業に特化すると効率的な社会になるという考え方です。労働生産性の高い産業が必要なところで伸び、生産性が上がるのですね。このような効率化を促進させる為に、貿易商人は裁定取引を行います。つまり市場間の価格差を利用して利益をあげるのです。株式投資と言う行為もこの貿易商人と同じです。
ここでリカードの比較生産費説を簡単に勉強しましょう。
世界にはイギリスとポルトガルの2ヵ国しかなく、また、生産している商品も毛織物とぶどう酒の2種類しかないと仮定します。
そして、イギリスは毛織物1単位を生産するのに100人、ぶどう酒1単位を生産するのに120人必要だとします。一方、ポルトガルは毛織物1単位を生産するのに90人、ぶどう酒1単位を生産するのに80人必要だとします。さらにイギリスの全労動量を220人、ポルトガルの全労動量を170人とすれば、貿易が行なわれないときの2ヵ国の毛織物の総生産量は、イギリス1単位、ポルトガル1単位の合計2単位です。同様に、ぶどう酒の2ヵ国の総生産量も2単位となります。
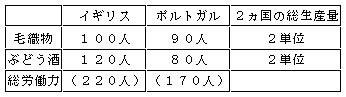
この表を見るかぎり、毛織物もぶどう酒もポルトガルの方が、イギリスより少ない人数で生産でき絶対優位の状態ですね。ポルトガルにとって、貿易を行なうメリットは何ら存在しないように思われます。しかし、リカードは、このような場合でも、両国の生産費を比較し、比較優位のある商品の生産に特化することによって、双方ともに利益を得ることができることを明らかにしました。
すなわち、ぶどう酒を基準にした場合、 (100/120) < (90/80) より、毛織物生産はイギリスが割安であることがわかります。
また、毛織物を基準にした場合、 (120/100) > (80/90) より、ぶどう酒生産はポルトガルが割安であることがわかります。
そこで、イギリスは比較優位のある毛織物に特化し、ポルトガルは同じく比較優位のあるぶどう酒に特化する。その結果、以下のようになります。
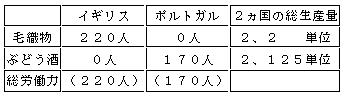
2ヵ国の総生産量は、貿易がない場合に比べて、総労働量に変化がないにもかかわらず、なんと「増加」しているではありませんか。すなわち、生産費に違いがある場合は、それぞれが、比較優位を持つ商品の生産に特化し、自由貿易を行なうことによって、双方ともに国際分業の利益にあずかることができるのです。まるで、手品のような話ですが、今日「自由貿易」こそが人類のめざすべき方向とされているのは、この比較生産費説が根拠となっています。
何故、効率的な方に特化するのか?
イギリスでの毛織物はぶどう酒に対する国内相対価格は10/12です。一方、ポルトガルでの毛織物のぶどう酒に対する相対価格は9/8です。このとき、ポルトガルで作られたぶどう酒を一単位イギリスに持って行き、12/10単位の毛織物と交換し、これをポルトガルに持って行きぶどう酒と交換すると、なんと、この貿易によって一単位のぶどう酒が27/20単位に増えるのです。貿易によって商人は利益を得ますね。つまり効率化が推進されるのです。(無論、リカードの理論に対し反対意見もあります。)
 つまり、株式投資と言う貿易商人がいるから市場間の歪みがなくなり、効率的な生産性の高い社会になるのです。今日はデヴィット・リカード(1772~1823)と言うイギリスの経済学者の主張した比較生産費説と言う考え方から株式市場を考えて見ました。このように考えると株式市場でも同じ半導体を作っている会社でも生産性の悪い会社を売り、生産性の高い会社を買うというロング・ショート戦略の投資は貿易商人取引みたいですね。
つまり、株式投資と言う貿易商人がいるから市場間の歪みがなくなり、効率的な生産性の高い社会になるのです。今日はデヴィット・リカード(1772~1823)と言うイギリスの経済学者の主張した比較生産費説と言う考え方から株式市場を考えて見ました。このように考えると株式市場でも同じ半導体を作っている会社でも生産性の悪い会社を売り、生産性の高い会社を買うというロング・ショート戦略の投資は貿易商人取引みたいですね。
金儲けは社会に貢献するのです。