« 一つの四季報の見方 | 最新の記事 | ROE »
財務諸表(2006年11月11日)
先回の株式教室では営業キャッシュフローと利益の事に触れています。
今日は会計の話を少し勉強しましょうか…
財務諸表には「貸借対照表」「損益計算書」そうして新設された「キャッシュフロー計算書」があります。昔は二つだけだったのですが、キャッシュフローの考え方は2000年3月より義務付けられました。会計法には一般会計原則があります。当たり前のことなのですが、嘘を言ってはだめだという真実性などの原則です。以下の原則をもとに財務諸表は作成されています。
1.真実性の原則
2.正規の簿記の原則(正規の簿記から作成される)
3.資本と利益の区分の原則(正確な損益計算を行うために資本取引と損益取引を区別する)
4.明瞭性の原則(充分な情報を分かりやすく提示すること)
5.継続性の原則(むやみに会計処理を変更しない 原価法や低価法など)
6.保守主義の原則(保守的な立場で、確かなものだけを計上する。)
7.単一性の原則(二重帳簿を作成しない)
8.重要性の原則(重要事項は適切に詳細に会計処理をする)
貸借対照表(BS)は、財産の残高を示す一覧表です。お金をどこから調達して、どのように運用しているかを示します。
損益計算書(PL)は、会社の成績表です。1年間の収入と支出の差額から、会社がどれだけ儲けたかを示します。損益の流れから利益がどのように生み出されてきたかを見ることができます。
一方、キャッシュフロー計算書は、お金の流れを見るための一覧表です。
お金の流れを見るために、営業部門でのキャシュフローと、投資部門のものと、財務部門のものに区別されています。お金が何処から調達されたか、また、そのお金が何処に使われたかを示します。
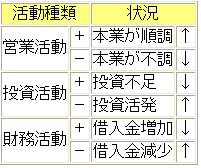 通常、営業キャッシュフローは黒字で、投資キャッシュフローは赤字です。そうして財務キャッシュフローは企業の経営方針によりますね。新株の発行や社債、または借り入れにより資金を調達していればプラスになります。借金の返済をすればマイナスですね。
通常、営業キャッシュフローは黒字で、投資キャッシュフローは赤字です。そうして財務キャッシュフローは企業の経営方針によりますね。新株の発行や社債、または借り入れにより資金を調達していればプラスになります。借金の返済をすればマイナスですね。
PL(損益計算書)上の利益と営業キャッシュフローは同列に見られがちですが実は違います。キャッシュフローでは、実際のお金の出し入れを問われていますが、PLでは売上と利益の関係を問われているのですね。二つの違いは色々考えられますが、大きな違いは在庫の考え方ともう一つは売掛金などもそうでしょうね。
例えば、1個80万円の商品を100万円で売る事にしましょう。儲かると思い、経営者は10個を仕入れました。しかし現実には7個しか売れませんでした。この場合の売上は700万円で原材料費が560万円ですから、利益は140万円になります。(人件費などの他の費用は考えない。)
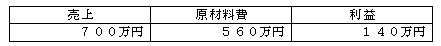
ところが、手許に残るお金は売上金の700万円ですが、実施は売れると思い10個仕入れていますから、800万円の支出をしているわけです。利益が140万円もあるのに手許にお金がない。このような例が黒字倒産の一例ですね。
もう一つのケースは売掛金です。
実際に売れているのですが、掛け売りをしており売掛金が現金化されない場合が考えられます。通常、売掛金は短期に回収されますから、通常の営業活動において、連続で営業キャッシュフローがマイナスになることはないはずです。
何期も営業活動のキャッシュフローで赤字を続けるのは問題企業と言うわけです。このように株価の影響を考えた場合、営業キャッシュフローがプラスの企業が望ましい事がわかります。
企業が一時的に投資キャッシュフローをふやす場合があります。企業が経営戦略で工場を拡張したり、新規の設備投資をした場合などのケースです。投資キャッシュフローには子会社の貸し借りなど、また投資有価証券の売却などの資金の出入りなども含まれますが、新規設備投資を増やす場合などは、将来の利益が膨らむことも想定されますから、株価を考える場合、合わせて投資キャッシュフローの動きを見ることも重要ですね。
通常、株価は損益計算書の利益に主眼を置いて、PERと言う指標で判断されがちですが、健全な利益の伸びかどうか?キャッシュフロー計算書を合わせて見るようにすると良いでしょう。