業績相場へ(2006年07月29日)
今日は非常に明るい話をしましょう。
株式教室を見ると分かりますが、春より「休むも相場」など…暗い話に終始しました。中間反落局面とか…述べてきましたからね。しかし、どうやら新しい段階を市場は迎えつつあるようです。そうです。業績相場の始まりです。
新興株が下がったので多くの個人投資家は株で損をしており、非常に暗い気持ちでしょう。通常は個人がやられれば、市場のムードも暗くなり全体の株価水準も下がる可能性が指摘されていました。アメリカ景気の減速が明らかになり、NY市場は金利が下がるので、この動きを好感し昨日のNY株は大きく上がっています。しかしアメリカ景気が減速すれば、日本も影響されるので景気にマイナスとされ、先行きの株価見通しも不透明だったのですが、足元の景気は好調で4-6月期の決算数字は、概ね増額修正されています。
その数字を見るのが日経新聞の指標欄に掲げられるPERや益利回りの推移です。PERの逆数が益利回りですのでPERと同じ意味を持つのですが…この益利回りは株式の金利水準を示したものと考えていいのでしょう。株全体を買うと何%に回るかを示した数字が益利回りです。
土地の価格が収益還元法で下げ止まったように、お金には常に金利裁定の動きが働きます。金利裁定とは、預ける場所により利息が多いか少ないか? 人間誰しも利息の多いほうへ預金をしますね。同じ品物がイオンとダイエーで売られていれば、通常は価格の安いほうへ買いに行くのが普通です。経済は常にこのような裁定と言う考え方で動いています。需給バランスも同じこと、人気の高い商品は価格が高くなりますし、人気のない品物の価格が下がります。
石油や金にお金が流れ、一次産品の価格が新興国の需要増加により高くなっていますが、世界の調達金利コストが上がり、採算が悪化すると需要は減り、当然、原料価格も下がる運命にあります。所謂、金利は全ての経済活動の源を調整するパイプです。そのお金の調達コストがドンドン上がる事により、経済活動が制限されインフレは沈静化されます。一番の経済活動の源であるアメリカは既に17回の金利引き上げを実施し、金利は5.25%に引きあがりました。二番目の日本は量的緩和政策を解除し、市場から30兆円近い資金を引き上げました。
このような環境下で原油価格が一段高するシナリオはあまり見えませんね。イスラエルの侵攻が始まっても、意外に原油価格は上がりませんでした。この辺りに注目すると、既に一次産品の価格は天井圏なのかも知れません。中国の経済スピードは速く、年率10%前後の成長をしていますが、固定資産投資への依存率は非常に高いですね。金利を引き上げれば簡単に成長が止まることを意味しています。一人当たりのGDPはおよそ1000ドル、日本は33000ドルですね。原油価格が引きあがる影響度はどちらが高いか、簡単に分かると思います。
さて、このような環境下で日本の株式市場は中間反落局面を迎えたわけですが、ようやく、先が見え始めています。一番大きな材料は日本企業の構造改革意識なのでしょう。日本は今まで儲かるか分からなかったのに、規模の拡大を優先してきました。しかし未曾有の金融不況で総資産利益率など、財務バランスに配慮した利益を求める傾向が強くなっています。松下の目標もそうですね。売上高に対する営業利益を、目標の一つにおいています。
このように、経営者の意識変化により益利回りが過去最高水準に上がっているのです。調達金利も上がってきましたが、企業の利益も伸びていますから、イールドスプレッドは、なかなか低下しません。このような環境下で日経平均株価が下がることはありません。故に年末に掛けて株価が上がるシナリオが見えてきたのです。業績相場へのシフトが起こるのでしょう。まだ始まったばかりの第一四半期の決算発表ですので、今後の数字も注目されます。
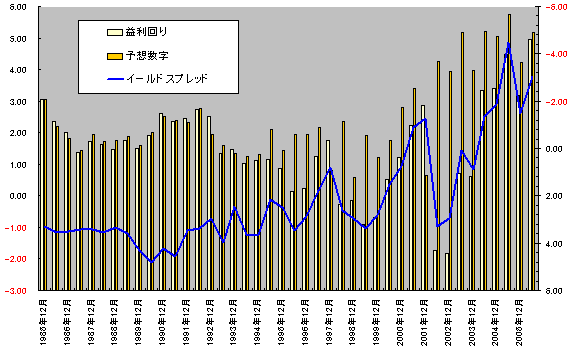
日本株全体が業績好調で株価が下がる道理はないのです。故に2度の追証に苦しめられた新興株も理想買いからの調整は終了し、再び、その会社の業績が上向いておれば、株価は回復傾向に入ってきたのでしょう。上のグラフを見てください。青の折れ線グラフは再び上昇し始めています。日銀が金利を年内据え置き、景気に配慮すれば株価の新高値も視野に入ってきました。個人投資家の皆さんも、ようやく過度の悲観を排除すべき時期に来ましたね。