« 財務会計(定額法と定率法) | 最新の記事 | かたる銘柄のパターン »
エリオットの波動論(2006年04月01日)
今日はテクニカルのお勉強ですね。しかし少々お疲れ気味のかたる君です。今日は手抜きをさせて頂き、僕が書くより上手くエリオットの波動原理を解説してあるサイトを見てください。
藤原さんのサイトへ…
基本的な波動だけ簡単に解説します。エリオットに言わせると上昇3波(衝撃波-修正波)と下降2波により一つの波動が構成され、この波動が何度も繰り返し登場し、マイナー波(89-55)、インターミーディエット波(21-13)、プライマリー波(5-3)、サイクル波(1-1)で構成されていると言うものです。
基本形は、下の図の1-3-5の衝撃波に対し2-4の修正波で上昇波が形成され、a
とcの下降波で波動が修正され、一つの波動パターンが完成されます。しかし、実際の波動にあわせ解釈するのは、なかなか大変で延長がかなりあるのです。
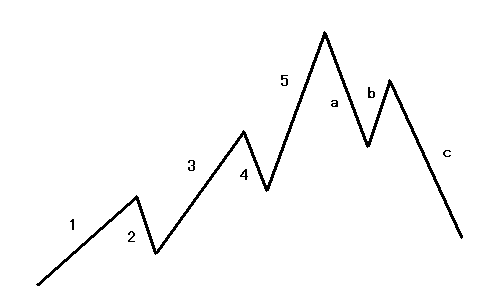
この解釈にフィボナッチ係数を加えて考えるようになったのですが…このフィボナッチ係数の意味は、インターネット上の何処かに載っていると思いますが…。よく例に挙げられるのがウサギのつがいの話しですね。簡単に言えば不思議な数字と言うところかな?
エジプトのピラミッドの角度だとか…アンモナイトの螺旋の比率とか…人間が心地よく思える不思議な数字なのでしょう。故に株価波動も何故かこの数字近辺が目標株価とされ、一つの目安にされています。株屋は面白いね。こんな事にも心の支えを求めるのです。
下のチャートはソフトバンクのもの…このように書くと、なるほどエリオットの波動論もまんざら…と思えないですか?
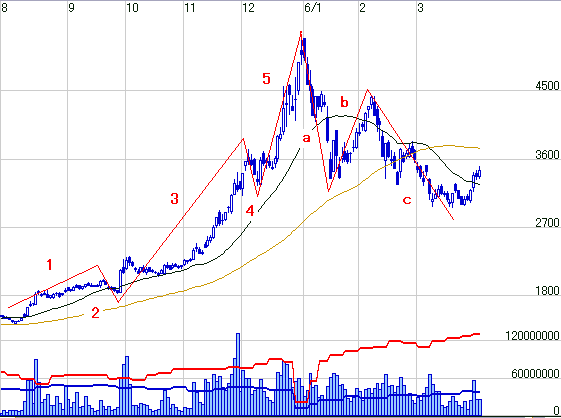
本間宗久もそうですが、エリオットも1934年と言われますから、古いですね。チャートは奥が深いし、一所懸命に勉強してもなかなか成果に結び付かないのです。これが、かたるの結論かな? 僕もかなり色んな本を読んで自分なりに勉強しましたからね。一応、フィボナッチ係数なども参考にはしますが…その程度なのです。まぁ、初めてエリオットの名前を知った人も居るでしょう。本間宗久もそうでしょうね。相場は日本の歴史の方がずっと古いですね。