« 流動性の罠の先行組 | 最新の記事 | 日本の方向性 »
規制の虜(2012年07月22日)
WSJの報道に「白川総裁は先週、円高は景気に悪影響を与えるとする従来のスタンスから離れ、堅調な内需の背後にある5つの要因の1つとして円高メリットを挙げた。日本経済は1-3月期、内需主導で4.7%の成長率を記録している。」との報道がありました。おそらく震災の影響で減った小売りが回復しているにすぎないと思いますが、「経済産業省のデータによれば5月の小売売上高は前年同月比3.6%増となり、6カ月連続で増加した。」のだそうです。ざっと調べてみたのですが、平成21年分からしか見当たらず長いデータを探すのを断念しました。これでは長期のトレンドが分からずに一概にこの報道が正しいとは言い難いのです。ただこの報道の数字は事実ですね。参考資料の中で平成17年度を100としたデータも現在は100を超えていますから、縮小する小売が止まっており横ばい状態とも言えるのでしょう。
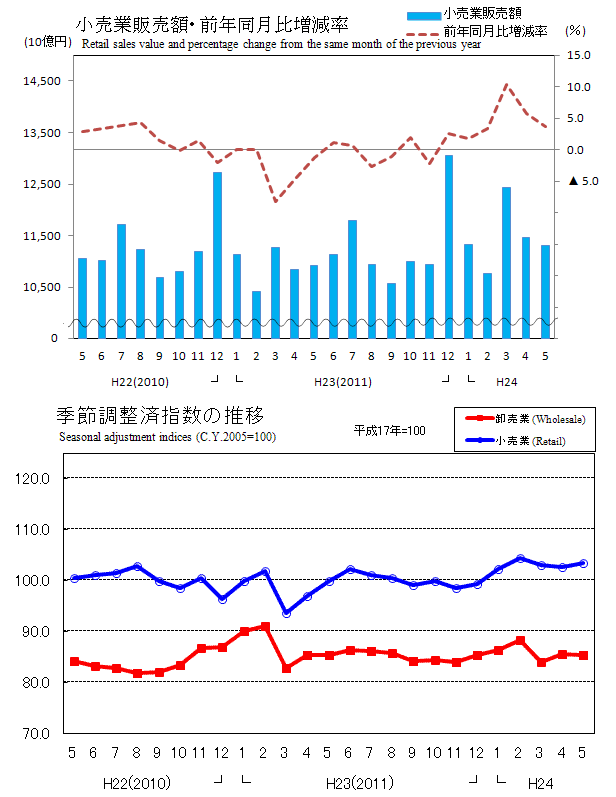
最近、考えているのが日本も捨てたものじゃない…と言う見方ですね。
確かにデフレ下で少子高齢化が続き、生産人口が減るので全体のGDPを効率化で増やすのは大変です。だから技術革新で付加価値を生み出す変換が求められます。例えば大企業に導入され効率化推進になっているアイパッドなどは、顧客データを手元で管理できセールスマンを始め効率的に仕事を出来る武器になっていますね。クラウドの世界です。まだ一般化されていませんがまだまだ伸び続けるのでしょう。車の世界ではカーナビがスマフォに置き換わり、情報端末の価値が無限に広がる一例なのでしょう。農業の生産管理などにも使えそうなアイテムです。やはりゲームだけでなく無限の広がりを持つ携帯コンテンツサービスは日本の新しい働き頭になるでしょう。チマチマした国内ではなく是非、早めにグローバル展開を考え活躍してほしいものです。
何度か取り上げている沢井製薬とオリエンタルランドの活躍は、デフレの縮小均衡が終わりつつある現象の一つではないかと考えています。ただ株価の値動きが地味で、カタル向きではないのですが…故に成長は分かっていても投資尺度に合わないとも考えていますね。おそらく百貨店株も長いデフレ状態から間もなく脱出する可能性を秘めている業界でしょう。何故なら、一つは団塊の世代が退職し、古い体質が変化するからですね。この意味は二つの点で賃金の高い従業員が続々と退職を迎える事。更に立地条件を生かした情報の発信地としての発展が可能だからですね。ブランドもまだ生きています。きっと働き甲斐のある職場に変化するでしょう。企画力次第で甦る百貨店業界となるでしょう。まだ芽は感じられませんが育つ土壌が存在します。
農業関連でなかなか浮上する銘柄が出てきませんね。何かある筈です。丸紅は世界有数の穀物商社でもありますが、この円高を上手く利用できるのかどうか…。ADM(Archer Daniels Midland Company)やカーギルには遠く及びませんが、きっと何か出て来るはずですね。今までは輸出がメインとの考え方で銘柄を見てきましたが、視点を変えないとなりません。きっと何か光る銘柄がある筈ですね。その意味でワタミなどは注目される銘柄の一つです。居酒屋なのですがその為に農業にも進出しており、更に介護と言う分野も手掛けています。ここ数年は1600円前後のボックスですが、最高値の5300円台を奪回できるかもしれません。注目して置いて下さい。残念ながら、銘柄探しをする時間が余りとれません。しかし、まだ銀行株がこの水準ですから慌てる事もありません。
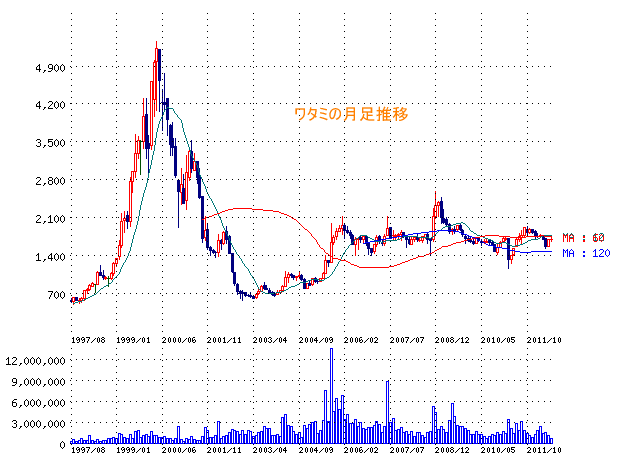
これだけの国債の高騰なので「りそな」は管理銘柄からそろそろ脱出できないのでしょうか?この銘柄を考えると1989年に起こったバブルの清算と言うのは大変だと言う事を認識できますね。今、世間を騒がしているスペインの銀行や米国の金融界も相当に内部は痛んでいる筈ですね。だから基本的に日本化現象が進み経済が停滞しているのですね。しかし間もなく23年の経過ですからね。中央政権下の日本経済が地方に分散移行し、地方政府の努力で新しいライフスタイルが定着するには、あと10年以上かかるのでしょうね。先ずは予算の執行権利を地方に移管すべきですね。その為に今の震災の復興予算は、良い実験です。中央集権で生きる、抵抗する官僚組織との戦いは、財務省主導の野田政権が崩壊し変化するのでしょうか?
見えそうで、なかなか見えない新しい世界、しかし沢井やオリエンタルランドは明らかに新しい世界を象徴している銘柄ですね。おそらく地味な介護も日本を代表する産業に育ち、このノウハウが蓄積され、「おもてなしの心」を売りにするグローバルビジネスに羽ばたく企業が出て来るのでしょう。何となく、分かってもらえますかね? 最近カタルが視点を変えて努力しているイメージが…。
これまでは世界競争に勝つ為に「追い付け、追い越せ」で、日本中の資源(人材などを含め)を東京に集め、中央政権が全てを決めてきましたが、先進国入りして明らかに迷走を始めた司令塔は猛省すべきですね。プラザ合意から先物導入で日本独自のよき文化である終身雇用と年功序列を代表とするシステムが崩壊しました。東電の迷走はある意味で日本の象徴だった官民一体が崩れた事例でしょう。
「規制の虜」は、まさに中央政権を支えてきた日本の恥部ですよ。狡猾に利益を狙ったシステムが東電の事例で明らかにされました。コンプガチャ問題も同じ土壌にあります。メディアは表面上の現象を追うのではなく、背後に隠された真実を伝え、社会を変革せねばなりません。単に大津の自殺問題で教育委員会を叩いても進歩はありませんね。文部省の指導マニュアルが教師の権限を奪い、いじめを生んでいる土壌なのかもしれません。同じ土壌ですね。なにも「規制の虜」は東電や日本の産業界だけでなく、一番大切な教育の場にもあるのでしょう。だからどんどん日本は負け続けるのです。システムに胡坐をかくダニのような輩を根底から排除するのが、中央政権から地方政治への展開かも知れません。
もう少しのイメージなのです。既に株価面では新しい成果の躍動が始まっているのでしょう。