« 視点を変えて… | 最新の記事 | 流動性の罠の先行組 »
方向性の模索(2012年07月15日)
日本の村社会はギスギスしておりユトリがなくなっているように感じます。僅かな「しのぎ」を探し、その僅かな「しのぎ」を得るために醜い生存競争が展開されている様なイメージです。こんなことを考えるのは、落ちこぼれの生活になった為でしょうか?
先ほどNHKの海外ニュースを聴いていたら、オランド大統領が自らプジョーの工場閉鎖を批判していると言います。世界の自動車業界は過酷な生存競争を繰り広げており、残念ながらフランス企業はユーロ安にも拘わらず負け組ですね。世界ではVWと現代自工かな?なんとか日本車はHVなどで善戦していますが…。基本的に効率的市場仮説と言う証券の世界の考え方では、生産性の高い産業へ資金が流れるようになっています。強い企業は、より強く、弱い企業は倒産するのですね。プジョーもパナソニックもソニーも負け組なのですね。故に資金が逃避し株価が下がるのですね。新興国の活躍で輸出企業のハードルが高くなり社会維持コストの高い日本での製造業は育ちません。電力料金から従業員の社会保障まで全ての面で製造環境は新興国と比べ割高になっています。基本的に技術蓄積の低い産業は、グローバル化の進展で労働コストの安い新興国に雇用を奪われました。ただ内需のサービス業や介護、医療の内需産業の株価だけは比較的に高いのです。一方、輸出産業の株価は価格競争に敗れ安くなっています。
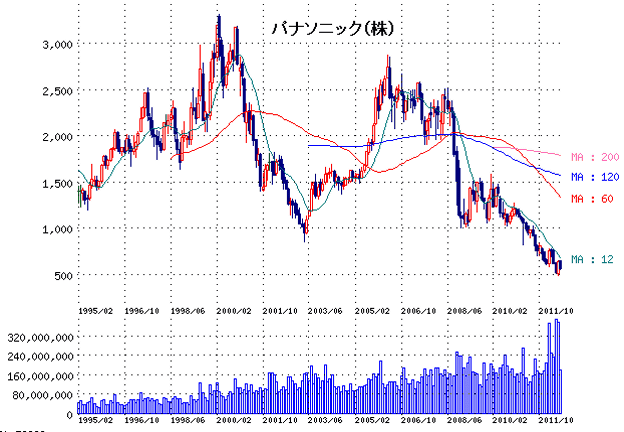
どうも、ここ点の認識が、僕ら日本人には欠けているように感じます。いや私に欠けていたのかな? 既に貿易統計の世界では原発の影響も大きいですが、赤字が定着しつつあります。幸い過去の蓄積である所得収支でプラスなので全体の経常収支では辛うじてプラスを維持しています。早めに空洞化を経験した強みでしょうか? 多くの競争力のある輸出産業は円高の為に現地生産を余儀なくされ、現地生産で得た利益を、配当などの形で国内還元しています。
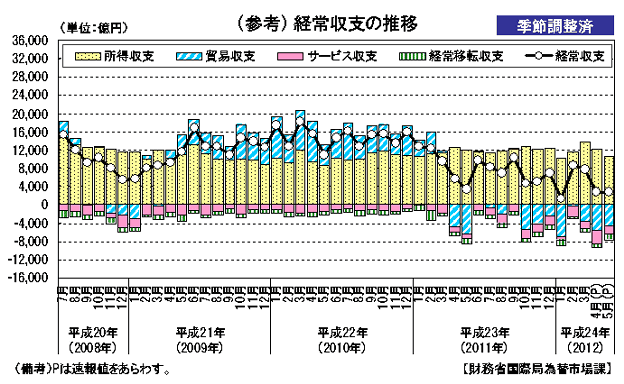
介護や医療の分野は基本的に内需産業ですね。団塊の世代が続々とリタイヤして行く中で、日本は世界に先行し金融バブルを経験し克服しました。そうして実社会では高齢化社会に突入します。多くの日本の官僚は北欧型の社会を理想としているようです。助け合う社会構造ですね。一方、小さな政府に代表される市場原理主義の社会は格差が拡大し否定されつつあるようです。その意味で、この秋に行われる米国の大統領選は興味が増すところです。オバマ大統領は医療保険に代表されるようにどちらかと言えば助け合い型の政策です。一方、共和党のロムニーは基本的に市場原理主義の競争にこそ、進歩があると言う考え方ですね。どちらが正しいかとの問題ではなく日本がどの選択をするかにより選ぶ株式も変わります。
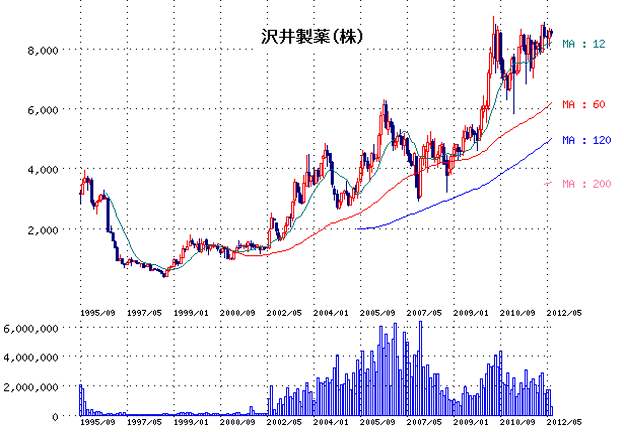
しかし…沢井製薬はある意味で高齢化社会において活躍する会社ですが、基本的に株価の動きが地味なのですね。少し方向性が気になりますがニチイ学館は同じ系統の銘柄です。シップヘルケア3360、トーカイ9792、メッセージ2400、ツクイ2398などは同じ介護グループですが売り上げは順調に伸びている名目の世界(インフレ型社会)に位置している会社ですね。自分が働く環境を考えてみれば毎年給料が上がる会社は良い会社ですね。基本的に介護の世界は売り上げが伸びており労働環境は過酷ですが公務員型の安定した世界です。斜陽産業を選べば、売り上げは減り労働環境はドンドン悪化します。当然、サービス残業は増え過酷な労働環境になりますね。
美味しいトマトに最近は巡り合っていませんが、食の文化も二極化するのでしょう。だから農業の世界も面白そうですね。工夫により作物は美味しく育ち、付加価値が生まれます。人間と言うのは欲求の動物で手に入らないと思えば、何とか手に入れたいと考えます。新潟には石本酒造があり、むかしは幻の酒と持て囃された「越乃寒梅」がありました。しかし石高を増やしたために、最近は幻ではなく普通に手に入るようになりましたね。
まぁ、取りとめのない内容になっていますが、内需振興が介護・医療だけでなく日本の株式を考えるうえでキーワードになりそうなので、もう少し、この考えを整理して調べる必要を感じています。デフレ環境なので株の世界は駄目だと考えていましたが、自分の考え方が陳腐化していたのかもしれませんね。沢井の動きはそんな叱咤に見えるのです。