« 興そう、ジャスミン革命を…! | 最新の記事 | ピンチはチャンス(歴史観) »
ルネッサンス(2011年03月21日)
まだ自分でトレーディングをするようになり、データの蓄積が十分でないので検証はできませんが、実はある条件のもとで、昨年の11月頃から様々なスクリーニングをしています。その一つのグラフは今回の値下がりの前に警告信号を出していました。下のグラフをご覧ください。
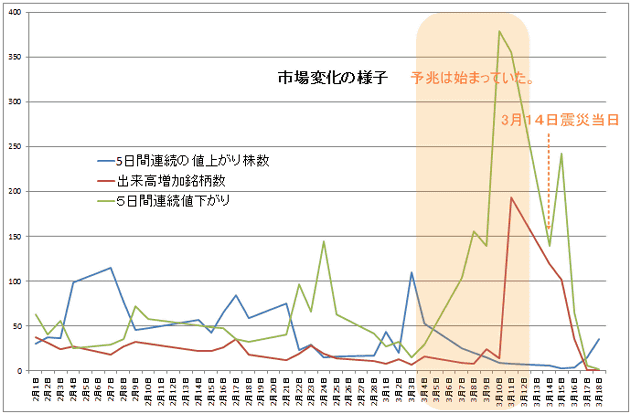
グラフは単に陽線とか陰線だけの条件を入れているものではありませんが、5日間連続の陽線銘柄や陰線銘柄を主体にし、ある条件下で出来高が増えている銘柄数の数字をみると奇妙なことに…震災の前から既に株価は下がり始めており、急激に悪化しているタイミングで、今回の震災がその下落基調の相場を、更に振幅を大きくさせ、加速させた事が分かります。しかし震災直後は既に株価面では明確に表れていませんが、回復に入っている兆候も見られますね。
株価は人間心理の現れです。
株式教室を読んでいただければ分かりますが、条件が整っても選択した銘柄が必ず上がるとは限りません。時間的な経過で更に好条件が形成されるかどうかが重要で、途中で新たな参加者が増えるかどうかですね。現在は残念ながら市場参加者は少なく、外人投資家が主体になっており、更に相場好きの一部の参加者に留まっていますね。日本は残念ながら、米国のような市場経済とは違い中途半端な展開です。中国と欧米の中間のようなイメージですね。長年、日本は計画経済の下で成長してきましたが、その成長が日米関係の転換点を迎え、新しいステップに入れずに挫折しています。プラザ合意からの26年は基本的に混迷していますね。ずっと新しい体制を模索している状態です。
戦後からの時代は奇跡の復興と言われました。明治維新もそうですね。鎖国制度で遅れた技術進歩を富国強兵により加速させ、日清戦争、日露戦争の勝利で時代性の方向感を失い大戦へ、戦後は復興と言う錦の旗印を掲げ追い越せ追いつけで、国民の目標感が一体となり成長し追い付いたら再び挫折です。加工貿易と言う成長モデルからの転換に失敗し26年です。今回の震災が切っ掛けになり、再び輝かしい希望ある社会に向かえばいいのですが…残念ながら、まだ見えませんね。
スーパー成長サイクル論を展開するカタル君は未来都市建設を提言しています。
循環型の未来技術を使った最先端の社会です。しかもお金もかかりません。復興国債10兆円で原状復帰する計画経済は過去のものです。三宅島の復興費用がどれくらいかかったか、わかりますか? 島民の人口は噴火前に3900人だったそうです。その後2005年には2439名に減っています。明確な数字は分かりませんが、インターネットで探すと2001年の東京都予算の原案に12年度の補正予算と合わせて508億円との記載があります。13年度の財務省の資料では災害復興費の総額が5727億円の予算額に対し3590億円が支出済みになっていましたね。その後も予算支出は続いており累積ではかなりのムダ金になっています。思い出しますが、当時、僕の友達が関連予算を組んでいました。その時、あまりにも馬鹿らしい金額だな。余程、被災者に一人200万なく、1世帯当たり2000万ずつ渡し、島ごと買ってカジノ島にすればいい…と提案したのを覚えています。そうすれば税収も上がり、島ですからギャンブルも自由です。島民は雇用を守られ三宅島は世界的な観光島になり経済も豊かになります。
東北の被災者の人には申し訳ないが現況復帰ではなく、僕は新しい予算の使い方を模索するべきだと思っています。仮に漁港として存続を図るなら、税金を軽減すれば企業は積極的に水産加工業の会社を次々に興すでしょうね。世界中から集めた魚の加工工場地になります。あの海域は養殖にも向いているようですし…様々な復興が考えられます。5年間の期間限定の処置で低利の融資制度を企業が利用するようにし、その地域から上がる利益の税金を免除すれば新しい産業も興るでしょう。
天災により折角のチャンスが到来しています。株式市場ではタイムマシン論を展開していますが、日銀は積極姿勢に変化しており相場は大きく育つ可能性を秘めています。仮設住宅の需要は高まりますが、故に一時的、日成ビルドなど株価推移も分からないではありませんが、夢がなさ過ぎますね。だから大きな相場にはなりません。果たして何が浮上してくるか明確に見えないから、やはり銘柄選択に迷いがありますね。結局、明日からの相場は、様々なシナリオを組み込んだ戦略で臨むことになりそうです。党派を超えた展開にならないかな?
復興か…良い響きだな。
ルネサンス〈ルネッサンス〉 Renaissance という語は「再生」(re- 再び + naissance 誕生)を意味するフランス語で、19世紀のフランスの歴史家ミシュレが『フランス史』第7巻(1855年)に‘Renaissance’という標題を付け初めて学問的に使用した。と解説されていました。