« ウォール・ストリート | 最新の記事 | 現状分析 »
ROE(2011年02月20日)
今日は昨日の続きを少し考えてみます。スクリーニングとは非常に便利なものですが、検索のトラッキングエラーを知るために様々な工夫が必要です。例えば昨日はROEの改善度に注目しましたが、今の市場は外人投資家が主体です。彼らは大きな会社しか追跡していませんから時価総額基準を設けねばなりません。しかしカタルは作為的に昨日のリストを検索したのですね。本来ならROEが今期5%以上の改善を見せる時価総額が3000億円以上の会社は28社しか存在しません。
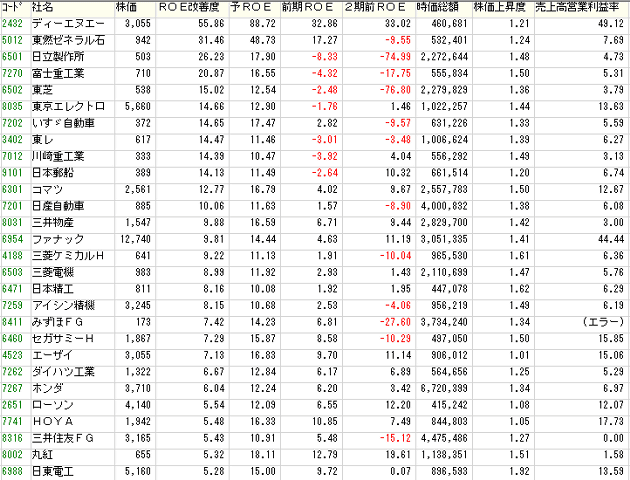
時価総額基準を外すと216社がリストアップされます。ただ時価総額基準を外したので前期ROEが黒字の基準を新たに設けると157社になりますね。このリストをみると…我ながら良い銘柄を選んでいると思う次第です。このリストの上位銘柄にはカタル銘柄のDENA(2)、タカラレーベン(5)、鬼怒川ゴム(13)と並んでいます。ベンチャリのカーブスを買収したコシダカは4位に登場しています。それで昨日の冒頭コメントになりました。
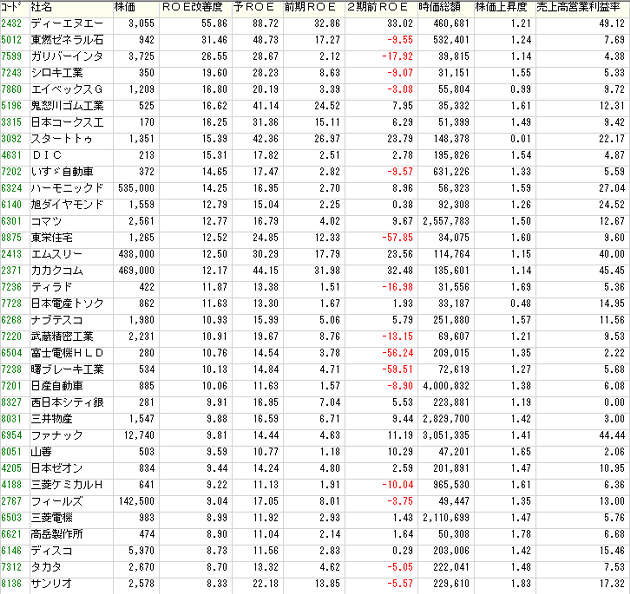
気を付けなくてはならないのは、あまりにハイリスク銘柄を狙うと危険なケースがあります。必ず危ないと言う訳ではありませんが、回復途上の会社は危険が付きまといますね。ベンチャリで懲りたわけですね。ベンチャリの失敗は利益余剰金の存在です。過去のリストラ清算の為に損失が膨らんでいたことです。今期のリストにも余剰金がマイナスの会社には株価が急上昇したフルキャストなどが並んでいます。危険を避ける為に利益余剰金のマイナスの会社を除外すると215社から157社に減りますが、リスクはかなり避けられますね。
株価の上昇度を見る基準も難しいのです。
市場は昨年の11月ごろから改善しましたが、8月には既に、いすゞなどは先駆した外人投資家により買い上げられています。出遅れ銘柄を探そうと11月末辺りを基準にすると既に相場に織り込まれていますが、前から上がっている銘柄を買う羽目になりますね。
僕らは失敗を教訓にして賢くならねばなりません。カタルは赤字から黒字転換への変化率の大きな銘柄を狙う投資を採用し、ハイリスクの変化率を狙いましたが、ベンチャリやインデックスで懲りましたね。この失敗は金融行政にも影響されたようです。昔なら銀行支援を受けられ改善する筈だったのですが、金融庁の指導によるマニュアル営業の影響から、立ち直るべき会社も見放されました。武富士などもその一例です。こちらは過剰な規制法令が影響し、意図的な計画倒産のようなものでしょう。
数々の失敗を経験し少しは賢くなりましたね。株価上昇率の観点から出遅れているガリバーやエイベックスは今後も注目されますが、エイベックスは利益の継続性に疑問があります。この点は決算発表で株価が急騰しているUBICにも言えますね。利益の継続性がPERを押し上げます。同時に少し売上高営業利益率が低いかな? 日本は資源のない国なので売上高営業利益率も問題化されますね。検索基準を変更すると、同じ発想の中でも異なる銘柄がリストアップされます。やはり検証していくとDENAの存在感は光りますね。このリストではカタルの一押しの007ことユビキタスは登場していません。ROEは18.8%、改善度は8.5%なので登場しても良いのでしょうが残念ながら小さな会社で連結会計してないからリストから漏れたのでしょう。今期に大幅なROE改善度を示す筈なのです。売上高営業利益率は42%ですね。基本的にインフレにも強い体質ですね。何しろ原材料費は人件費だけですからね。
経済情勢を考え検索の方法を変え、銘柄の追跡を行い、変化日を目途にトライする実験をスタートさせているわけです。問題は主眼を株価のテクニカルに置くか…業績推移に置くかで、ずいぶん投資方法も変化しますね。何度も述べますが今のカタルの課題はこの点にあります。短期のテクニカル分析を主眼に投資を進めるか…、それとも業績変化に主眼を持っていくのか? 株価は業績に影響されますから同じことですが、待たされるのを嫌っています。短期投資繰り返せば投資効率は上がり、利益が利益を生み天文学的な利益を得られると思って実験を続けていますが、時間的な余裕が限られてきました。僕に残された時間はあと3か月余りでしょう。果たして、わずかな期間に実験を適度の水準まで実践体制に引き上げられるかが今の課題です。
少し専門的でしょうか?
株価の世界はROEが基準なのです。投下資本に対する利益を競っているわけです。市場原理と言うのは投下資本を何処に投資するかです。GDPの成長率争いもそうですね。国家の力と言うのは何処に政策の主眼を置くかです。東大法学部出身の政策担当者はこんなことは分かっているでしょう。自分達が資金配分するのが正しい道と信じているのでしょう。故に市場原理を無視した規制や法律を設けるのでしょうね。市場は本来、高い効率経営する企業に資金を集め、その恩恵により国家が成長しようと言うのが市場主義の考え方です。その為に流動性は必要で冒険も必要です。
市場原理主義は非効率を排除するフィルター機能ですね。当然、弱者は敗退します。社会保障は弱者保護です。基本的に相反する性格を帯びていますが、頑張る人が更に強くなれればGDPも上がり弱者も救済できます。長いデフレは頑張る人を排除し年金生活者などの弱者を支援してきました。しかし…いずれ社会負担が増し沈没しますね。こんな考え方をするとROEと言う基準は面白いでしょう。世の中の仕組みの原点は繋がっていますね。漢字の生い立ちもそれぞれ意味があります。基本的な考え方の原点はみんな一緒です。手段が問われているだけなのでしょう。