新春を迎え…1(2011年01月02日)
新年を迎え、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年は人生で二回目の転換を試みました。1989年にサラリーマン生活10年に見切りをつけ歩合セールスで21年を過ごし、昨年末に新しい生活をスタートさせました。普通の人間からみれば馬鹿な人生を送っていると思うかもしれませんね。でも僕は自分なりに一所懸命に生きているつもりです。
さて私のことより、昨年の相場はリーマンショックの金融危機から立ち上がりましたが、一時、二番底懸念でもたつきました。しかしQE2の政策を受け米国は資産効果による心理的な効果から2010年12月のS&P500種の月間上昇率は1991年以来、最大の上昇率だったと言います。失業保険の申請も2年半ぶりの低水準で消費も盛り上がっているという米国発の報道があります。
同時に中国では世界で最初に金融危機を克服したのですが、その後の展開は堅調ですが、ここに来て、もたつき始めたように感じます。株価の動きが正しいのかどうかわかりませんが、上海総合株価指数は明らかに横ばい水準になっています。年末にかけ金利を引き上げていますね。金利を引き上げるということは、経済活動を抑える動きになっているわけで、特に政権は物価水準に強い関心を示しているようです。この原因は元の売り介入で輸出活動を助ける政策が限界を迎えたのでしょう。世界で最も堅調な国はドイツです。欧州危機の恩恵をフルに受け、輸出により経済を立て直しました。日本は円の独自通貨ですから円高に見舞われ苦戦しています。
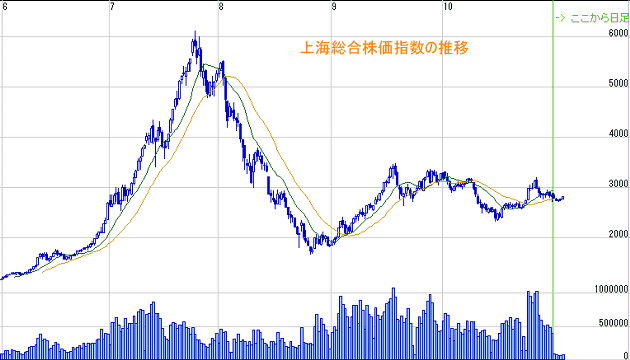
最近、あまり話題にされなくなりましたが交易条件指数という数字が落ち、加工貿易立国、日本の競争力の欠如があります。新興国に輸出産業が移転し日本国内の競争力が低迷したのでしょう。しかしここに来て中国のインフレが問題化され、金利を上げる現象を見ると、ようやく空洞化の流れが減速し始めたようですね。一方では力を付けた中国の横暴な行為が目立つようにも感じます。当然、空母も建設する中国を、米国は面白く思っているはずはありませんね。もともとプラザ合意も日本の出る杭を打つ行為で、その後の日本の低迷は米国の政策とも考えられます。世界の金融界はユダヤ資本に牛耳られています。このユダヤの母国ともいうべきイスラエル沖で、昨年、イスラエルのエネルギー消費量の50年とも70年ともいわれる大規模なガス田の発見がありました。
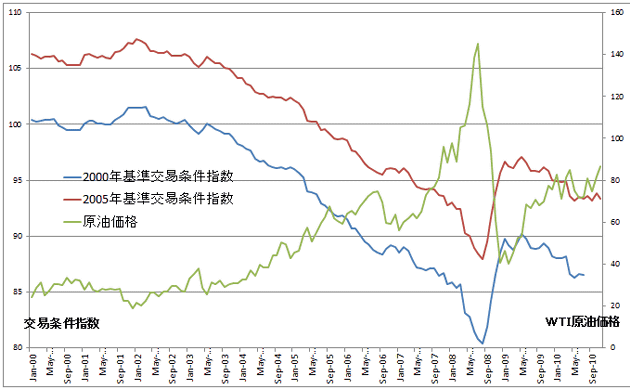
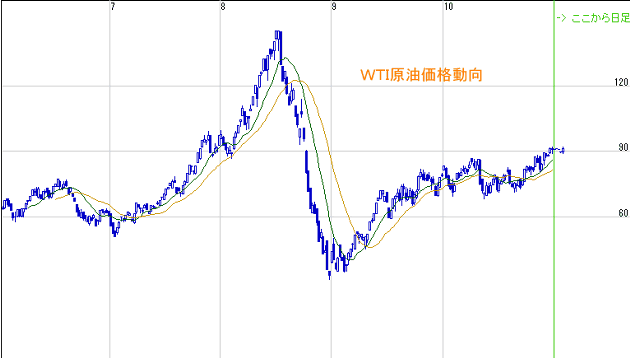
何故、米国はQE2の政策を実施したのでしょう?
表向きは二番底回避のための金融政策の実施ですが…カタル君はそう見えないのですね。もともと一人あたりのGDPの差がある国が、一気に世界最高峰の地位まで上り詰めることは無理なことです。そんなに甘いものじゃないでしょう。たしかに中国はすごいですね。その背景には共産党一党支配の優位性があります。地方政府の財源は地価です。土地の利用権を売却することで収益を上げて地方が競って産業を招聘しています。打ち出の小槌にも限界はあるでしょう。地価のバブル現象と言われていますが、この地価を支える原動力は国民の意欲です。この力が続けば財政を支えている地価を維持もできるでしょうが…どうでしょう。故に中国の政権担当者は日本がかつて成功した所得倍増論を採用したのでしょう。
つまり物価を上げると一番困るのは、一人あたりのGDP水準が低い国々なのです。おそらく米国はこれを狙っているのでしょう。イスラエルのガス田の発見もこの説を裏付けますね。故にQE2政策が浸透する今年は一次産品の価格上昇がメイン・テーマでしょう。年末に来て、それを感じ取るような銘柄が上がっていますね。市場では電子書籍やスマートフォン関連が賑わうような展開が指摘されていますが、カタル君の読みは米国と中国の戦いが焦点だと思うのです。
明日は国内要因を考えてみます。