歴史の展望1(2005年09月23日)
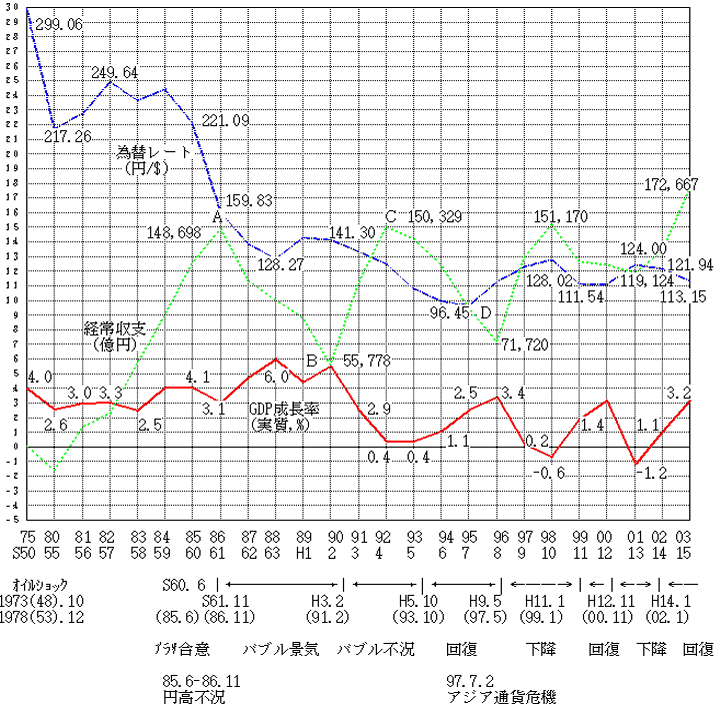
昨日、9月22日は歴史的な日だったのです。20年前の1985年にプラザ合意が発表されました。この重要な日を解説しながら、江戸時代から明治初期の動乱の構造に似ているので、その対比した年表を作り、相場を考えてみようと思ったのですが、その途中で面白い事に気付いたので、今日はその分析をしてみようかと考えています。その前に、何故プラザ合意なのか? その報道されてない意味とは何か考えて見たいと思います。
一般的にプラザ合意は、アメリカの貿易赤字削減のための処置と理解されていますが…果たしてそうなのでしょうか?
1ドル240円前後だった相場がみるみる騰がり170円台になり、僅か2年後に120円台まで急騰する過程で澄田日銀総裁は重大な過ちを犯すのです。金利平価説を採用するあまり、日本の公定歩合を長らく低い状態に維持し、内需拡大を図ろうとするのです。…が、実需の需要ではなく、借り入れによる仮需の需要だった偽物の繁栄だったのですね。お金がお金を生む、資産インフレを澄田日銀総裁は見逃し、大蔵官僚も狂っていたのです。銀行は貸し出し競争に奔走するのです。このツケの払いが、その後の失政も重なり2003年まで掛かったのです。
しかし、その後の国際社会の流れを見ると、プラザ合意の意味は別の所にあることが窺われます。わが国は通貨の市場経済を受け入れて、その後、BIS規制により銀行の土地本位制による信用創造を断ち切られます。更にIASにより、今度は会計制度の縛りを受け矢継ぎ早に、グローバル基準体制に移行していくのです。いよいよ時価総額主義と言うか市場経済の目玉と言うかM&Aの嵐を前に、今の日本はあるのでしょう。つまり、プラザ合意の真の狙いは官僚社会主義から市場経済への転換を示しているのでしょうね。その第一弾として通貨体制の市場化を狙ったのでしょう。ベルリンの壁崩壊、天安門事件と同じ性質なのでしょう。
時を遡ること、およそ150年。1853年にペリー提督が浦賀に来て開国を迫ります。その後の江戸幕府は体制維持に向け努力しますが、世情には逆らえず崩壊します。それから15年後戊辰戦争が起こり、明治政府が樹立されますが、新制度が確立するのに時間を要します。内部分裂に決着が付くのが西南戦争だと仮定すると、1877年ですから、なんと、体制転換まで24年の時間を要しています。つまり同じ速度で推移するとすれば、1985年を基点にすると24年後は2009年と言う事になります。あと4年ですね。次の衆議院選挙のときになります。1853年の丁度20年後と言うと、1873年は徴兵制度が確立され、地租改定が実施され土地の私有制度が確立されますが、同時に政府部内では対立が深まります。征韓論を支持する西郷隆盛グループが欧米視察から帰ってきた岩倉具視などのグループと対立するのですね。この決着は西南の役に発展するのですが…
1870年に岩崎弥太郎は藩から汽船を借り受け、九十九商会を創り1875年に郵便汽船三菱会社と改名し、政府の保護で成長し西南の役により莫大な財産を築きます。有名な福沢諭吉の「学問のすすめ」が1872年です。百姓一揆の発生数を見ると、1869年の110を境に減り始め、1873年に56の第二のピークを付け沈静しますから、世情は1873年を境に落ち着きを取り戻したのでしょう。
2003年を転換点に2年の歳月が流れています。しかし大手銀行は未だに公的資金の返済を終えておらず政府の管理下にあります。長かった改革の時間。ネット族が市場経済を謳歌する出来高30億株時代は新しい幕開けなのでしょう。過去の概念が失われ新しい考え方の定着が進む現代。どのように時代を考え、どう取り組むか? 一度、ご自信で子供の教科書などで歴史を振り返って今の時代を考察されては如何でしょうか?
今日は長くなりましたので、1979年に起こった第二次オイルショックから、1980年への株式相場の回顧と現代の相場の推察は、後日に…