« 問われる金融システム | 最新の記事 | 問われる国際通貨体制 »
市場原理と規制(2008年11月08日)
これから重要になるのは市場原理(自由主義)と規制の考え方でしょう。
先週も触れましたが、新しく開発した製品がどのくらい市場で売れるか分かりません。だから試行錯誤を繰り返し、正解を求めるわけです。ところが社会主義は計画経済なので予算が優先され、間違った試行を繰り返すのですね。この間違った試行を繰り返すことを回避する考え方が資本主義です。常に正解を求める為に試行錯誤を繰り返します。これが市場主義なのです。
ただ今回の場合は詐欺に近い事件なのでしょう。値上がりを前提で住宅を買えない人まで巻き込んだのがサブプライム問題です。契約後、3年程度で金利が大きく上がる商品なのです。日本でもミニ版ですが同じような問題が表面化しつつあります。金利が上がる契約でローンが払えなくなる現象です。このリスクを切り離し販売したのがMBS(Mortgage Backed Security)と言う商品です。RMBSは住宅用の債券で、このような商品から組成されたCDSを元に算出される指数がABX指数です。まぁ、今日は用語解説ではないのでこの辺にして…
サブプライムのような行き過ぎた投機の咎めが今の動きなのでしょう。ドバイの発展を見ると異常ですからね。海岸に人工島を建設して理想のオアシスを作るのです。一度、行って見たいのですが…相場で失敗したかたる君は社会見学も出来ません。ロシアのグルジア侵攻も行き過ぎた富の片寄りがもたらした弊害なのでしょう。今の動きが良く現れているのがHFRX指数です。簡単に解説すればヘッジファンドの現状を示したグラフです。まさにこのような動きが世界中で起こっているのです。スクラップは荷動きすらなくなりました。動きが凍結しているのです。トヨタが大幅な減額修正を発表したのも、全て急激な金融システムの混乱から生じています。
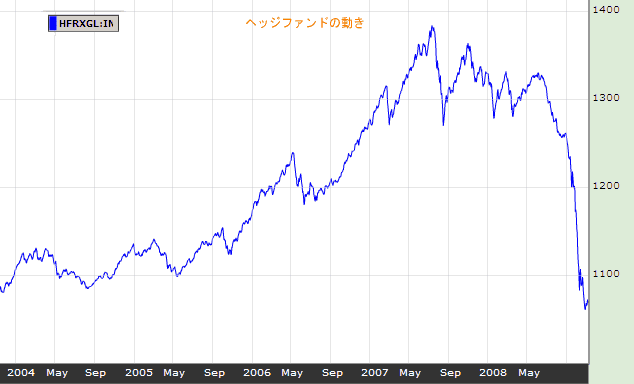
サブプライム問題自体は大きな問題ではないのでしょうが、小さな躓きが大きな問題に発展した印象です。ダムが決壊する引き金を引いたのがポールソンの決断です。今から思えば、リーマンの破綻は阻止すべきだったのでしょうね。日本で社会問題化しているSFCGの動きも、この流れの一環です。彼の読みは甘かったのでしょう。私も一時、「ネイサンの逆売り」を考えていました。ポールソンはすべてを知っている。だからリーマンを破綻させた。との読みですね。まだ結論は出ていませんが、今のところ、この読みは外れています。堤防の小さな穴がやがて決壊に繋がる。しかし仮に巨大な資本を維持する為にはこのような仕掛けが必要なのかどうか…
いつも私は思うのです。
金融ステムを操っている巨大な組織が背後に隠れていると…思うのですね。つまり今回の金融危機も演出されていると考えているのです。日本には戦略がありません。日本村だけの論理を翳し小さな覇権争いをしているように感じます。同じ仲間を追い落とすゲームがそんなに楽しいでしょうかね? くだらない。東洋電機がどんな選択をするのか分かりませんが明らかに目先の痛みより将来の夢を買うべきでしょう。日本電産の永守と言う人はたいしたものです。ハードディスクからモーターですか…この発想はパナソニックの三洋電機の買収と似ています。グローバル化を睨んだ戦略ですね。三菱UFJも世界戦略に乗れる可能性を秘めた会社です。日本にもグローバル化対応した会社が増えれば良いですね。