« 樅の木は残った | 最新の記事 | 市場原理の根幹を守るFRB »
益利回りの概念(2012年09月08日)
製造業に従事する人間の労働条件は新興国の生産性向上により、一見すると成功しているサムソンなどの韓国でも生活は苦しいらしいですね。青年ユニオンが話題にされる韓国も日本同様の現象が続いているようです。きっと文化の形態が似ているのでしょう。韓国も学歴や資格重視の国柄だそうです。OECDの統計によれば、韓国は日本同様に自殺者が多いとされます。人口10万人当たり韓国は31人が…日本は24人が自殺していると言います。米国の11人に比べると日本は2倍以上になっていますね。その米国もフードスタンプの受給者が急増していると言います。フードスタンプは嗜好品を除く食料品を買うために政府が補助する制度で、4人家族の月収が2500ドルを下回る家庭に対し、一人あたり月に100ドルを補助するのだそうです。2004年度は2200万人ほどだったのですが、最近の統計は4600万人に受給者が急増していると言います。6~7人に一人が受給者という事になります。この現象は格差拡大の弊害の象徴だとされていますね。
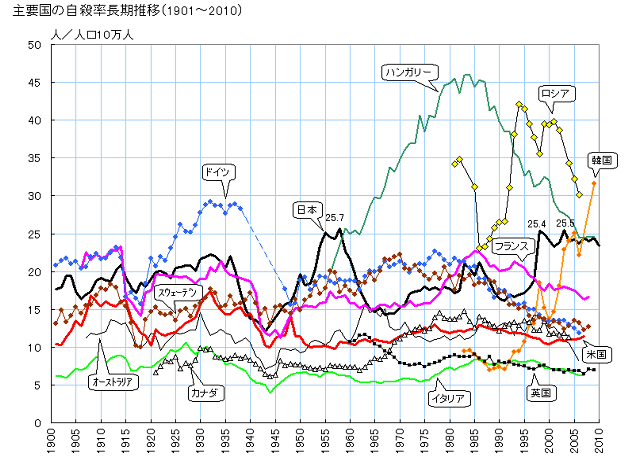
先ほどNHKの梅ちゃん先生を見ていました。新幹線の部品を製造することになり蒲田の下町工場が世界の最新技術を支えたシーンが報じられていました。丁度、カタル君が誕生した昭和30年代の日本の豊かな心を舞台にしたノスタルジーの世界ですね。あの映像は実際に工場の機械を動かし、ベテランの旋盤工の人が演技指導をしているのだそうですね。梅子のおじさんが月光仮面の主題歌を歌っていましたが…この映像がネット上で、今は見られるのです。驚きました。此方です。僕の小さな頃、必ず見ていたテレビの番組です。丁度、この頃は鉄人28号やエイトマンが、かたるのお気に入り番組でした。必ず、正義が悪をやっつける番組でしたね。ユビキタスの世界は、いつでもどこでも、必要な情報が簡単に手に入る時代ですね。
旧来型製造業受難の時代に変化は生まれます。イノベーションが新しい時代の転換を促進させます。産業革命は蒸気機関の発明により時代のスピードを速め、革新を社会に呼び込みましたね。鉄道株指数が誕生するほど…基礎社会資本整備が多くの人に進化を与えました。鉄道や道路、通信、電気などの開発が、豊かな産業を支える基本構造を作った昭和30年代は、明日への希望に満ち溢れていました。今はインターネットの発展がスマートフォンの誕生を生み、情報という価値が人々の生活様式を変えているように感じています。マックはこの情報媒体を上手く活用しているようです。マクドナルドの存在はある興味で深いものですね。飽和的に思われる社会構造の中で、売り上げは伸びないのに利益を上げる工夫をしています。分かりやすい事例は売上高営業利益率が大きく伸び始めています。この比率はそれまでは1%程度で2006年も2%程度だったのですが、4%、6%と伸び、最近は8%台になっています。規模の拡大から利益重視の姿勢は、今の日本社会にとって見習うべき重要な要素かもしれません。統廃合を進め、儲からない店舗を閉めて儲かる店だけを存続させ、実験を繰り返す姿は、なにか…頼もしい企業に見えますね。不思議なものです。
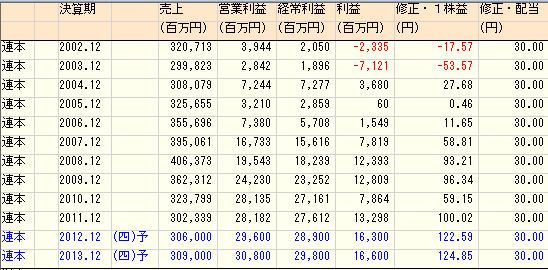
過剰生産設備とか需給ギャップとか言われる社会構造ですが…ここにも日本が変化するヒントがあるような気がしています。シャープの失敗が話題になっているようですが…いろんな考え方が存在するようです。方向性を模索し、選択と行動の結果、結論としてある現象が生まれます。その結論をどう受け入れるか?失敗したら、次にどのような改善策があるのか?また模索し試行錯誤し進化する。日本村社会構造を、よくカタルは批判的に見てきましたが良い面もたくさんありますね。その良い面は豊かな心なのでしょう。人間は一人では生きられないし、実際に一人になってみると良く分かりますね。会社に勤めている人は、昔は会社オンリーで…会社の為に一所懸命に頑張ってきたが、会社が苦しくなるとリストラされ、嘗ての上司や同僚などの人脈も、一時的なものだったと実感されているかもしれません。
日本株が低迷している現実を考えると、形のない物まねだけの資本主義社会の形態が良く分かりますね。野村証券の低迷は日本社会をよく物語っています。金太郎飴とは…日本人の教育制度の問題であり、日本型のキャッチアップ制度の体質を象徴していたのでしょう。その野村証券は1987年で5990円の大天井を打ちました。どのセールスも同じセールス文句で、強引なセールスが問題視された時期もありました。その野村証券はなんと8年も営業キャッシュフローの赤字を続けました。今年は黒字だったのですが、基本的にかつての栄光に支えられ食う事が出来たのですね。瀕死の重傷状態です。プラザ合意が1985年、日本の金融株の多くは1987年に天井を付けます。そうして全体の株式は、先物導入により嵩上げされた1989年に38915円の高値を付け、単純平均株価のピークは翌年の2月の913円です。今は1/4以下の200円ですね。
本日の日経新聞には中国の公共事業投資が12兆円規模となっていますが…日本の復興関連予算は19兆円ですね。東北3県の景気回復は力強いものでしょう。折角、お金を使うのですからスマートシティーの建設概念を取り入れて欲しいものですね。兎角、中央官庁の役人は原状復帰に拘ります。もともとの災害復興の概念がそうなのですね。嘗て、災害復興予算をカタルの友達が財務省で作成をしていましたが呆れる概念なのです。原状復帰にひどく拘っていましたね。元のあった場所に同じ道路を造るとか…この固定概念を打破しないと掘っては埋める無駄な公共事業と同じ発想ですね。
日本は、ようやく正しい問題点が指摘され始め、新しい発想が動き始めて来たところです。かたるは長年、下げ続ける市場を通じて様々な問題点を感じてきました。民主党立ち上げ当時、諫早やヤン場ダム建設が問題視されていましたが、過去の選択より現在の選択の視点をどう変えるかですね。今、カタルが一番感じていることは…益利回りの概念が働かずに、何故、効率的な資金配分に変化しないかという事です。今週号の日経ビジネスの41ページに武者さんも同様な切り口で語っています。構造的な金融機関の姿勢が問題で…この変化なくして豊かな社会形成はあり得ませんね。具体的には金融機関に眠る国債資金を動かす事です。停滞する社会構造を効率化社会に変化させる行動が必要になっています。誰もやらないから…自分がやるしか方策はないのでしょうか? 本当は金融教育の問題だと思うのです。経済の活性化は、お金を動かす事ですね。1%以下に眠る資金をROEの高い10%以上の企業に振り向ければいいのです。お金の回る速度が上がれば、自然に経済は自立回復します。マックの変貌はその事を物語っているのでしょう。金太郎飴の規模拡大から、儲けの時代なのでしょう。