野田総理は及第点か…?(2011年11月19日)
何故、みずほが再び100円の大台を割れるのでしょう。我が国を代表する会社が次々に株式市場で新安値を更新しています。一向に上向かない日本経済は根本的な政策運営が間違っているのでしょう。どうも日本国の信用問題を市場は織り込んでいるのではないでしょうか? そこで…この可能性を考える為に少し調べてみました。ここではトヨタの株価を用いましたがパナソニックを始めソニーなど…主だった企業が新安値を更新しています。
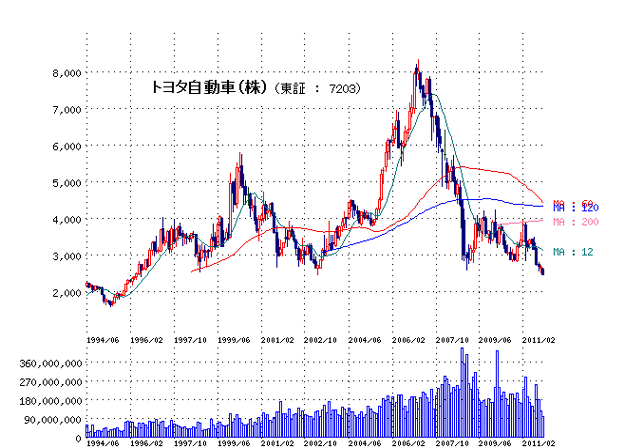
個人の金融資産は2011年6月末で1491兆円あります。(日銀の資産循環統計からの数字です。)日本全体の短期証券などを含む全体の債務残高は1151兆円と言われています。一方、国債の発行残高は901兆円(国庫短期証券、国債・財融債の合計)で、海外投資家が保有している金額は7.4%の67兆円です。つまりおよそ93%程度を国内で消化しているのです。故にギリシャやイタリアが騒がれるのに、日本がはるかに高いGDP比の債務残高状態であるのに低金利を維持しています。GDP比の債務残高の主だったグラフは財務省の作成したグラフより掲示しました。
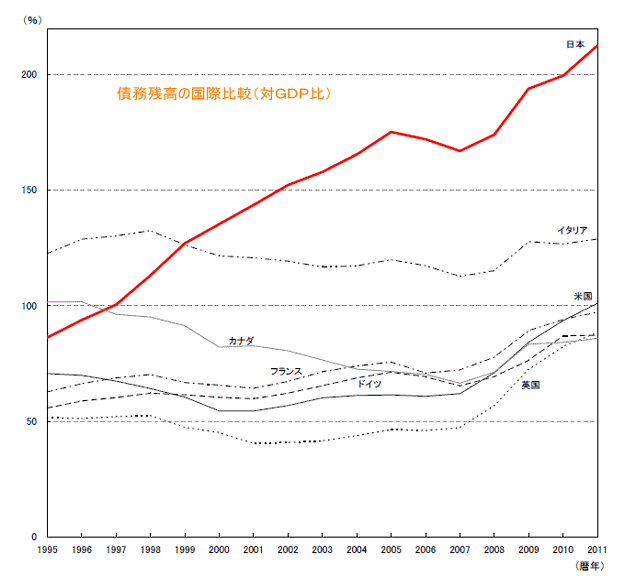
財政規律が緩んでおり、行く末、日本企業も国が沈むから買われないのではないか? 企業業績がどんな向上しても、国がダメなら株式の価値はなくなるのではないか? 一抹の不安を感じますね。逆説的に仕組み上、効率の悪い「過去の投資」(国債)に、お金を振り向ける政策を採用しているので、日本株の復活はROEの高い民間企業(効率の高い未来の投資)に流れないのではないでしょうか? 最近の僕の概念はこんなものです。日本で最も頭のいい財務官僚が、なかなか分かり切っている政策転換を実行しないのは、この辺りにポイントがあるのではないか?と考えているのです。
本来は、財務官僚の意図は間違っているのですね。財政規律が緩んでもROEの高い効率的な運用の場に資金を誘導すべきなのです。そうすれば日本国全体のGDPは上がりインフレが進みGDP比の債務比率も下がりますね。増え続ける社会保障費を上回る経済成長を実現させればいいのです。この成長投資がスマートシティーの建設ですね。日本にはごみの資源化を始め、ITS(高度道路交通システム)など幅広い沢山の未来技術が眠っていますが、総合的にプロデュースする人が居ないのですね。縦割り行政の弊害なのでしょうか?
2003年から小泉・竹中改革が認識され株価は上がり始めました。この動きは強引にROEの高い企業へ資金を移動させようと、ゾンビ企業を切り始めました。非効率な資金を
切り効率化投資に移したのです。郵政民営化は効率の悪い財政投融資資金の削減です。
強引な手法でしたが、ある意味で評価されます。しかし小泉側の支持者が少なく、改革はとん挫します。所謂、亀井静香などの既得権力者の集団ですね。年功序列、終身雇用、株式持ち合い、鎖国制度による内外価格差の維持等により、輸出依存度による加工貿易体制の維持で食べる米国庇護のもとの架空の経済成長の残像が捨てきれなかったのでしょう。
しかしこの幻想は、1985年のプラザ合意で明らかに政策の転換を要求されましたが、そのメッセージを見誤った大蔵官僚の失政が生んだ失敗が、バブル経済とその崩壊ですね。14年後に新しい出発を図り、成功し始めたところにライブドア事件の勃発です。これは、おそらく権力闘争ですね。そこに一部の国粋主義者の地検幹部が乗った話でしょう。この動きに金融危機が重なり、パラダイムショック(枠組みの転換)が起こっています。
日本がTPPに参加すると表明すると、すかさずにカナダやメキシコが参加表明し、中国がASEAN+3を主張していたのに、態度を軟化させこれまで否定していた+6を主張し始めたのも、アラブの春から欧州危機が背景にありますね。リカードの比較優位論(比較生産費説)は自由貿易を推進すれば、更に効率的な生産効果が得られると言うグローバル論からも支持されます。我が国のメディアの論調を見ていると、生産者側の論理に満ち溢れていますね。そりゃ、スポンサー契約の獲得の意味合いもあるので、あのような報道になるのでしょうが、受信料を徴収している国民放送のNHKは生産者の論理で報道を組み立てるのではなく、消費者、一般の国民の側に立って報道を組み立てる必要があります。
安くておいしいコメが自由化され、おいしい牛肉が安く食べられるなら消費者にとってラッキーですね。しかし食料の自給率が低下している現状は、安全保障上、許されるものではありません。自由化したうえで農業の保護政策は国際競争を支援する方向性でしなくてはなりません。時代遅れの三ちゃん農業を支援するものではありません。国論を二分する難しい舵取りが要求されますが、自民党的な政策運営ですが、野田政権はこれまでの所、及第点です。何故なら、南沙諸島問題からASEANを取り込んだ2兆円投資など自由貿易圏の主導権を握るものだからです。慌てている中国…の行動が、その成果を評価しています。この背景はおそらく米国のけん制がありますね。今後、消費税の問題から財政規律の方向性を見せれば、株価も上向くでしょう。