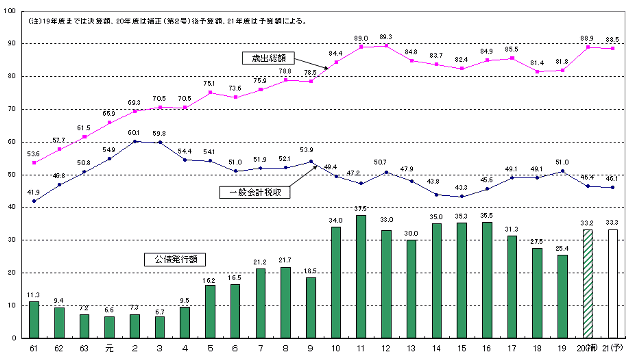« 2009年10月 | メイン | 2009年12月 »
2009年11月29日
ビスタからの原稿2
この歳になって歴史を勉強するとは思ってもみませんでした。日本史についで、今度は世界史です。何故か? 1989年のベルリンの壁崩壊から東西冷戦が崩れ、中国の鄧小平が「富める者から豊かになれ」と市場原理を導入したように、旧東側諸国が次々に市場経済化を果たし、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)が躍進します。前回のレポートでは1989年のベルリンの壁崩壊から2003年のみずほの増資までの14年の歳月が1853年のペリーの来航から1867年の大政奉還までの時間と奇妙にも一致し、しかも調べると現代社会の流れと良く似ている事に気付いたのです。それと同時に産業革命時のヨーロッパの時代にも似ているように感じています。

イギリスでは絶対君主制(封建国家)が、ピューリタン革命(1649年)・名誉革命(1689年=これらを総称して市民革命と呼ばれる)により崩れ、資本主義への近代国家の道を歩むのです。この時代のオリヴァー・クロムウェルは日本の松平定信のような厳格主義だったらしく、庶民の楽しみの演劇などを禁止したそうです。年代はだいぶ違いますが…、実はこのような下準備がイギリスにあり、産業革命がイギリスで発展したといわれているようです。フランスのこの時代は、まだルイ14世(ブルボン朝)の時代ですからね。このあと100年ほど後に、フランス革命(1789年)が起こります。強い組織だった故に、フランスは産業革命の波に遅れるのでしょう。まるで今の日本のようにも感じます。
18世紀の後半から産業革命は始まります。伝統的な農業社会が工業化されていくのが産業革命で、人々の生活様式や価値観が、技術革新により大きく変わるのです。最初は綿工業の発達から始まります。この頃、ノーフォーク農法と言う冬の家畜飼料としてカブの栽培方法が開発され、農家では囲い込みが行われ労働者が溢れる農業革命が同時に進行します。更にジャガイモの栽培(同じ耕作面積で小麦の4倍の人が養える)が盛んになると、溢れたアイルランドの人も工業化の人材を支えていきます。一番大きな事は7年戦争などで、イギリスが世界商業の覇権を握り、広大な植民地を形成し、自国と西アフリカ、カリブ海や北米南部を結ぶ三角貿易によって巨大な利益を得たことが産業革命の資金源を支えました。


イギリスの産業革命は、前半の軽工業化とスティーヴンソンが試作した蒸気機関車の鉄道整備などによる後半の重工業化へと変化しますが、1850年前後に産業革命は完成されたと云われています。ロンドン万国博覧会が1851年です。ハイドパークに作られたクリスタルパレスは、パクス=ブリタニカ(イギリスの平和)を象徴するものだったとか…。その後のフランス・パリ万博(1889年)のエッフェル塔のようなものなのでしょう。やはりイギリスに比べかなりフランスは改革が遅れているのですね。ふと…思ったのですが、この記事を書いている今、2010年に行われる上海万博の事が頭をよぎりました。万博は覇権国家(力の証と言う意味で…)の象徴なのでしょうか?
イギリスのトインビーと言う学者が「産業革命」命名したとか…
彼は産業革命により生じた都市のスラムの生活に見られる貧困や病気、犯罪などの社会問題を救うべくセツルメント運動に取り組みますが、志半ばで31歳の若さで死ぬのですね。「格差の時代」と言われ始める日本の現状も、当時のイギリスに似はじめているのかもしれません。インターネットを始めとする携帯電話などの通信革命は、あの当時の鉄道網整備に似ているように私は感じるのですね。
1705年 ニューコメン、火力機関の開発
1709年 ダービー、コークス製鉄法の開発
1733年 ケイ、飛び杼の発明
1764年 ハーグリーヴズ、ジェニー紡績機を発明
1769年 ワット、蒸気機関の改良に成功、アークライト、水力紡績機の特許獲得
1776年 アメリカ独立宣言の発表
1779年 クロンプトン、ミュール紡績機を発明
1783年 パリ条約
1784年 コート、パトル製鉄法を開発
1785年 アークライトの特許取り消し
1787年 カートライト力織機を発明
1789年 フランス革命の勃発
1796年 ジェンナー、種痘接種に成功
1804年 ナポレオンの皇帝就任
1807年 フルトン、汽船の発明
1814年 ウィーン会議、スティーブンソン、蒸気機関車の試運転に成功
1825年 蒸気機関車の鉄道開通(ストックトン・ダーリントン間)

18世紀のヨーロッパ各国では啓蒙思想が広まって新しい社会の息吹が聞こえていました。
自由と平等を掲げ独立したアメリカ合衆国は、他国に先駆け近代国家へ進みます。一方、プロイセンやロシアでも絶対君主制の枠を超えるものではありませんでしたが、啓蒙専制君主が誕生しました。

当時のフランスはブルボン朝による絶対君主制の時代でルイ16世の時代です。
贅の限りを尽くすマリー・アントワネットの話は有名ですね。そうしてフランス革命が起きます。1793年1月にルイ16世が、10月15日にアントワネットも死刑判決を受け翌日、ギロチン刑を執行されます。その後、フランスは1795年に二院制の議会と5人の総裁による総裁政府が共和政維持と社会秩序の回復を目指します。
この時代にナポレオンが誕生します。1796年に総裁政府の総裁ポール・バラスの愛人のジョゼフィーヌ・ド・ボアルネと結婚するのです。これによってイタリア方面軍の司令官に抜擢され、皇帝になっていくのですから歴史は面白いですね。この時代の指揮官は余程のつてがないとなれませんからね。
このような世界背景のなかで幕府は開国を求められていきます。1767年から1786年が田沼時代(徳川家治)、1787年から1793年が松平定信(家斉)その後、徳川家斉の大御所時代が続きます。そうして水野忠邦の天保の改革が1841年です。ヨーロッパで市民革命が起こり、産業革命が起こり、時代が変化していきます。1810~1820年代にかけてラテンアメリカやギリシャで独立運動が展開され、フランスでは7月革命(1830年)2月革命(1848年)などが起こる時代に、ペリーが来航します。1861年からアメリカで南北戦争が起きます。ようやく日本も長い鎖国社会から、その渦に飲まれて、ついに開国を迫られ体制転換が起こります。

欧米との技術力の違いを見せ付けられ、日本も岩倉具視率いる使節団が欧米に派遣されます。それ以後富国強兵路線をひたすら走るのです。19世紀の前半は時代が著しく変化する時です。民衆は現状に不満を抱き改革を叫び、革命が起きます。価値観がどんどん変わるのですね。鉄道についでグラハム・ベルが電話機を発明するのが1876年です。やはり鉄の作り方が簡単になり、鉄道網が整備されたことは大きな事ですね。この時代を大きく進めたのでしょう。
ここまでで二つの大きな事を学びます。技術革新が時代を進めGDPを押し上げる。その為にはお金が必要で、清貧思想などは必要ないのです。むしろ確立された社会構造は新しい時代の妨げになりました。フランスの例を見れば明らかです。ルイ16世などの強い君主制が進歩の妨げになりました。疲弊する財政の環境も似ています。今の官僚社会主義の形態は、特別予算などの扱いをめぐり混乱している様子と似ていますね。郵政民営化などの改革への反対勢力の力関係と似ています。昔を懐かしむ昭和30年代の夢のある時代への黄昏と新しい時代への戸惑いは、産業革命じのフランスと現代の日本の関係は似ているように感じます。
もう一つ驚いたのはイギリスの都市のスラム化です。労働環境が整備されていないこの時代の労働者は、低賃金で過酷な労働条件下で働かされ、貧困と病気が蔓延します。更に暴力が…、日本ではフリーターなどが生まれる環境下は、後世の歴史の中で産業革命時と比較され「格差の時代」と呼ばれるかもしれませんね。産業革命と通信革命(IT革命)は非常に良く似た背景を持ちます。軽工業から始まった技術革新は重工業へ変化し、今の時代はIT革新だけでなく、バイオ分野など遺伝子工学が非常に変化していますからね。
さて、いよいよ次回は、何故、私が新興株にこだわり、この「時代の背景」をビスタニュスの最初のレポートに選んだか? その理由をこれまでの歴史観と合わせ、相場の流れを中心に述べて行きたいと思います。株式相場は歴史の中で生まれるのです。次回はその理由をテーマに取り組んで行きます。
投稿者 kataru : 13:48
2009年11月23日
ビスタからの原稿1(2007年1月)
これよりコラムでは3回連続で過去にかたるが書いたビスタの原稿を掲載します。この『時代背景を考える』は大勢観を養う意味で大切だと考えるので、ビスタより拝借しました。以下本文です。…
失われた時代を考えると多くのヒントがあります。それまでの日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれ、焦土と化した戦後の日本の復興は奇跡と世界中から賞賛されていたのです。その影には適正な資金配分による、大蔵官僚の努力があります。貴重な外貨を有効に使い、電力債やNTT債はインフラ整備の為に編み出された素晴らしい仕組みでした。資金難の中で社会資本を整備し、日本を加工貿易国家に作り変えた経済成長は目を見張るものがありました。今は批判されていますが、ガソリン税などの特別会計の仕組みは有効に機能していた時期もあったのです。
ところが…1985年のプラザ合意の辺りから日本の政策当局の機能が停止します。この当時の日銀総裁は澄田智です。元大蔵事務次官のあと輸出入銀行総裁から日銀総裁。現在はユニセフの理事長をやっています。かれは1984年から日銀総裁になります。その時の総理大臣は中曽根康弘、大蔵大臣は竹下登です。当時、アメリカは膨大な貿易赤字を抱え苦しんでいました。対日貿易赤字解消の為にプラザ合意が実行に移されます。その為に235円ぐらいだった円は、僅か1年後に120円台になるのです。
このプラザ合意の過程で起こったのが資産バブルです。株と地価が急騰していきます。日銀総裁は資産価格が跳ね上がる中で、為替相場を気にするあまり低金利状態を容認し、銀行の貸し出し競争を煽っていたのです。農耕民族である日本人も土地は先祖伝来から引き継がれたもので、非常に大切で上がり続けるという土地神話も事態を複雑にしました。
この影で、巧妙な仕掛け作りが進みます。1988年に大阪証券取引所に株式先物相場制度が導入されます。このために裁定取引と言う仕組み上、株価は更に上昇して行き1989年末に38915円の高値を付け、今度は逆に解消売りで叩かれるのです。

この先物導入の後の仕掛けがBIS規制です。バーゼル銀行監督委員会はバブル期の日本の銀行の躍進を考えていました。リスク管理が欠如していると…1988年にBIS規制の国際ルールが発表され、銀行は自己資本比率規制(最低8%)を1992年12月に国際ルールで盛り込まれるのです。株が下がるとは考えていない当時の銀行は持ち合い株式の含み利益があった時の話しです。(含み利益の45%の参入が認められる)この規制により銀行は貸し出し枠にセーブが掛かります。
この時の日銀総裁は1989年から就任した三重野康です。彼は東大法学部から日銀に入ったエリートです。現在は大学教授。彼のあだ名は「平成の鬼平」
株価が急落し地価が下がり始めているのに、彼はなかなか利下げを実行しませんでした。どんどん株と土地は下がり傷口が拡大します。BIS規制の為に、銀行は融資できずお金が市場に還流しない事態が生まれたのです。流動性が不足しているのに、日銀はなかなか金利を下げないのです。この致命的な金融政策が、その後の不良債権の山を築いた原因の一つでもあります。
先物から株が売られ銀行の含み利益が含み損に変わり自己資本が毀損していきます。こうして90年代は、銀行がリスク資産の持ち合い株式を売ることを強いられます。かくして長い株価の下落相場が始まりました。この売られた株式を買うのが外人投資家です。

過剰借り入れで資産投資していた企業が、バブル期に踊っていました。上場企業のかなりの経営者は本業に関係ない絵画を購入したり、財テクと称し株を買ったり、中にはゴルフ場を造ったりする会社が多く増えました。みんな銀行の指導です。背景に銀行の貸し出し競争がありましたからね。バブル期の過剰借り入れはいつしか不良債権に変わり、過剰な生産設備は競争力が維持できる中国などへ移行し、日本の製造業には空洞化現象が生じます。よって過剰な人員はリストラと言う形で整理を余儀なくされたのが失われた時代です。
この間、およそ14年の歳月が費やされます。1989年から2003年まで…
世界一優秀な官僚制度と賞賛された仕組みは、ノーパンしゃぶしゃぶ事件(接待の為に使われたノーパンの女の子がしゃぶしゃぶを給仕するレストランの顧客名簿に多くの官僚の名前があった)に代表されるように、組織の形態を維持できなくなっていました。道路特別財源は使いきり予算の為に、年度末になると生産性を生まない投資に変わり、ただ土を掘っては埋める作業代に消えています。今も自治体の多くの予算は、必要ない非生産的な箱物に変わっています。維持費も払えないのに…。必然的に夕張市のような財政再建団体が生まれるのです。
体制崩壊と新政権へ、日本の過去にも似たような時期がありました。幕末と明治維新ですね。司馬遼太郎が好んで題材に使った時期です。かれは戦争体験を経て「日本の形」に疑問を感じ、多くの書物を残しています。この幕末の改革は、世情に疑問を感じた下級武士が主役になります。坂本竜馬などはその一例でしょう。黒船来航(1853年)が幕末から明治への切符になるのですが、その前から既に政権の矛盾は起こっていました。奇妙にも1853年の黒船来航と1867年の大政奉還の時間の流れは14年で、バブル相場崩壊の1989年から2003年のみずほの増資の安値までの時間が、これまた14年なのです。体制転換にはやはり必要な時間と言うのがあるのでしょう。
1778年 ロシア船、厚岸に来航
1792年 ロシア使節、ラックスマン来航
1804年 ロシア使節、レザノフ来航
1806年 幕府、外国船に薪水等供給を命ずる。
1808年 フェートン号事件(イギリス)
1818年 英人ゴルドン浦賀来航
1825年 幕府、異国船打払令を発す。
1837年 米船モリソン号来航、大塩平八郎の乱
1841年 天保の改革
1842年 幕府、異国船打払令を緩和し薪水飲料を供与させる
1844年 フランス船琉球に来航
1846年 アメリカ使節ビッドル来航
1853年 アメリカ使節ペリー来航
1854年 日米和親条約
1858年 日米修好通商条約(~59年、安政の大獄)
1860年 桜田門外の変
1864年 禁門の変、四国艦隊事件
1866年 薩英戦争、第2回征長の役
1867年 大政の奉還、王政復古
1868年 戊辰戦争、五箇条のご誓文
1869年 版籍奉還
1871年 廃藩置県、岩倉使節団

この当時の日本は化政文化の時代です。
よく時代小説に十八大通(じゅうはちだいつう)の話題が書かれていますが、この時代が背景ですね。十八大通は蔵前の札差仲間のお金持ちが、金の力にまかせ馬鹿あそびをするのですが…
札差とは…幕臣(旗本、御家人)は年に三度、俸禄の蔵米(切米)を支給された。自家の糧食分を取り置いた残りは市中で売却した。その仲立ちをするのが札差である。武家は収入である俸禄が一定である一方、支出だけは増え続け、ほとんどが手元不如意に陥っていた。先の日限で受け取る切米を担保にして、札差からの借金で賄うしかなかった。もとは切米売りさばきの仲介人だった札差だが、次第に武家相手の金貸し業が商いの中心になっていった。
田沼意次が老中になるのが1772年、そうして松平定信の寛政の改革が1787年です。1841年に水野忠邦の天保の改革へ、寛政の改革に続き、二度目の棄捐令などと言うおかしな政策が発動されるのです。大名、旗本の苦境を救う為に借金の実質的な棒引きです。最近のゼネコンやダイエーなどの借金棒引きと同じ現象ですね。優先株の処理は、所詮、借金の棒引きのような制度です。あの当時の金貸しの札差が大変な損害を被り景気が悪化します。同じことが現代社会で起こるのです。今回は貸し手責任を問われ、銀行が疲弊しました。歴史は繰り返す。
その影響を受け自己資本が毀損した銀行は増資に走ります。2003年のみずほ銀行は1兆円の増資を行いました。激動の波乱を自らの力で乗り切ったのです。実は幕末のあの当時は、イギリスで産業革命が起こっていました。今のインターネットなどの通信革命と、あの当時の鉄道は同じ社会資本整備の飛躍期です。産業革命が時代を大きく変える様を、次回の「時代背景の背景」で探りたいと思います。次回は世界的な動きから日本を見てみたいと思います。1989年のベルリンの壁崩壊から東西冷戦が崩れ、BRICsの誕生と列強の植民地主義の変化が、またよく現代と似ているのです。
投稿者 kataru : 11:33
2009年11月22日
今日は…
今日は一日、悶々をビスタの原稿の構想を練っていました。
政府の「デフレ宣言」の意味を考えていたのです。かねてから指摘していたように、こんな現象は前からあったのですね。しかしここに来てユニクロ現象が加速しています。その事について考えていたのです。そうして…今しがた、ある方向性が頭に閃きました。故に、ビスタの原稿は明日アップします。
市場人気を得るにはスターが必要なのですね。
石川遼君の存在は輝いています。何故か、池田勇太君ではないのですね。林に入れてもバーディーを奪うし池に入れてからリカバリーする。昨日は最後に難しいバ-ディーを決め期待に応える。そうです、人気と言うのは期待に応えないとなりません。そのようなスター銘柄が市場に誕生すると良いのですが…。強気を前提に政策を無視して買い方針を貫いてきたので、やられても仕方がありませんが、いつか復活できなくては意味がありません。現在、IRNETはビスタと合わせ6000人から7000人程度に減っています。しかしまだ、これだけの人が、かたるの原稿を読んでくれているようです。
最近は相場の強弱観が分かり過ぎて…どちらに向うのか読めないのですね。
例えば目先、上海総合株価指数は3478ポイントの今年高値をいつ抜くのでしょう。
この様な背景に、日産自動車は上手く時代対応していますが、電気自動車の時代は政策対応がなければ、時間がかかるかもしれません。現在は中国戦略で業績は好調ですが、積極策の為に増資問題があるのかどうか…。いろんな事が見え過ぎると、かえって迷いが生じます。大和証券の乳母車や手帳のコマーシャルで述べている通りです。選択肢が増えると迷うのですね。
今日、浮かんだアイディアが現実になるかどうか?
この発想は面白いですね。何れ皆さんにもご紹介できる日が来るでしょう。…と言うわけで、ビスタの原稿は一日遅れで明日アップします。今日は原稿を書く合間に、のんびりと相撲を見ていました。九州の人は、是非、ライブを見てください。何故か満員御礼にならない空いた席を見るのは寂しいですね。これもデフレ社会の弊害かな?
いつも前向きに…を合言葉のかたる君には、やはりインフレ社会が相応しい。
そうそう意見メールをありがとう。確かに消費を伸ばすために移民政策も一つのアイディアですね。現在のデフレ社会では即効性のある政策対応がないと駄目だと考えています。土地担保融資の復活は、無駄な投資に繋がりバブルを産むとの非難はあるでしょうが、そこまで行くのはかなり時間が掛かりますね。20年も続いた弊害は大きいのです。余程の転換をしなければ、なかなか躍動感のある社会に繋がらないでしょう。
投稿者 kataru : 22:12
2009年11月15日
あぁ~。
世の中には色んな考え方があるもので、自分の考えが正しいと思い行動する事に疑問を感じるのですね。通常は信じる道を歩む生き方が正しいと思うのですが、株屋としては間違っているかもしれません。既に日本は20年間、暗い時代を歩んでいます。暗いと思うのは僕の考えで、果たして正しいかどうか分かりません。でも人間は向上心のある動物で常に「今日よりも明日」と希望を抱き、より豊かな生活を求める動物だと考え私は行動しているわけですが、どうもこの潜在的な願望が強すぎるがために、ジレンマを感じるプレッシャーを人より強く感じるようです。生きる目的を何処におくか?
東京大学の宇沢弘文名誉教授のような考え方は嫌いなわけです。
やはり株屋なのでしょうね。お金が全てとは思いませんが、正常に流れる仕組みを維持すべきだと考えます。市場主義が日本を救うと考えているのです。しかし亀井静香さんなどの考え方は、昔のよき日本の時代への揺り戻しですね。確かに彼の考え方は一理あるのです。日本は加工貿易で稼いだお金で、株式持合いをして、終身雇用、年功序列の世界で成長してきました。共存主義とも言うのかな? 日本村社会ですね。だから村の掟が重視され経済的な合理主義より、先ず秩序が優先されました。
しかしこの秩序の制度の中で不平不満が出るわけです。病院などは良い事例でしょう。教授に睨まれれば生きていけませんね。外科は手術の経験が技量の発展に繋がりますが手術もさせてもらえないのです。故に若い医者は海外に出て行くケースもあります。兎も角、仲間内のルールが優先されるわけです。チームワークですね。仕事の出来る人は不満を覚えます。出来る人は仲間の分を自分が犠牲になり補うわけです。しかし報酬面ではたいした差はないのです。だから独立の道を歩みますね。僕のケースはこれだけではありませんが似たようなものです。丁度、10年で資格が取れたのでサラリーマンをやめて歩合セールスに転向しました。
しかしベルリンの壁崩壊で日本もジレンマを抱えたのですね。1985年のプラザ合意で既に日本の加工貿易体制の転換を求められたのですが、日本は構造改革が出来ずに低金利や為替介入で乗り切ろうとして失敗したのが1989年のバブルですね。その失敗で多額の損失を押し付けられたのが銀行です。だから異常なデフレ社会が構築されています。未だにこのデフレが悪だという報道が、マスコミにないのでなかなか真の転換が出来ません。きっと既得権力者にとって、この実体は有利だからです。日経新聞などもその仲間ですね。
失敗した小泉改革も、今、行っている民主党政権も構造転換を求めています。
しかし国民が真実を知り自ら改革を選ばないと、なかなかこの構造的なデフレのジレンマから抜け出られません。幸いと言うか…日本人の一所懸命さが個人金融資産の増大を生んで、政府が借金まみれでも自前の資金なので、まだユトリがあります。財務省はプライマリーバランスを叫び864兆円を越える借金だと騒いでもまだユトリがあります。でもまもなく時間切れ。まだ間に合うのですが…。亀井さんのおかげでまた郵政省の資金が役人の手に落ちたわけで…。財政投融資の資金源になりますね。うまいと言うか…粘り越しと言うか…。踊らされる日本人は真実を報道機関が報じないから騙されているのです。
ところが株式市場は市場経済で動いていますから、市場原理が歪められてどんどん疲弊しているわけです。呆れます。NECに三井化学、挙句に三菱UFJから日立だと言う話しで宝の玉手箱のような扱いをしていえば、いくら懐の広い市場経済での海でもやがて汚染され自浄能力さえなくなりますね。可哀想に誰も守ろうとしない。みんなが勝手に自分たちだけの利益を考え行動するのだから…呆れてものが言えません。問題解決を先送りした結果が膨らむ1000兆円の借金です。その延命策が強烈なデフレ経済を生んでいます。デフレの破裂は悲惨ですよ。ハイパーインフレを生みます。適度なインフレが必要なのに日銀は医者であるのに、その処方をせずに放置しているのです。
いくら馬鹿な私でも、異常な状態は感覚で分かります。野村證券は手数料ビジネスで喰えないのは決算書を見ればわかりますね。何年も営業キャッシュフローが赤字なのに財務で補っています。日本中の企業が安易な方法を選んで問題を先送り…。大変ですね。いくら私がホームページでおかしいと訴えても意味がない。市場はどんどん枯れていくのです。
投稿者 kataru : 08:09
2009年11月08日
成長戦略
サブプライムローンから金融デリバティブの問題に発展した当事者の米国は景気回復の途上にありますが、市場の二番底懸念を打ち消す形で追加の景気刺激策を発表しました。
マスコミの総合評価は、減税策では雇用の改善を打ち出すには力不足との評価が多いようですが、流石、市場経済の国ですね。羨ましい限りです。
この追加対策は今年の夏ごろから指摘されており、株式相場を支える原動力になっていたようです。先週末、株価が確りしていたのは、この追加景気対策が理由ですね。金曜日の「今日の市況」の冒頭で、「NY市場は失業保険申請件数が減ったとか…、労働生産性が上昇したとかと言う理由で株が上がったと言いますが…どうしてなのかな?」と市場の解説に疑問を持ち調べましたが…こういうことだったのでしょう。如何に市場の解説がいい加減なものか、お分かりいただけると思います。マスコミの言葉など当てになりません。
11月末で切れる予定になっていた住宅取得者への減税措置を来年4月まで継続することや失業保険の給付期間の延長を柱とする法案を賛成多数で可決し延長が決まったようです。この背景は改善しているとは言え、弱い景気回復の梃入れです。その様子は少し長い期間の失業率の推移を見れば明らかですね。1982年から1983年にかけて米国は深刻な経済状態でした。その時以来ですから…26年ぶりになるのでしょう。
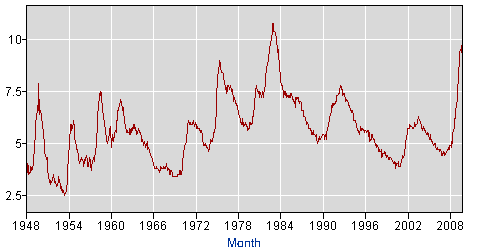
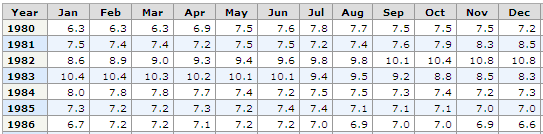
日本は政権交代により、本格的な効率化社会に向けた第一歩を踏み出しました。しかし現在までは予算の見直しが中心で、株式市場は現政権の政策を及第点と見なしていないようです。2006年に、わが国は折角のチャンスを生かせずに既得権勢力の圧力に屈して構造改革を成し遂げられませんでした。今回は政権を変えて再挑戦です。今のところ内需振興を謳う新政権のプロセスは具体性に欠け、市場は評価していません。
日本政府が東南アジアのメコン川流域5カ国と初めて開いた「日メコン首脳会議」は7日、長期的なビジョンとしての東アジア共同体の設立に各国が貢献するとした「日メコン首脳東京宣言」を採択し閉幕しました。また鳩山由紀夫首相が6日に表明した3年間で5千億円以上の開発支援の具体策など63項目の行動計画にも合意した。…と発表されています。参加したのはタイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー(ビルマ)。
タイは2008年の調査で6338万人。カンボジアは2006年の推定で1332万人。ラオスは2006年で621万人。ベトナムは2009年の調査で8578万人。軍事政権下のミャンマーは5322万人だそうです。何故かこのような成長戦略の報道は少なくマスコミは報道姿勢を変えるべきでしょう。
少子化高齢化など、経済成長の阻害要因になりません。経済圏を融合すれば問題は解決できます。日産自動車は来年の3月から世界で売り出すコンパクトカーをタイで生産します。IBMの株価はこの金融危機でも意外に確りしています。世界戦略を的確にこなしていれば株価は下がりません。この一例ですね。IBMは早くから実行部隊をインドに移管しています。この例でも分かるように日本でも同様の動きが現れ、ホンダは寄居新工場の稼動を延期して、わが国でいち早く世界戦略対応に乗り出しています。今日の日経新聞にも掲載されていましたね。実は日本精工なども動き出しています。
成長戦略が垣間見られる民主党政権の政策が、どう開花するか?
今日のビスタニュースでは、アジア戦略を含め具体的な銘柄を検証します。同時に短期戦略も…考えて見ます。
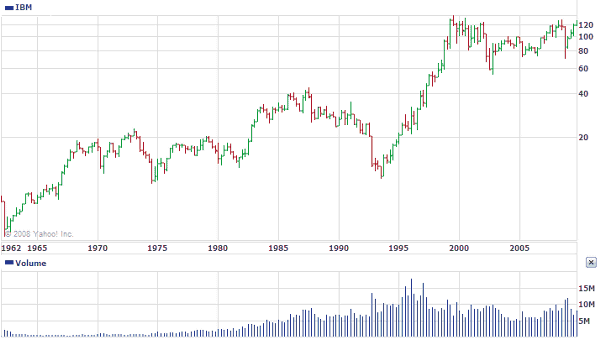
投稿者 kataru : 12:00
2009年11月03日
ドライブ

今日の東京は天気がよくて絶好のドライブ日和です。
車の運転が嫌いな僕ですが、かみさんと二人で箱根へ行きました。渋滞を覚悟して出かけたのです。京橋インターから東名へ、普通なら厚木まで随分時間がかかるのですが、渋滞はなくスムーズな動きでした。小田原―厚木に乗り箱根へ。
ターンパイプ(有料道路700円)を利用してTOYO TIRESビューラウンジの展望ルームでセルフのコーヒー(400円)を飲んできました。この道路も途中で景色は良いしお薦めです。途中で海を見たり出来ます。極め付きはこのビューラウンジでしょう。富士山が望め芦ノ湖を見下ろす絶景のスポットです。是非、2階のトイレに入ってみてください。腰を下すとクラッシク音楽が流れる高級便座です。窓から富士山が望めます。
そうして元箱根へ入る時に少し渋滞です。
そこから仙石原の近くにあるホテルグリーンプラザで昼食付きの日帰り温泉で休憩(3800円なのですがインターネット・クーポンを利用し3300円)ここの露天風呂からは富士山が望めます。女性のお風呂の方が良いかな?(ホテルの写真によれば…?)残念ながらバイキングの食事の内容は褒められたものではありません。まぁ、何とか喰える程度で落第点にならないぐらいの内容です。生ビールの900円は高いかな?(これは別料金)
このホテルを後にして仙石原のススキの草原は見事ですね。
夕日の時間帯なら最高でしょう。陽射しに揺れるススキは黄金色に染まりキラキラと…。この時期は人が多く平日がお薦めかな? 車で素通りして138号線へ。乙女峠を越えた所にふじみ茶屋があります。野菜を売っているようです。ここからの富士山も綺麗ですね。このラインをクルクル回り御殿場ICから東京に戻ってきました。首都高速が若干渋滞していましたがおおよそ2時間で帰ってきました。
雄大な富士山の姿を見て、普段の相場を忘れ自然の偉大さを感じます。やはり自然は疲れた心を癒してくれる優しさがありますね。
投稿者 kataru : 17:22
2009年11月01日
お疲れ様…
金曜日は最後の先輩が業界を去りました。
彼女との出会いは1989年11月に上京して初めて外務員になった時です。
そこの証券会社に10名ほど歩合外務員が居りました。その時の仲間です。当時、僕はお客さんが居らず、毎日、新規開拓の毎日です。会社に出社して朝の様子を見て外出して名刺を毎日100枚程度、配っていました。1989年の暮れに日経平均株価は38915円の高値を付けます。それから一度も上回らずに株は下げ続けます。
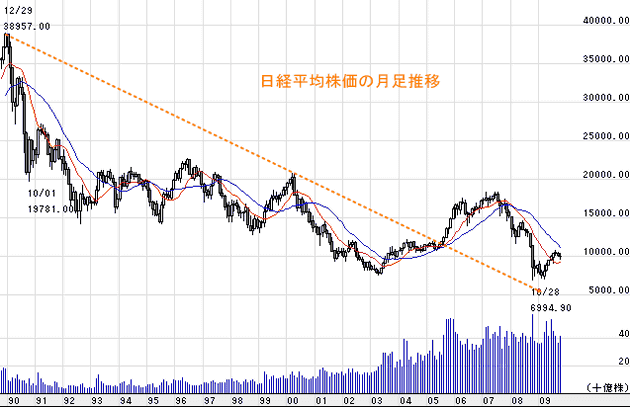
最初の証券会社には、僕は6年ほど在籍しました。
しかしノルマが果たせずに会社を変わる事になりました。そうして今の証券会社を、この先輩から紹介していただいたのです。先輩はその後もその会社に居り、途中、会社の都合で子会社に行かれました。その後も彼女とは時々顔を合わせる程度だったのですが…、人生は分からないものです。1年前に彼女は、またまた会社の都合で支店閉鎖により僕のいる会社に来る事になりました。そうして、また一緒に働きます。この縁は奇妙なものです。偶然の繋がりといえばそうですが…
彼女の出身は日興証券です。
この激動の証券界でよく外務員としてやってきたものです。当時の先輩は9人いました。僕を含め10人ですね。現役の最中に病気で亡くなった方も居られましたが、多くはノルマが達成できず会社を変わらざるえなかったのです。そのなかで彼女は最後までノルマを果たし続け、今回、引退されました。話しを聞くと昭和35年にこの業界に入ったとの事です。この年代で大卒の女性はかなり珍しいのでしょう。当時は日興証券だけが大卒の女性を採用していたらしいですね。
僕らの業界は女性の人でも立派な成功者が居られます。
GSにはアビー・コーエンやマリア・フィオリニ・ラミレスなど…ただ日本では独立される方は少ないのです。この相場の中でも成功して辞められる人がいるのですからね。僕は多くの先輩に色々教えていただきました。結構、生意気な方なのですが…可愛がってくれる先輩も多くいます。証券マンとして日本を見るとやはり色々無理な面がたくさんありますね。株価と連動して予算編成を見てもわかります。こんなグラフを発見したので上の株価と比較しながら考えて下さい。先輩、長い間、お疲れ様でした。
出来れば僕も証券マンとして継続できれば良いのですが…果たしてどうかな?
(下のグラフをクリックすると財務省の大きなグラフ画面に飛べます。)
投稿者 kataru : 17:00