« 2013年11月 | メイン | 2014年01月 »
2013年12月31日
2013年を振り返り…
2013年を振り返り、年末の9連騰がムードを明るくしましたが、全体的には5月23日のFRBの金融緩和縮小宣言が、響いた印象です。本来、力強い経済なら、三菱UFJや野村証券は、年初来高値を更新して、年末を終了する筈です。三菱UFJは下値ボックスを抜けましたが、需給バランスが悪い野村証券は。831円、833円のボックス高値を年末に抜けていません。しかし時価総額は、昨年末の東証一部時価総額は296兆4429億円から463兆1798億円と、166兆円増加しました。56.2%増加したわけです。一方、カタルがよく採り上げる東証一部単純平均株価の昨年末は228円41銭で大納会は324円56銭でしたから96円15銭の値上がりなので、42.0%の上昇でした。この14%の違いは、外人投資家が主体で指数売買の影響もあり、全体的に有名な会社が買われ、逆に陰では見捨てられている銘柄が、多く存在することを示しているのでしょう。つまり底上げになってない訳です。本当に強い時は、株価全体が底上げ状態になります。このような現状でしたから、平均で投下資本が5割ほど増えていれば…平均並みの成果だと言えるのでしょう。今年一年の皆さんの成果は、如何でしたでしょうか?
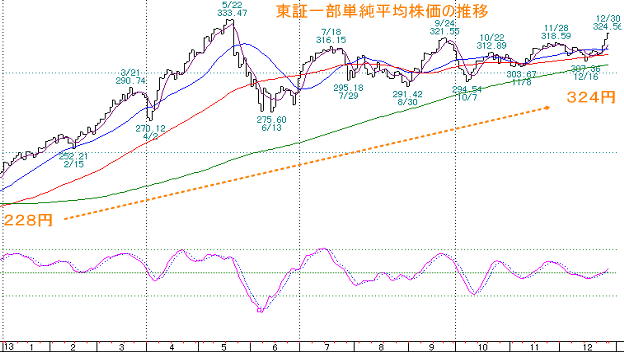
昨日と今日の今年一年を振り返り、残念ながらデータが全て手元にある訳ではありませんが、TICK回数は3月からの分で集計すると、上位5位の登場回数で一番多かったのは東電で88回登場していました。その様子を下の表に示しました。左側がTICK回数の上位5位までに登場した回数を示したもの、右側は売買回転率を示した人気株のもので此方は年間を通じての回数ですが上位3位までの集計です。代表的な東電のチャーを掲載しておきます。多くの人気株はこの形を形成しています。中には新興御三家と表現した。新規上場株のエナリス、ネット広告のアドウェイズ、ゲームのコロプラなど…終盤で賑わっていました。
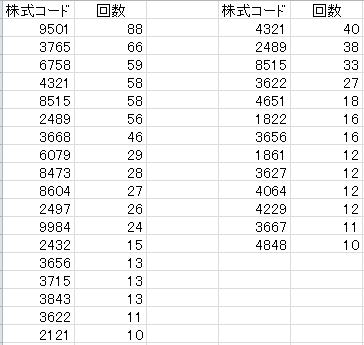
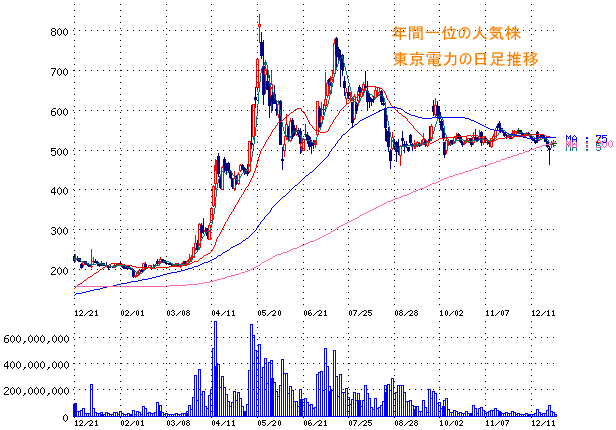
カタルの反省点として、もう少し市場全体を、しっかり見るべきだったと思います。問題は「アドウェイズ」なのです。正直、よく分からないのです。相場のスタート地点は7月10日ですから、どうもこの時にLINEとの提携により仮想通貨の契約を結んでおり、最近のビットコイン人気と関連性がありそうですね。しかしそれならば、LINEの親会社である韓国の「NHN株」を買えばいいのです。株価は724000KRWのようです。年初は336545KRWですから、およそ2倍になっているイメージですね。此方は9月から株価が上昇しています。ライブドアを買収した会社ですね。日本村論理のいやらしさが生んだ悲劇です。ひょっとすればLINEは、ライブドアが生んだのかも知れません。カタルは、よく背景を知りませんが米国ではグーグルなどが活躍しているのに…ものづくりに拘る日本人の「心の貧困さ」が影響しているのでしょう。
今年前半はマズマズでしたが、後半はカタル自身も買っては投げの繰り返しで、資本力の無さが敗因に繋がっています。そこでカタルは現在、投資手法を変更しようと考えています。その実験が成功するかどうか…試行錯誤を繰り返すわけです。証券マンを辞め、自分で売り買いをするようになり、生活費も掛かるので大変ですね。成果としては褒められたものではありません。結局、昨年の10月から4倍に過ぎませんからね。少ないお金で如何に効率よく成果を上げるか?工夫が続く訳です。別に今までのやり方がまずいと言っている訳でありません。のんびり成長する可能性のある株を下値で買って、人気になるのを待てばいいのですね。今回提供した古河電工や日本板ガラスなどはその代表事例です。
上がる銘柄は決まっているのですね。順番待ちしている007やケネディクスは何れ、人気株になる順番が来ますからね。その時に手持ち株を売り始めれば良いだけなのです。ただ折角、自由に株が売り買い出来るようになったので、もっと高い成果を得られるんじゃないか…と考えている訳です。株価は2倍になれば、通常は5倍程度の成果は当たり前なのですね。カタルは現役当時の事例を示しています。銘柄は第一中央汽船でしたが、100円で10万株買ったものが、株価は1000円になり最終的に持ち株数は100万株になったのですね。つまり1000万なら10億円ですね。カタルは常にハイリスクを狙い、成果を確実にあげたいと日々、努力している訳です。今回のレポートを書くにあたり、データの整理に、およそ10時間程度も掛かっているのです。皆さんはそのエキスを読んでいる訳ですね。カタルの意見が正しい訳ではありませんから、参考にされ自分なりに研究してみると良いでしょう。分析に充てる時間が乏しく個別株まで踏み込めませんでしたが、概略だけ纏めて2013年最後のレポートにさせて頂きます。1年、ご購読有難うございました。
投稿者 kataru : 14:03
2013年12月29日
村論理の矛盾
市場における2013年の総括は、あとで振り返ってみたいと思いますが、ニュースを見ると、日本の実情が、浮かび上がるように感じます。貧乏をすると心も貧しくなるのでしょう。戦後の復興から日本は世界的にも類を見ない高度成長を続け、オイルショックも克服し成長を続けてきました。しかし昭和30年代のノスタルジーは、何を懐かしむのでしょう。バブル期の思い出より、何故か、心に響く映像が、体の中で流れています。物質的には現代の方が、ずっと豊かになっている筈なのですが…。人間的な心の豊かさは、やはり昭和30年代ですね。隣近所の子供たちが、陽が沈むまで缶蹴りや鬼ごっこ、縄跳びにビー玉、メンコなど…と、一緒に遊んだ楽しい思い出が、何時までも心に残っています。
先ほど読売新聞を見ていたら、JR北海道の乗務員が、乗務室で勤務中にパンを食べていたことを問題視され、厳重注意を受けたと報道されていました。この国は、やはり狂い始めている…と感じる次第です。些細な事を通報する乗客の倫理観は、まるで戦前の特高警察、中国の文化大革命やイランの現状に似てきたようですね。直木賞に選ばれた「ホテルローヤル」には、供養のために開いた法要に来なかった坊さんへの浮いたお布施をホテル代に充て、楽しむ夫婦の田舎の姿が描写されており、何故か地方経済の現状を描いている様で…悲しく感じました。経済面でも軽乗用車の生産台数が過去最高だそうです。レクサスなどが売れるなら分かりますが、長いデフレが生んだ結果なのでしょう。やはり高級車は乗り心地は、安い車と全然、違いますからね。そのレクサスは中東でも売れているようです。原油価格が高値で安定しており、日本の失われた時代と相反して豊かになったはずの中東ですから、イスラム過激派は勢力を失っている筈です。しかしシリアなどを見ると…未だに貧乏だから、食えないから革命などが起こる訳ですね。
ソフトバンクの孫さんが日本のお金を海外投資し、利に適った行動ですが…同時に野村監督がマー君の移籍を見て嘆いたように、ガラガラポンのリスクに備えた動きは、至る所で起こっている訳です。三菱商事も金属部門だけですが、稼ぎ頭の本社機能をシンガポールに移している訳ですね。節税ですね。この動きは日産自動車のマーチの生産をタイに移管したのと同様に影響力の大きな話です。グローバル化と言えば聞こえは良いですが…優秀な企業は、既にガラガラポンに備え、手を打ち始めているとも言えます。果たして政策担当者の人々は、この現象の意味を正確に理解しているかどうか…。たかが5400万株の信用買い残の壁を前に、怯んでいる市場のパワーレベルを考えると、清貧思想を続けた弊害を、日本の指揮官たちは認識しているのかどうか…。高級管理職の年収は2000万ほどです。多くはありませんが、少なくもなく生活に不安はありませんからね。
ただ東芝を始め、一流と呼ばれた企業は、挙ってリストラを敢行しています。あの松下銀行と言われたパナソニックも遂に追い込まれました。やはりかなり追い込まれたことは事実ですね。今は、半導体技術者は大変ですね。エルピーダに、ルネサスと食えない時代を迎え、NECなどがリストラした時は、まだ余裕がありましたが、今はあとがありません。ニートの語源は(Not in Education、Employment or Training NEET)だそうですが、若者のフリーターも多く生まれている日本では、まともに就職できれば良し…と言う社会環境ですからね。ブラジルなどへ移民をした時代に逆戻りしているようにも感じます。
日本村論理を維持する力もなく、だんだん追い込まれています。ベースマネーの存在が、かたるの株高根拠を支えていますが、同時に、みずほのやくざ融資を過大に問題視する清貧思想も、依然、存在し続けるわけです。折角の緩和力が抑えられています。米国はボルガーにEUも似た動きにあります。この感覚の綱引きが続いているのです。
さて最後になりました。カタルは正常な経済運営をする為には、民間資本による投資活動が活発にならないと正常とは言えないと思っています。現在は日本を始め、米国もEUも金融システムが崩壊し、その回復途上にあります。しかし日本がいち早くバブルを経験し、そのバブルを過剰に清算し続けてきたと言えるでしょう。りそなの公的資金返済をよく本文で引き合いに出すのは、そのためですね。米国ではフレディーマックやファニーメイなどのGSEを象徴的な現象としてカタルは考えており、時々、その話をします。
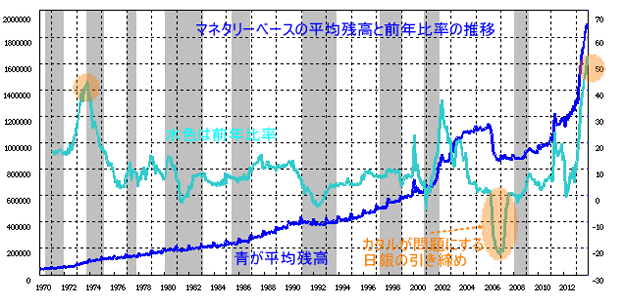
通常、これだけマネタリーベースを増大させれば、必ず、通貨と相対する資産価格は上がる訳です。だから株と土地は、絶対に上昇する筈ですね。故にソフトバンクの孫さんは銀座のティファニービルを、現状では馬鹿高値で購入したのですね。そうして日本で借り入れを起し海外に投資するのです。カタルが「ケネディクス」に拘っている理由が分かるかと思います。その様子を、上のマネタリーベースの推移と、下の東京都の地価推移を見て、自分なりに考えてください。本当は自分でカタルのようにグラフを作ればいいのですね。縦割り行政が、色濃く反映されていると感じるはずです。地価の価格評価には、路線価や基準地価、公示価格など…たくさんの算出方法が存在する矛盾も同時に感じると良いでしょう。何故、このような二重や三重の無駄な仕組みが、存在するのでしょう。地価価格はあくまでも一つの筈です。これは日本村論理の一つの表れでもあります。コメの減反政策と同じ土壌に存在する日本の矛盾ですね。司馬遼太郎が嘆いている根拠は、この辺りにもある訳です。
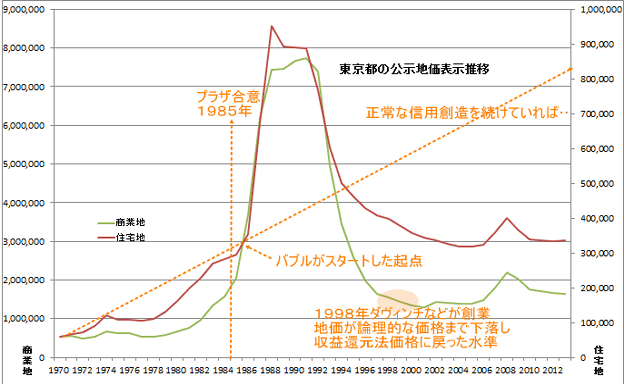
投稿者 kataru : 11:55
2013年12月23日
理想買いと現実買い
ホドルコフスキー氏の釈放など…興味深いテーマは進展しています。重要な話で触れたいのですが…今日は約束通り「見えない利益と相場観」の話を展開しましょう。カタルのホームページを見ていると、平日との土日の差が2000人程あります。おそらく証券マンなどの現場の人間が閲覧している可能性があるのでしょう。考えてみると「失われた時代」は長く、現場に熟練工が育ってないのは、何も製造業だけではなく、証券界も同じなのでしょう。今ではイチジクの制癌剤開発の科研製薬の相場や仕手株の誠備の宮地鉄工などの相場を知る人は少ないのでしょう。ひょっとすれば、ITバブルの光通信を知らない人も多いかもしれません。だから過剰流動性相場のバブル相場も、過去の話ですね。NTTの上場が引き金になり、この馬鹿相場が演出されました。通常は知識の伝達の為にリストラなどを避けて、目に見えないこのような内部留保(人材確保)が積み上げられ、技術の伝承が続くのですが、長い不況が続きリストラが当たり前になり、日本の良さが消えたのですね。無駄に思える中高年の雇用も、若い人材形成には欠かせなかったのですが…。日本にはその余裕も奪った「失われた時代」が続いたのです。カタルは現役時代、小さな証券会社だったために、株式部長からの直伝で、相場のイロハを教えて頂きました。新聞の読み方から…どのような記事が相場に響くかまで…。
例えば増産投資の記事、今日の日経新聞にはカタル銘柄の古河電工のワイヤハーネス工場新設の記事が掲載されています。この記事は一見すると、日産と古河電工だけを連想します。カタルは自動車産業全般について相場としての峠を既に越え上昇確度が鈍ると述べていますが、同時に中国との関係改善が、来年のキーポイントになると述べています。つまり間接的に円安効果と、マツダの中国工場の出来、如何では、2010年に述べた500円~4桁への相場を語ったマツダの相場が、来年、実現するかもしれませんね。為替が115円程度まで円安に振れ、中国のマツダ工場が順調に利益を計上出来れば…の話ですが…。古河電工の工場新設の記事は、このような連想も働くのです。新聞記事も表面だけでは駄目ですね。同じく日経新聞の一面トップには、HEMSを応用した電力データの活用が報道されています。知っている人は「007」の記事だと分かりますが、一般の知識だけでは分かりません。だから、ここに小さくユビキタスと記者に書かせると…月曜日の007はストップ高します。プロは日経の記者に、さりげなくヒントを与え、無意識のうちに記者に応援記事を書かせるのですね。実話ですよ。和光証券のTさんは日経新聞に出向き、さりげなく自分の知識を披露し、その関連記事が新聞に載る時に相場を煽り、自分達が抜けていました。日経新聞は非常に効率的な仕掛けですね。
蛇の目の時は、経理部長だったかな?地位のある内部人物に罠を仕掛け、酒と女や博打などに溺れさせ、仕手筋の言いなりに誘導します。そうして乗っ取りましたね。資産価値があったからですね。まぁ、裏の世界には裏のやり方がたくさん存在し、チャートなどは意識的に創られている面もある訳です。一応、歩合の世界はアングラな部分も多く…自殺した同僚もたくさんいるわけです。やくざ屋さんも絡みますから…綺麗なものばかりではありません。しかしそのような面も消え、今では過去の遺物になっています。金融屋さんも居なくなりましたからね。アイチなどの存在は過去の産物です。カタルは当初、誠備の加藤さんに憧れていましたが…現場を知れば知るほど、厭になり、昨日、登場させた岡三のKさんからの注文も断わった程です。彼はカタルの上京に際し、収入を保証していました。月給50万ぐらいあれば、食えるだろうと言い、彼の配下に置こうとしたのです。でもカタルは断りました。あの時に注文を受けていたら…きっと大変だったでしょう。年収で1億も3億と稼ぐ人は、顧客筋も大物が多いですからね。武富士やサンリオ、マクドナルドに、すかいらーくと…新興財閥の一代目は、みんな相場が好きなのですね。ABCマートの三木谷さんも好きですよ。昔なら松下幸之助が、信用取引をして追証になっています。実話ですね。まぁ、昔話は兎も角、そろそろ本題に入らないとスペースがありません。
昨日掲げた「相場サイクルの見分け方」浦上さんの書かれた理論は素晴らしく、参考になります。今でも基本は一緒です。ただ時代が変わり応用できない部分も多くあります。相場には「金融相場」に「業績相場」があります。喩えて言うなら「理想買い」と「現実買い」ですね。前者は利益が見えない時に、相場がスタートします。故に強弱感が対立して仕手化します。仕手化とは…先行きの見通しに対立が生まれ、こんな赤字の会社がこんな株価などおかしいと思うのですね。一方、買い方は時代の変遷を考えれば、この会社の製品は一般化して、やがて大きく伸びると思う訳ですね。この未来の「見えない利益」を巡り対立が生まれます。赤字なのにこんな株価はおかしいと…空売りが入り、相場が仕手化して行きます。あるいは、先ほど述べた科研製薬のケースは制癌剤の是非を巡り論争が起こるのです。意見の対立から、生まれる相場ですね。だから「知ったら終い」と、結果が分かると相場が終るのですね。意見の対立に決着がつくからですね。これが金融相場で理想買いの段階です。007もそうでしょう。ユビキタス社会を迎え、KDDIと共同でソラテナなどに参画していますから、日経新聞の一面の材料が、直接、響くと見る人も大勢存在するわけです。カタルが時代性の重要度を述べるのは、こういう事なのです。
一方、マツダのケースが良いですかね。既に利益が見えて増額修正をして、株価が反応しています。カタルが推奨した時は、2010年の春で株価は200円台でした。あの当時、中国の生産が伸び、マツダは仕手性の真価を発揮すると考えていましたが、結局は円安効果でしたね。この段階になると、既に理想買いではなく現実買いになります。更にカタルは世界で飛行機が売れていることを知っており、大阪チタンに惚れていた時代があります。しかし時代の変化で炭素繊維に流れ、東レが上がっています。この背景は加工技術の進化ですね。三菱重工と共同作業の中で、例のMRJですね。この開発過程で東レは炭素繊維の加工技術を進化させました。最近では高級車にも使用され始めています。やがて大衆車利用まで広がるでしょう。そうなると汎用化され利益が爆発しますね。東レは故に有望なのですよ。
話しはそれましたが…飛行機のトイレなどを製造する会社のジャムコですが、世界ではドイツと日本だけが抜けています。…が数量は売れていましたが、単価が厳しく円高の為に利益が出なかったのです。先日、参考に掲げましたが過小資本銘柄で株価が飛ぶので公開は控えてきました。実は1000円割れの400円~500円の時から、カタルのお気に入りの銘柄だったのです。お客様の中には買った人も居られるでしょう。でも相場になったのは円安の今回でしたね。マツダと同じ理屈です。でも既に利益も膨らんでおり、相場としては6合目を過ぎているのでしょう。ひょっとすれば、8合目かも知れません。マツダと五十歩百歩ですね。でも今回は上場来高値は抜けるでしょう。それほど飛行機は好調なのですね。結果論を解説していますが、それが業績相場なのです。理屈と株価が合い割安に見えるのです。
しかし株と言うのは、金融相場の段階、所謂、理想買いが一番面白く、ワクワクして夢が膨らむのですね。皆が、未来が分からないからです。007は村田の意向次第で売り上げは50億、100億と膨らみます。採用単価を高くしても良い訳です。村田にとって50億や100億など鼻紙代程度です。ユビキタス時代を迎え、QBの価値はエネルギー価格が上昇し更に高まりますね。待機電力が必要ないからです。テレビにプリンターにCD機など…様々な製品は稼働してないのに、待機電力が使われています。カタルを2010年に魅了した焦点は此処でした。もし一般化した時に、どれだけの需要が発生するか…世界の消費電力は、どれだけ効率化されるか? やはり証券マンとしては、育てたい銘柄の一つです。2010年の段階では本物かどうか、分かりませんでした。しかし今では、数社がカーナビに応用し、QBが眉唾の技術でないことが証明されていますね。開発期間の2年も待たされましたが…。
科研製薬は大相場になりましたが…実際はイチジクからの制癌剤開発は、偽物に終わりました。しかし相場になったのですよ。たしか200円ぐらいから4000円程まで…買われたのかな? 持田製薬のスタートは、OH1という制癌剤を材料にして、当時の株価は1000円台だったと思いますが、16000円まで育ちました。両者とも偽物でしたが相場になりました。小野薬のプロスタグランジンは800円台から15350円まで…育ちました。これは本物で、その後もこの物質の発見で小野薬は食っています。住友鉱山の相場も金が発見されたとか、偽物だったとか…の対立で相場になり、この話は本物でしたね。100円台の株が2000円まで行きますが、熱狂的だったのは1981年から1982年でしょう。最近では、ITバブルですね。光通信は偽物、ソフトバンクも偽物でしたが…今は本物になりつつあります。ITバブルは、ある意味で理想買いなのでしょう。故に、これから現実買いが訪れるから、ナスダックの上昇に絡み、カタルは好業績に移行している光通信も参考銘柄として、時々掲げています。
何故、カタルは好みでもない古河電工を、カタル銘柄に採用したか? それは1999年から2000年にかけた相場の中で、光通信の技術買収に多額の資金を投じ、一旦は失敗しましたが…ようやく、あの理想買いの相場が、現実買いの業績相場に移る可能性があるからです。その理想買いの株価のスタートは300円台の株価でしたが…2000年に古河電工は最終的に3600円台に、仕手化してなりました。理想買いの相場は大相場なのです。カタルが007に拘る理由も、なんとなく理解されるかと思います。
更に大切なことを最後に書きます。株価の上昇が企業を育てるのです。株価が上昇すると社会的な信頼が増し、やがて好循環が生まれます。任天堂の世界的な成功を支えたのは、野村証券の営業部隊です。資金面でフォローしました。あの当時、おもちゃだったファミコンを、世界的な一大産業に育て上げた功績は大きいのです。カタルが新潟支店を挙げて取り組んだ任天堂、あまり市場から買うもので…野村証券からストップがかかりました。値決めの期間中だったのです。いくらでも必要なだけ、公募株を分けますから、市場から値決めが済むまで株を買わないでほしい…との協力要請が掛かったのです。昔は「公募が買い」だったのです。今は、公募は希薄化という事で、売りに変化していますが、実際は違いますね。公募は買いですよ。ケネディクスの公募は、財務内容の保全の意味もありましたが、これから資産を買い揃え、更に利益を膨らます道具になります。前向きな増資だったのですね。株価を高値にして資金面などでバックアップすれば、日本にも未来型の産業がたくさん育つでしょう。「共有する理念」が市場を育て、日本を豊かにするのです。なかなか理想買いの見えない利益の話を、理解されるのは難しいでしょうが、障りだけでも感じて貰えれば…と考えています。007…。
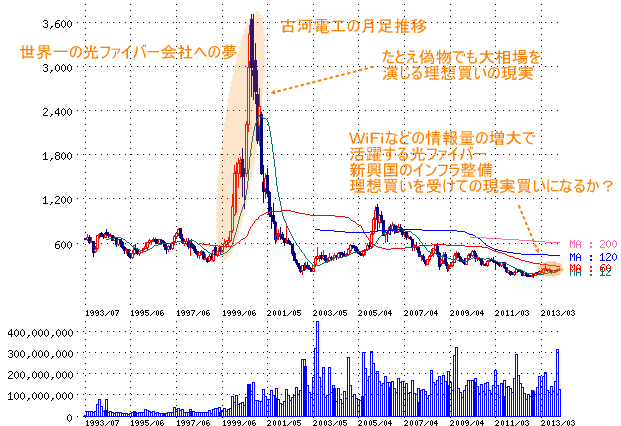
投稿者 kataru : 10:33
2013年12月22日
カタルのプロフィール
読者からのメールでお勧めの本はありますか? と言うものがありました。読者には返信メールしたのですが、上手く届かなかったようなので…ここでもう一度、回答しておきます。実はカタル君もずいぶん色んな証券関係の本を読みました。100冊以上、読んだかもしれませんね。しかしあまり身についたものはなく本も参考にならずに、実践から学ぶ試行錯誤の毎日を繰り返しました。如いて掲げるなら、日本証券新聞社の「酒田五法は風林火山」と言う江戸時代の米相場を研究した本間宗久の秘伝を解説した本や、日本経済新聞社の「相場サイクルの見分け方」浦上邦雄さんが書かれた本ですが、しかし、もう既に絶版になっていると思います。
だからIRNETのトップページで、グーグルのIRNETのサイト内の検索を用い「相場サイクルの見分け方」と検索すると…関連ページが出てきますから、それを読まれると良いでしょう。景気循環と物色銘柄を解説しているコラムは非常に重要です。
浦上さんはお父さんを早くに亡くされ家計を助ける為に、神戸で荷揚げ作業をされて兄弟を育てた苦労人だと聞いています。日興証券は戦災孤児等を多く受け入れていました。カタルを興銀の杉下常務に紹介してくれた岡三証券のKさんも、両親とも戦争で亡くされ、兄弟は離ればなれで育てられた戦災孤児です。経済的な理由などで大学は出ていなくても優れた人は多いですね。このKさんはカタルが出会った当時、1億円以上の手数料を毎月叩き出していました。月間の話しですからね。ピーク時の月給は数千万だったはずですね。カタルも一度、2700万円位の月給を貰ったことがあります。その年の年収は1億を超えましたが…手数料が安くなった今でも対面取引では年収1億ぐらいが、歩合セールスの一つの目安になるでしょう。
最近、新規の読者も多く、カタルのプロフィールを、再び少し話しています。カタルは現役時代の証券マンを営業で10年続け、歩合セールスとしての免許条件を満たしたので、それから21年かな? 歩合セールスを経験し、合計31年間の証券マン人生を歩んできましたね。現役時代は2回の転勤を経験し、最後は法人課長で退社しました。今では懐かしい「とっきん」などもやりましたね。そうして上京し下げ続ける株式に買い向かい、自分の力量の限界を感じ勉強をして、平成5年に証券アナリストの資格も取ったのですが、やはり駄目でした。1990年2月に東証一部単純平均株価は1913円だったのです。そこから、なんと単純平均でおよそ1/10です。その様子が此方のチャートで分かります。日経平均株価などは嘘の塊です。日本経済の実態は、やはり単純平均株価でしょう。これがデフレ経済の実態ですね。
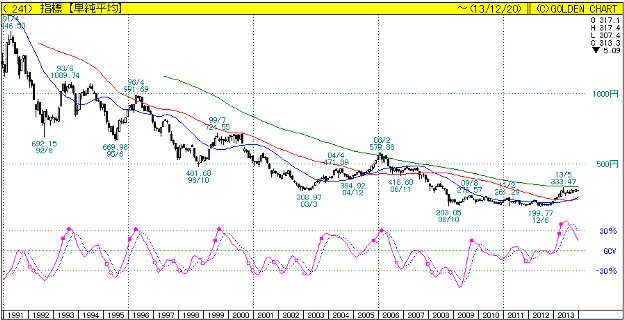
司馬遼太郎はノモハンの戦いで戦車部隊に所属しており、ソ連製の戦車と日本製を比べ、装備の差は精神力では補えるものではないことを実感し、彼の作家としての美意識は、その経験にあるのでしょう。日本製の戦車は、鉄板を弾が貫通するほど薄かったそうです。その為に「男の生きざま」と「合理性」のテーマが底流に流れており、晩年は「この国のかたち」に拘っていました。彼の心が「失われた時代」を通じて、カタルにも流れています。故に昔のIRNETは官僚批判や政策批判ばかりでした。下げ続ける株式に夢を語り、買い向かう姿は、まるでドンキホーテですね。カタルはそんな証券マンだったのです。でも政策が正しければ、カタルは儲けられます。事実、2003年から2006年は3億円の預かり資産を40億円まで増やしたのです。その結果が先ほどの収入ですね。しかし今のカタル君は借金だらけで…、その為に1000万円の収入があった歩合セールスを辞めて、投資家に転向しました。でも現状は褒められた内容ではありません。こんな感じですね。
自民党政権の復権は、ある意味で哀しい現実です。診療報酬など予算編成を見ても妥協の産物ですね。理念がありません。ソフトバンクの孫さんは、この理念を共有する仲間を募り、世界にチャレンジしています。カタルは不器用で空売りが出来ないのですね。それを克服するために証券マンを辞めたのも理由の一つです。でも染みついた観念はなかなか変えられません。せいぜい、東電などの相場を批判する程度です。最近では新興御三家ですかね。
日経平均株価と東証一部の単純平均株価と比較すると…眉唾の中央集権体制の実態が見えます。日経新聞を始めとするメディア批判を、カタルが繰り返しているのは、真実を突いていると思っています。司馬遼太郎は、書きたくても書けなかった「ノモハンの戦い」の矛盾を引きずったまま、死んでしまいました。当時の朝日新聞などは、ひどいものだそうです。撤退ではなく、転進ですからね。国会図書館に行けば、当時の新聞を読むことが出来るでしょう。既に国会図書館では電子化が完了している筈で公開すれば良いと思うのですが…。それともしているのかな?
日本には正しい指揮官が居ないのですね。故に彷徨い続けているのです。簡単なんですよ。反対意見を押し切り、正しいと思う理念を追求すればいいのです。妥協をせずに突き進むのですね。目指す理念に向けて…。でもメディアを始め、みんな敵になりますね。日本を救う道はスマートコミュニティーの実現で、効率化社会の実現ですね。その為に予算を使い邁進すればいいのです。本当はお金も必要ではありません。PFIを利用すればいいのですね。政府や日銀が理念を持った企業の資金を保証し、昔のNTT債や電力債同様に、債券の発行を認めさせて、ワリコーなどの仕組みを使い、税制などの支援をすれば簡単に資金がなくてもスマートコミュニティーは実現できます。その組織がないから駄目なのですね。
ソニーが迷走している実態と同じです。カタルは早くからネットテレビの話をしていました。既に10年以上、前だと思います。スマートテレビですね。残念ながら、日本で一番近い立ち位置に居るのはソニーです。しかし…経営者が馬鹿なのです。最近では中国でスマートテレビのブームだとか…。完全に日本は後塵を拝しているイメージです。NHKの活用や民放と組んで、映画に、ゲームに、音楽と…日本を挙げたソフト会社を作ればいいのですね。ところが4Kや8Kなどと、的の外れた経営をしています。トホホですね。民間も日本国と同じです。
例えば汚染地区の福島原発周辺を一括買い上げして、スマートシティーを計画すればいいのですね。日銀がメザニンローンを引き受ければ、エクイティーも個人の金融資産から集まるし、国内行ばかりか、海外からもシニアローンは集まるでしょう。50兆円規模の新都市開発を実現させればいいのです。簡単なことですよ。坪単価10万円の地価を100万円にして分譲すればいいのです。付加価値を高める方法は、いくらでもあります。税制支援など…色んな仕組みがありますからね。戯言はこの辺にして、如何に「理念」が大切か説いたつもりです。原発反対で自然エネルギー大国に向かうなら、最後まで理想を追い求め、太陽光の買い取り価格を下げずに、促進させればいいのですね。電力会社にすべての電力を買い取らせればいいのです。ところが現状では、電力会社は買い取りも拒否していると言いますからね。この現象にも「理念の欠如」が見え、日本村論理の「妥協の産物」が復活するわけです。55年体制の自民党政治です。
カタルは現状打破には、中央集権では無理だと考え道州制を採用し、地方分権政治が突破口かな…とも考えています。交付金の配分権を中央官僚が担う事が、間違っているのかもしれません。今回の診療報酬に、国家予算の一般会計と特別会計のカラクリなど…仕組みを知れば知るほど、反吐が出てきます。メディアはこのカラクリをなかなか叩きませんね。しかしネットなら叩けます。真実は、やがてどんどん広がり、構造改革が進むのです。「アラブの春」はイスラム圏だけの話ではなく、日本でも静かに進行しています。株式相場を見てみれば、分かりますね。共通する理念にお金を流す事が正しい道だとカタルは考えています。スマートコミュニティーの実現に向け、関連産業に資金を流さねばなりません。007はそんな一翼を支える銘柄ですね。ケネディクスもそうです。信用創造の重要性が認知されるまで…。時代性とは…そういう事なのでしょう。
明日は、見えない利益と相場観の話を考えています。全国の証券マン、必見のテーマです。
投稿者 kataru : 10:10
2013年12月15日
ケネディクスの魅力
最近発表されている報道傾向を注意して観ていると、あらゆる方向でカタルの信用創造機能回復期待が、現実化しているように感じています。この信用創造機能とは、土地や株の価格上昇ですね。失われた資本財の価値を取り戻す揺り戻し現象が始まります。例えば先日、カタルはREITによる取得総額のグラフを含めたレポートにリンクをはりました。そのグラフは此方です。今年の異次元緩和から、新規不動産の取得が活発に始まっていますね。実は2010年10月の日銀が行った包括的金融政策の採用から、流れは既に変化していますが、インパクトが弱く、充分なアナウンスメント効果が得られませんでした。白川さんは、政治家に背中を押されたポーズと…市場は判断したのでしょう。しかし黒田さんの異次元緩和は、アベノミクス効果と重なり成果をあげています。リートの市場利回りが低下すれば、採算の合う物件開発範囲は大きく膨らみます。だから裁定効果が出て、一気に新規取得が2兆円を超えたのです。この現象だけなく、海外からも新規の不動産マネーが投入され、日本の首都圏の地価が、底値圏から2割ほど上がっている現象が確認されています。
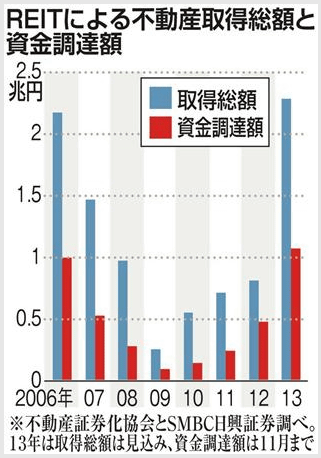
カタルの基本的な構想は、これから加速します。例えば、本日の15面の日経新聞の求人欄には「住友不動」や「東急リバブル」などの積極的な会社が、人材募集を始めています。オリンピックを控えた首都圏の地価は、当分、右肩上がりでしょう。カタルが日本全体の土地資産の話をよくします。2400兆円もあったのに…半分以下の1100兆円まで富を失ったのがデフレの元凶の一つです。古き良き時代では、事業で失敗したら土地を売り借金を返済できましたが、現在の首都圏は、兎も角、田舎の土地などは全く買い手がありません。どんなに安くても…。まったく信用創造機能が機能してないのです。だから日銀が異次元緩和を実施しても、流動性の罠に嵌り、マネーサプライが伸びないのです。一度、火を落とした高炉を、再び稼働させるのは大変なのですね。余程のエネルギーが必要です。此処に「相場の芽」が存在します。明治以来、蓄えた土地資産の含み利益を、一気に吐き出した三菱グループまでも、ユトリがないです。だから東京駅、丸の内側に資本の集中投資をして付加価値を創造している訳です。あの狭いエリアだけの投資なのですね。
この揺り戻しは、相当なスケールで起こりますね。先頃、ドイツ銀行が世界の不動産市場の分析をしたそうです。その中で、カナダがもっと割高で、日本はもっと割安だったそうです。このレポートは投資規制のハードルが高い為に、起っていると結んでいるようです。このレポートは此方ですね。無料会員向けかどうか…分かりませんが、一応リンクしておきます。異次元緩和から、ものである土地と言う資産価格が上昇する背景を十分に理解して置いて下さい。時代背景が大切なのです。さてここまでは、これまでに何度も述べてきたことなので、概ね、読者の方は概略を理解されている事と思います。さてそこで、何故、カタルがケネディクスを選んでいるか? 本当は、上場されていればダヴィンチを選んだのです。金子さんの構想は正しかったのでしょうが、時代が味方しなかった。金融庁の方針が本来は変わらなければならない時に変わらないから…日本は狂って居るのですね。半沢直樹のようなドラマが誕生するのは、松平定信の「寛政の改革」への批判で生まれた川柳のようなものです。「白河の清きに魚のすみかねて もとの濁りの田沼こひしき」賄賂政治の田沼政権への郷愁は、バブル時代にディスコで騒いだ、お立ち台ガールの姿を彷彿させます。
ダヴィンチの金子さんの論理は正しいのです。それを偽物と決めつけ、権力を行使して上場廃止に追い込んだ清貧思想が、これから打破されていきますね。あの三菱が、明治からの蓄えを飛ばした政策が、どうして正しいのでしょう。秀和や桃源社レベルではないのです。その政策の結果、中国に馬鹿にされ、うつ病患者を増やし、ブラック企業を生んでいる社会を構成している訳ですね。絶対に揺り戻しが始まるのが、自然の論理ですよ。その現象が「倍返し」の流行語を生んだのです。残念ながら、核となるダヴィンチには投資が出来ません。故に、二番手銘柄のケネディクスをターゲットに選んだ次第です。幸い、ケネディクスは、米国金融を駆使した不動産投資会社です。レバレッジを掛けており、効率的な資産運用を行っています。
此処までは前座です。さてここから、ケネディクスと言う会社の解剖を始めます。不動産会社の収益源は何か? 不動産の組成から管理、運営、そうしてキャピタルゲイン、つまり値上がり益ですね。証券会社の仕組みに似ています。証券会社は株ですが、不動産会社は土地ですね。此処でマジックが存在します。不動産とは一般認識では自前のお金で100%分を持つ事と考えている人が多いでしょうが…違いますね。森ビルの創設者の森泰吉郎氏は平成5年になくなりましたが、彼が一代で、あの財産を作ったのはレバレッジを活用したからです。親父さんは港区で米屋と僅かな貸家業を営んでいたのですが、転機は戦後の預金封鎖でした。その直前にどういう情報網があったのか知りませんが、預金の引き出した成功しそのお金をレーヨンに投資して成功したのです。その成果を、今度は全て、虎の門周辺の土地にぶっこんだのが始まりでしたね。今回も危なかったのです。ギリギリのところまで追い込まれました。初代の金子さんは沈み、二代目の森さんは生き延びる。
もともと、金融レバレッジの仕組みを使えば、5%の利回り採算なら、およそ4倍の20%程度の利回りは確保できるのです。これが不動産の運用管理から上がる利益です。そうして一番おいしいのはキャピタルゲインですね。カタルがこれから起こると予測している2400兆円の奪回です。実は不動産会社の儲けは、このキャピタルゲインの方が大きいのですね。だから受託資産規模が問題になります。自分達の決定権が活きる、縄張りと言うか…勢力範囲をどれだけ持っているかが、これからの利益のタカを決めるのです。ケネディクスの投資で注目すべきは、この受託資産規模なのです。
この受託資産はリートや私募債ファンドで構成されており、ファンドを直接、買った投資した人がキャピタルゲインも享受できるんじゃないの? だからケネディクスは持っている土地も少ないし…カタルの倫理は違うんじゃない?と、多くの人は思いますが…、貴方の持っているリートが、何処のビルを所有していて、その取得価格などの情報をいちいち調べますか? 多くの投資家は配当利回りや純資産程度しか見ませんね。此処にマジックがあります。だから不動産価格が2倍になると、30%程度が何らかの理由で、利益を搾取するのでしょう。もともとエクイティー部分を、自ら10%、20%と握っていることもあるでしょう。故にカタルの目安は、おそらく30%と睨んでいます。
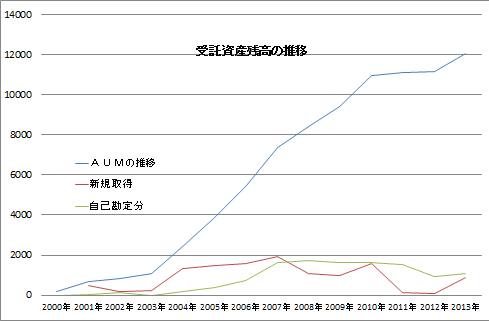
今期の決算でケネディクスの負の遺産は、おそらく後処理を完了したのでしょう。負の遺産と言うのは、高値で買った2007年、2008年の不動産価格と、時価との差額ですね。既に2009年からの3年程度は減損処理に追われ、新規の物件取得などのユトリはなかったですからね。それでもケネディクスは受託資産残高を伸ばしているから立派です。ダヴィンチなどの同業の躓きもあり、シェアが伸ばせたのでしょう。その受託資産残高の推移が、此方のグラフです。2007年以降、受託資産残高の伸びが悪くなります。そうして、一旦、回復傾向になりますが。2011年、2012年と再び落ち込みますね。この過程でダヴィンチがパンクします。過剰な金融庁の独自認識の押し付けが、信用創造機能回復を拒んでいます。だからドイツ銀行のレポートが生まれる背景があります。
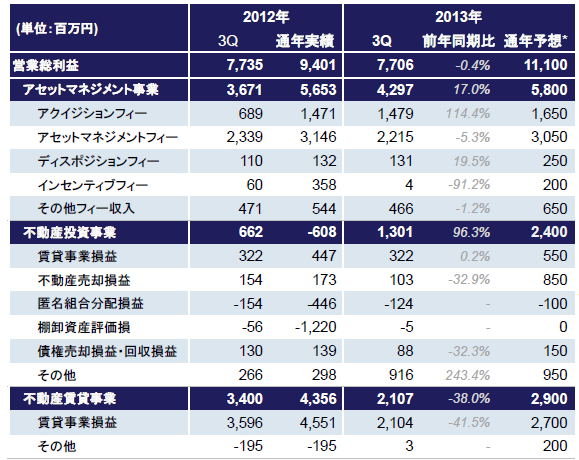
さて受託資産が元になりケネディクスの会社の業績が決まっていきます。ここで3Qの会社説明会資料から収益構造を考えてみましょう。現状のアセットマネジメント事業のアセットマネジメントフィーは、受託資産規模が増えれば増えるほど、増える不動産の運用管理による報酬で、安定化して増えて行きます。アクイジションフィーと言うのは、不動産の取得価格に対する所得報酬です。つまり不動産ファンドに組み入れる時に手数料を取り、運用しているときも、毎年、報酬を取り、そうして売却するとも手数料を抜くのですね。この売却の時に発生するのがディスポジションフィー(売却報酬)です。さらに、この売却報酬とは別に、インセンティブフィーと言う項目があり、当初予定する以上の想定外の高値で不動産が売れた時に生じる成功報酬制度もあります。今回の決算では売却に生じる業績数字高はほとんどありませんが、現状の受託資産残高は減損会計が強いられており、安値で評価されているとすれば、およそ2割の含み利益が発生していることは、容易に想像が付きますから、これから年を重ねるに従い、不動産のキャピタルゲインが得られることは容易に想像ができます。オリンピックが控え、開発が加速されますし、日銀を始め、政策筋は容積率の緩和などもスタートさせますからね。1兆2000億円は、まさに宝の山です。カタルが何故、自信を持って4桁から、最高値4000円の奪回を目指しているか?その背景がわかるかと思います。
それで四季報を見て下さい。先ずは需給面の解説です。春先の株価高騰で多くのヘッジファンドが利食いをしています。残存玉の整理もあるのでしょう。注目するのは、新規のファンドなどの介入があるかどうか…今回の移動で目を引くのは、ゴールドマンサックスが名前を連ねていますね。この8か月間の株価の保ち合いは、株主の手替わりによる移動の為に生じた時間なのでしょう。007の企業業績の読みは、契約内容は秘密だし突然の部品採用などもあり、予測が難しいのですが、ケネディクスの業績の読みは、世間の常識で容易に判断が付きます。受託資産の含み利益の読みなどは、実際の不動産市況の取引価格推移などを見れば、予測は可能です。ただ詳細に調べるには、かなりの時間と調査が必要で…お金が掛かる話です。だからアナリストは、先日のティファニービルの売却事例や長銀本社の売買、軍艦ビルの売買にメザニンローンが活用されたと言う事例などを参考に、現状を推察するわけですね。実にいい加減でしょう。
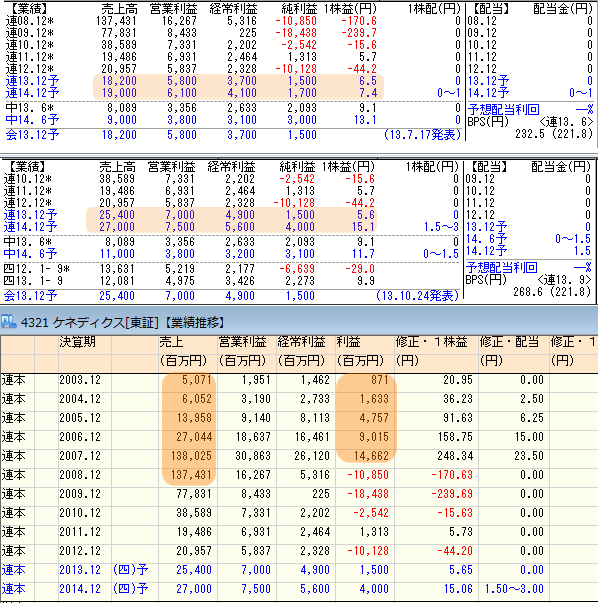
その四季報予想が劇的に変化しています。本当は実際の取引は年初から始まったのですよ。しかし数字に変化を及ぼすのがこの辺りから…、一般の認識に変化が生じ始めます。ほら、四季報第4集と、今回の新春号の数字と比較して見て下さい。直近の2013年12月予想の変化を…。3か月前の認識は、今期の売り上げが182億円で、営業利益は58億円、利息を加味した経常利益が37億円で、最終利益は15億円なのです。ところが今回の新春号では同じ決算期なのに、売り上げが254億になっており、営業利益は70億円で経常利益は49億円で、最終利益は変わらずの15億ですよ。おかしなマジックですね。12億の利益が何処かに消えていますね。これが利益の先送り分ですね。
更に、今回の四季報の2014年12月期の売り上げが、2013年に比べ、僅か16億円しか増えないと…四季報の編集者は読んでいますね。直近の金融緩和時代をまったく見ていませんね。2003年は50億だったのですが、2004年は60億円、そうして2005年は139億円になり、2006年は270億円で、ピークに近い時は1380億円も売り上げが大幅に増えます。この構図は不動産のキャピタルゲインが増えるからです。そうしてディスポジションフィーや、インセンティブフィーが大きく膨らむのです。だから最終利益が、前回は8億7百万円から17倍の146億62百万円に変化したのですね。今2013年は、前回の2004年近辺に発生した時代変化に位置しているのでしょう。おそらく2014年の売り上げ規模は、倍増の500億ラインと言う読みが自然でしょうね。四季報予想は、ある意味で間違って当然です。ケネディクスも、007同様に「見えない利益」の対立が背景にあり、強弱感が対立しやすい銘柄です。
仮に、本当に日本の土地資産が以前のピークである最高水準の2400兆円まで復帰するなら、何もせずに居ても、現在の受託資産規模の1兆2000億円は、5兆ほどまで膨らむのでしょう。首都圏周辺の利回り採算に合うビルはそれほど貴重な宝物なのですね。ケネディクスの多くは、首都圏の物件でオフィスビルなどが中心になっています。これに加え、PFIの概念からリートの変化と言う夢が加わりますから、この理念は我が国の財政状況から共有されますから、介護リートなどは膨らみ、ケネディクスの成長度が増しますね。見えない利益ばかりか、見えない成長度が、サスティナブル成長率も加味されるので、株価は4桁から4000円、場合によれば政策次第で1万円も可能になる夢があります。
最後は長くなり、端を折っての解説になりましたが、読者の方は、ご自身でカタルの原稿を元に自分自身で調べることをお奨めします。ドイツ銀行のレポートは、出遅れている日本投資を加速させますね。決算期が変化する来年は、ケネディクスの株価が走り出す年になります。だから仕掛けが入って、株価が走り出してからでも、充分に間に合います。僅かな値幅の鞘取りでは、自分のお金は増えません。大きく増やすにはリスクを取り、果敢に挑戦するわけです。
通常はレーヨンの投資で儲けたお金で、森さんのように六本木周辺の土地を買い漁るなんてしませんね。成功に胡坐をかくのでしょう。孫さんもソフトバンクの成功だけで…普通の人間ならスプリントの買収などしませんよ。事実、NTTはグローバル展開を積極的にしていませんし、新日鉄も最近グローバル展開を始めましたが、遊びの程度で小さいですね。しかし理念は人を動かします。故にスプリントの買収だけに留まらず、米国トップのベライゾンに対抗するために、Tモバイルの買収まで、アリババを原資にして孫さんは取り組むのでしょう。AT&Tでは独禁法が足かせになりましたが、スプリントとでは、仮に合併が実現しても、AT&Tの売上高にも及ばず、おそらく合併が認められるでしょう。面白いグローバル時代になってきましたね。日本企業を総体的に元気にするために、信用創造機能の復活は、絶対に必要条件のパーツです。続々と退職する団塊の世代の未来のインフラ整備には、介護リートの実現は必要不可欠です。
お金は溜める事ではなく、活かす事で価値が生まれるのですね。澱んだ日本の金融市場の水を浄化させ、魚が活発に行動できるような環境を整備することが…政策官僚の役目の筈です。金融庁の幹部さん、違いますか? 若い人の行動を阻害するのではなく、後押しできる政策を、是非に実現してほしいものです。容積率を上げれば付加価値が生まれます。様々な規制を撤廃すれば、外人資本は大挙して日本の不動産に参入しますね。ゴールドマンサックスが、ケネディクスの株主に登場したのは、その期待なのかもしれません。未来は誰も分からないから、強弱感が対立し大相場が生まれるのでしょう。
投稿者 kataru : 12:45
2013年12月08日
市場原理
市場経済って…一体どんな仕組みなのでしょう。
戦後、多くの識者と呼ばれる人達が、社会主義に魅了された時代があります。日本の歴史を考えれば社会主義の形態が理想的な社会に見えます。しかし東西冷戦の崩壊は、その理想が破れた現実を示しています。イラクのフセイン政権崩壊からの再生過程をみると、理想を貫いたはずですが、混乱は続き安定は容易ではないですね。一つのパワーバランスを歪めると、混乱は周辺国へ波及し「アラブの春」が、本当に美化されるべきなのかどうか…。現在のシリアの混乱なども、イラク崩壊の影響が大きいのでしょう。「自由と平等」のお題目が、何故か霞んで見えます。日本は、この「自由で平等」な社会環境が確立されていると一般的には考えられていますが、恣意的な報道形態、1票の格差問題など考えると…分からなくなりますね。歪んだ妥協の産物がコメ問題に集約されています。
EUの誕生からTPP問題も、明らかにグローバル論理で、国際会計基準の確立からIFRS採用の企業も増え始め、BIS規制からバーゼル3の流れも地球連邦の方向性を示しています。先日、触れたハレーすい星の探査衛星協力が東西冷戦の崩壊に繋がった流れ、現在の国際宇宙ステーションの誕生なども時代の流れの一環なのでしょう。
1989年からの株価崩壊を考えると…、歪みを取り繕ってきた日本村の見せかけの形態がどんどん崩壊し、グローバル基準に集約されています。日本株の水準は、国際基準に収斂されました。バブル期、高いPERなどを肯定するために、様々な仮説が語られてきましたが、結局はグローバル基準に収斂されましたね。株式持ち合いなどは、野村証券を中心とする官僚論理が生んだ副産物だったのでしょう。「失われた時代」と言うのは、この日本村論理から脱皮する時間だったのですね。
昨日は企業業績と株価の基本的な考え方を述べました。市場には「潮流」があります。この流れを見極め、この流れの本流に付くのが、筋論なのでしょう。企業業績の源は、時代の流れが生んだ利潤なのですね。スマフォの誕生は2007年1月に、アップルがアイフォンを最初に発表し6月から米国で売り出されますが、2004年には構想が練られ、開発されていたと言います。そうしてグーグルがアンドロイドを発表するのは2007年11月です。この端末が発売されるのは2008年10月ですね。着想段階から見れば、既に10年近い歳月が流れていますが、一般化してから、僅かに5年程度しか経ってないわけです。携帯端末の誕生は、革新を世界に与えています。アリババのネット通販が、たった1日で、いくらセールとは言え5700億円ですからね。TSMCやサムソンの設備投資金額は、今では兆円単位の段階になっているのです。日本で何社の企業が、このグローバル競争を勝ち抜くことが出来るのでしょうか? この考え方が古いかもしれませんね。日本で…と言う発想が貧困な源かもしれません。
市場原理は、儲かるものに資金を集中させる仕組みで、投資家の夢、人類の夢を実現させるために資金を提供する場です。だから本来は割安株投資をする場ではないのです。配当利回りなどの安全を求めるなら、銀行預金や債券投資をすべきなのでしょう。市場には様々なリスクレベルの商品が用意されています。CDSなどの開発は、博打を増長させる仕組みですね。5年以内にトヨタが倒産すると考える人は、おそらく居ないでしょう。そのようなパッケージ商品を開発し、その中にBBBランクの企業を数社混ぜ、パッケージとして販売するわけですね。色んなリスクバランスの商品を提供することで、危険とされる融資や投資が起り、新興国の発展が促進されました。この博打に成功したなら高いリターンが得られるわけです。
昨日のリポートの中で、カタルは非常に重要な文言を盛り込んだのですが、お気づきの読者は居られたでしょうか? トヨタなどの企業業績のいい優良企業を買うのが、株式投資ではないのですね。常に高い「変化率」を追い求めるのが株式投資の神髄なのです。カタルはこの事を理解するまでに、どれだけの時間が掛かり、多くの資金を飛ばしてきたか…。この神髄を理解されれば、かなりのレベルにまで、自分の投資技術を高める事が出来ます。カタルはこの変化の大きな企業ばかり追っている為に、数々の失敗もしてきました。市場はある意味で、公正で公平なのです。だから誰にでもチャンスはありますね。自分がどのレベルのリスクを共有できるかでリターンも決まる訳です。だから投資家それぞれが、独自の判断で、自分のリスク許容度と闘う訳ですね。
投稿者 kataru : 12:39
2013年12月01日
リベンジ
今日のテーマは「グローバル化」と言う話に触れたいと思います。昨日も話したように…日本企業はようやく目覚めたようにも感じるのです。1985年のプラザ合意の辺りから、時代はファブレス化(生産設備を持たない)している訳です。つまり新興国の躍進ですね。先進国から新興国への技術移転の始まりです。アップルなどは代表事例でしょう。この時期1987年に台湾のTSMCが設立され、1984年にサムスン電子は米国マイクロンより技術支援を受け、その後、1986年の東芝に始まり1991年のバブル崩壊で日本企業がリストラするのを受け、韓国政府の支援を受けながらサムスンは日本人技術者のヘッドハンティングに乗り出しました。日本の曲がり角は、このプラザ合意の時代変化に、官僚組織が中央集権型の日本村論理に拘る余り、政策の主眼を見誤ったことに「失われた時代」は起因しているのでしょう。
最近の相場を観ていて、日本を脱出している企業の活躍が目立つように感じています。日経平均先物指数先行の動きから、指数への寄与率の高い銘柄が物色される背景もあるのでしょうが、海外展開を加速している企業の物色にも見えるのですね。そこで昨日かな? LIXILGや日本板硝子の話を掲げましたし、最近、海外展開を加速し始めたニトリなども関心を抱かせる銘柄です。このシナリオの延長線を探る思考パターン下に、カタルは置かれている訳です。こんな心理状態のところで、先週の人気株を調べていたら「古河電工」が登場していたのですね。実はこの銘柄は、色んな思い入れがあるのです。隣の浜ちゃんが、大ヤラレする銘柄なのですね。ITバブルの時に一緒に上昇した人気株ですが、光通信やソフトバンクは2月に崩れましたが、古河電工も一旦は同じように連れ安しますが、その後株価は戻し高値を更新したのです。その年の夏に付けた高値の動きは凄かったですね。それで隣の浜ちゃんが値惚れで、1000円割れ辺りからだったか…買い始めたのかな?それがなかなか止まらずに、下がる、下がる。最終的には200円台ですからね。
丁度、この時期の2001年11月に古河電工は、ルーセント・テクノロジーの光ファイバー部門(OFS)を買収するのです。当時、27億5000万ドルでしたかね。日本円で3400億とか…。この馬鹿高値での買収が後々尾を引き古河電工は苦しみ続け、もう直ぐ構造改革が終了するのでしょう。来年の注目企業の一つとなるのでしょう。日本板硝子と共に、何故か、気になる存在なので決算書などを眺めていたのです。
日本企業はM&Aに於いて、過去、数々の失敗を経験しています。松下(パナソニック)などは良い事例でしょう。今回は三洋電機の電池部門に着目した狙いもあるのでしょうが、明らかに、この買収は失敗のように見えます。過去にMCA(ユニバーサル・スタジオ)と言う映画の会社を買って多額の損失を計上していますね。この時はソニーと競っていました。タブレット端末が低価格で一般化され、やはり映画や音楽のソフト資産の活用をソニーが中心になり、アマゾンなんかと共に協業すれば…まだ覇権を握るチャンスはあると思いますが、なかなかソニーは、このソフト資産の再構築に動きませんね。水面下では色んな動きはあるのでしょうが、アジアの通信インフラを手にする企業は何処になるのでしょう。もしソフトバンクが早期に米国市場で成果を上げる事が出来るなら…更に期待できますね。カタルは米国より人口の多いアジアを優先すると考えていましたが、孫さんの考え方は違いましたね。トップ争いの王道に進んだ印象です。
今日はヒントだけなので原稿は簡単にしますが、第一三共のランバクシー・ラボラトリーズ社の買収を始め、野村証券のリーマンや日本板硝子のピルキントン、古くはこの古河電工のルーセント・テクノロジーの子会社であるOFSの買収など…失敗が続くM&Aですが…グローバル化の推進と言う観点から、一度は失敗した投資が、再び輝きを取り戻る可能性はないのでしょうか? 先週の人気株リストの登場した古河電工の姿は、何故か、新鮮に感じるのですね。あれから10年以上が経過し失敗も完全に消化したのでしょう。
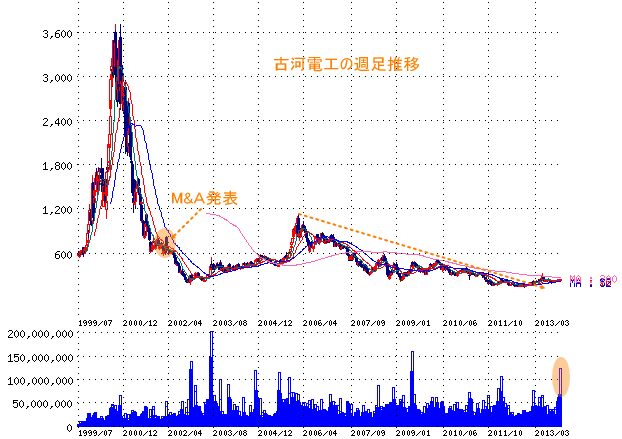
投稿者 kataru : 13:15