« 2011年12月 | メイン | 2012年02月 »
2012年01月29日
ユーロ安の想定
考えてみると…この2週間の日経平均の上昇はかなり強いのだけれど、やはりアルゴリズムの関連で動いている可能性は否定できませんね。一つは最近、連動性の高いユーロと日本株の組み合わせです。ユーロが安くなると日本株も売られるポジションですね。奇妙にもこの2週間程度の動きはユーロ高、日本株高となっています。
僕には不思議なのです。一気に50兆円ほどの資金供給をECBが実施したので、当然、需給バランスが崩れユーロの全面安になる筈だと思いました。FRBは緩和姿勢を続けておりドルがだぶついています。日本も緩和はしていますが、ドルの供給量の方が圧倒的に多いから円高傾向が続くのでしょう。為替の変動には、貿易収支、経常収支、金利平価説など…色んな説がありますが、私は基本的に需給バランスなのだろうと考えています。
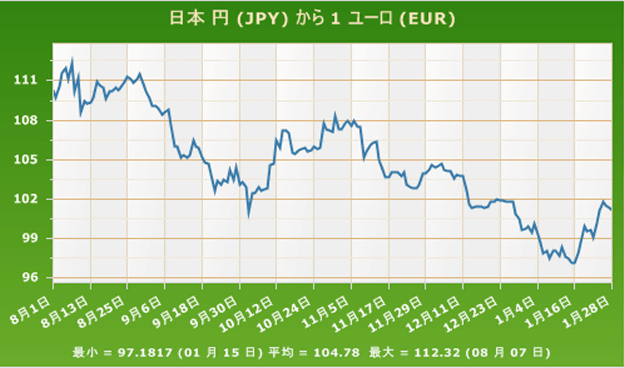
だからECBの大量供給を見て一気に100円を割り込むユーロ安は、なるほど…理屈通りだと考えていました。ところが1月半ばに突っ込んだ後で、一気に反転しました。この理由が見えなかったのですね。一気に102円近辺まで買われましたね。その後、現在は101円前後です。この戻しは乖離調整もあるのでしょうが…どうもECBの供給資金が眠っているからではないでしょうか? 資金提供を受けた銀行は、国債を買う利ザヤ取引をするところもあるようですが、ECBの翌日物預金の残高が急激に増えたのですね。つまりECBが折角、資金供給しても、資金が再び戻っているわけで緩和効果が打ち消されており市場に資金が投入されていません。だからユーロは大きく売られないのかもしれないのですね。
当初、50兆円もの大量投入なので、一気にユーロ安が生まれ、場合によればドルと同じ水準の80円程度まであるのかな?とも考えていました。だって12月に50兆、2月に50兆だとすれば、大量の資金がタブ付きますからね。イタリア国債はそんなに発行されませんし運用先もないですね。最近の欧州国債の堅調さはECBの行動の成果でしょう。ここでFRBとECBが違うのは、自らリスクを取りFRBは国債を買い入れ、市場に資金をばら撒いていますが、ECBはワンクッション入れ銀行を通じています。リスクを銀行に負わせているわけですね。
次第に欧州の銀行は鞘取りを増やすでしょう。だってECBの供給金利は安いし期間も3年物と長く、投資した国債を担保に取る訳で、その利鞘だけが銀行の利益になります。この利ザヤはリスク負担料金ですね。労せず利益が約束されるから、銀行は大量の資金をECBから受け、国債投資すればいいわけですね。おそらくジリジリと…、再びユーロ安の局面になり、株価は調整を続けるのかな?…と言うのがメインの考え方。ただ2月の資金提供は大きく伸びないのでしょう。よってその時点で別の流れに変わりますね。
おそらく…。これと同時にFRBのインフレ・ターゲット論が存在するわけで、此方は株高の方向性です。一番の注目点は資産価格の動向が気になりますね。株はともかく住宅価格ですね。乖離調整が済み次第に供給量が増え、再びユーロ安に戻る。しかし2月末のユーロの供給は大きく伸びないから、FRBのターゲット論がやがて市場の信認を得るのでしょう。これが今のシナリオですね。よって再び、強くない調整が1か月程度は続き、ECBの供給額を確認したら、株は力強く上昇する。イメージかな?
なんて…このように当たらない仮説を打ち立てて、明日から行動するわけですね。そうしてまた違う現象が市場で現れれば、自分の考え方を市場に合わせ修正するわけです。事前に自分なりの相場観を打ち立てて、その仮説を元に実験を繰り返していますが、成果が生まれるまで繰り返すのですね。既にカタル君の実力は、健全な…と言うか、強気の上昇相場の環境下では、おそらく投資だけで、飯が食える水準だろうと考えますが…。今のような市場参加者が少ない低迷相場では、損をする側に回り、食えないのですね。何しろ空売りをしないわけですから、駄目な訳ですよ。それで何とか…嫌でも飯が食える方針に転換せねばなりません。本当は僕の意地を通したいのです。でも家族が居ますからね。株屋を辞めた時に、空売りを考えていましたが…やはりできなかったけれど。もう一度だね。
野田さんの気持ちはよく分かりますが、誤魔化すような発言は頂けませんね。あのような発言をしないと政治は運営できないのでしょうが…、僕には合わないかな?選択は間違っていませんが、表現のプロセスにシックリ来ないものを感じます。石原さんが新党構想か…年寄りは後進に道を譲りバックで動くべきだと考えますが、亀井さんも裏方に徹すれば良いのに…。橋下さんは、どう動くのでしょうかね? 国政に参加せずに、先ずは大阪市での実績を創り上げれば、自然に流れは爆発すると思うが…。それにしても米国FRBのインフレ・ターゲット論は羨ましいな。
投稿者 kataru : 14:29
2012年01月22日
呆れる自民党
米国では共和党選挙が行われ穏健派のロムニー氏が、保守派のキングリッチ氏に破れたと報道されているようです。何故か、パッとしない共和党候補のイメージを抱いておりオバマの清貧思想は嫌いだけれど…共和党も人が居ないような気がします。でもこのように全国の地域で選挙を行い、政治家も鍛えられ成長するのかもしれません。ロムニーは前回も大統領候補者で、討論会で失敗して敗北したのですよね。たしか…。民主主義の概念が正しいのはどうか…本当は優秀な独裁政治が正しいと思いますが…。
日本の首相も公選にすべきでしょう。国民投票にすればもっと力強い内閣になると思います。議員が選ぶから駆け引きの道具になり歪むのでしょう。それにしても民主党は、なかなかいい線を行っているように感じます。岡田さんが副総理になってからの対応と言うか…流れは嫌いじゃありません。野田政権に移行してから今の所は失敗の選択はないように思います。それに引き替え愛する自民党の凋落は哀しい現実です。党大会の席上で、「民主党は公約違反だから政権奪回」と述べた谷垣氏の発言に、日本国民の姿はないようです。
今日は自民党に意見メールを出しました。皆さんも是非参加してください。僕の書いたメールは下記のようなものです。意見メールはこちらから簡単にできます。是非参加して流れを変えましょう。
『私は本来、自民党の支持者です。友人も多く参加しています。しかし野党になってからの自民党の姿勢にはがっかりしています。自公民の政権時代の失政が、今日の日本の姿を作っている訳で、少なくとも自民党は、嘗て政権政党として消費税の引き上げを主張していたわけです。それを民主党の公約違反だから、国民の真意を問うために選挙に持ち込もうとする姿勢が、今までの野党時代の民主党と同じで、政争の具にしています。なんだか日本のことは別に次元にあり、政権を担う事だけが自民党の主眼に見えますね。本当に国民生活を思っているなら、話し合いに参加し責任ある態度を示し、自分たちは何時でも政権を奪回できる責任ある政党だと言う態度を示すべきでしょう。』
このような長い低迷時代が続けば、人間の心も歪むようです。その現象がこちらのグラフですね。本日の日経新聞に取り上げられていました。少し解説した方が素人の人には分かりやすいでしょうから…通常の経済状態や市場なら、こんな逆転現象は生まれませんね。何故なら、過去、最高利益を更新すると言うことは高いPERで買われるはずなのです。少なくとも平均値を上回る現象を示します。ところがアルゴリズムが主流になり、システム売買が主軸になっているから、相対論で株価を判断するわけですね。過去の株価や全体の株価の動きでプログラムが発動されます。ここには業績を考慮してないものが大半です。だからこのような異常な現象が生まれます。
だって、常識的に考えれば、過去の利益を更新し成長している会社が、市場から評価されるのが当たり前ですね。ところがこのデータはそれを否定しています。本来の姿は逆転し1以上になる姿が、市場原理が正常に働く姿の筈ですね。政治の低迷が社会の混乱を招き、歪む社会現象を生んでいる一例ですね。是非、みなさんも意見メールを出してください。
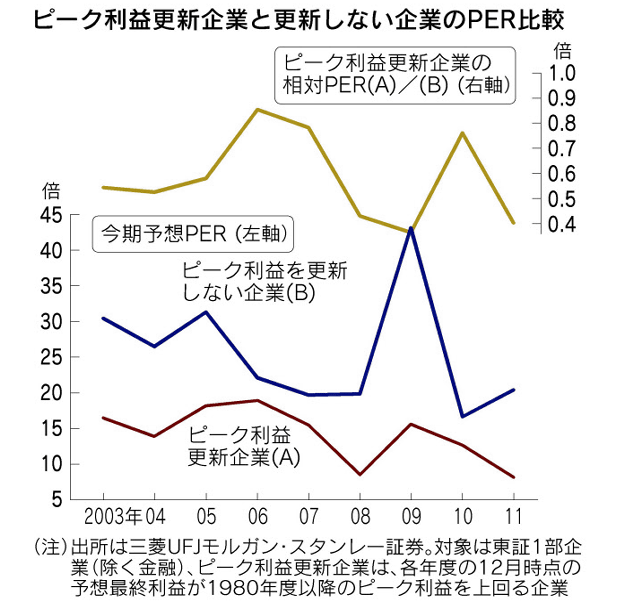
投稿者 kataru : 13:13
2012年01月15日
相場の選択
日本が太平洋戦争にやもえず突入する背景に、今日行われているイランへの制裁と同じ背景がありますね。世界の政治力学に翻弄され、対米敵視になっていく過程を思うとイランの感情が分かる気がします。詳しくは此方を読むと良いかな? 田中さんは最後にブレジンスキーの事に触れられており可能性がありそうな話です。
最近は、先日シーナ・アイエンガー教授の話を聞いてから、選択と結果について考えるようになっています。「トリレンマ」と言う好ましくない選択肢から、選ぶことしかできない屈辱を感じていることが多い結果、選択と結果について考えるようになりました。イランの状況はまさにその事例でしょう。
軍事予算の関係から米国はアジア太平洋地域での配置を優先的に考慮し、当該地域にある盟友の需要を満たして、各種挑戦に対応していく考えであることを示しましたが、この1極主義を覆すホルムズ海峡の緊張状態は呆れるばかり。中国にしたら、国益を考えイランを支持し彼らを煽る方が得ですね。その中国の傀儡政権と言えるのかどうかわかりませんが、台湾では国民党の馬英九総統が辛うじて再選されました。689万対609万と拮抗していました。
フィッチの発言の後でS&Pがフランス国債の引き下げを敢行し、市場の動向が注目されますね。台湾の選挙の影響からエルピーダやエレクトロンが注目され、日本の枝野さんが再任され東電の行方が焦点になり、全体の相場環境はS&Pの引き下げで影響を受け、今週は見所が満載です。
昨日は市場経済に触れましたが、このように考え方の違いが市場でぶつかり合い、市場の動向が人々の選択肢を変えていくわけです。米国内にもイランの対する扱い方をどうするか揉めるわけですね。イスラエルを中心とするネオコンの力は相変わらず強いですね。僕らが触れてきた学習では、なかなかグローバル化の交渉に耐えられないのでしょう。僕は滅多に外人の書いた本を読んだことはありませんが、最近読んだ「空の都の神々は」N・Kジェミシンのなかで主人公のイェイナは母親からの言葉を反芻する場面が出てきますが、代々「生きる術」を伝える伝統には敵いませんね。
近代史の検証もしない日本は、失敗を繰り返す、学習しない国民に成り下がっています。今日の日経新聞に乃木希典大将の自責の念を綴る手紙が発見されたとか…。明治天皇の崩御と共に殉死した彼の失敗と責任の取り方が、武士道を感じさせ共感を覚えます。似たような気持ちを抱いた宮沢喜一も、自分の犯した失政を悔いたのでしょう。
もっと僕ら国民は、歴史を正しく学習し自分なりに考えないとなりませんね。目先の報道姿勢を繰り返すメディアとの関係を見直すべきでしょう。
投稿者 kataru : 10:41
2012年01月09日
村田メールか…
今日の話題の中で…関心を持ったのはJBPRESSの記事で、村田メールへの反論です。
『官僚には、未来に向かって、斬新な方法を考え出して、危機的状況を突破する能力は、原理的に期待できません。日本中で、活力を持った個人が、知恵を振り絞って、様々なことを試みなければなりません。めったにないであろう成功体験を、日本中で共有しなければなりません。活力のある個人の活動は、社会を大きく変えます。未来のスティーブ・ジョブズ(アップル)、ビル・ゲイツ(マイクロソフト)、ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリン(グーグル)が活動を開始した時に、彼らの活動を抑圧してはならないのです。』というくだりかな?
この村田メールと言うのは、南相馬市の市長に宛てた南相馬市立総合病院の非常勤医師、坪倉医師(26)が送ったメールに対する村田副市長(37)からの返信ですね。要約すると、坪倉医師は給食のセシウム検査が必要だと市長に進言したが、総務省から出向している村田副市長が、市長に要望するには、しかるべき筋を通せとの返信が、高飛車に書かれているので問題化しているようです。これを読んで2006年のライブドアの選択で、もしホリエモンを叩かなかったら、もっと日本は違った世界になっていたんじゃないか?…と言う僕の思い込みを再確認したのですね。
総務省からの出向役人の村田さんはエリートですね。そろそろ官僚色に染まり、権力を自分の力だと勘違いする年齢でしょう。それに引き替え坪倉医師は正義感の強いタイプなのかな? 橋下大阪市長が組合を相手に戦う構図と似ています。予算が膨れ上がる民主党。18歳未満の医療費無料化を求める福島知事と汚染物の中間貯蔵施設を求める政府か…。更に言うなら、使途が不明確な沖縄の2936億円の沖縄振興一括交付金と、普天間基地移転の環境影響評価書の扱いが、引き換えになっている現実ですね。結局、何処もお金のやり取りの話で、ゴネている様に感じます。ここには国家論はないのですね。目先の利益だけの話ですね。だから米国にもティーパーティーが生まれ、小さな政府に賛同する人が増えるのです。強制的に総予算を30%程度削減すると…どんな世界になるのでしょう。
人生を振り返って…失敗した選択を反省する日々は続きます。自分の親を超えることが出来ない時代になったのでしょうかね? 株式相場を見ていると…人生の縮図のようにも感じます。個別株がどんなに優れていても…全体が沈む時は輝きを失い、相対的に沈んでいきます。現状維持が出来ればいい方で、一般的な対策に留まる株、会社は株価が半値以下に下がる時代ですね。パナソニックはその象徴的な事例です。多少優れている日立も沈んでいますね。結局、国家の行方が大切なのですね。心ある人は国を離れ海外へ移住します。
不良債権処理と言う、後ろ向きの処理に嫌気がさして中国に逃げた若者も居ましたね。直木賞をもらった池井戸潤さんの世界ですね。彼の年代はその時代です。これがグローバル化と呼ばれる現象なのでしょうね。どんなに逆らってみても激流の流れに逆らうことはできません。ただ僕は諦めきれずに努力をしているのです。まるで馬鹿を絵に描いたような生き方だな。
投稿者 kataru : 11:30
2012年01月08日
今年の動き
今年の株式市場はやはり高くなりますね。
ひょっとすれば、本格的な上昇に向かっても不思議ではないですが…それは今の所、分かりません。「失われた時代」は過去の清算に時間をかけたためだと思います。基本的に日本は内外障壁を高くして日本の雇用を守りグローバル化を阻止して輸出を伸ばしてきました。この背景は東西冷戦があったために、世界の基準国家である米国の庇護があったので達成されました。ところが米国は1985年のプラザ合意でこの関係を断ち切ろうとしました。そこにベルリンの壁崩壊ですね。日本はグローバル化の中に放り込まれます。ところが我が国はそれまでの成功体験から抜け出せず、また抜け出そうともせずに抵抗しますね。(まるでトヨタの戦略です。)これが既得権力者たちの抵抗です。その極みが2006年に様々な現象として顕著に現れました。政治の世界では「八ッ場ダム」や「諫早湾などの干拓事業」などは象徴的な事例でしょう。
私は昨年から、日本も変わり始めたな?…と、感じています。金融危機後にドルの流動性供給で円高になり、いまはECBの資金供給で、ユーロに対しても円高が進んでいます。だからFXをしている人はユーロ売りの円買いが目先は正しい姿勢なのでしょう。何故なら昨日述べたように、2月末もECBの大量の流動性供給が予想されています。FRBは管理しながら資金供給し毎月実施しましたが、ECBは民間の要望に応じていますから、一気に進む可能性があります。だからユーロ安が加速しても驚きません。FRBの例から見ればユーロが80円程度まで売られても別に不思議ではないのでしょう。まぁ、ECB次第です。自ら資金供給すれば無駄なブレは防げるでしょう。ドラギ総裁は市場原理派のような危険な考え方なのかな?本来はECBが自ら問題国債の買い入れを実施した方がよかったようにも感じます。
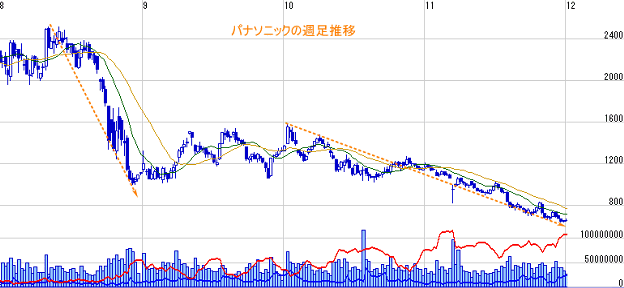
余談になりましたが、何故、明るい兆しを感じているかと言えば、一例を掲げると松下(パナソニック)ですね。まだ株価は反応しておりませんが、組織力を動かそうと努力していますね。この株価推移をみると日本経済全体の動きを示しています。トヨタも日産に比べグローバル化が遅れましたね。中国アレルギーがあるらしく、大きく出遅れました。代わって失敗の反省からか?インドは積極投資し始めていますね。しかし嘗ての歴史上、中国は覇権国だったのですね。日本の貿易数字を見れば輸出入ともに米国を抜いています。当然、日本は中国寄りに舵を切るべきなのでしょう。この辺、野田内閣は下手ですね。TPPに参加した影響もあるのかもしれませんが、米国は軍事予算削減の為に中国に的を絞りましたね。でも日本は天秤にかけた方が得だと思います。
野田内閣は米国の要望通りに、航空自衛隊の次期主力戦闘機(FX)に、第5世代ステルス戦闘機「F35」を選定しました。この事実は日本がアジアの非公式の連合航空隊の一員になれる可能性があり、すなわち米国やオーストラリア、韓国と同じ戦闘機を有することになり、それら国々とより緊密な協力が可能になったことを示しています。この辺は日本の親米派の勝利ですね。小沢さんなら、別の選択をしたかもしれませんね。TPPではなくて日本・韓国・中国のFTAと言う選択もあったはずですね。中国を中心とする東アジア戦略の方が自然な動きのようにも思いますが…現時点では、どちらが正しいか、難しい選択ですね。ただ欧米の中央銀行が流動性を大量に供給しているから、日本は選択肢が増えますね。
最近、官僚が取り組んだ政策の中でヒットがあります。しかし、メディアはあまり評価していません。でも昨年8月に財務省が行った「円高対応緊急ファシリティ」は素晴らしい政策です。もっと大規模に実施すべきですね。1000億ドルと言わずに日銀と組んで短期国債を日銀に引き受けさせて50兆円規模で実施すべきでしょう。規模が小さすぎます。でもあのアイディアが後押しをして日本企業はグローバル化に拍車をかけています。一方、震災復興の流れが単なる復旧ではなく復興に重点を移すべきですね。菅内閣は盛んにその事を言っていましたが、今の所、目に見えて実現されていません。折角のチャンスが無駄にならねば、いいのですが…。
震災復興は90年代に行った公共事業と同じなのですね。次世代の産業を育てる点に主眼を移すのです。細かい点まで指摘すれば、全ての都市はLED照明しか使わせないとか…。スマートグリッドを導入し、太陽光発電を地域で整備するとか…。色んな実験が考えられます。是非、行ってほしいのが電子マネーの普及です。端末機に補助金を付けて、全ての商店に導入させて税務署組織まで広範囲に情報を一本化します。更に重要な交通の要所や繁華街に監視カメラを導入しセキュリティー対策も完備させます。警察庁のNシステムもすばらしい仕組みで、復興都市に予算を組んで実現させてほしいものです。
グローバル化と内需振興の両輪が動くことになりますね。
東アジアへの予算の重点配備を実施して、情報のデファクト・スタンダードを握ることですね。本当はソフトバンクに期待したが…荷が重いかな?…やはり国家レベルでしょうか? 目先の株価は下げて、欧州危機も炎上しているように見えるから、多くの人は不安でしょうが私はいろんな点で明るさを感じています。まだほんの走りですね。その意味で誰もが期待している大阪市長の橋下さんに、私も期待をかけていますね。だから2012年は明るいな…と漠然と考えています。私の予想が正しいなら…と言うより皆が理想通りに動けば、3月頃から新しい兆しが台頭する筈ですね。果たして今年はどんな年になるでしょう。
私自身は、上記のような期待もありますが…自分なりに努力し、どんな変化にも対応できるようになりたいと考えています。
投稿者 kataru : 13:03
2012年01月03日
昨年の反省3
昨日の続きです。
実は日立の動き(トレンド系)とRSIの動き(オシレーター系)が逆相関しているのですね。通常RSIは値上がり幅を分子にして値上がり幅と値下がり幅の合計で割るので、値上がりの割合が高くなればRSIは上向くのに何故か株価は下降トレンド形成していました。こんなことがあるんですね。下げる時は一気に下げて上げはチビチビ上がるときのパターンなのでしょうか? 期間が短いから誤差が生まれるのかもしれませんね。余りテクニカル分析を研究してこなかったカタル君。実はチャートを意図的に作る現場を見て、あまり信じなくなった経過があります。仕手系のグループは形を形成するために無理やり株価を動かしますからね。その影響かもしれません。
最近はアルゴリズムを用いたテクニカルのシステム売買が増えているから、テクニカル指標の分析も有効かもしれませんね。そこでRSIに注目しました。RSIとは、アメリカのテクニカル・アナリストのJ.W.ワイルダーによって考案されたオシレーター系のテクニカル分析指標だそうです。
原理は簡単です。14日間の値上がり幅Aを、この値上がり幅と14日間の値下がり幅Bの合計で割った数字ですね。A/(A+B)つまり人間心理に沿って考えられたオシレーター系の指標ですね。何故かと言えば、上がる日が多ければ人間心理は好転します。検索してみたら…奇妙なことに気付きました。日経平均ダウだけ見ていると見逃しますが、多くの銘柄が11月末から好転しトレンド変化しているように感じます。代表例は花王やエーザイ等です。どちらかと言えばディフェンシブな銘柄が並んでいますね。つまり先日の海運株と同じで叩くだけ叩き、売り物が切れた動きなのではないでしょうか?
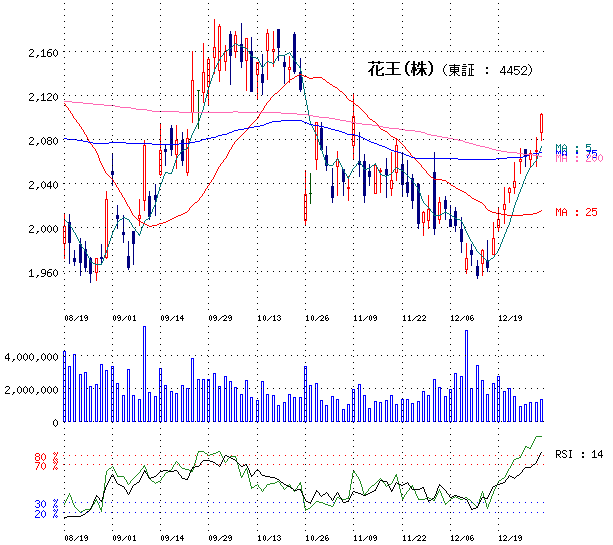
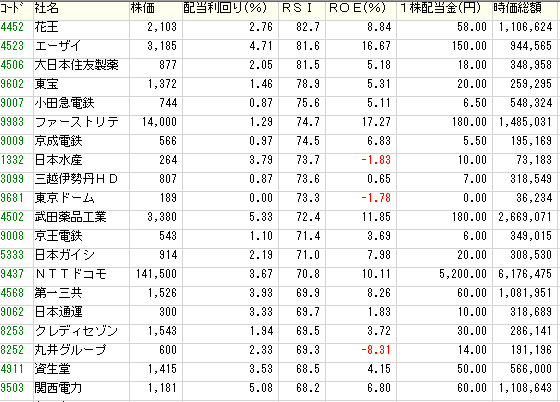
国内首位の花王は人口の多いアジアの消費を狙い積極化すれば業績は伸びるでしょうからね。ただ割安じゃないですね。既にかなりの高評価です。リスト上位のガイシは先日NAS電池で損失を計上し叩きましたね。要するに叩いた銘柄が浮上していただけの話ですが…相場の環境が好転しているのでしょう。外人の売りは11月末で切れていると思われますね。
アルゴリズムを用いた投資方法で成功している例は多く、NY市場も主要な売買手法になっています。これを利用しない手はないですね。本当にRSIが正しいとすれば最近の株価は奇妙です。日経平均株価を例にして一般的な14日、25日、75日のグラフを作ってみました。通常、期間を伸ばせば騙しのトレンドが減り正確性が増しますが、機動性に欠けるようになります。どう考えても日経平均株価は近々騰がることを示唆しているようでコールオプションの買いの効率が高いことになりますね。むろんプットを売っても良いですね。果たしてどうでしょうか?
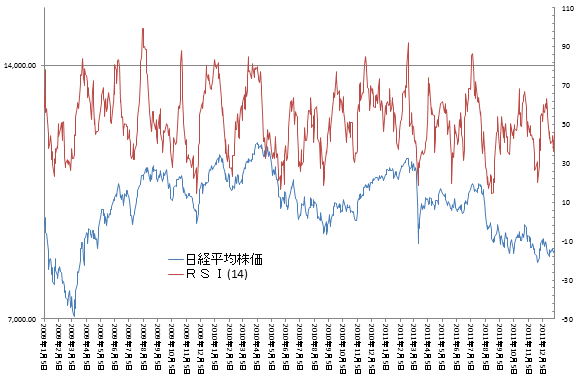
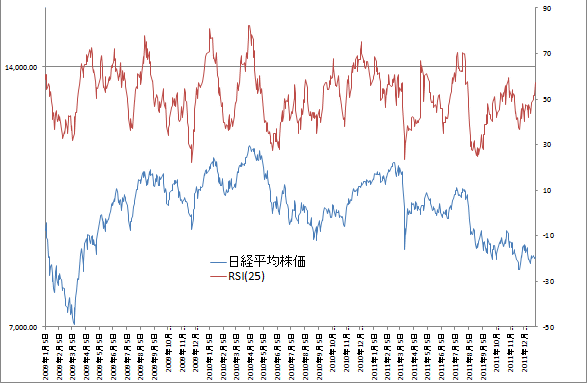
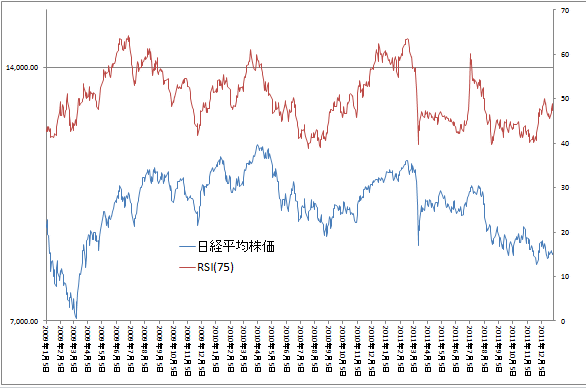
投稿者 kataru : 03:30
2012年01月02日
昨年の反省2
先ほどまで箱根駅伝を見ていました。今年は東洋大学が往路優勝しましたが、柏原君に頼ろうとはせず1年生の田口君などが頑張り、トップで5区にタスキを繋ぎました。それにしても、期待通りに区間新記録を樹立する根性はたいしたものですね。2位争いの早稲田の山本君と明治の大江君の抜きつ抜かれつのデットヒートも、駅伝を盛り上げていた5区の争いでした。農大の津野君は無事に完走できたでしょうか?
さて昨日からの続きで失敗の検証でしたね。昨年を振り返ると手数料が少ないので、昨年前半はディーリングも何度か実施しているのですね。そうして損はしなかったけれど、大きな成果がないので昔の売買に戻し失敗した1年でしたね。全体相場が下落するために、持っていれば下がる相場なのですね。現在もその買い姿勢を保持する売買手法がアダになっており損失を計上している有様です。
多く損を出した銘柄にユビキタスがありますが…全体の損の40%ぐらいを、この銘柄が占めていました。チャートを見れば明らかですね。年初から一貫して値下がりしているわけで、下げ相場の中で買い向かい儲かる道理はありませんね。この会社の業績はピーク利益を更新したのですが、任天堂の売り上げからの変化の途上で、大きく利益を減らすのですね。先ず大きな間違いはこの任天堂から外れると言う読みです。3Dに繋がると思っていたのですが…。もう一つはQBなどの開発の遅れですね。どうにか赤字にならなかったのはSQLやWiFiなどのソフトがどうにか支えたのでしょうが…新規事業の立ち上げにより埋めきれなかったのですね。まぁ組立ソフトの業界は一発スター的な素質を秘めている分野なのであまり悲観はしていませんが、企業業績が悪いのに、夢に目を向けすぎる傾向が強いから失敗するのでしょう。もっとも魅力のある株なのですが、残念ながら時期ではないようです。自分の心を制御する難しさを感じます。惚れた女に弱いカタル君の性格でしょう。
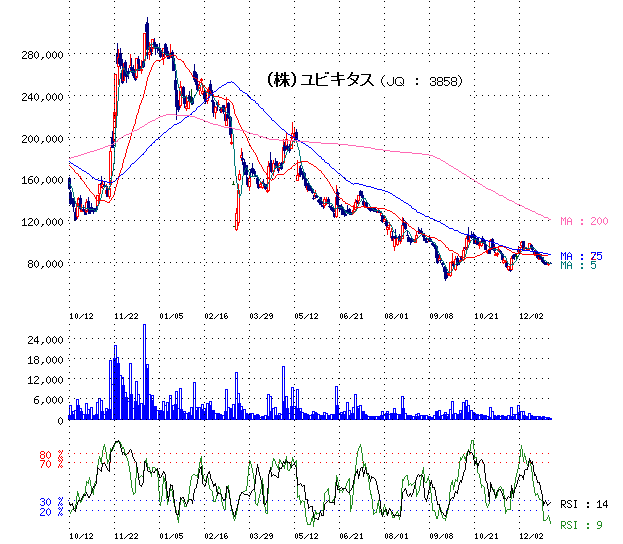
いざ検証してみると前半はディーリングが多く皆さんには参考にならないでしょう。人気株グリーなども手掛けているのに…。結果は悲惨でした。今は再び短期売買に戻そうかと戦略を考えています。時間軸を短くすれば損失の度合いが減ります。そうして相場の好転を待つかどうか…。市場の流動性は低く、人気が偏りますからどうしても流動性のある銘柄を手掛けるべきかとも考えています。ただ昨日、事例検証した鬼ゴムのような投資方法が一般的な手法なのでしょう。好業績銘柄のタイミング投資ですね。いくら好業績が分かっていても動かないケースもありますからね。もう一つが先物からの連動性に賭ける投資方法ですね。
一例を掲げるとエレクトロンですね。この銘柄はおそらく先物連動率はかなり高いのでしょう。もともとシステム売買は全ての銘柄で組み合わせるわけではなく30銘柄ほどの選択で連動させる仕組みが多いと聞きます。故にコア30銘柄の中で過去の株価連動の中から選択しNY市場の動きに連動する銘柄を売買させる方法も有効なのでしょう。余り面白いやり方ではありませんが市場が低迷している現在は仕方がないかもしれません。オレンジ色下部分は、僕が実際に売り買いした実例部分ですが、結果論ですがAで買ってBで売るやり方が最も正しい方法ですね。この時のRSI(14)は39.7から82.4となっていますが、実際の安値は1日前の3325円で高値は3日後の4445円でした。まぁAの買う方は兎も角、売る方のBは難しい選択ですね。先ず、僕が実際に空売りから入った10月17日からの下げで投げさせられますね。結果論だから言える話でしょう。
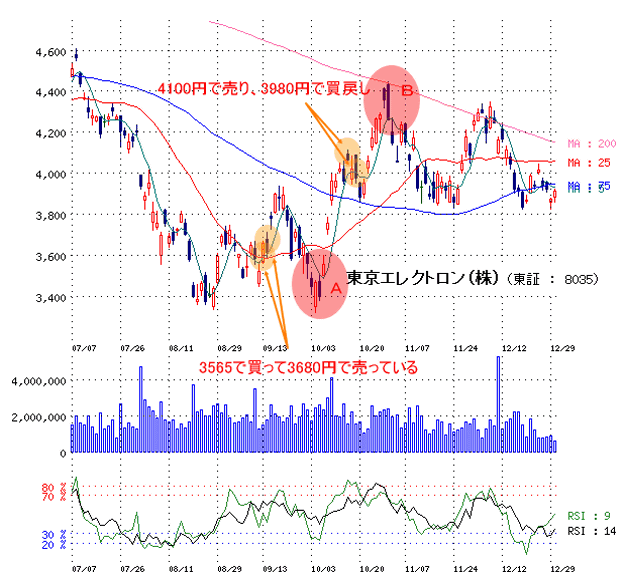
最近はRSIを少し勉強してみようかと考えていますが教科書通りにいかないケースが多いようですね。この為に計算数字を変化させ組み合わせたチャートを掲示していますがヒントが見つかるかどうか…もう少し検証して見ようと思います。
もう一つは日立です。震災の復興銘柄一番手に掲げていた銘柄ですが、未来都市の建設は未だに話題にもなりませんね。スマートシティーは日本を救う計画だと思いましたが誰も動きません。その大本命として掲げた株です。それまで何度か売り買いを実施して若干の利益を計上していましたが6月16日に買ったのですが思わぬ下げを感じ投げさせられました。しかしその後反転し、持っていれば利食いは効きましたが…8月初めの欧州危機で下げの筆頭になっています。結果論を見れば買いではなく売りなのでしょうね。
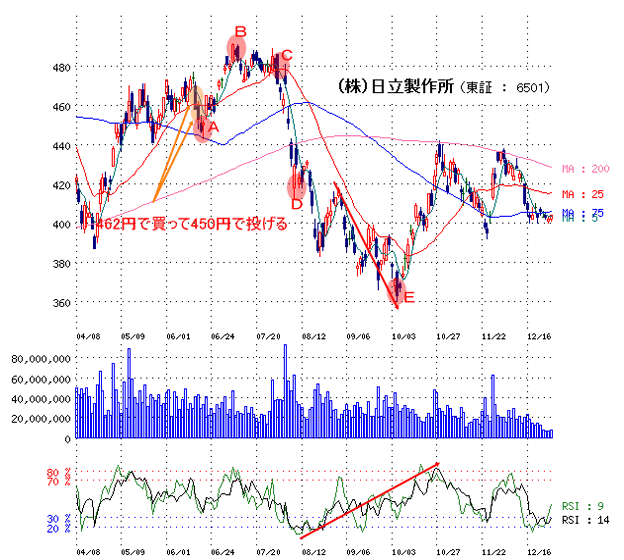
Aで買ってBで利食いしてCで空売りを実施してEで買い戻すのが理想ですが、間違いなくDで手仕舞いますね。それでも成功だと思いますが…。でも奇妙なのはこれからです。RSIは右肩上がりに思いますが株価は下げ続けています。こんな奇妙な事例があるのですね。RSIは値上がり幅と値下がり幅の比率なのですが…この年末までのデータで見る限り、年初の銘柄として日立は有望な候補銘柄に見えますね。おそらく株価は上昇すると思います。ただ8月末にも同様な形が現れ下げてから上げてきていますね。もしここから下の下げがあれば確実な買い場でしょうが…どうでしょうね。
実はこの日立はショックでした。震災から復興銘柄としてかなり期待していたのです。この日立が崩れたことにより、欧州危機の影響もあったのでしょうが下げ相場が確定的になりました。その辺りは明日に総括してみたいと思います。
投稿者 kataru : 16:27
2012年01月01日
昨年の反省1
あけまして、おめでとうございます。
例年とは異色のアップです。事を検証するために反省から入ろうかと考えています。
人気の海外ドラマの「24」ファイナルで、テイラー大統領は真実を歪め和平調印をしようと画策しますが、最後は自らの罪を認め事の収拾に乗り出しました。難しい問題に対処するために困難な決断をしなくてはならない事が、間々あります。最近、耳にした珍しい言葉の「トリレンマ」と言う、好ましくない三つの選択肢の中から決断を迫られ、決断せざる得ない場合が多くなっています。欧州問題も一例ですが、日本では米軍基地移転や八ッ場ダム、消費税なども…その範疇の選択でしょう。苦汁の決断と言う表現が用いられます。
本日の日経新聞の社説にも、中外商業新報のくだりが用いられていましたね。2006年にくだした選択から、私はしばしば政策批判を繰り返しています。ライブドアの粉飾決算発覚の1月から、ホリエモン逮捕の3月、上場廃止の決定は4月。その後IHIの粉飾が明らかになります。その粉飾決算数字をもとに2007年2月に公募増資実施し639億円者お金を集め、6月に300億円の社債で資金調達を実施していますね。2007年10月?事実は発覚しました。このIHIは上場廃止にはならず、16億円の課徴金で済んでいます。今はオリンパスで揺れています。同じ粉飾と言う事実に対する異なった対応は、裁量権の難しさを指摘し、市場原理に疑問を与える問題です。
ブルドックソースの問題をたびたび引き合いに用いるのは、スティール・パートナーズがブルドックソースの株式を保有していることが、最初に判明したのが2002年12月ですが、私が疑問に感じるのは、論理的価値に基づく経営提案と日本的な経営との対立ではないのです。
この経営対立はやがて激化しスティール側はTOBを選択しますが、(2007年5月)、同年7月に会社側は、全株主に新株予約権を発行し対抗します。しかしスティール側には新株予約権を選ぶことが出来ず、お金で対価が支払われます。この処置は株主総会を経ているからという理由で、最高裁は平等な筈の株主の権利を、歪めた会社側の対応を支持したのです。この後出しジャンケンの仕組みを容認した日本の考え方を批判しているのです。株主の権利が、市場で株を買った人によって、株主権利の内容が変わると言う異例の判決です。
最高裁の判例によって、市場原理の根幹を歪めた日本の社会は、海外勢が論理的に割安になった日本企業を買収しようとしても、所詮、無駄だと世界に公言したようなものです。故に日本企業の株価価値が純資産価値を大きく割り込み、底なしに下がる一因を作りました。本来は解散価値を基準に株価は動くはずです。
まして黒字で配当をしているのに、純資産価値を割る異常な株価をどう説明するのでしょう。前に掲げた事例が影響しているのは事実でしょう。選択と結果は自明の理でしょうね。今年、予定される東証のよる大証の併合は、まぁ、合併でも統合でも良いですが、上場規律が歪められる問題を孕んだ裏口上場とも考えられます。東証はこれまで上場基準を歪める裏口上場を否定してきましたが、当事者になると許されるのでしょうか?
欧州問題においてドイツが財政規律を必要以上に問題視するのは、このような根本的な事例を歪めると、どんどんタガが緩み危険ゾーンに入るからですね。それこそ法律が通用しない無法ゾーンに突入する前兆なのでしょうね。昨年は原発処理で誤った決断をしました。原子力賠償法の解釈において裁量権があったのですが、一義的に東電の責任としました。私は 原子力委員会、原子力安全委員会、そうして経済産業省の原子力安全・保安院と…三つの組織が検査、承認して起こった結果なので、国家責任を問い、民間企業は支払い能力からみて1~2兆円の有限責任にして、あとは免責にすべきだと主張しました。しかし結果は最悪の互助会方式です。政府の昨年の対応により、原発の技術を否定し、なし崩し的な廃止論に向かっています。資源のない日本の選択はどうなのでしょう。私なら原発を否定しませんね。誤った選択の決定は、必ず後で結果の報復を受けます。今のところ、世情の評判は芳しくありませんがTPPと消費税の方向性は正しく野田内閣の選択は及第点でしょう。
さて、ここまでIRNET述べた過去の批判を纏めましたが、要するに選択と結果に至った理由や背景を検証することで、失敗を犯す選択を減らす事が、成功への選択に繋がると思われます。新年は何処も希望や期待を前面に取り上げますが、今年は反省でスタートしたのは、このような考えからですね。よってこれから、何故、昨年、あのタイミングで株を買って失敗したのか? どんな理由でその株を買ったのか?を、時間的に検証してその背景を探ってみたいと思います。
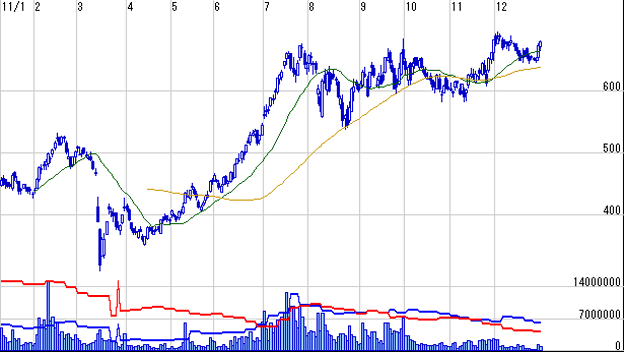
さて昨年初は…鬼怒川ゴムを選んでいますが…買っているタイミングが中途半端ですね。週足のチャートでみると11月から動意付き2月に小天井で休んでいる時に震災を経験しています。その後一貫して上がり続け夏から横ばいですね。しかし流石に多くのファンドが介入している事と業績は読み通りの展開でいつこの揉みあいを抜けてもおかしくないですね。おそらく間もなく前からの約束である4ケタ銘柄に育つのでしょう。
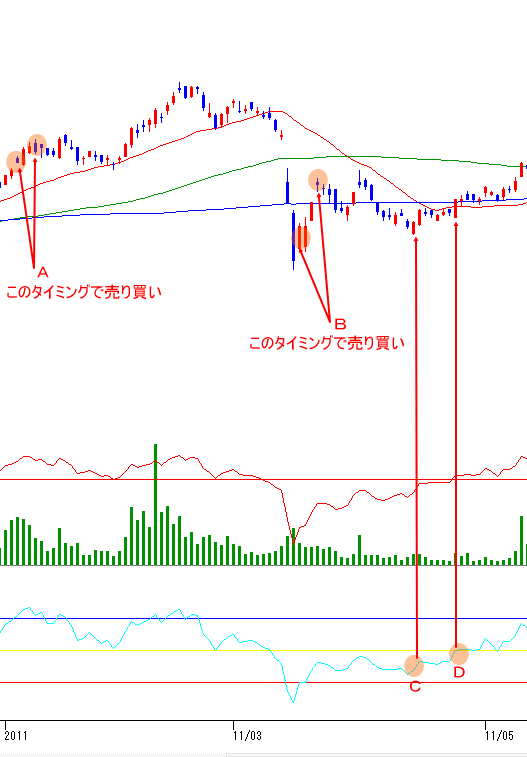
Aでは、1月6日に439円から440円で買っており1月11日に457円で売っていますね。その後Bでは3月の震災直後の3月18日に367円買って22日に414円で売っています。しかし…結果論ですが一番正しいのはその後の、CかDのタイミングでしょうね。基本的に業績の裏付けのある銘柄なので…あとは売買するタイミングが問題なのですからね。AのタイミングではRSIは過熱状態を示していますから、失敗していた可能性もあります。Bのタイミングは素晴らしいが…危険もありますね。だから落ち着いたCかDの時期が相応しいのでしょう。その後、この株価は7月27日の677円まで駆け上がります。1万株買っておけば、200万は儲けられましたね。生活費の足しになります。要するに…いい銘柄は限られており、あとはタイミングの問題だけなのですね。
明日は大好きな箱根駅伝がありますが…時間が許せば、コラムにて続きを書きたいと思っています。今年もご愛読をよろしくお願いいたします。
投稿者 kataru : 16:43