« 2011年11月 | メイン | 2012年01月 »
2011年12月25日
創造力
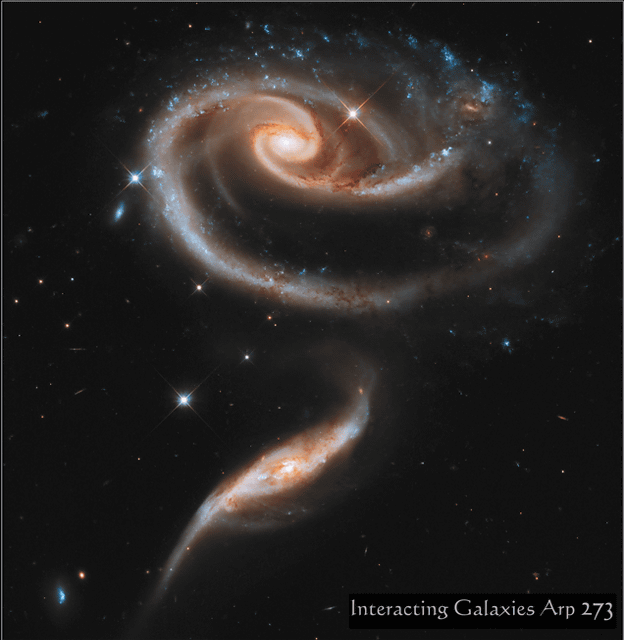
今朝、日経新聞を見ると3面の社会面に上記の写真が載っていました。白黒画像でしたので是非カラーで見てみたいと考え、早速、NASAのホームページに飛んで写真をみました。他にも素敵な画像が沢山ありましたね。宇宙は夢の宝庫です。同様にハップル望遠鏡のサイトも存在しました。最近は翻訳の性能も上がっているようで、どうにか…英語が分からない僕でも意味が、何となく掴めるようになっています。やはりインターネットと言う知識の宝庫は素晴らしい存在ですね。
実は昨日、日本の公共事業投資のあり方を批判しました。
しかし90年代の経済対策の中でIT費用は多く計上され、今日の通信環境が成り立っています。これほど安価でインターネットなどの情報を手にできるのは、この投資のおかげです。光通信網の整備などの背景があるから、世界でも安い通信費でサービスが利用できるのです。その為にソフトバンク、楽天、DENAなどの産業が育ち、プロ野球のオーナーになれるほど躍進したのです。つまり国策の成果でもあります。
日本の官僚は一極集中で東京に経営資源を集め、世界競争に勝つ為に文部省なども画一化教育を推し進めました。その為に今の官僚は記憶力と言う能力はある程度優れているのですが、発想力、創造力と言う機能が大きく極端に欠けています。だから白熱教室でのコロンビア大学のシーナ・アイエンガー先生の講義が人気になるのでしょう。最終回が今晩の6時からNHKで放映されます。まさに裏返し価値観です。記録力と創造力を養う教育の違いを見事に解説している一例をこちらの講義は(クリックして是非冒頭部分だけでも見てください。)冒頭の砂糖の話で取り入れていますね。
この教育の結果、プラザ合意からのグローバル変化を予知できず、「ベルリンの壁」の崩壊を迎えます。東西冷静の終了は日本の存在を希薄にするもので、米国の庇護がなくなったのです。田中角栄の「先見性の明」がここで真価が問われます。残念なことですね。米国から決別して中国と共に歩む道があったはずです。
あれから10年、2001年に日本は中国に購買力平価で抜かれます。鄧小平の南巡講話は1992年1月の末から2月だから、およそ組織改革に10年の歳月が費やされています。それから10年で実際のGDPも中国に抜かれました。本日に日経新聞のある国家予算の公債比率をみると、僕が株で儲かった時は、必ずこの公債依存度は下がっています。株価は正直ですね。僕が東京に出てきてからと言うものは、公債依存度と逆相関関係が成り立っている人生だったな?…なんて考えて、新聞を読んでいましたね。10年単位で移りゆく時代の流れ、今年、日本はこの購買力平価でインドに抜かれました。今度はインドの番ですよ。10年後をめざし、夢のある若者は旅立つべきでしょう。日本の100万円はインドでは10倍以上の価値があるのでしょう。
上記の映像は2011年4月に撮影されたものらしいですね。上部の青い光を放つ星の集団は若い星なのだとか…新星は宇宙に光を何億光年も放ち続けるのでしょう。
投稿者 kataru : 12:33
2011年12月23日
選択
しかし…この国の選択はいったいどうなっているのでしょう?
私は東電の処理の仕方に大きな疑問を抱いています。この原発処理の仕方は後世にツケを押し付けるもので本当に腹立たしい限りです。菅政権は、本来、政策責任を認めるべきところ責任を逃れ、東電に責任を押し付け前面に立たずバックアップに回りました。しかもその処理に互助会形式を採用し、後でルールを変えて、東電以外の電力会社にもコストを押しつける「後出しジャンケン」は呆れる処理の仕方です。
案の定、東電の国有化が叫ばれ、電力料金は引きあがると言います。国有化で電力料金が下がるのでしょうか? 公立の病院は看護師が公務員なのでコストが高く、なかなか黒字化できないのですね。ただでさえ国際競争力の社会基盤が希薄化しているのに、年金などの労働コストは引きあがり、電力料金などのインフラ料金は上がり、どんどん国際競争力は奪われています。韓国は政府が電力料金を肩代わりして産業支援しているのに…我が国からドンドンと産業移転は必然的に起こり、とうとう貿易収支は赤字が定着する状況になりそうですね。
民主党政権が誕生した時は、甘える老人保護から若者支援に軸足を移し、働く人が頑張れる形ができるのかと思ったのに…。子ども手当はその象徴的な政策かな?…と考えて居ました。でも考えてみれば僕らは国に頼り過ぎていますね。
東京都は、今度、発電所を建設すると言いますが、僕にはやはり、その趣旨が理解できません。何故、地方自治体が畑違いの産業に乗り出すことになるのでしょう。もともとごみ処理も、下水道も、学校なども…みんな民間企業に委ねるべきと考えています。僕は基本的に小さな政府で自由な社会が望ましいと考えているのでしょう。法律は時限立法で公正な競争を保てる法律を主眼に据えれば良いと思っています。税金なども消費税だけと言うシンプルなものが望ましいと考えています。やはり株屋らしい考え方ですね。
弱者救済も程々にすべきだと考えています。生活保護なども本来は必要ないと思っているし、年金も本来は必要ないと思っているのでしょう。更に、尊厳死も認めるべきだと考えているし…。きっと、このような僕の考えを支持できない人は大勢いるのでしょう。
今年を振り返ると、年初こそ、QE2から景気回復機運がありましたが、震災、そうして欧州危機、タイの洪水に…次々に足腰が弱くなった体制が叩かれました。民間企業も…国家が民間の活力を奪い、足を引っ張っているから、どうしても浮上できない企業が多く存在するようになりますね。パナソニックやNECなどの大企業の株価を見ていると、情けない時代になったと考えています。
私が証券界に入った時は「ジャパンアズNO1」と言う会社型組織が生きていました。終身雇用、年上序列、株式持ち合い、土地神話など…日本独自の仕組みが生きており、高成長を実現するので、世界からあこがれの的だったのです。様々な仕掛けがきれいに働いていました。国民の生命と財産を守るのが国家目標なら、戦後の日本の躍進的な成長は見事なものです。
その根源を支えた仕組みがすべて否定され、新しい枠組みの競争を強いられています。資源の乏しい日本が生き残るには、ソフト資産の開発、そうして効率的な省エネ社会の実現ですね。この二つに力を注ぎ走らねばなりません。折角、天が与えた試練である震災を利用しない手はないですね。まだ残された時間はあるでしょう。何とか指導力を発揮し未来型社会を構築して欲しいものです。問題はお金でしょうが…何度も言いますが、日銀保証や国家の保証さえ与えれば、お金はいくらでも集まりますね。しかしこのタイミングを逃すと…切羽詰まったところでは、いくら国家が保証すると言っても…いくら日銀が保証すると言っても国民は馬鹿にして、信じなくなる時期が迫っていますね。
2006年のライブドアからブルドックの選択は、大きな間違いを犯しました。あのまま改革路線を歩めば金融危機の影響も少なく、立ち上がったと考えています。折角のチャンスだったが…既得権力者に陥れられたのです。そうして5年の歳月が経過し、2011年の選択も原発の処理で大きな失敗をしました。誰も電力料金が引き上がると産業基盤が失われると…指摘しなかったのでしょうか?もし東電の原発責任を有限にして、原発の継続運転も認める転換を選べば、社会コストは大幅に軽減され、未来社会への展望が開けた筈です。
まだ間に合います。是非、フクシマの汚染地区をすべて早急に買い上げ、未来都市建設を試みてほしいのです。予算などいくらでも集まりますね。日銀がメザニンローンで参加したり…いろんな方法があります。50兆円規模の未来都市建設なんて…夢のある話ですね。世界の何処にも存在しないSFの未来都市の実現を…内需振興の目玉にして欲しい。
投稿者 kataru : 08:22
2011年12月18日
惻隠の情か…
昨日は市場原理主義、所謂、新自由主義のフリードマンの考え方が正しいのかどうか?
疑問を呈しています。
市場原理主義は市場を通じて、効率的な資金配分を実現し切磋琢磨して成長して行こうと言う考え方だと認識しております。だからこそ、人間社会では欲を刺激して競争を促進させるやり方が正しいと言うのが、これまでの実験の結果でした。日本でも一時は共産主義的な考え方が正しいとする人間が大勢いましたが、共産主義は汚職が蔓延り経済が停滞し不平等が生まれるとの見方から、ベルリンの壁が崩壊し東西冷戦が崩れたことにおいて、市場原理主義が世界での共通認識として確立されたのでしょう。自由競争の環境を整備するために企業統治が問題とされるのですね。オリンパスの事件やブルドックソースの問題はこの環境を維持するために厳格に対処すべきなのですね。しかるに日本はブルドックソース側の意見を最高裁は認めました。つまり、あの判決は市場原理を否定したのです。だから株屋の僕は批判し続けました。2006年からの株価の下げは日本の間違った選択による結果だと考えています。
しかし昨日の日経新聞夕刊には藤原正彦さんが登場し「惻隠の情」を題材に震災の事を書いておりフリードマンの新自由主義を否定していましたね。おそらく今回の金融危機をこれらの考え方の人達は「それ見たことか…」とほくそ笑んでいるのでしょう。事実、藤原先生の雑感の中にもギリシャ危機の悲劇が新自由主義の犠牲者だと言う感覚で捉えられていました。僕とはずいぶん違う考え方です。市場原理主義は、常にこのような矛盾を探し叩くのですね。そうして是正を強いるのです。政策の矛盾がマグマのように貯まっている所には、合理的なギャップとの矛盾が存在し、そのギャップを叩くことが市場原理者にとって利益になるのです。休火山が爆発するようなものです。だからギャップを見つけるとそれを叩く準備をして、仕掛けをいくつか作ります。メディアの誘導は重要なパーツです。
あとは資金力ですね。散々に人々の心を、メディアを通じて洗脳するのです。そうして資金力を使って矛盾を叩き始めると、だんだんその矛盾が一般の人にも理解され、やがて是正に向けて行動するようになります。その行動を通じて常に効率的な社会を形成すると言う考え方が市場原理主義(新自由主義)の考え方です。ところが藤原先生は、全く別な観点で物事を見ていますね。
ただ今回の欧州危機のように、なかなか動かない現実の狭間で、市場原理が正しいと大きく主張すれば、どんどんその考え方の対立の中で犠牲になる人が増えます。だから市場原理と言うのは正しい考え方かな?とも考えますね。オリンパスの問題はある意味で「惻隠の情」の賜物かも知れませんね。前任者の失敗を庇う訳です。だから菊川さんは別に次元では素晴らしい経営者かも知れません。市場原理主義と相反する考え方の中の武士道の世界では菊川さんは英雄ですね。お家の大事をつつがなく収めた立役者です。皆さんはどう考えるのでしょう。
投稿者 kataru : 11:03
2011年12月11日
欧州危機を受けて
昨日の日銀短観からの銀行の貸し出し態度をよく見て頂くと分かると思いますが、既に日本は復活の序盤入りしている可能性が非常に高いのですね。1998年12月にバブル崩壊の整理が一巡する底です。それから改善し、私が批判した小泉・竹中内閣の二番底に向かいます。このボトムが2002年12月です。何故か12月ですね。
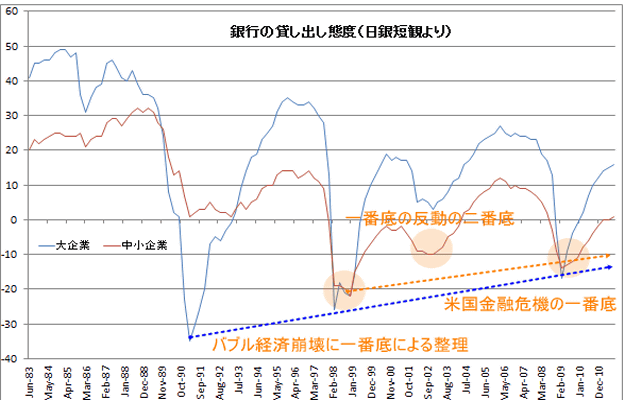
そうして名目成長率が久しぶりの成長し、株式市場も右肩上がりの時代を迎えます。
しかし2006年に私が政策批判しているように日本は選択を誤ります。ライブドアからブルドックソース。市場原理派は旧来主力の既得権力者派閥の反逆に遭います。更には新日鉄の株式持ち合いの復活は、企業統治の問題でありオリンパスと同じ問題なのですね。
しかし2006年~2007年に米国の金融危機です。サブプライムからCDSの崩壊ですね。このボトムは2009年6月です。そこから立ち上がりますが今回の欧州危機は米国の金融危機に対する二番底になります。この下降波動は短く小さいはずですね。
バブル崩壊による不良債権処理は時間がかかり処理が大変でした。日本が震源地だからですね。米国発の金融危機は震源地の影響は大きいとはいえ米国ですからね。日本ほど深刻ではありません。この二番底の震源地は欧州なので、日本経済は軽微の被害と言えるでしょう。
この短観による業況判断指数は、日本経済の実態を良く捉えていますね。株式市場はこの銀行貸し出し態度に先行します。およそ半年から1年でしょう。来年の夏ごろにはかなり改善されます。この欧州問題は、無完全ながら一応、財政規律問題に楔を打ち一定の評価を得られるでしょう。加えて市場関係者は2000億ユーロのIMF拠出金による安全網が設定されましたが、ESMは合意に至らず先送りされました。棚上げするんじゃないかな? 米国の大統領選挙は来年後半に予定され、圧力をかけても改善しませんでしたね。しかし対症療法は実施されています。時間的に不安感を抱えていますし、イタリアの危機まで市場は織り込みましたね。この織り込み方は不完全ですが…。イタリアは輸出依存度から見て、産業は確りしておりギリシャと違いますね。市場関係者としては、財政規律が持ち込まれたから共同債の発行かECBの登場を願ったのですが…両方とも見送りになっています。共同債は大変ですが、ECBは何とかなりますね。
世界の経済は米国の大統領選に向け動いているわけで、アーカンソー州から予備選挙は始まります。やはり時間的に見てそろそろFRBは動かないとなりません。基本的に日経新聞はようやく新興国からの資金引き上げ懸念を報じていますが、こんなことは既に報じているように改善の糸口が見えた連鎖による事象ですね。だから市場は弱いながらも新しい上昇期に入っている可能性は高いと思っています。
投稿者 kataru : 12:52
2011年12月04日
一川保夫防衛相の進退
今日は一川保夫防衛相の進退問題を考えてみます。
事の発端は日米同盟の問題ですが、鳩山元首相が安易に沖縄米軍基地移転を沖縄以外にすると発言した辺りから県民感情がこじれていきました。安易に人間の感情を刺激するとの認識が乏しかったようです。もともと鳩山元首相も移転したかったのでしょうが…勉強不足だったのでしょう。素人考えでは何処かの無人島に移せば良いように感じますが…きっと、いろんな問題があるのでしょう。この問題を契機に日米同盟のあり方を考え直し、徴兵制度を含めた国防のあり方も考えれば、いい切っ掛けになると思いますが、今の所、今回の沖縄問題も根底に流れる日米同盟から国防のあり方を考えるまで発展せず、小手先の話題に終始しているようです。
それにしても、政治家は橋下市長誕生の背景を学んだのでしょうか?自民・公明・民主・共産が支持する候補者を打ち破り、橋下市長が誕生したのは、このような目先の罷免争いにうんざりしているからですね。それよりTPPや消費税、更にはGDPを伸ばすための経済再生のあり方に時間をかけるべきで、一大臣の進退などどうでも良いように思います。国民感情を無視する世論誘導のメディアと政治家の実態は、失われた時代を長引かせるばかり。何故、こう近視眼的な風潮が続くのでしょうか?
事の発端の田中聡前沖縄防衛局長の不適切発言とは…、名護市辺野古移設に向けた環境影響評価(アセスメント)評価書提出をめぐる話で「これから犯す前に犯しますよといいますか」との不適切発言があったからだと言います。この犯すと言う言葉が強姦を連想させ、「1995年9月沖縄のキャンプ・ハンセンに駐留するアメリカ海軍軍人Marcus Gill (22)、アメリカ海兵隊員Rodrico Harp (21)、Kendrick Ledet (20)の3名が基地内で借りたレンタカーで、沖縄本島北部の商店街で買い物をしていた12歳の女子小学生を拉致した。小学生は粘着テープで顔を覆われ、手足を縛られた上で車に押し込まれた。その後近くの海岸に連れて行かれた小学生は強姦され負傷した。」事件を連想させたようですね。
そう言えば、つい先日も沖縄で起こった交通事故の話で、この「日米地位協定」が話題になっていました。この交通事故を起こしたのは聞き慣れない「軍属」と言う言葉でしたが、辞書の解説では、軍人でなくて軍に所属する者。陸海軍文官や技師などの総称。となっていました。敗戦を切っ掛けに沖縄は米国に占領された歴史があります。北方領土は返還されませんが、1972年5月に、敗戦から27年後に返還されました。この時の経緯がどうなのか詳しいことは分かりませんが、その背景で「日米地位協定」が生まれたのでしょう。もともと沖縄は無条件降伏し米国のものだったのですね。北方領土の存在を見れば、如何に米国が紳士的か分かります。まぁ、ある意味で別の見方をすれば、情報のコントロールが優れているのでしょうが…。
だからあまり強く米国に、ものを言えない立場が日本にはあります。この1972年は重要な年でした。前年の1971年にヘンリー・キッシンジャー米国務長官が極秘に訪中し1972年にニクソン大統領が中国を訪問します。この時に、総理である田中角栄は米国に先手を打ち、日中共同声明を発表し国交を正常化させます。米国への事前説明なしに行った、この動きが米国の逆鱗に触れ、ロッキード事件から地検の動きに繋がります。沖縄返還から日中国交正常化へ、この一連の動きは、戦後の日本のあり方を大きく変える働きをしました。この時に間髪入れずに、ソ連との北方領土交渉も実現させればよかったのですね。お金で北方領土をアラスカのように買っても良かったのです。国際紛争の領土問題はお金で解決すればいいのに…竹島なども問題もそう考えます。しかしもう駄目ですね。
話しを戻しますが、この1995年の沖縄少女暴行事件を「詳細には知らない」と述べた国会答弁が問題になり、現在は問責決議に至っているようです。ただ田中局長の話も朝日新聞に報道されていますが、(田中局長は「『やる』前に『やる』とか、いつごろ『やる』とかということは言えない」「いきなり『やる』というのは乱暴だし、丁寧にやっていく必要がある。乱暴にすれば、男女関係で言えば、犯罪になる」)なると内容が報道されていますが、言葉のアヤだった可能性は高いですね。確かに比喩の表現は相応しくなく、どんな集まりで述べたものか? 背景は伝わっていません。不適切には違いないが…政治情勢を歪める問題なのかな?
私は今のあげあしを取る為に、時間を費やすこんな情勢を改善すべきだと思います。メディアも悪戯に視聴率を稼ぐために面白おかしく、一面だけを誇張し取り上げるやり方はドンドン日本を悪くしていますね。猛省すべきでしょう。橋下知事が何故、既存政党相手に圧勝したのか?今の堂々巡りを繰り返す時間が日本に残されているのでしょうか?
何故、TPPのあり方や消費税のあり方を、もっと突き詰めないのでしょう。沖縄問題も基地の移転に終始する近視眼的な視線ではなく、日米同盟のあり方から徴兵制度を含めた日本の国防問題に議論を発展させるべきでしょう。昨日、NHKで日清戦争から太平洋戦争の体験者の証言が放映されていました。しかし上に、人が居ませんね。メディアもメディア、報道の主眼を変えなくてはなりません。スキャンダルのような次元の低い報道を繰り返すのは井戸端会議の世界ですね。メディアは国民教育の義務を秘めているのでしょう。その義務を成し遂げる精神は何処に消えたのでしょう。NHKも最近はその影が薄くなっています。視聴率など、どうでも良いのです。もっと別の次元の評価があっていいはずですね。頑張れニッポン!
投稿者 kataru : 12:05